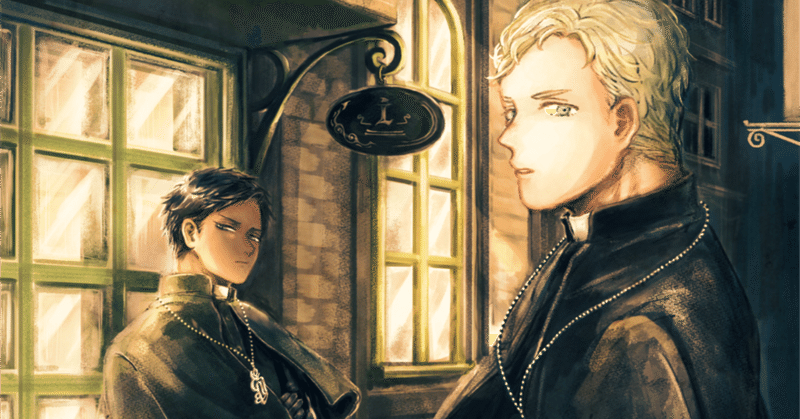
勇気と無謀の違いは神様も教えてくれなかった (9)
それから数刻もしないうちに、僕らは町外れを歩いていた。タクマイン家の前を通り過ぎると、家並みが途切れた。目の前にだだっ広い平原が広がる。
少し離れたところに、巨大な建物がそびえ立っていた。
それは、タクマインがかつて勤めていたガラス工房だ。
ロランはガラス工房の経営者に話を聞きに行くつもりなのだ。
「おまえ、オーランド・ヴォルダのことをどれぐらい知ってる?」
いきなりロランにそう尋ねられ、僕はとまどった。
「ヴォルダ? ……誰だい、それ?」
「このぼんくら野郎が! 本部から支給された資料に、三ページも使って説明してあっただろーが! まさか、読んだ内容を全然覚えてねえのか? てめえの頭は穴の開いた砂袋か?」
資料?
僕は、本部から支給された荷物の中に、黒い表紙の本が何冊か含まれていたことを思い出した。
それらの本はきっちり重ねられ、革のベルトで縛られている。ときどき、立ち寄った教務支庁で新しい本を渡されるので、ベルトをほどいて新しい本を束に追加し、もう一度縛り直さなければならない。
少なくとも、ヨハヌカン先輩と旅していた間、本を追加するとき以外にベルトを解いたことはなかった。つまり、本を開いたことは一度もないということだ。
黒表紙の本は僕らにとって、「使う可能性は低そうだが、何かの時のために本部から持たされている余分な荷物」ぐらいの存在だった。本部の支給荷物の中には、教服のボタンの予備とか、何に使うのかわからない謎の容器や用紙とかが入っている。あの黒い本の束も、それと同じような不要物なのだ。そう思い込んでいた。
そう言えば、ロランはいつも宿屋で資料を熱心に読んでいた。暇つぶしで眺めているだけなのかと思っていたが。
「あの資料って……読むための物だったんだ……」
僕が茫然としてつぶやくと、ロランが足を止めて振り返り、すさまじい罵声を僕に浴びせかけた。
僕はただ、ぼんやりとしていた。ロランの発する単語の多くは、あまりにも柄が悪くて、僕のような山奥育ちの人間が聞いたこともないようなものだった。
ただ、罵声の最後の、
「……そんなだから、てめえは免罪符を一枚も売れねえんだよ。頭からっぽでぶつかって何とかなると思ってんのか? 免罪符を売るには戦略が必要なんだ。相手のことも知らずにどうにかなるわけねーだろ!?」
という言葉が深く突き刺さり、僕はうなだれてしまった。
「わかったよ……僕が努力不足だったってこと、よくわかった。これからは心を入れ替えてもっと勉強する。資料も読むよ。だから、とりあえず今は……そのヴォルダさんって人のことを教えてくれないか」
ロランは、ふん、と盛大に鼻を鳴らした。しかし、ひとまず、悪態の流れは止まった。
不機嫌がはっきりあらわれた口調で、ロランは説明してくれた。
オーランド・ヴォルダとは、ガラス工房の持ち主で、タクマインの元雇い主だ。
そして、このカロリック大平原でも指折りの資産家だ。
ヴォルダはこの町の大農場の息子として生まれた。少年の頃から科学技術なるものに強い関心を持っていた彼は、成人すると村を離れ、帝都アレリーズへ出奔した。科学技術の最先端の地であるアレリーズで、薬師としての修業を積んだ。
彼は五年前に町へ戻ってきたが、農場の経営を継ぐのではなく、農場の土地を利用してガラス工房を建てた。
最初はまだ、納屋に毛が生えた程度の規模だった。
もともとカロリック大平原ではガラス産業が盛んだ。原料となる石灰が多く採れるためだ。どの町村にも必ずと言っていいほど数軒の工房があり、親方から弟子への技術の伝承が行われている。
カロリック大平原のガラス製品は昔から有名で、帝国内外に愛好者も多い。けれども製品を一つずつ手作業で仕上げていたため、数多くを製造することはできないでいた。
それを変えたのが、ヴォルダの画期的なやり方だ。
彼は大勢の職人たちを工房に集めた。ガラスを作るために必要な作業を細かく分け、それぞれ別々の職人に担当させた。
砂や石灰などを混合する作業。
混ぜ合わせたものを液体状のガラスだねに溶融する作業。
ガラス窯の口のところで液体状のガラスだねを加工する作業。
ガラス製品を乾燥窯から取り出し、分類する作業。
出荷のため運び出す作業。
これまで一人の職人がやっていた工程を、数十人の職人が手分けして行うことになった。
分業することで、一人一人の担当する作業が単純になったので、より手早くできるようになった。大勢で集中して作業をするので、材料や道具を無駄なく使うこともできる。
一つの作業所に五十人が集まって分業することによって、五十人の職人が五十の工房で作っていた頃よりも桁違いにたくさんの製品を作れるようになった。
ヴォルダの工房は数多くのガラス製品を出荷し、多額の利益をあげた。
ヴォルダは気前のよい雇い主だった。工房が儲かると、職人たちにもその分賃金をはずんだ。
働きたいという者たちが遠方からもどんどん集まってきた。ヴォルダは窯を増やし、さらに大勢を雇い入れた。未熟な見習い職人にもできる仕事はあったので人集めに苦労はなかった。
ヴォルダは工房を開いてわずか五年で三百人以上の職人を抱える大実業家となり、巨万の富を築き上げた。
「……立派な人のように聞こえるね」
それが、僕の心に浮かんだ感想だった。
「頭のいい商売の方法を思いついて、成功した。職人に高い賃金を払い、自分も他人も豊かにしている。いいことじゃないのか?」
「豊かさは善だってのか? 使徒のくせに生臭ぇこと言う野郎だな」
「そういうわけじゃないけど。このヴォルダって人は、ただまじめに商売をしてるだけの人に思える。この人の何が問題なんだ?」
ロランは肩をすくめた。
「アレリーズで薬師やってたんなら、〈生命の欠片〉のことを知る機会はあったはずだ。……訊いてみる価値はあんだろ?」
「……」
〈生命の欠片〉という語を耳にしただけで、僕の気分は沈んだ。
苦痛に歪むタクマインのすさまじい形相。獣のような叫び声。それらがぞっとするような鮮明さでよみがえってくる。
いつの間にか僕らは、巨大な建物の戸口のすぐ前に立っていた。
すぐ近くで見上げると、改めてその大きさに圧倒される。褐色の煉瓦で組み上げられた、三階建ての直方体の建造物だ。装飾のほとんどない簡素なつくりの建物だが、ガラス工房だけのことはあってガラス窓は実にたくさん付いている。
工房内では大きな自動工具が動いているらしい。単調で機械的な振動が地面を伝わってきた。
気は進まなかったが、工房の玄関の呼び鈴を押した。これから会うヴォルダが悪人でないことを天に祈っていた。自分だけでなく周囲にも富をもたらしている成功者は善人であるはずだ。そうであってほしい。
実物のオーランド・ヴォルダは「こざっぱりした」という形容がぴったりの五十歳前後の男だった。髪をきちんと撫でつけ、恰幅のいい体を都会風の洗練された服に包んでいる。色白の顔に、にこやかな笑みを浮かべていた。
「この工房では、人が『命』なのです。すべてを生み出し動かしているのは人間の力ですからな。私は工房で働いてくれている職人に心から感謝しておりますし、職人を大切にしていきたいと思っております。ここでは今、三百二十四人の職人が働いていますが、私はその一人一人と家族同然のつき合いをしておりますよ。本当に、職人たちは私の家族のようなものです。いや、家族以上ですな」
深い響きをもつ、耳に心地よい声。
相手が予想通りの善人らしいので、僕はほっとしていた。どこの馬の骨とも知れない若造が何の約束もなく訪ねてきても、いやな顔一つせずに、すぐに会ってくれる。ずいぶん出来た人だ。
ロランが周囲を見回し、吐き捨てた。
「薄気味悪ぃ工房だな、ここは。まるで死体の安置所だ。しーんとしていて……人の生気が感じられねぇ」
(うわーーっ! 会ったばかりなのに、いきなり悪口かよ!)
「ここで働いていたタクマインさんについて、お話をうかがいたいんですが……」
僕は必要以上に大声を張り上げた。ロランとヴォルダの間に割り込み、僕の体がロランを完全に隠すようにした。
ヴォルダはちょっとあっけにとられた顔で僕を見返したが、小刻みにうなずき、僕の質問に答えた。
「ホレス・タクマインですか。ええ、覚えていますよ。とても腕のいい磨き工でね。うちとしても重宝していたのですが、健康上の理由でどうしても辞めたいと言って、二月ほど前に退職していきました。残念でしたし、意外でした。これと言って健康に問題がありそうな男には見えなかったので……」
ヴォルダと僕は、工房の中を肩を並べて歩いた。広々とした空間だった。外から見ると三階建てと見える建物の内部は、実際には天井の高い一つの大部屋になっている。たくさんの窓から差し込む日差しのおかげで、室内は明るく快適だ。窯や大鍋、木製の長テーブルなどが整然と配置され、職人たちがてきぱきと作業を進めていた。
忙しげにガラス瓶を磨いている職人の一人が、親しげにヴォルダに声をかけた。ヴォルダも笑顔で言葉を返した。なごやかな雰囲気が漂っていた。
ロランは僕らと少し離れて、肩をいからせ、ぶしつけな鋭い視線を工房内の至る所に投げかけながら歩いていた。完全に、聖職者ではなくちんぴらの態度だった。不意に、尖った声で僕らのやり取りに割り込んできた。
「ここでの仕事がきつくて健康を害した、ってことはないのか?」
また来たな。穏やかな雰囲気を一瞬でぶち壊す、真正面からの暴言だ。
静かな空間に響いたその声は、ヴォルダにはっきり届いただろう。もう、ごまかすにも無理がある。
僕は身の縮む思いで首をすくめた。
ヴォルダは笑顔を崩さなかった。でも周囲の温度がすーっと下がったような気がした。
「……どういうことです?」
「何人もの人間が手分けして一つの製品を仕上げるってことは、誰か一人でもついていけない奴がいれば、全体の作業が止まっちまうってことだ。
朝から晩まで一瞬も気を抜かず、常に周りに合わせて一定の速さで働き続ける……あんたが職人に求めてるのは要するにそういう事だろ。人間に、自動工具になれと言ってるわけだ。そんなんじゃ体を壊す奴が出るんじゃねえのか?
それに、聞いた話じゃ、この工房の窯は決して火を落とさねえんだってな。昼も夜も製造を続けていると。働いてる連中をちゃんと休ませてやってんのか?」
ヴォルダはしばらく答えなかった。
どんな憤慨の表情を浮かべているだろう、と思ったが意外にも彼はまだ笑顔だった。ずいぶん失礼な事を言われているのに、気分を害した様子もない。
「……夜も窯の火を落とさずにいるのはね、人より多く働きたいという職人に機会を与えるためですよ。うちでは働いた者にはその分だけ賃金で報いることにしていますので。皆よくやってくれます。無理をしてでも夜中に働くように、私から指示したことは一度もありませんよ」
「その割に、こいつらみんな顔色悪いぜ。墓の下から這い出してきた死人みたいな顔じゃねーか」
「たしかに今はちょっと疲れ気味かもしれません。大口の注文が入って、しばらく忙しかったのでね。でも、休めばすぐ良くなる程度のものですよ。……お疑いでしたら、ここで働く者、誰にでも尋ねてみてください。私に深夜の作業を強制されているのかと。答えは、間違いなく『否』です。誰に訊いてもらってもいい」
ヴォルダの応対は立派だった。落ち着いていて、堂々としていて、揺らぎがない。まさしく良心に曇りのない人の態度だ。
「ちっ」
ロランがそっぽを向く。
――今、舌打ちしただろ? ちゃんと聞こえたぞ! なんて失礼な奴だ。
僕はふと周囲を見回した。
ロランに指摘されるまで気づかなかった、たしかにどの職人も、目のまわりがどす黒く縁取られている。異常なまでに疲れている様子だ。表情だけはやけに朗らかなのだが――。
ヴォルダは急に足を止め、こちらに向き直った。両腕を大きく広げ、辺り全体を包み込むような仕草をした。
「ご覧ください、使徒様。ここにはまったく新しい形の『労働』があるのです。あなた方がよくご存知の古い形の労働とは違っているので、初めは受け入れがたいのも無理はありませんが。
人と人とが力を合わせることによって、より大きな結果を生み出す。一足す一が二ではなく十にも百にもなる。それが分業の力。それが効率化というものです。すばらしくありませんか?
この工房の成功は、協力というものの尊さを示しています。人の和を尊ぶのは神の御教えにもかなっていると思うのですが、いかがです?」
「ええ……そうですね」
僕は相手の熱意に押され、あいまいにうなずいた。整頓された工房内で大勢の人間が休まず作業を進めている様子には、たしかにある種の美しさがあるな、と思いながら。
「私は予言します。ここ数年のうちに、このような種類の労働が国じゅうに広まっていくだろうと。なぜならこれは、神にも祝福された仕組みであり、万人に幸福をもたらす仕組みだからです」
ヴォルダは瞳を輝かせ、夢見る人の熱意をもって語った。
「進歩」を語るとき、人は往々にしてこういう憑かれたような表情をする。
進歩について論じるのは僕の意図ではなかったので、話を本題へ戻させてもらうことにした。
「ところで、〈生命の欠片〉というのをご存じですか」
ヴォルダは夢から現実に引き戻されたという風情で、急にまじめな顔になって僕をみつめた。
「私はアレリーズで薬師をしておりましたから、噂だけは聞いたことがあります。人の生命を燃え上がらせる禁断の薬だと。それが何か?」
「このカロリック大平原で〈生命の欠片〉が手に入るでしょうか? その、つまり……そういう薬を作ったり、売ったりしている人物の話をお聞きになったことはありませんか?」
「それは……もしかすると、タクマインのことと何か関係が?」
僕は返事につまった。どこまで打ち明けていいのか、とっさに判断できなかった。
ヴォルダは穏やかに微笑んだ。こちらの動揺を見て取りつつも、それを追及したりせず、その場をなごやかに収めようとする。大人の態度だ。
「聞いたことがありませんな。そもそも本当に存在するのでしょうか、そんな絵空事のような薬が? 私も名前だけは聞いていますが……実際にそれが作られたとか、販売されているとか、そういう話は聞いたことがありませんぞ」
彼の返事はきっぱりとしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
