
最近、大事にしてること
最近は、ざっくり
気づき
興味
探求
学び
といったプロセスを大事にしていて、段階に移行する穴埋めの役割として、徹底して黒子になることを常に心がけています。
気づきから興味にいくまでの子には興味を持てるように、興味から探求に行くまでの子には探求に進めるように。
そして、おそらく探求できた子は自身で学びにする力を身につけているので、じっと見守ることが多いですが、時と場合によってはサポートしたり、学びを広げる仕掛けを用意するようにしています。
なんでこのプロセスを大事にしてるの?
気づき、興味、探求がないと「学び」になりにくい、ということを日々感じています。
ここで示す「学び」とはお勉強というよりも、獲得した力を様々な場所で発揮できる、汎化できる、といった力を指しています。
気付かないと興味にならない、興味が出ないと探求しない、探求しないと学びになりにく、とステップはつながっています。
例を出すと、興味のないプリントを机上でやっている子がいるとします。
おそらくですが、やらされているだけの感覚が強い子は、その机上で行うそのプリントは上手になるけど、その世界で汎化できるのか?といったら……やや怪しいかなと思います。
もちろん、汎化が上手な子や他と結びつけることに長けていることもいるので、絶対とは言い切れません。
もう少し、例を掘り下げていきますね。
そのプリントが、数にまつわるものだったと仮定します。その数への気づきを促したいと。
プリントで問題を解くことも、悪くない案ではありますが生活で使えることをおそらく望んでいるのなら。
興味のあるドーナツ屋さんごっこを使ってみたとしたら?
その遊びの中で数を数えたり、適当な値段(数字)をつけてみたり、複数人に分配してみたり、いろんな方法で数に繋がる仕掛けをしてみると、どうなるのか。
遠回りに見えるかもしれないけれど、他の方法から数に繋がるアプローチです。
あたかも自分で気がついたかのように、学習ではなく遊びに使う道具として取り入れられるように、とあくまで自然発生的な状況を狙います。
その興味のある遊びで学んだことは、もしかしたら他の遊びや生活でしれっと使えるようになっていて、なんだか分からないけど数や数字があそびを豊かにすると気付かれるかもしれません。
興味は、ひとつの遊びから向かうこともあれば、あらゆる遊びから「あ、ここでも、ここでも数を使ってる。」と気がついて、複合的に興味に辿り着くこともあります。
対象に気がついて興味が出ると早いんですよ、探究や学びに変化するまで。
ジェットコースターに乗ってるみたい。
「若いうちの苦労は買ってでもせよ」っていうのも、もちろん一理あります。
確かに、昔嫌々やったことが巡り巡ってどこかで役立つ、それも人生の面白さだったりしますしね。
でも、これは自己のコントロールがそこそこ効く大人の場合だったり、その関係性に気がつけるくらいに、過去と現実を照らし合わせ結びつけられるくらい精神的に大人になっている必要があるなと思うのが現場にいて感じるところです。
かなり個人的な意見
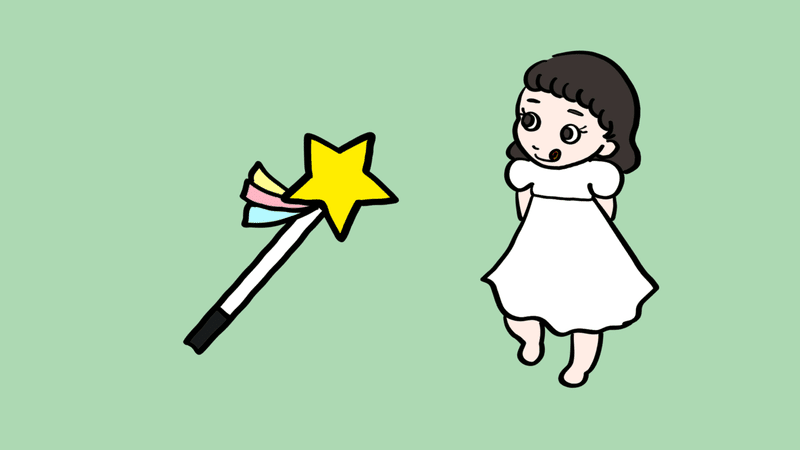
以下はとても個人的な意見、ぼやきですので、あまり気に留めないでほしいのです。
的外れということもあると思います。
本当に。
私が教育を受けていた時代、まぁ今も古い教育を受けて来た世代が指導をしている時点で現在もそうなのかもしれませんが…私たちの時代は、安定して平均点を取ることを教えられてきた時代だなと思っています。
例えば、平均は70〜80点を求められ、50〜60点の子はまあまあ合格、それ以下の子は才能が乏しく、反対に80〜90点の子は優秀で、100点になると才能あり!みたいな。
でもきっと、今後の社会に、世界に求められるような子は、平均は20くらいなんだけど、美術だけ100点とか、他のはてんで苦手だけど、数学だけやたらできたり、料理だけは超得意とか。
興味関心を中心に伸ばした才能を、世の中でどう使っていくか?
どう還元していくか?
といったところかな。
あなたはどう還元できるの?
を求められる時代に突入しているかなと。
簡単にいうと、好きなことだけでご飯を食べよう!ってことですね。
好きなことを伸ばしていこうね!ってことです。
ただし、これって落とし穴もあって。
全員が全員、興味関心の花が開き、才能がぐんぐん伸び、それをサポートする体制があって…など、個々人を取り巻く環境や能力やパワーの差がみんな一緒ではないこと、むしろパワーバランスがそれぞれといった状況になることは否めません。
みんなが好きなことだけやるって、かなりアンバランスになってしまいます。
では、そこでどうするのか?
おそらく、才能とともに、同時に才能を支える力や、社会を支える力を持つ人材も育てなければいけません。
やっぱり世の中というものには、縁の下の力持ちによって支えられてる側面って大いにあると思うんです。
むしろ、縁の下の力持ちのおかげで、なんとか成り立っている社会です。
(だんだん沼に入ってきました……。笑)
そうなると、やはりちょっと耐え忍ぶ、ちょっとだけ頑張ってみるとか、嫌いな人を完全無視するのではなく、腹の中でくそって言いながらも必要なコミュニケーションはとる、とかいろいろ力を育てる必要があるわけです。
この力を育てるために、気づきや興味から広げていく、それらをうまく使いながら力を育んでいきたいところです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
