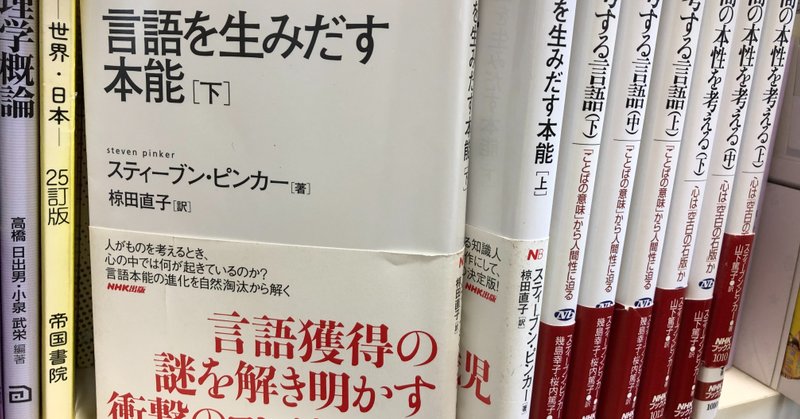
言語が生み出す本能(下) スティーブン・ピンカー著 書評
<概要>
言語(話し言葉)に関しての系統的領域、発生論的領域、脳科学的領域、進化論的領域に加え、言語の流動性に関して考察した書籍。
<コメント>
下巻も言語が本能から発したというその論拠を様々な領域から展開して、これでもかとばかりに解明していきます。
◼️系統的領域
地球上には4,000〜6,000の言語があり、種の進化のように1つの祖先から言語が枝分かれしたのかと思ったらそうではなく、言語タイプに全く相関関係がない場合が多いらしい。言語は本能だからもともとからしてホモ・サピエンスは言語を話していたが、移動しつつ断絶していったのでしょう。言語が通じない同士で新たな言語(=クレオール語)を発明するのが事例としてたくさんあるのも納得です。
ただし、全ての言語に共通する部分もあり、それは主語・目的語・動詞に相当するものが必ずあるということ。そして数千・数万の語彙を持ち、名詞などの品詞に分類できる分類できるという。
日本語の場合は韓国・朝鮮語とのみ類似しており、独立した言語体型。人によってはトルコやアジア大陸で話されているアルタイ語系に近いとも言われるらしい。
今では、朝鮮半島と日本列島に住む人たちはあまりうまくいっていませんが、あの金正恩たちと最も近い言語体型=民族というのも、複雑な心境です。
◼️発生論的領域
(1)胎児
赤ちゃんは、生まれる前からお母さんの言葉を聞いているらしい。生後4日のフランス人のお母さんから生まれた赤ちゃんは、ロシア語を聞いた時よりフランス語を聞いた時の方が乳首を吸う回数が増えるなど、明らかに違う言語を聞いたときの反応が違う。
(2)〜生後6ヶ月
音響学的にあらゆる音素の判別が可能で、世界中の言語を聞き分けることが可能。大人は500回訓練しても1年間専門で勉強したとしても聞き分けることができない。
(3)〜生後10ヶ月
世界中の言語を聞き分けることはできなくなり、母語の音声しか言語として聞き取れなくなる。
(4)1歳〜3歳
生後1年を待たずに単語を覚え始め、2歳後半から3歳までに一気に言語能力が開花し、文法的な文章を滑らかに話すことが可能になる。
(5)言語習得の臨界期
アメリカイリノイ州のある実験では、6歳までに習得した言語はネイティブと全く同じ状態になれるそうですが、7歳ぐらい以降は、完璧にマスターするのは相当稀なことらしい。
→完璧なバイリンガルを育てたければ就学以前に覚えさせないと相当ハードルが高いということか。
◼️生物学的領域
言語を制御するのは脳の左半球(97%)。同時に左半球は身体の右半分を制御しているので、右側の耳から聞いた方が理解しやすいらしい。
→講義を聴講するときは、先生から向かって左側に座ると良い。そうすれば主に右耳から音声がはいってくるので左脳で理解しやすいから。
→逆に左利きの人は右半球で言語を制御(81%)しているので、先生から向かって右側に座ると良い。
言語を司どる領域はいずれもシルビウス裂溝の両側らしいので、ここを損傷すると失語症など、言語障害を起こしやすい。
◼️総括
こうやってみていくと言語は人間固有の本能で、進化論の産物であり遺伝子という設計図に基づいて物理的に人間に備わった能力。
もちろん外的環境によって様々に人間の個性は集団的にも個人的にもヴァラエティに富むが、ベースには普遍性があって、先天的な部分も大きいというのがピンカーの全体を通した主張。
特に言語の場合は、それが顕著だということなのかもしれません。
ネアンデルタール人が絶滅しホモ・サピエンスだけがヒト属の中で唯一生き残り、これだけ繁栄しているのも社会的能力の差という説が有力。
少なくとも現時点では社会的動物として最も生物学的に成功したホモ・サピエンスは、社会性の根本ともいえる「言語」を獲得したことが他の種と異なる最も重要な能力なのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
