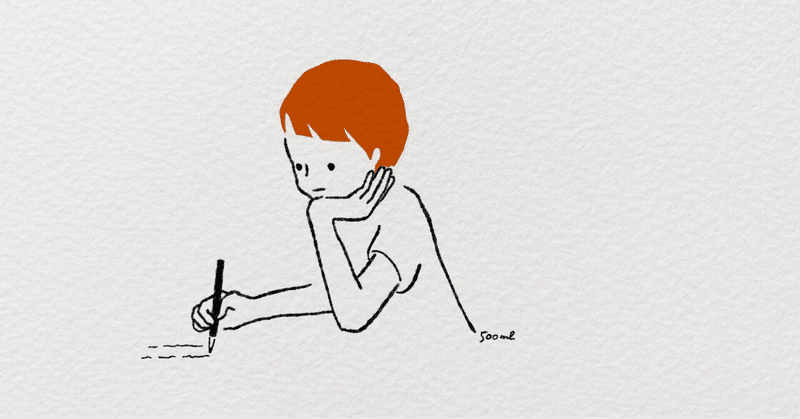
5才までにやっておきたい「子どもが勉強嫌いにならない」ための種まき
皆さんこんにちは、みどりです。
今回は、私が先日ふと思いついて現在実行中の、「将来子どもが勉強嫌いにならないための“種まき”」について書いていきます。
いま、就学前のお子さんがいて、将来勉強嫌いになってほしくないと思っている方にとって参考になればと思い、書き残しておきます。
「ぼく、勉強きらい」
「ゲームばかりしてないで勉強しなさい!」
「勉強なんて何のためにするの?」
これらは、ほとんどの家庭において悩みのタネの一つでしょう。
私の子どもは4才と1才なので今のところは問題ないのですが、私自身の幼少期は母親と上記のようなやりとりが幾度となく繰り返されていたのをよく覚えています。ゲーム機は100回くらい隠されました。
出来れば、我が子には勉強に対する苦手意識を持ってほしくないんです。
別に勉強が得意じゃなくたって良いんですよ。
でも、勉強が嫌いだと学校がつまらなくなるじゃないですか。
何か、未就学児のうちにできる対策はないものか。
そうやって頭を捻り続けて、やっと編み出した方法がこれです。
子どもが「勉強」の意味をまだ分かっていないのを利用して、先に「勉強=楽しいもの」と結びつけてしまおう!
私の思いつきであり、実績が出ている方法ではないので効果は確かではないのですが、妻を巻き込んで実験してみようと思います。
就学前のお子さんがいらっしゃるパパママで、今回の話を「良さそう」と思っていただける方は、ご家庭でも試してみて下さい。
それでは最後までよろしくお願いします。
なぜ子どもたちは勉強が嫌いになるのだろう
ベネッセ教育総合研究所が2014年に行った調査(下図)によれば、勉強が「好き」と答えたのは小学生で約6割で、学年が上がるにつれてその割合は減少していくようです。

言い換えれば、学習内容が多く難しくなるにつれて勉強が嫌いになる割合が高くなる、ということです。
ではそもそも、なぜ子どもたちは「勉強が嫌い」になるのでしょうか?
私は「勉強」という言葉自体に原因があると思っています。
「勉強」のもともとの意味とは、広辞苑によれば以下の通りです。
べん‐きょう【勉強】━キャウ
精を出してつとめること。
学問や技術を学ぶこと。
さまざまな経験を積んで学ぶこと。
しかし、小学生にとっての「勉強」とはどのような意味でしょうか?
ぜひ、ご自分が小学生の頃を思い出してみて下さい。
私が当時考えていた「勉強」の意味とは、
「机に向かい、自分は学びたくはない事柄について学ぶこと」
です。
これは(当然ですが)親や先生に教えてもらった定義ではありません。
自分の経験が「勉強」をこのような意味に定義づけてしまったのです。
学校の授業で、家で、塾で。
それでも授業内容が分かるうちはまだ良いです。しかし学年を重ねるにつれて「分からない」が増えていき、
「別に学びたくもない事柄について学ばさせられた上に、内容も分からない」というサイアクな状態になります。
これが冒頭に紹介した調査結果の真実ですね。

だから、
「勉強はつまらない」
「勉強はしたくない」
「勉強と言われただけで反抗したくなる」
ということになるわけです。
「勉強=ネガティブなイメージ」が、日々の生活で刷り込まれるのです。
そしてそこまで染み付いてしまったイメージは、簡単には変わりません。
それなら「勉強の意味がまだ分からない未就学児のうちに、良いイメージを持ってもらおう」と考えたのが、今回の本題です。
「勉強」を勝手に定義してしまおう
と、いうわけで。
まだ「勉強の何たるか」を知らない4才児に対して、私が勝手に定義した「勉強」とは、これです。
べん‐きょう【勉強】━キャウ
新しいことを知って「なるほど」と思うこと全て。
重視したことは、
勉強の定義を具体的な「行為」ではなく、「意識」にしたこと
です。
もっと分かりやすく言えば、
「机に向かう」ことや「鉛筆を持つ」ことではなく、「面白いと思う」ことそのものにした。
のです。
これは子どもにとって勉強のハードルを下げることに繋がります。
なぜなら、この定義に従えば、遊びですら「勉強」と言えるからです。
公園で「カマキリって茶色いのもいるんだね」と気付くこと。
初めてグレープフルーツを食べて「こんなに酸っぱいのか」と分かること。
ピタゴラスイッチを観て「ハンガーってこうやって作るんだ」と思うこと。
これら全て、「勉強」でOKです。

そしてこれが一番重要なのですが、
この「勉強」という言葉を日常生活で自然に登場させるわけです。
「へぇー、それ自分で気付いたんだ!勉強になったね」
「図鑑を使って勉強してみようか」
「お父さん、この前、本で勉強したんだけどさ…」
という感じで「勉強」というワードを入れ込んでいきます。
ただし不自然にならないように、たまに使う程度が良いですね。
これが我が家で絶賛チャレンジ中の取り組みです。
学校生活とのギャップを少しずつ埋めておく
さて、そうなると一つ疑問が湧いてきます。
いくら「勉強という言葉」を好きになっても、机に向かってする「学校での勉強」とは別物なんだから意味なくない?
これですね。
こればっかりは実際に入学してみないとどうなるか分からないのですが、一応対策は考えてあります。
それは「ギャップを少しずつ埋めておく」ことです。
具体的には、
「今回定義した勉強」の中に、少しずつ「小学校における勉強」の要素も加えていく
ということを考えています。
例えば「図鑑で勉強する行為」について。
今は自由に見させていますが、これをだんだんチューニングしていきます。
図鑑で勉強してみようか
↓
机の上で、図鑑で勉強してみようか
↓
机の上で、時間を決めて、図鑑で勉強してみようか
この例では、小学校での勉強には必須である、
「机に向かってする」「一定時間座っている」といった特徴を取り入れていくわけです。
もちろん、いきなりやらずに少しずつ導入していきます。
これで、子どもが小学生になった際に「学校での勉強はつまらない」と感じる可能性は低くなるでしょう。
いかがでしょうか?
上記が、私が実行中の「将来子どもが勉強嫌いにならないための“種まき”」です。
上手くいくかは分かりませんが、少なくとも子どもに悪い影響は無いと思うので、子どもの将来のために、細く長く、辛抱強く向き合っていきたいです。
普段は読書によって得た知見をもとに、育児や仕事、社会について思ったことを書き連ねています。
最近よく読まれている記事を貼っておきますので、よければ読んでみていただけると嬉しいです!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
いつもサポートしていただきありがとうございます。 頂いたサポートは全て、近隣の本屋さんで書籍の購入に使わせて頂いております。
