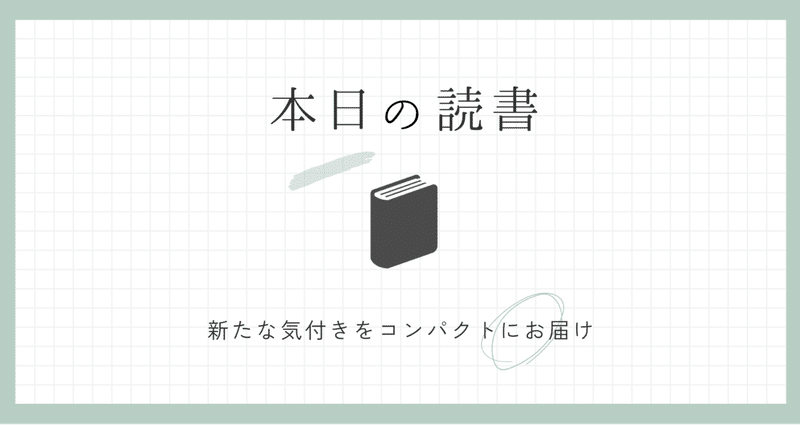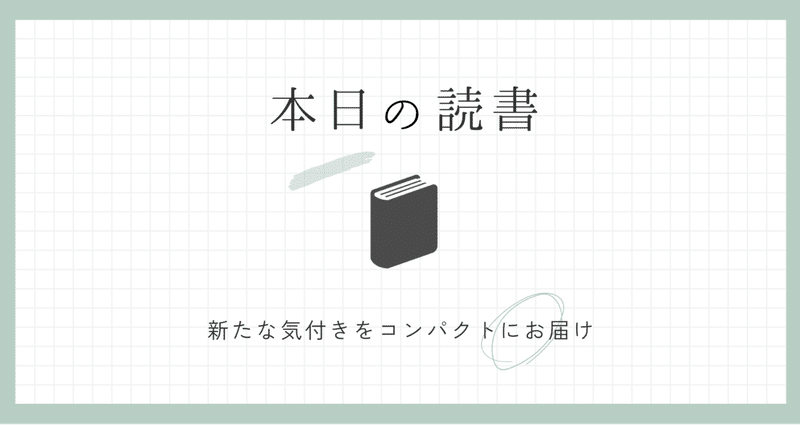本日の読書 #025 「ミラーニューロン」
参考書籍:『学びとは何か』今井むつみ
第五章 熟達による脳の変化 より
ミラーニューロン。
簡単に言えば「他人の動きに反応する脳内回路」のこと。
他人がしたことを、あたかも自分がしたかのように錯覚する。
これは技術的なものだけでなく、例えば相手が悲しい顔をしたときに共感することなどにも役立っている可能性がある。
「もらい泣き」なんかはその典型だ。
子どもたちはこのミラーニューロンによって、親から技術を学び、お友だちから感情を学びとる。
本書『学びとは何か』においては