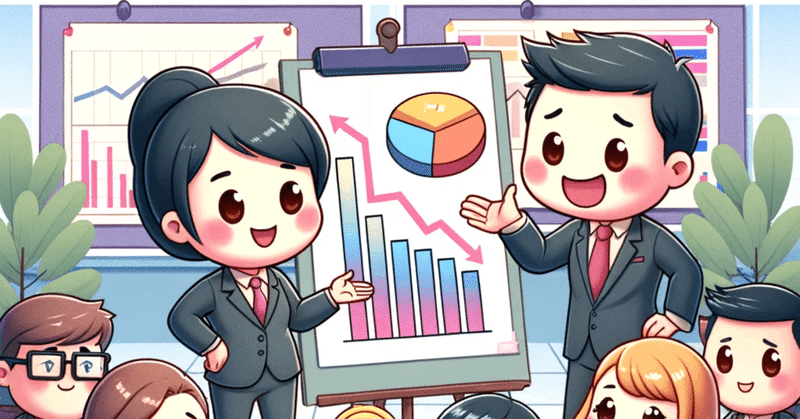
営業組織における失注報告の改善策
多くの営業組織では、失注報告の際に正しい情報が上がってこないことがあります。
今日はその原因と対処法のお話をさせてください。
これは以下の3つの原因が考えられます。
上司が「なぜ」で聞いてしまう
失注のとき「だけ」詳しい報告を求める
失注が部下の責任になっている
失注に関する正しい情報を得るためには、これらのポイントに注意して、マネージャーが部下に確認を行う必要があります。
1. 「なぜ失注したのか?」と聞かない
上司が「なぜ失注したのか?」と質問すると、部下は「自分の責任ではない(しょうがなかった)」ということを示したくなります。
これにより、大事な情報が隠れたり歪められたりします。
そのため、上司はまず報告に感謝の意を示し、理由ではなく事実を確認することが重要です。
”具体的なアプローチ”
最初の一言:「報告ありがとう。お客様からの連絡は電話だった?それともメール?」
↓メンバーも事実で答えやすくなります。「電話で連絡頂きました」
↓続けて、「なるほど。お電話では、何という台詞だったの?」と聞く。台詞の”事実”を確認することが重要です。
台詞の事実を確認したら、次に「ちなみに、他にも何かお客様がおっしゃっていたことはあった?」と確認します。
意外とここに大事な情報が含まれていることが多いです。こうして、お客様からの失注連絡について、台詞の事実をしっかり把握します。
2. 事実から確認する
失注報告を受ける際には、事実から確認していくことで、正しい原因を把握でき、本人にも気づきが生まれます。
決着案件の振り返りは、学びの宝庫です。失注の振り返りに対して、受注の振り返りに3倍以上の時間をかけることが望ましいです。
”なぜ、失注よりも受注の振り返りを重視するのか?”
それは「再現性」を上げるためです。失注を詳しく責めると、メンバーは「うわー憂鬱。責められるのは嫌だ…」となります。
一方、受注を掘り下げるとメンバーは嬉しいし、また繰り返したくなります。成功要因を言語化することで、本人への助けにもなります。
3. 失注の原因を正しく把握する
失注の原因が正しく把握できたら、「メンバーがいつの時点でどう行動を変えたら受注になっていたか」がクリアになります。
これは裏を返すと、「上司がどう介入すれば失注を防げたか?」が明らかになることでもあります。
”上司の役割”
上司が介入すれば防げた失注は、部下の責任ではありません。多くの上司は「部下の成長のために(悔しい体験を繰り返させないために)」という善意で「なぜ?」と聞いてしまいますが、原因を解決するのは上司の役割です。「なぜ?」の矢印を自分に向け、メンバーには事実の確認から入るべきです。
まとめ
営業組織における失注報告の改善には、上司の質問の仕方や報告の受け方が重要です。
理由ではなく事実を確認し、失注と受注の振り返りを通じて学びを深めることが、組織全体の成長につながります。
今日も頑張ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
