
チノカテ from ヨルシカ
ペラッ、、、、、、ペラッ、、、ペラッ
私1人だけの部屋に紙を捲る音だけが響いている。

時刻はもう夕方の5時。
朝から読み続けた長編小説もようやく最後の章へ辿り着く。
オーク材で出来た木製テーブルに置いてあるマグカップを手に取り、カフェオレを一口。
窓から差し込む夕陽がマグカップを飲み込み、ルビーのように美しかった。
飲み掛けの土曜の生活感をテーブルに置く。
ふと見ると、ひらひらと1枚の白い花弁が私の元に舞い込んできた。
あぁ、、、
この花も枯れてしまうのか。
大事に育てていたのが、ついに寿命が訪れてしまったようだ。
また、押し花の栞が増えてしまうな、、、
私は窓の外に目を向けた。
先ほど、マグカップを包んだ夕陽。
『あっ、夕陽だ、、、本当に綺麗だね。』
、、、っ。
『愛萌さんもそろそろ、、、』
、、、やめて。
このままだと現実に戻されてしまいそうだ。
私はまた本に目を向けた。
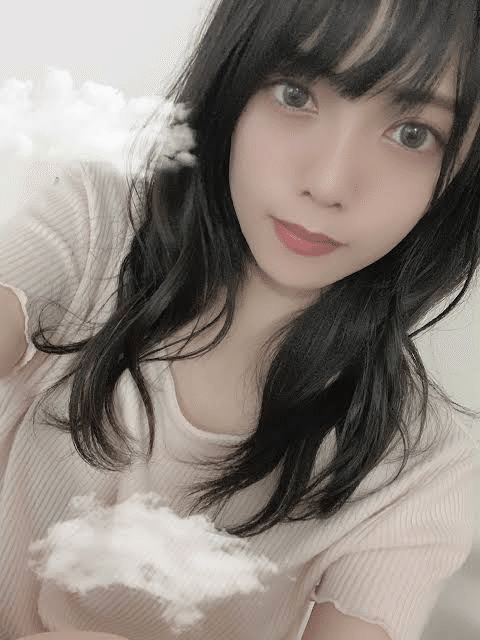
2年前。
家の近くに新しい書店が出来る。
そこには小さなカフェも併設されていてゆっくりと読書を堪能できるらしい。
私は浮き足立った気持ちを抑えながら書店を訪れた。

なんて素晴らしい書店なんだろう。
落ち着いた雰囲気が読書には最適な空間だ。
私はどの本を読もうか、本棚に並べられている本をじっくりと選別する。
、、、、、、これにしよう。
インスピレーションの働くままに選んだ一冊。
その本に私が手を延ばした瞬間。
〇〇「、、、あっ。」
こんなことって本当にあるんだな。
隣にいた男性と手が触れ合ってしまった。
〇〇「あっ、、、すみません!」
愛萌「いえ、どうぞ。」
他の本を探そう。
私はその場を立ち去ろうとする、、、が。
〇〇「あっ、、、あの!」
先ほどの男性に呼び止められてしまった。
面倒だな。
早く本を読みたいという気持ちが腹立たしさを生んだ。
〇〇「宮田さん、、、だよね?」
、、、なんで私の名前を知っているの。
少し不気味に思い、身構えてしまう。
〇〇「あっ、同じクラスだったの渡邉!渡邉〇〇。」
、、、、、、誰?

愛萌「ごめんね、、、」
どうやら彼は高校の時の同級生。
1年生と3年生の時、同じクラスだったらしい。
同じ委員会にもなっていたらしいが全く覚えていない。
その頃から本にしか興味がなかったからだ。
〇〇「ううん!もう何年も前のことだから、、、」
そうは言いつつも寂しげな表情をする〇〇くん。
その純粋さに少し微笑みがこぼれてしまった。
愛萌「、、、ふふっ。」
〇〇「ちょっと、なんで笑うの、、、」
愛萌「ごめんごめん!
こんなにピュアな人は久々だから。」
友人に1人、純粋の権化とも言える子がいる。
彼はその子と同水準くらいかな。
〇〇「もう、、、宮田さんって今は何やってるの?」
彼からの質問。
私は大学の文学部を卒業し、今は司書として働きつつ、、、いや。
この先はいいかと思い、司書として働いてるとだけ伝えた。
〇〇「司書さんなんだ!高校生の頃も図書委員会
だったし、本が好きなんだね!」
愛萌「まぁね。」
、、、思い出した。
一緒の図書委員会だった子だ。

翌々週。
私はまたあの書店に訪れていた。
以前立ち寄った際に読めなかった本を読むために。
、、、そういえば彼が何をしているか聞いていなかったな。
まぁ、たいして興味のないことだったから別にいい。
カランッ、、、カランッ、、、
入り口の扉につけられたドアベルが私の入店を知らせる。
〇〇「いらっしゃ、、、あれ?宮田さんだ。」
以前ここで見た顔が、もう一度私の前に現れた。
しかし今度は、こちら側ではなくカウンターの向こう側にいた。
愛萌「ここで働いてるの?」
〇〇「うん。ここは僕の両親が作った本屋さんでね。
僕もたまに手伝ってるんだ。」
だからこの前も、、、
愛萌「そっか。」
私はそっけない返事を残し、目当ての本を目指した。
あれから私はこの書店が行きつけのお店になっていた。
もちろん彼がいるからではない。
ただ単に、あの雰囲気が気に入っただけだ。
、、、あそこだったらいい文章も書けるかな。
私は普段は持って行かないノートパソコンをカバンにしまい、あの書店へ向かう。
カランッ、、、カランッ、、、
今日はカウンターに彼はいなかった。
私は少し心に違和感を覚えたが、いつもの席へ腰を落ち着けた。
普段は紙の捲れる音が心地よく響いているが、今日は違う。
キーボードを叩きつける無機質な音が響く。
、、、いつもだったら嫌気がさすこの音も今日は心地いい。
コトッ
〇〇「こんにちは、今日はパソコンなんだ?」
先ほど注文したカフェオレを〇〇くんが持ってきた。
さっきはバックヤードにでもいたのか。
愛萌「ありがとう。
今日は書けそうな気がするから。」
〇〇「書けそう?」
そういえば〇〇くんには話していなかったな。
、、、彼ならいいかもしれない。
愛萌「小説。恋愛ものの。」
〇〇「えっ!」
静かな店内に彼の驚いた声が響く。
数人の客がこちらを見ている。
〇〇「すっ、、、すみません、、、」
愛萌「ふふっ。」
顔を赤くして、他のお客さんに謝る姿が可愛く思えた。
〇〇「、、、小説家だったの?」
愛萌「一応高校の頃から書きつづけているんだ。」
〇〇「、、、知らなかった。」
まぁ無理もない。
私はあまり『自分が小説家』ということは言わないようにしている。
これは高校2年の秋の事。
1度みんなに話したことがある。
その結果、心底馬鹿にされてしまった。
「恋愛小説書くって、、、笑。」
「現実が充実してないんだねー笑。」
「こんくらいだったら俺でも書けるわ笑。」
今だったら、なんで子供っぽい理由なんだと自分でも思う。
だけどその経験が今もなお、私の心に影を入れる。
そういう理由で、自分から「小説家です」ということは言わないよにしていた。
それに高校2年は〇〇くんとクラスが違ったし。
愛萌「、、、馬鹿みたいだって思った?」
なんだか卑屈になって〇〇くんに聞く。
私もまだまだ子供なんだなと心の隅で思った。
〇〇「、、、思うわけないじゃん!
めちゃくちゃかっこいいよ!」
目をキラキラさせて私を見つめる〇〇くん。
愛萌「、、、そっか。」
私はまたそっけない返事をしてしまった。
だけど内心、とても嬉しかった。
私と〇〇くんは、あのお店以外でも会うようになった。
話す内容は他愛もない話題ばかり。
最近書こうと思ってる小説の設定、面白かった本、高校時代の思い出、新しく上映されてる映画、、、、、、
今までの私にない体験だった。
友達も少なく、本ばかり読んでいた私からしたら一生分の会話をしたんじゃないかって思うくらい。
〇〇くんとは会話をした。
そんなある日。
2人で食事を終え、〇〇くんの運転する車で信号待ちをしていた時。
〇〇「、、、愛萌さん。」
いつになく真剣な口調の〇〇くん。
愛萌「なに?」
次に〇〇くんの口から出てくる言葉。
きっと、、、
〇〇「ぼっ、、、僕と付き合って欲しい。」
色々とすっ飛ばしすぎでしょ。
急に結論から言うなんて。
、、、でも〇〇くんらしい。
愛萌「うん。いいよ。」

、、、昔のことを思い出してしまった。
私の人生が、世界が綺麗に輝いて見えたあの頃。
まだ彼がこの世界にいた頃を。
〇〇「、、、、、、うん!めっちゃ面白い!」
私の書いた小説を〇〇くんが読んでくれている。
だけど、小学生のような感想に少し呆れてしまう。
、、、でも。
それが彼の本心からの言葉だと言うことはよく分かっている。
愛萌「ありがとう。」

今の私には、この言葉が一番嬉しい。
〇〇「僕、愛萌さんの書く小説が一番好きです!
美しくて、煌びやかで、、、!」
愛萌「そんなに褒めないで、、、///」
〇〇「本当のことですから!
小説家の愛萌さんのことが大好きです!
本当にずっと読んでいたいくらいです!」
部屋に差し込む夕陽が私たちを照らす。
照れて赤くなった顔が夕陽によって。さらに赤らみを増す。
〇〇「あっ、夕陽。」
窓の外を見て〇〇が言う。
〇〇「本当に綺麗だね。」
愛萌「、、、本当だね。」
〇〇くんはこの日から2ヶ月後に亡くなってしまった。
死因は心臓発作だ。
以前から薬を飲んで何とか凌いでいたらしいが、いつまでもそうは行かなかったらしい。
医者から余命宣告を受け、薬での治療を取りやめたらしい。
、、、そんな素振りは今まで見せたことがなかったのに。
でも心のどこかで分かっていたのかもしれない。
あの時も、、、
亡くなる1週間前。
〇〇「ゴホッ、、、ゴホッ、、、」
最近〇〇くんは咳を良くするようになった。
本人はただの風邪だと言っていた。
愛萌「大丈夫?」
〇〇「うっ、、、うん。」
いつもだったらまっすぐに目を見つめて話してくれるのに、体調のことを聞くと必ず目を逸らしてしまう。
〇〇「そういえば!今度、愛萌さんが書く小説なん
だけど、、、」
愛萌「、、、うん。」
〇〇くんの体調がどんどん悪化し、ついにその日が来てしまった。
酷い雨が降る日だった。
部屋の窓が割れてしまうのではないか心配になる程の雨。
プルルルッ、、、プルルルッ、、、
私のスマホに着信があった。
〇〇くんからだ。
愛萌「もしもし?どうかしたの?」
〇〇「はぁ、、、まな、、、もさん、、、」
途切れ途切れに私の名前を呼ぶ〇〇くん。
今にも千切れて無くなってしまいそうな声。
愛萌「〇〇くん、、、!!」
私は電話繋いだまま、〇〇くんの家へ急いだ。
幸い、走れば10分くらいで着くような距離。
玄関を出た途端、私の体を無数の雨粒が襲う。
愛萌「うっ、、、〇〇っ、、、くん!!」
私は電話の向こうにいる彼に呼びかける。
〇〇「ありがとう、、ござい、、、、、、ました、、、、、、」
そう言って切れてしまった電話。
愛萌「〇〇くん!〇〇くんっ!!」
私は夢中で足を動かした。
、、、うごけ。
、、、、、、もっとはやく!!
愛萌「はぁ、、、はぁ、、、」
雨に濡れてびしょびしょになった体を引きづり、ようやく〇〇くんの家に着いた。
ガチャッ
愛萌「〇〇、、、くん、、、!!」
、、、2本の足が横たわっているのが見えた。
急いで近づき、手を握る。
愛萌「〇〇くん!しっかりしてよ!」
「、、、、、、、、、」
〇〇くんからの返事はない。
まって。
行かないで。
あなたのいない生活なんて。
私はスマホを取り出し、すぐに救急車を呼んだ。
、、、遅かった。
私が呼んだ救急車は豪雨による交通事故で到着が遅れてしまった。
そして救急車が到着した頃、既に〇〇くんは亡くなってしまった。
、、、私の足がもっと早かったら。
、、、、、、、、、あんな雨が降っていなかったら。
、、、、、、、、、、、、、、、もっと早くに私が気づいていたら。
〇〇くんが亡くなってから、私は小説を書けなくなっていた。
何度も何度もパソコンを開き、文章を書こうとする。
だけども指がピクリとも動かない。
私が思ったより、〇〇くんが私に開けた穴は大きかったようだ。
先ほどまでの夕陽は既に沈み、夜の影が私の部屋を包んでいた。
本の字が見えなくなってようやく夜が来たことに気づく。
部屋の電気をつけ、先ほどの飲み掛けのカフェオレを飲んだ。
ミルクとコーヒーが分離してしまっていてあまり美味しくない。
愛萌「はぁ、、、」
私は〇〇くんがいなくなってから、自分の生き方が分からなくなってしまった。
ただただ味のしない食事をとり、あれほど好きだった本には微塵も興味が湧かなくなってしまった。
、、、この1冊以外は。
これは〇〇くんが一番好きだと言っていた小説。
私はこの本を知らなかったのだが、〇〇君から強く勧められて読んだんだ。
この本を読んでいる時間だけが今の私をこの世と繋ぎ止めている。
彼を思い出しているこの時間だけ。
読み終わった瞬間、私を真っ暗な闇が襲う。
、、、私の将来を描いた地図は彼と共に亡くなってしまったんだな。
翌日。
もう何度読み直したか分からないほど読んだこの1冊。
きっと一字一句話せと言われても余裕だと思う。
今日も彼に会いに本を読む。
ピンポーン、、、
インターホンが鳴る。
私は気怠く立ち上がり、玄関に向かった。
ガチャッ
配達員「すみません。渡邉〇〇さんと言う方から
お手紙が届いております。」
、、、、、、〇〇くんから?
拝啓 宮田愛萌さん
この手紙が愛萌さんに届く頃には僕はもう死んでいることでしょう。
僕の友人に、僕が死んだら愛萌さんの住所へ
送ってもらうように頼んでいました。
まず、謝らなければいけないことがあります。
何も言わずに死んでしまうことをお許し下さい。
愛萌さんに話そうかすごく悩みました。
だけど、愛萌さんはすごく優しい人だから僕の
ために沢山の時間をかけるんだろうと思いました。
先の短い僕のために、愛萌さんの時間を奪ってしまうことが嫌だっからです。
どんな理由であれ、愛萌さんにショックを与えてしまう事をどうか許してください。
次に、言いたいことが1つ。
自由に生きてください。
実は、僕には気がかりだったことがあります。
小説家としての宮田愛萌のことです。
以前、僕は愛萌さんに
「小説家としての愛萌さんが好きだ。」
と言ったことを覚えているでしょうか。
この言葉を言ってからの愛萌さんは、無理をして小説家になろうとしている様に見えました。
以前の様に、自分の書きたいことではなく。
僕に見せるための文章の様に思えました。
どうか、僕のことなど忘れて愛萌さんの人生を歩んでください。
目を開いて、世界を歩いてください。
そしてまた小説を書いてくれたら嬉しいです。
愛萌さんの感じたことを。
愛萌さんの書きたいことを書いてください。
絶対にこっちで読みますから。
、、、時々でいいので僕のことも思い出してください。
以上です。
本当に今までありがとうございました。
最後の方の文章はよく読めなかった。
私の目に溜まる涙が邪魔をしたから。
、、、〇〇君を忘れて自由に。
〇〇君の手紙を読んで私は色々なものを捨てた。
好きだった本。お気に入りだったペンや鞄、〇〇くんと一緒に座ってたソファ、、、
みんな捨てて私は世界を歩くことにした。
そうしてまた私の文章を書こう。
私は必要最低限の物を持って、もぬけの殻となった部屋を去る。
あっ、そうだ。
私は手帳を取り出し、適当なページにペンを走らせる。
タイトルを決めた。
私が今度書くお話のタイトル。
私がこれから渡り歩く場所。
そこで私が得るもの。
偉大なフランスの小説家から頂いたタイトル。
『地の糧』

from ヨルシカ/チノカテ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
