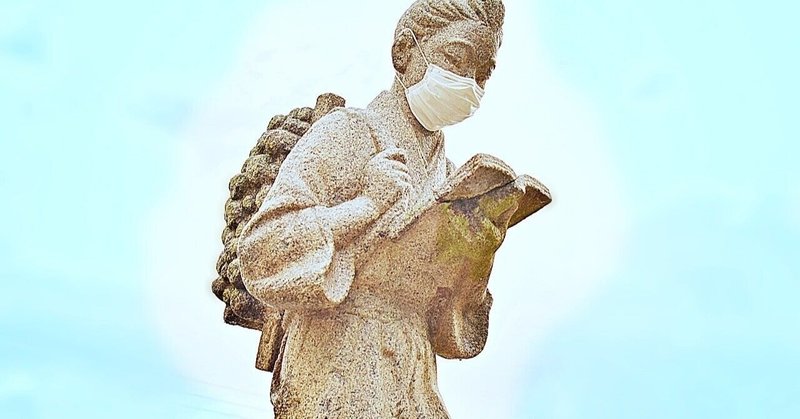
「活力ある企業」の条件①著者:赤岩 茂
【3Point】
①人生の目的はどこにあるのか
ブッタが亡くなるときに、弟子のひとりのアーナンダの「これから何に頼ればよいのでしょうか!」との問いに対し、ブッタは、「自分を頼め、法をよりどころにせよ。」と言ったそうです。これが「自灯明・法灯明」の話ですが、「自分の中には、汲めども尽きない、こんこんと湧き出ずる泉があるのだよ。その水脈を掘り当てることだ。それこそが大いなる力になるのだ。また、私が説いた法が正しく生きる道しるべになるのだよ。」ということです。
【法灯明と自灯明の意味】
法灯明は、法つまり教えを灯火のようにして生きなさいということ。ブッタが「私のことを崇拝する必要はなくて、私の教えを灯明のようにして生きていきなさい」と言う。
自灯明は、自らを灯明とする教えで「他を頼らず、自分の足元を照らす、その灯明に基づいて生きていきなさい」ということを説く。
つまり、「私じゃなくて、私が教えたことを大事にしていきなさい」と言うこと。
スティーブ・ジョブズも後継のティム・クックに亡くなる直前に、「スティーブだったら、どうするかなんてことは考えるな」と言い残しています。
【幸福の定義】
幸福の定義は人それぞれでしょうが、あえて私見を述べれば、「成長」と「貢献」が実現している状態であると思います。我々が生まれてきた意義の第一番目には「成長」があります。これは、単に知識のみを習得し、物知りになることではなく、人間としての魅力を高めていき、周りの規範となるような生き方ができるようになるということです。言葉を換えれば「魂を磨く・人間性を磨く」と言ってもいいでしょう。
②「類は友を呼ぶ」
ことわざの「類は友を呼ぶ」とは、端的に言えば、「明るい人の周りには明るい人が集まり、暗い人の周りには暗い人が集まる」ということです。性格や資質の同じ人が仲間になりやすいことを意味しますが、一般の組織体や企業を見ても、その法則は驚くほど当てはまるものです。人材の質ばかりか客層も良い会社があれば、その逆の会社もある、という現実があります。
経営改善のスタートは、社長の意識改革にあり、その行動にあるということです。この会社も社長が変わり、その結果、従業員が変わっていったのです。つまり、「類は友を呼ぶ」の本当の意味は、「良き人と交わりたかったら、まず、自分が変われ!」ということなのです。
③企業経営の本質を探究せよ!
売上高の本質は何でしょうか。売上高は、お客様(ひいては社会)の喜びの総和と考えると、売上高が下がるのは貢献力が乏しいからだ、と考えるべきなのです。貢献力が乏しくなるのは、商品・サービスそのものが時代に適合しなくなっていたり、その提供の仕方が良くなかったりするからです。本当の商品力は、商品そのものの力とそれを提供する人間の人格(人間力)によって決定されます。そうであれば、経営者と従業員がそれらを謙虚に分析するとともに、不断の経営革新(新たな取組み)を続けなければ企業の存続も難しくなります。もちろん、この新たな取組みは、経営理念に沿い、それを具現化するものでなければならないことは言うまでもありません。
【1Action】
[発見]
「類は友を呼ぶ」の本当に意味「良き人と交わりたかったら、まず、自分が変われ!」ということについて。
成功したビジネス・リーダーたちが仕事仲間を選ぶのに、どうしてあれほど慎重になるのでしょうか。それは、どんな分野でも、成功する人間というのはほとんどの場合、成功という観点から考えたり行動したりする人間を自分の周り置いておきます。そして、彼らにもう一つ共通することは、明確な目標を持って行動し、それを自分の仕事仲間にも要求することです。
つまり、明確な目標(経営理念)が大切になってくるのです。
[行動]
人間を洞察し、顧客視点で物事を見えるようになる。
日本電産・永守重信さんの人心掌握力について挙げたい思います。
一度会った人の名前は忘れないで覚えている永守さん。
永守さん自身、昔は電話番号、家族構成など、従業員全員の情報が全部頭の中に入っていたといいます。
このことからとてつもない人心掌握力があることを読み取れます。
一橋ビジネススクール教授の楠木健さんは永守さんに対して以下のように言っています。
永守さんはある意味で「自分が小さい」んだと思うんですね。これは必ずしも謙虚とか控えめということではありません。自称「ほら吹き」でいつも大きなことを言ってるような印象がありますが、大きな人こそ自分を小さく考えている。だからこそ他者に対して注意が向く。相手の立場になってものを考えることができる、自分に都合がいいように考えない。自己中心的に考えない。これが人間洞察の基盤にあると思います。器が小さい人ほど、「自分が大きい」んですね。
【引用:「仕事ができる」とはどういうことか?著:楠木健・山口周】
[気づき]
経営とは一生涯かかって真理を探究し、実践することである。
人は気づいて、行動し、習慣化されれば、人格が変わるとよく言われます。
経営は自分の品性を養う手段であり、自己実現するための場であるということです。
【1Episode】
禅僧からの教えとして、人間の究極の幸せを、「人から愛されること、人に褒められること、人の役に立つこと、そして最後に、人から必要とされること」と言いました。
皆さんもたくさんの家族からの愛や、頑張って褒められたことや、何か人のために動いたことで幸福感を感じたことがあると思います。
それこそが、究極の幸せのかたちといえるのです。
実際はどうでしょうか..
私たちはあまりに長いこと「辛く苦しいことを我慢すれば、その先に良いことがあるよ」と学校や職場で洗脳されてきてしまったために、「いま、この瞬間の幸福」に対する感受性を著しく摩耗させているのではないでしょうか。
しかし、これには理由があります。
それは、他者視点がないことです。
誰かのお役に立ちたいという「貢献」の気持ちがあれば、「いま、この瞬間の幸福」に気付くことができると思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「活力ある企業」の条件(赤岩 茂)
ぼくに寄付するとよいことがあります。 サポートして下さった方、本当にありがとうございます。
