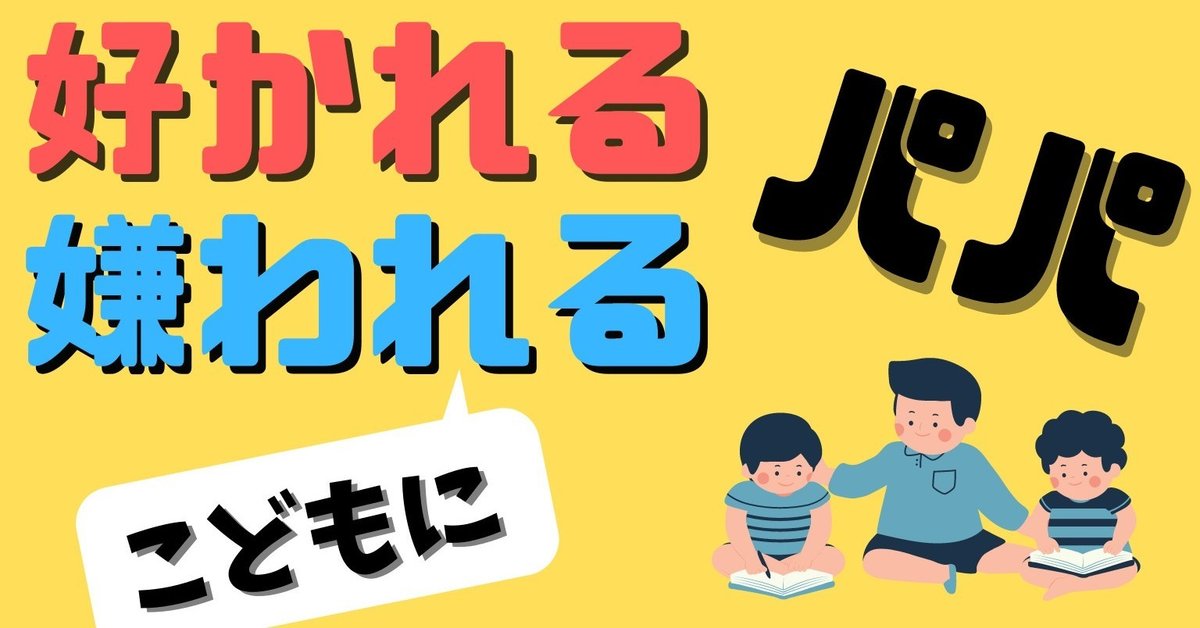
子どもに好かれるパパ、嫌われるパパ
1.はじめに
「子育てはお金や時間さえかければうまくいく、だから、その両方が十分になければ、子供に多少嫌われても仕方ない」
子育てをしていてこんな諦めを感じたことはありませんか?
僕は2020年時点で5歳と1歳の娘2人の父親です。子育てで壁にぶち当たったころに、アドラー心理学に出会いました。提唱者のアルフレッド・アドラーはオーストリア出身の心理学者で、今から100年以上前の人です。
このアドラー心理学の考え方のなかに「共同体感覚」と「目的論」という考え方があります。
共同体感覚は、自己受容と、他者信頼、貢献感などからなる考え方で、社会の中で人と繋がっているという感覚のことを言い、人はこの感覚を感じられる時に、幸福だと感じるとされています。アドラー心理学の書籍としては異例のベストセラーになった「嫌われる勇気」は、他人に嫌われてもいいからまず自分を大事にしてみようという、自己受容がテーマとなったことでも知られています。
目的論は、変えられない過去の事象の原因を考えていくことよりも、目指すべき本来の目的に焦点を当てて考えていく立場です。その反対の立場が原因論で、何かしらの原因があって今の状況があると考える立場です。
僕は娘との関わり方の改善策としてアドラー心理学を学ぶことで、少しずつ子育てに自信を持てるようになってきました。
これからご紹介する、子育てにまつわる失敗と成功のお話は、僕のささやかな実体験と学びによるものです。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、仕事や生活環境が大きく変化しています。大変な中でも「少しでも子どもに好かれたい」「子供の成長に寄与したい」と積極的に子育てに関わる皆さんの手助けになれば幸いです。
2.否定的な言葉に脊髄反射したら嫌われる
次女が生まれた頃から、長女が「お父さんなんか嫌い」と言うようになりました。
これまでずっと可愛がっていた娘からの一言に、私はショックを受けたのを覚えています。
「どうしてそんなことを言うんだい。良くないよ」
「だって、嫌いなんだもん」
「お父さんは、お前のことが好きだよ」
「私は好きじゃないの」
「もうたくさん、これ以上嫌いとか言わないで」
こんなやりとりが、繰り返されるようになりました。
子どもの問題に向き合う上で助けとなった考え方が「共同体感覚」です。この考え方は自己受容、他者信頼、貢献感などからなります。人が人を支配しない、共同体感覚の時だけ、人は人を信頼するという、アドラー心理学の中心となる考え方です。
まず僕は、子どもにふさいだ気持ちをただ認めるための「自己受容」の取り組みとして、「なぜお父さんが嫌いなの?」とか「何で嫌いなのか行ってくれないと分からないよ?」などというかわりに、否定的な気持ちを受け入れるようにしました。
「お父さんなんか嫌い」
「何か怒っているみたいだね」
「そうなの」
「何かお父さんがしたことに、腹が立っているのね」
「お父さんは、赤ちゃんばっかり抱っこするんだもの」
「お父さんが、お前ともっと遊んでくれたらいいなと思ってるんだね」
「うん」
「お前の気持ちを話してくれてうれしかったよ」
おそらく娘は「あたしはお父さんのことが嫌いではなかったんだ。私が嫌いだったのは、お父さんが私より赤ちゃんをかまうことだったんだ」と、自分の気持ちがはっきりしたのでしょう。何が嫌いだったのかの理由がはっきりしたのか、それ以降「お父さん嫌い」ということが少なくなりました。
3.過剰な「共感」は嫌われる
ここから先は
¥ 299
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
