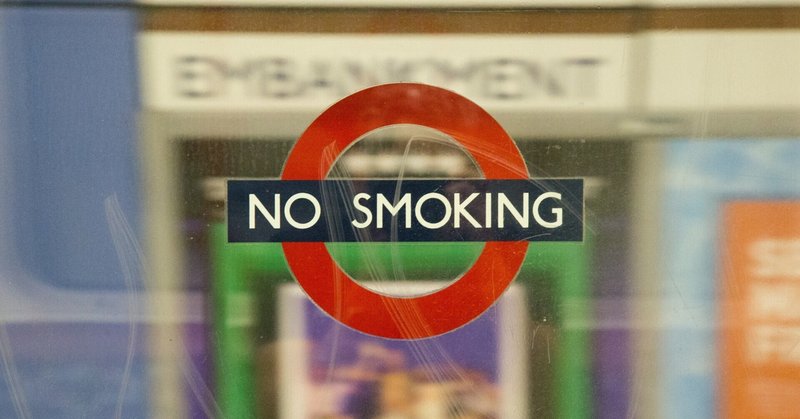
124)がんで死なないための12か条
体がみるみる若返るミトコンドリア活性化術124
ミトコンドリアを活性化して体を若返らせる医薬品やサプリメントを解説しています。
【がんを防ぐための12か条:新旧の違い】
がん予防の方法には第一次予防と第二次予防と第三次予防の3種類があります。がんの第一次予防というのは、食生活や生活習慣の改善によってがんの発生を予防することです。がん検診を使って早期診断・早期治療でがん死を減らそうというのが第二次予防で、がん治療後の再発を予防することを第三次予防と言います。
がんの発生に対する食事の関与が具体的に指摘されたのは1970年代の米国においてです。米国では1960年代には生活習慣病の増大により医療費が膨れあがり、がんや心臓病の予防を目指した研究に巨額の予算がつぎ込まれるようになります。
その成果の一つが1977年の「アメリカ合衆国上院栄養問題特別委員会報告書(通称:マクガバン・レポート)」という5000ページにも及ぶ膨大なレポートです。このレポートでは、「諸々の慢性病は肉食中心の誤った食生活がもたらした食原病である」とし、肉や動物性脂肪や砂糖や食塩の摂り過ぎが心臓病やがんや脳卒中などの生活習慣病の発生に深く関与していることを指摘しました。
1960~70年代の米国の食事が悪いという観点からスタートしているため、まず動物性脂肪と肉と精製度の高い糖質(砂糖や精白した小麦粉など)の摂り過ぎの改善が目標になっています。野菜や果物や精製度の低い穀物が豊富で、食物繊維が多くカロリーが少ない食事が、健康的な食事でがん予防にも効果があると永く考えられてきました。今でも、この考えは間違いではありませんが、細かい点では多くの議論はあります。
このような背景で、1978年に国立がんセンターは「がんを防ぐための12か条」を発表しています。この12か条は全て、がんの発生を防ぐ一次予防に関するものです。(下表参照)

表:『がんを防ぐための12か条(1978年発表)』と『がんを防ぐための新12か条(2011年発表)』の比較
喫煙や運動などの生活習慣と食事の内容の改善によって、がんの3分の2くらいは予防できると考えられています。
その後、脂肪や焦げたものの発がんにおける関与はそれほど高くないということで、「新12か条」では脂肪や焦げたものは削除されています。
がんの発生を増やす原因としてタバコの関与が極めて高いことが明らかになっているので、「たばこは吸わない」と「他人のたばこの煙をできるだけ避ける」がトップに来ています。
「新12か条」のうち第1条から第9条までは第一次予防の項目です。つまり、がんを防ぐ食生活と生活習慣に関する内容です。
第10条の「定期的ながん検診を」と第11条の「身体の異常に気がついたら、すぐに受診を」は早期発見・早期治療を目標とする第二次予防の方法になります。第12条の「正しいがん情報でがんを知ることから」は、第一次予防と第二次予防とがん治療と第三次予防の全てに関連します。
つまり、「がんを防ぐために新12か条」は「がんで死なないための12か条」というのが正しいタイトルと言えます。
新12か条は国立がん研究センターがん予防・検診研究センターがまとめたので、早期発見・早期治療の第二次予防の項目も入れたのだと思いますが、第10条と第11条は「がんを防ぐため」の方法ではないので、「がんを防ぐための新12か条」とするには日本語として多少の違和感があります。「がんで死なないための12か条」が正しい日本語です。
がんで死なないためには、がんにならないこと(第一次予防)、もしなっても早期に見つけて治療を受けること(第二次予防)、がんに関する正しい知識を持つこと、の3つが必要と言えます。この観点では「がんを防ぐために新12か条」の内容は極めて重要です。
【2人に1人ががんになる】
人間の死亡率は100%です。いずれ何らかの原因(病気や老衰や事故など)で必ず死にます。現在、日本における3大死因は悪性新生物、心疾患、老衰です。数年前まで第3位は脳血管疾患したが、平成 30 年(2018年)に老衰に抜かれて第4位になっています。
2020年人口動態統計によると日本人の死因別死亡率は、①悪性新生物(27.6%)、②心疾患(15.0%)、③老衰(9.6%)、④脳血管疾患(7.5%)、⑤肺炎(5.5%)、⑥誤嚥性肺炎(3.1%)、⑦不慮の事故(2.8%)の順です。
悪性新生物は1981年に心疾患を抜いてから、それ以降はずっと1位です。2020年は死亡した人の3.6 人に1人が悪性新生物が原因で死亡したことになります。
一般的に「2人に一人は一生のうちにがんに罹る」と言われています。2019年のデータでは、生涯がん罹患リスクは男性が65.5%、女性が51.2%です。
日本人ががんで死亡する確率は、2021年のデータに基づくと、生涯でがんで死亡する確率は、男性26.2%(4人に1人)、女性17.7%(6人に1人)です。
60歳の男性がこの後の20年間でがんが診断されるのは38%、がんで死亡するのは13%です。60歳の女性がこの後の20年間でがんが診断されるのは21%で、がん死亡するのは7%です。がんが見つかった人の3人に一人ががんで死亡する割合です。
この数字は日本国民全体の平均であり、がん予防の食生活や生活習慣を積極的に実践すればこのリスクは半分以下に低減できます。
60歳の男性が生涯でがんになる確率を20%以下にすることは努力次第で可能です。しかし問題は、「ゼロにはできない」という点です。
ある確率でがんが発生することは避けられません。そこで、がんで死なない対策が重要になります。対策というのは「がんを早期の段階で発見する」ことです。
その方法として定期的ながん検診が有効です。新12か条では第10条の「定期的ながん検診を」になります、しかし、増殖の早いがんでは1年に1回や2回のがん検診では、検診と検診の間に進行がんになることもあります。
毎年がん検診を受けていたのに、手遅れで進行がんが見つかる人は珍しくありません。
そこで、なんらかの症状を自覚したときに、がんを疑う気持ちが大切です。第11条の「身体の異常に気がついたら、すぐに受診を」はこのことを指しています。
【がんを疑うサインとは】
がんで死なないためには「がんにならない」ことが最も確実です。しかし、どんなにがん予防に良い生活習慣や食生活を心がけても、発がんリスクを3分の1程度にするのが限界です。
酸素呼吸する限り体内で絶えず発生する活性酸素や、体内で毎日起こっている細胞分裂時のDNA複製エラーなど、生きている以上、避けられない発がん要因が存在するためです。
そこで、がんで死なないためには、がんを早期に発見して、早期の段階で治療するしかありません。がんの第二次予防です。
定期的に検診を受けることも意味があります。しかし、1年に1〜2回程度のがん検診では、増殖の早いがんを早期に発見できるとは限りません。何らかの症状を自覚したら、医療機関を受診することも大切です。
「がんを疑うサイン」というものがあります。たとえば、英国のcancer research UKのサイトの「がんのサインや症状(Key signs and symptoms of cancer)」には、以下のようなサインや症状があれば医療機関を早く受診するようにと記載されています。
がんを疑うサインや症状(Key signs and symptoms of cancer)
l 息切れ(Breathlessness)
l 原因不明の膣出血(Unexplained vaginal bleeding)
l 非常に激しい寝汗(Very heavy night sweats)
l 耳障りな声や声嗄れ(Croaky voice or hoarseness)
l 持続的な胸やけや消化不良(Persistent heartburn or indigestion)
l 治らない口や舌の潰瘍(Mouth or tongue ulcer that won’t heal)
l 持続的な膨満感(Persistent bloating)
l 嚥下困難(Difficulty swallowing)
l 便秘、軟便、頻回な便意などの排便習慣の変化(A change in bowel habit, such as constipation, looser poo or pooing more often)
l 治癒しない痛み(Sore that won’t heal)
l 食欲不振(Appetite loss)
l 異常な乳房の変化(Unusual breast changes)
l 血便(Blood in your poo)
l 血尿(Blood in your pee)
l 排尿障害(Problems peeing)
l 原因不明の体重減少(Unexplained weight loss)
l 新しいほくろ、またはほくろへの変化(New mole or changes to a mole)
l 喀血(Coughing up blood)
l しつこい咳(Persistent cough)
l 原因不明の痛み(Unexplained pain or ache)
l 異常なしこりや腫れ(Unusual lump or swelling anywhere)
しこりや腫瘤があれば、それを腫瘍と認識することは容易です。
寝汗や微熱、声枯れ、食欲不振、体重減少、排尿障害などの症状からがんを想定する人は少ないと思います。しかし、医師の多くは、これらの症状からがんを疑います。
一般的に2週間以上続く症状(咳や痛みなど)はがんの可能性を示唆します。
このような「がんのサイン」を見逃さずに、早めに医療機関を受診して検査を受けることが、がんを早めに発見する上で大切です。早期のがんはほとんど症状はなく、症状が出た時はかなり進行していることが多いのは確かです。それでも、「がんのサイン」を放置すると、さらに手遅れになります。
【がんのサインに対する認識の低さががん死亡を増やす】
「がんを防ぐための新12か条」の11条の「身体の異常に気がついたら、すぐに受診を」は、極めて当たり前のことです。しかし、症状を自覚しても「がんのサイン」ということを認識できなければ、がんが手遅れになるまで放置されることになります。
実際、このような理由で手遅れになるケースはかなり多いのが実情です。つまり、がんのサインに対する認識の低さががん死亡を増やしているのです。
以下のような報告があります。英国からの報告です。
Educational differences in likelihood of attributing breast symptoms to cancer: a vignette-based study.(乳房の症状をがんに起因すると考える傾向における教育上の相違:ビネット(描写)を使った研究)Psychooncology. 2016 Oct;25(10):1191-1197.
【要旨の抜粋】
背景:乳がんの診断時の病期(ステージ)は社会経済的状態(socio-economic status)によって異なり、社会経済的状態が低いと生存率は低くなる。乳房の症状をがんに起因すると考える傾向と社会経済的状態(教育レベルで指標化)との間の関連を検討した。
方法:様々な教育水準を持つ961人の女性(47-92歳)を対象にオンライン調査を実施した。通常の乳房と見慣れない乳房の変化(腋窩のしこりと乳首の発疹)を描いた2つのビネット(vignettes)を使用し、乳がんとは明示せずに、女性は「これは何だろうと思いますか…」と質問された。
結果:考えられる原因としてがんを挙げる傾向は乳頭発疹(30%)より腋窩のしこり(64%)の方が高かった。多変量解析では、学歴が低あるいは中レベルの女性は、乳頭発疹の原因をがんとする可能性が低いことと独立して関連していた(それぞれのオッズ比=0.51、0.36-0.73およびオッズ比=0.55、0.40-0.77)。腋窩のしこりでは、低学歴群は、考えられる原因としてがんに言及する可能性の低さと関連していた(オッズ比= 0.58、0.41-0.83)。
結論:学歴の低さは、両方の症状についてがんを原因と考える傾向の低さと関連していた。がんを検討する可能性が低いと、診断が遅れる可能性があり、診断段階でのステージの違いにおいて教育レベルが関与する可能性がある。
ビネット(vignettes)というのは、ここでは「人や状況などを的確に描写したもの」で写真や絵のことです。乳がんに起因する腋窩のしこりと乳首の発疹の写真や絵をみて、それらが乳がんによるものと考える率を調査しています。
腋窩のしこりの方が乳頭発疹よりがんを思い浮かべる可能性が高いのは容易に理解できます。そして、学歴が低いほど、これらの症状から乳がんを想定しないので、診断が遅れる可能性を指摘しています。
乳がんの診断時のステージ(がんの進行度合い)の違いの要因に学歴が関与する可能性を指摘しています。
次の論文も同じ研究グループの研究です。
Low cancer suspicion following experience of a‘warning sign'.(がんの「警告サイン」を経験した後の低いがん疑い)Eur J Cancer. 2015 Nov;51(16):2473-9.
【要旨の抜粋】
目的:低い社会経済的状態(Lower socioeconomic status)は、がんの診断が遅れるリスクと関連している。これについては多くの説明がなされているが、最近注目を集めているのはがんの警告サイン(cancer warning signs)に関する患者の知識の低さであり、これが診断の遅れにつながっている。しかし、社会経済的状態によってがんの症状に関する知識に違いがあるという心理測定の証拠はあるが、実際に古典的な警告サインを経験している人々の間において「がんの疑い」の違いを調べた研究は無い。
方法:10個のがんの「警告サイン」を含む症状リストが記載された「健康調査」を9771人の成人(50歳以上、がん診断なし)に郵送した。回答者は過去3ヶ月間に何らかの症状を経験したことがあるかどうかを尋ねられ、経験した場合は「原因は何だと思いますか」と尋ねられた。がんについての言及はすべて「がんの疑い」として評価された。 社会経済的状態のレベルは教育レベルによって分類された。
結果:回答者の半数近く(1732/3756)が「警告サイン」を経験していたが、考えられる原因としてがんを挙げたのは63/1732(3.6%)のみであった。がんの可能性を疑うことの低さは低学歴と関連していた。がんの可能性を疑ったのは、高校までの教育を受けた回答者の2.6%に対し、大学教育を受けた回答者では7.3%であった。多変量解析では、がんの可能性を疑うことの低さと独立して関連する要因は低教育のみであった(オッズ比= 0.34、95%信頼区間=0.20-0.59)。
結論:今回調査した集団では、がんの可能性を疑う確率は低く、教育水準の低い背景を持つ人々の確率はさらに低くなっている。これは早期の症状の段階でのがんの診断を妨げ、がんの診断が遅れる要因となる。
通常、がんが小さい早期の段階では症状は出ません。がんで症状が出たときは、ある程度進行した状態です。
なんらかの症状に気づいて、病院で診察や検査を受けるまでの期間が長くなるほど、がんが進行した状態で治療が開始され、その結果、予後が悪くなります。
がんを疑う症状に気づいたら、早く医療機関にかかることが重要です。しかし、どのような症状があればがんを疑うかの知識がなければ、症状が出ても放置して手遅れになります。
何かの症状があったとき、「がんかも知れない」と思うことが教育レベル(学歴)で明らかに差があるという報告です。
この研究では英国の9771人の男女で調査票を送っています。そこには以下の10項目の症状を最近の3ヶ月間に経験したことがあるかどうかを質問しています。10個の症状は以下です。
1)持続する咳あるいは声枯れ
2)持続する便通の変化
3)持続する原因不明の痛み
4)持続する膀胱症状(頻尿や排尿時痛など)
5)ほくろの外観の変化
6)原因不明のしこり
7)治らない痛み
8)原因不明の体重減少
9)持続する嚥下困難
10)原因不明の出血
これらの症状があった時に、その時に自分で想像した原因を自由に書かせて、その中に「がんを疑う」ような記述があるかどうかを調査しています。約半数(46.1%)が1つ以上の症状を過去3ヶ月間の間に経験していました。
持続する咳が最も多く(16.9%)、原因不明の出血が2.9%でもっとも少ない頻度でした。
「がんの警告」と思われる症状を経験しても、その原因としてがんを疑ったのは3.6%(63/1732)でした。
がんを疑った人とがんを疑わない人との違いを解析すると、性別、年齢、結婚しているか、働いているか無職か、人種は関連がありませんでした。独立して関連が認められたのは教育レベル(大学教育の有無)のみでした。
がんを警告する症状からがんを疑う人は大学教育を受けなかった人(2.6%)に比べて大学教育を受けた人(7.3%)で有意に高いという結果です。「がんのサイン」をがんの可能性に思いを至らせるかどうかは教育レベルにかかっているという報告です。
【がんで死なないためには「正しいがん情報を理解すること」が大切】
『がんを防ぐための新12か条』の12条の「正しいがん情報でがんを知ることから」というのは、がんで死なないために非常に重要なことです。
がん予防の知識、がんのサインを知ること、がん治療の正しい情報など、がんを十分に知れば、がんで死なない確率が高くなります。がんに対する知識がなければ、がんで死亡する確率が増えます。
「学歴」や「教育レベル」という言葉は差別的で、使用は控えるべきかもしれませんが、予防医学の領域では、しばしば要因として検討されています。
健康リテラシー(ヘルス・リテラシー:health literacy)という言葉があります。医療リテラシーとも称されます。
健康リテラシー(ヘルス・リテラシー)とは、個人が健康情報を理解し、評価し、活用する能力のことを指します。つまり、健康に関する情報を正しく理解し、実践する能力です。
パンフレットの図や文章を読んで理解したり、医療機関の診療予約を取れたりするにとどまらず、健康情報を効果的に利用し、健康維持・増進に役立たせる能力を向上させるのに重要です。
健康リテラシーの低い人々は、健康問題の早期発見や予防、治療計画の遵守などの健康管理の面で困難を抱える可能性があります。
リテラシー(literacy)とは「読解記述力」で、日本語の「識字率」のような意味で、「文章を正しく読んだり書いたりできる能力」です。つまり、リテラシーは教育レベルや学歴と密接な関連があります。
「喫煙ががんや循環器疾患を増やす」という情報があっても健康リテラシーが低ければ、禁煙を実行しようという意思決定はできません。
喫煙と学歴の間には「学歴が高いほど喫煙率が低い」というきれいな相関があります。
つまり、健康リテラシーの程度を知る指標の一つが学歴や教育レベルとして使用されています。
いずれにしろ、健康リテラシーが低いとがんで死ぬ確率が増えます。したがって、12条の「正しいがん情報でがんを知ることから」というのは、がんで死なないための極めて重要な要因になります。
まとめると、国立がん研究センターの「がんを防ぐための新12か条」は、1条から9条までは第一次予防(がんにならない)の項目です。
10条の「定期的ながん検診を」と11条の「身体の異常に気がついたら、すぐに受診を」は早期発見・早期治療を目標とする第二次予防の方法になります。
第12条の「正しいがん情報でがんを知ることから」は、第一次予防と第二次予防とがん治療と第三次予防の全てに関連します。がんに関する正しい情報を知ることはがんで死なない確率を高めます。
1978年の「がんを防ぐための12条」の改訂版の位置付けなので、「がんを防ぐための新12か条」となったのかもしれませんが、「がんで死なないための12か条」とタイトルを変えれば、もっとインパクトがでてきます。
少なくともこのタイトルは科学的に間違っています。がんを防ぐための項目は1条から9条までです。10,11,12条はがんの発生予防でなく、がん死を減らす要因です。
がんで死なないためには、第一次予防だけでなく、一般の人ががんの症状やがんの生物学を知ることが重要だと思っています。がんに対する無知ががん死を増やしていると、最近強く思っています。がんで死なないためには、「がんを知る」ことが最も重要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
