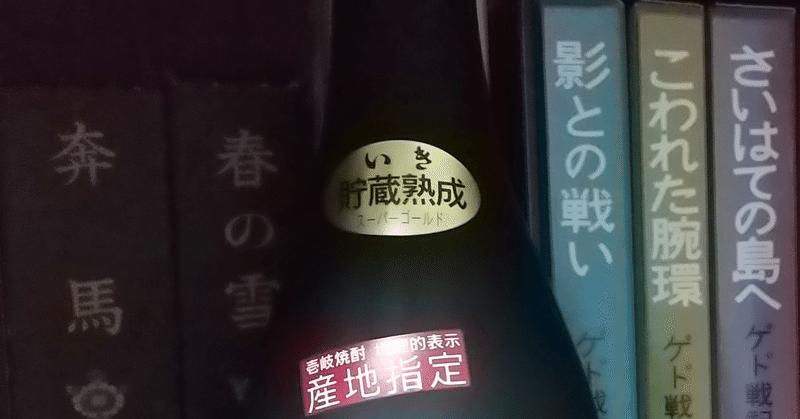
ゲド戦記の読書感想文
昔に書いていたメモであった。
* * *
3巻までに流れている作者の思いは一貫していて、読めばじかに伝わってくる。それは
『信じる』とはどういうことか
であって、3巻が3巻ともそうである。ただ、「誰を」信じるかのベクトルの向きが異なるだけである。この物語に、そのベクトルの向きはふたつしか無くて、
ひとつめは「自分を」信じる
ふたつめは「他人を」信じる
1、2巻は表面だけなぞって読んでいても、爽快感のあるみずみずしい物語ではあるものの、その下地には読んだ人を立ち止まらせるコンセプトが織り込まれている。1巻「影との戦い」、2巻「こわれた腕環」のそれは、いずれも「自分を信じる」というように括ることができる。
1巻は、知らず知らずに使っていた自分の力の凄さに開眼し、それゆえに自分の能力を見誤ってしまったゲドが、自己の真の姿を認める物語。ある種の英雄譚であり、それはそれで面白い。
2巻は、墓守として育てられた少女(墓守というと陰気で不気味だけれど、この登場人物の描き方がファンタジーっぽくて良い)が、ゲドと出会い、諭され、墓守の世界しか知らない自分と決別し、新しい世界へ自分の足で歩いていこうとするところで幕を下ろす。
1巻と2巻に共通していることは、自分とは何者なのかを真摯に見つめる姿勢、よくわからない自分という存在に対する不安や葛藤が描かれているところである。
自分を信じるとは、自分の過去を肯定することである。
文字で書いてしまえば簡単だけれども、実際には、物語に描かれたゲドのように鮮やかにはいかない。我々は魔法使いではないし、ファンタジーの主人公でもないのである。現実と物語とは、違う。
現在の自分がここに在るのは、過去の自分が在ったからで、過去から現在まで自分が在り続けたからである。あるタイミングで自分の過去が断絶されてしまったら、もうそれは自分ではない。過去の忌まわしい出来事、思い出したくもない体験でさえ切り取ってしまうことは出来ず、それをしてしまったら自分を「失う」ことになってしまう。
現在の自分というのは、有形無形の過去の経験の積み重ねからしか出来ておらず、それが良くも悪くも自分と他人を分け隔てる「個性」として成り立っている。つまり現在の自分は、生まれ落ちてから、ほんの1秒前、一瞬手前までの経験の集大成である。
そこから、過去の経験を切り取ったり否定したりしようとすることは、自分の現在の姿を見失わせることにつながる。自分を否定するというのはそういうことである。
さて、
自分を信じるとは、何か。
ありのままの自分を受け容れることである。
ありのまま受け容れるとは、否定しないことである。
この場合、否定しないというのは、うやむやにせず明らかに認めることである。ゲドはそれをやってのけたのである。他人に対する嫉妬や憎しみや、虚栄心。そういったものがしでかしたカッコ悪いことを受け容れるのである。えらいのである。えらいだけじゃなく、心が強いのである。
ゲドは自分自身が自分を認めるという体験をしたから、迷宮で出会った箱入り娘(墓守だけど)を諭すことができた。彼自身の体験がなければ、同じことをしても彼の言葉は嘘となり、嘘は、話す相手に伝わらない。
まずは自分が己を認め、そのあとだからこそ他人に、自分を認めるとはどういうことかを伝えることができた。1巻から2巻への流れは必然なのである。逆だとあべこべで説得力ゼロである。
次に3巻の話は、他人を信じるとはどういうことか、というコンセプトが一番根っこにある。ゲドはいいおっさんになってるだけでなく、大賢人なんていうなんだかエライ人になっている。
いいおっさんは、おっさんであるが故に冷静な判断ができる。自分が出来ることと出来ないことの区別がつくのである。で、自分が出来ないことはどうするか、他人にゆだねるしかないのである。3巻はその物語である。もう一人、アレンという小僧がメインの登場人物として出てくる。
得体の知れない、しかしどうやらすっげぇ偉いおっさんに「オマエ信じてるぜ」と言われた小僧がいったいどういう風に思うか。相手は魔法使いの大ボスのくせに「魔法使うのやだもん」とか言う、正体不明のおっさんである。
案の定、小僧はゲドを裏切ってしまう。生死の境をさまようゲドを見殺しにするのである。しかし、その後九死に一生を得たゲドは、その相手を赦すのである。ただ、赦すのである。アレンがゲドを見捨てた行為、回復したゲドにアレンが懺悔する行為、それらの行為自体を良いとか悪いとか評価するのではなく、ただ赦すのである。その後、アレンはゲドを疑うことを一切しなくなり、手に汗握る物語のヒーローとしてゲドと力を合わせ大活躍するのである。さすがファンタジー。
他人を信じるということは、何か。
その存在、考えをありのまま受け容れることである。
他人とは、本来自分が口を挟む存在ではない。
これまで過ごしてきた環境も、物事の経験も、全てが違うのだから、おんなじはずが無いのである。それを大上段に構えて、いいとか悪いとか勝手に自分のまな板に乗せて選り分けるのはナンセンスなのである。そうやって自分勝手に贔屓したものに対して「信じてるからね」なんていうのは目も当てられない。そういうのは本当の信じるとは程遠くて「自分が思ったとおりの奴だと『信じてる』(勝手に妄想して、その役を演じることを相手に強制している)」だけである。
そうじゃなくて、他人を信じるというのは、その存在をそのまま受け容れることである。やっぱりゲドはえらいのである。3巻は「さいはての島へ」という名が冠されていて、人間の欲望とはどういうものか、生と死とはどういうものか、というなかなか斬り込みづらいところを興味深く読ませるように書いてある。
結論としては、自分も他人もとやかくいわず「ふーん」と思って認めちゃえばいいのである。そしたら楽ちんなのである。
人が苦しみを乗り越える時、きっとゲドが苦しんだのと同じ道を辿る。苦しみを乗り越えたとき、自分・他人を信じることが出来る。それは自分・他人を認めるというプロセスを踏んでいるから。そういう大事なことを児童文学に溶かし込んだ原作者はすごい人だし、上手く日本語に訳した訳者の人もスゴ腕なのである。
