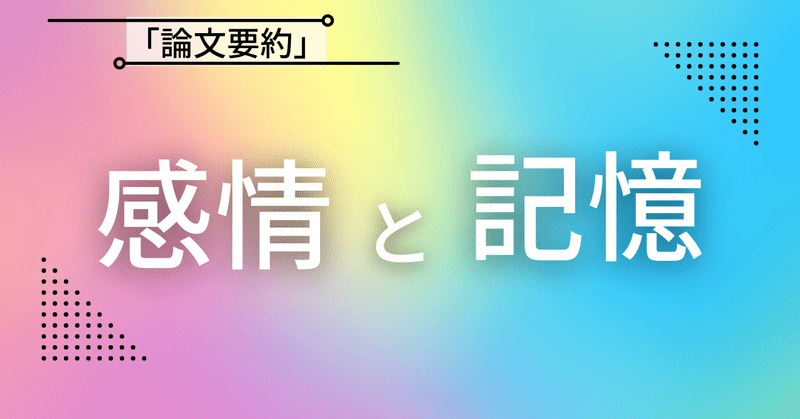
感情と記憶【論文要約】
感情が記憶に関わっているということに興味を持って調べてみました。すると勉強にも応用できそうな面白い知識が得られたのでまとめてみようと思います。
参考論文はこちら:仲真紀子(2007)「感情と記憶」
【1】気分が記憶に及ぼす影響
【1-1】
この論文内で引用された実験では大学生を対象に記憶やソースモニタリング¹を調べました。
①単語を快の感情語(繁栄、陽光など)と不快の感情語(緊急、虐殺など)と中立語(開閉、領域など)に分ける
②コンピューター画面に現れる語を読んでその後に思い出してもらった
結果、快や不快によらず、中立語よりも感情語の方が成績が良かった。つまり感情の伴った情報の方が覚えやすいということですね
1.”ある特定の記憶について、その記憶がいつどこでどのように得られたかという情報源についての記憶・認識である”
【1-2】
記憶は手がかりとなる情報があると思い出しやすくなり、感情はその手がかりとなります。
「気分一致効果」
現在の気分に沿った情報が思い出されること
Ex.楽しい時に明るい音楽を想起する、悲しい時に静かな音楽を想起する
(逆に楽しい気分の時に悲しいことを思い出したり、悲しい気分の時に楽しいことを思い出そうとすると、想起に時間がかかる)
【1-3】
「気分ー状態依存効果」
気分一致効果の特殊なパターン
ある気分で覚えた情報が、同じ気分になった時に思い出しやすくなるというもの
(気分一致効果との違い)
気分一致効果は現在の気分だけが想起に影響するが、
気分ー状態依存効果は覚えた時の気分と現在の気分とのつながりが想起に影響する
「記銘特殊性原理」
気分ー状態依存効果のようなことは感情だけに限った話ではなく、覚えた時と思い出す時の文脈が同じなら思い出しやすくなる
その点を踏まえると、気分ー状態依存効果は記銘特殊性原理の特殊なパターンとも捉えることができる
何かを思い出したい時にはその時、どんな気分だったかということを思い出すと記憶が自然と引き出されるということですね
【2】日常体験の記憶と感情
【2-1】
「フラッシュバルブ記憶」
”情動を喚起するような社会的事件や、それを見聞きした場面に関する記憶”
その事件を見聞きした時に、どこで誰と何をしていたか?などの状況に関する記憶です
これには事件の重大性や意外性は関わっておらず、通常の記憶と同様に思い出す頻度によって形成されていくようです。
でも、自分にとって衝撃的な事件だと何度も頭の中で思い返すものですよね。だから結果的に大きな事件ではフラッシュバルブ記憶が形成されやすいんじゃないかなと思いました。私も東日本大震災のニュースを見た時のことは鮮明に覚えています
【2-2】
ポジティブな記憶とネガティブな記憶をそれぞれ報告してもらい、その違いを調べた結果、2つの違いがみられた
①ポジティブな報告では「人物」「事物」についての言及が多かったのに対し、ネガティブな報告では「内的状態(自分の気持ち)」に多く言及されていた
②ネガティブな報告の方が話の流れに一貫性があった
(考察)
この違いについて筆者は次のように考察しています。
”楽しかった出来事,おもしろかった出来事は外の「人物」「事物」に 向かっており,事実をただ報告するだけでもおもしろく,意義がある。これに対し悲しかった出来事,辛かった出来事は,それを何度も問い返し,話合い,意味を見つけ,乗り越えていくことが必要であるだろう。こうしたプロセスの違いが,出来事の報告にも現れたのかもしれない。”
【3】記憶の抑圧と回復
【3-1】
回復した記憶は裁判における証拠になるのか?
結論:記憶は変容し、再構成されるものであるため、回復した記憶の真偽はそれを示す証拠がなければ判別できない
これに関して回復した記憶を肯定する心理学者と否定する心理学者の間で論争が起こったようです
【3-2】
回復した記憶をめぐる論争の中、実際になかった出来事の記憶を「回復」したと否定派の学者が報告しました
①参加者が子供の頃に起きた出来事を前もって調べておいて、参加者に子供の頃の出来事を思い出してもらった
②実際に体験していない出来事を思い出すように指示し、繰り返し想起を求めた結果、参加者の20~30%に偽りの記憶が形成された
この実験でクリスという少年にショッピングモールで迷子になったことを思い出してもらったことから、偽りの記憶を形成するパラダイムをショッピングモール・パラダイムと呼ぶようになった
【3-3】
実験1:あり得ない出来事であっても偽りの記憶は形成される
①参加者に40の出来事について信じられるかということと自分の身に起きたかどうかを評価してもらう
②参加者に短い読み物を読ませる(その中には「大人は子供に悪魔憑きを見せることがある」というようなあり得ないことが書かれた記事が3件含まれていた)
③参加者の恐怖度を測るテストを行い、「あなたの恐怖は子供の頃に悪魔憑きを目撃したからじゃないですか?」というフィードバックを与える
④再度①の評価を行った結果、「悪魔憑きを目撃する」という項目にて14%の参加者が「ない」から「あったかもしれない」に変更した
実験2:偽りの記憶はのちの行動にも影響を及ぼす
①参加者に「子供の頃にゆで卵を食べて気分が悪くなった」という偽りの記憶を植え付ける
②別の研究と題して参加者に「パーティーでどのような食べ物をたべたいか」ということを聞いた結果、偽りの記憶を植え付けられた参加者はゆで卵を選ばなくなった
偽りの記憶を植え付ける方法
①その出来事があり得そうだと信じ込ませる
②補強証拠などを引き合いに出して、その人が体験したことがあると信じ込ませる
③視覚化を伴うイメージを用いる
※注意
相手を欺くことですから、信用を失うことに繋がります。場合によっては詐欺に繋がる可能性があるので、使うときは「君の前世は買ったけどあんまり使われなかったオーブントースターだったんだよ」と友達に信じ込ませるぐらいの害のない使用を心がけましょう。
【感想】
心理学は面白いなー!たまには論文要約すると福が来たるというお告げを聞いたのでやってみたら超ハッピー。ここまで読んで集中力の篩にかけられた精鋭の皆さんへお知らせがあります!終わります(ジーザス!なんということだ!)
ぽめらーと byぜらまる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
