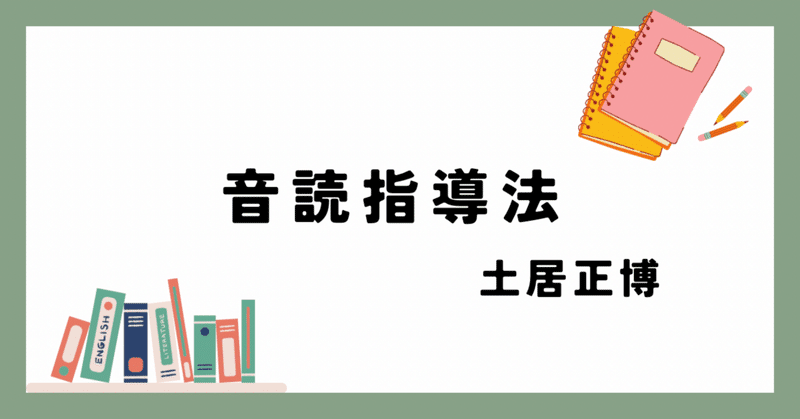
【教育書】音読指導法 #16
こんにちは、GIANT KILLINGです。
今回、紹介する本はこちらです。
音読指導法
漢字指導法で有名な土居正博先生の本です。
漢字指導法につきましては、
以前、noteでまとめさせていただきました。
よければ、こちらもお読みください。
音読指導は、漢字指導と同じくらい、
多くの時間をかけてどの先生も行っています。
授業の冒頭や宿題等で、
音読をしている学級が多いのではないでしょうか?
本書はその音読指導について、
わかりやすく指導のポイントをまとめた1冊です。
誰でも、意識して継続さえすれば、
確実に子どもの力を高めることができます。
本の概要
音読三原則 ①ハキハキ ②スラスラ ③正しく
本書では、
音読の三原則として上記の三つを挙げています。
特に小学校段階では、
②スラスラと読めることが重要ポイントです。
初めて出会った文章をスラスラと読める程度の
音読力が身につくように日々の指導を行います。
音読をするときの望ましい姿勢は、
背中を伸ばして、胸を張り、
足をピッタリと地面につけることです。
まずは、基本の三原則と姿勢を指導していきます。
以下にそれぞれの具体をまとめます。
①ハキハキと読む
ハキハキの指導は、年度はじめが重要です。
口を大きく開け、息を吸い、良い姿勢で読む。
適当な音読を許さないことを教師が示します。
ハキハキの指導では、
声の大きさではなく、
声をしっかりと出そうとしているかで評価します。
休み時間の声の大きさを参考にして、
子どもたちの声の出し方を確認します。
②スラスラと読む
スラスラとは、
やや早いかなレベルのスピードで読むことです。
子どもたちがスラスラと読めるようになるためには
追い読みの機会を増やすことが効果的です。
追い読みでは、
子どもたちが読み終わる少し前くらいから、
教師がテンポを上げて読み始めることで、
文章をスラスラと読むことに慣れます。
基本的には、
句読点で息継ぎをするように指導し、
句読点までは一息で読めるようにします。
スラスラと読むためには、
文章を読みながらも、
先の字を認識していく目ずらしの練習も必要です。
追い読みをしたり、
目ずらしの練習をしたりすることで
少しずつ文章をスラスラと
読むことができるようになってきます。
③正しく読む
正しくの指導では、
教師が言い間違いを正すことが大切です。
子どもは知らず知らずのうちに、
適当な場所で区切ったり、
イントネーションを間違えることがあります。
句読点で区切ること。
声の高低を意識することを指導します。
間違えたら交代読みをすることで、
集中して正しく読む練習をすることができます。
音読指導こそ即時評価
音読指導の基本的な流れは、
教師の範読→追い読み→丸読みです。
授業の中で見本を示し、
教師の真似をしながら、個別に評価していきます。
個別評価・即時評価で子どもの音読に
フィードバックを返すことで、
音読に対する意欲が高まり、力が伸びます。
ハキハキ・スラスラ・正しく音読できることが
かっこいいという
学級の雰囲気をつくることも重要です。
おわりに(こんな人におすすめ)
今回土居先生の音読指導法についてまとめました。
音読も漢字と同様に、
どの学年でも必ず行う学習活動です。
だれでも取り組むことができ、
成長が見えやすく達成感を実感しやすい学習です。
国語の全ての単元で
音読に力を入れることは難しいですが、
単元の軽重をつけながら、
確実に指導していくことが大切です。
そして、何度も何度も文章を読むことは、
物語や説明文の文章理解にも確実につながります。
より深く物語・説明文を味わうために、
学級の雰囲気を活気のあるものにするために、
私自身、今後も音読指導に励みたいと思います。
・なんとなく宿題を中心に音読指導をしている先生
重ねてになりますが
音読指導は継続し続ければ、
子どもたちの姿が少しずつ変わります。
本書が気になった方はぜひ読んでみてください。
よろしければサポートお願いいたします🙇♂️
