
日本ミステリー文学大賞の軌跡・第4回 笹沢左保(後編)|羽住典子
日本ミステリー文学大賞の第一回の選考は一九九七年十一月五日に行われました。
その後、昨年二〇二一年の第二十五回までに選考された受賞者の一覧は、戦後から現代までの日本ミステリー史をそのまま映し出しているといっても過言ではない、錚々たる顔ぶれです。
本企画では、作風と特徴、作家の横顔、いま読むべき代表作ガイドなど、第一回からの受賞者を一人ずつ特集します。
回を追うとともに、日本ミステリー史を辿っていきましょう。(編集部)
▶日本ミステリー文学大賞《これまでの受賞者》
▼前回はこちら
文=羽住典子(探偵小説研究会)
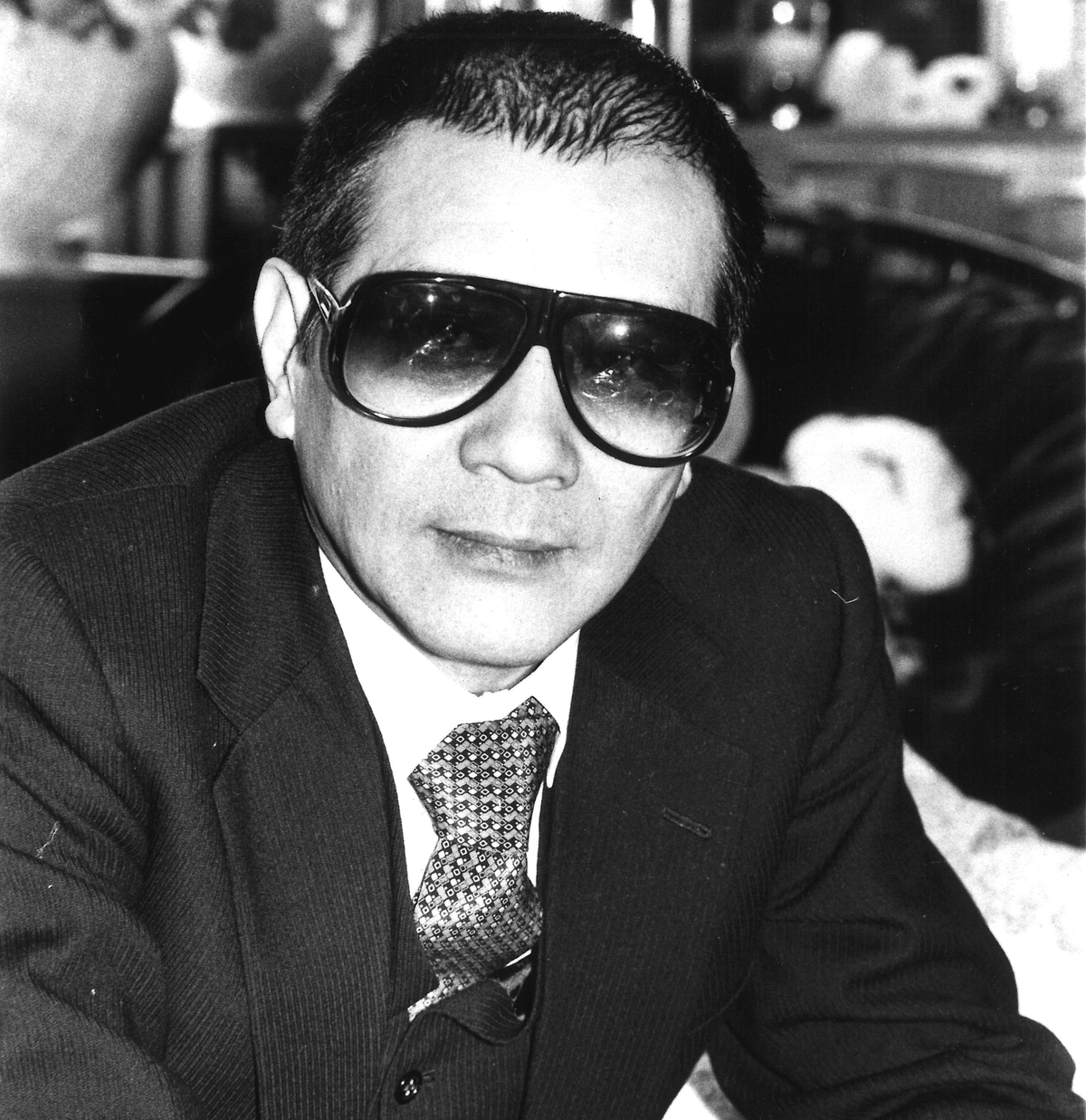
本稿前半の最後で、笹沢左保が出版社の人から指示された「笹沢が書くべき推理小説の三要素」について触れた。
一つめの要素は、「本格味を必らず作品の背景とするべきだ。本格派なのだから」。ここで言う「本格」とは、序盤で殺人事件が起き、推理をおこなう過程があり、解決に至るといった、現代では本格ミステリという名で受け継がれている骨組みを指す(言わずと知れた形式だが、SNS上ではいまだに定義論争が見られるので、この場を借りて断言する)。
本格には真相をごまかすためのトリックが絶対条件であり、なかでも笹沢は、有栖川有栖『マジックミラー』の作中講義で言及されているように、凄腕のアリバイ・トリックメーカーだ。
一九六一年に刊行された『空白の起点』(「宝石」連載時は『孤愁の起点』)は、男性が崖から突き落とされる姿を、主人公である保険調査員が走行中の列車内から目撃したことから物語が始まる。男性に多額の生命保険金がかけられていたことを不審に思った主人公は、独自に調査を開始する。警察が突き止めた容疑者は、投身自殺を図った。釈然としない主人公は、自分と同じ列車に乗り合わせていて共に目撃者となっていた被害者の娘と親しくなり、事件を追っていく。
『女は復讐する』というタイトルで一九六六年に映画化され、二〇一六年に二時間ドラマ化された本作は、数多のアリバイを使った推理小説群の中でも、ベスト級の作品である。真犯人の想像はつきやすいが、フーダニットよりもハウダニットとしての完成度が高く、すべてのピースがはまったときに感嘆の声をあげる人も少なくないだろう。「偶然に頼りすぎている」という批判をネット書評で見かけるが、人間の心理を操り、成功できると確信していた犯人の計算力に脱帽する。
翌一九六二年刊の『暗い傾斜』(一九八九年の徳間文庫版では『暗鬼の旅路』に改題)には、非常に珍しい類のアリバイトリックが登場する。親が遺した製作所を切り盛りする女社長の周辺で、二人の男性が殺害された。一人は東京、一人は高知県にある室戸岬で、同じ人物の犯行によるものと思われる。だが、二人の被害者の死亡推定時刻は数時間しか変わらない。容疑者として女社長が浮かび上がるが、彼女は犯行時刻に四国にいたと目撃されている。どうやって遠く離れた二つの殺人は成し遂げられたのか。
一九八二年角川文庫版のあとがきで「ムード小説としてこの作品を書いた」とあるように、女性の情念が推理小説という形式を通じてこれでもかというほど伝わってくる。いきなり事件が起きる笹沢作品にしては珍しく、第一章をすべて費やして女社長の背景を丹念に描いているが、この描写がなければ真相解明時の説得力は出せないだろう。投稿時代の作品にも遠隔地でほぼ同時に殺人事件が起き、容疑者にはアリバイがあるといった内容のものがあるが、そのアイデアを膨らませてムード小説に仕立て上げたことからも、作家としての成長がうかがえる。目的のために犯人はどう動いたのかという動機も当時は想像もつかない人が多かったと推測できる。真相を知ってから冒頭の一ページを読み返すと、哀愁感は増すはずだ。なお、本作はいかりや長介主演「取調室」シリーズ、賀来千香子主演「女取調官」シリーズでドラマ化もされた(「女取調官」では舞台を佐賀県に変更している)。
これらの二作品は、アリバイを崩して犯人を導き出す形式ではなく、どのようにしてこの人物に犯行がおこなえたかという、ハウダニットを主軸にした共通項がある。動機に納得ができ、心理的にも説得力があるため、倒叙形式の作品と同様の満足感を味わえる。
私的には、思いもよらない移動手段でアリバイを作り上げた、一九六七年刊行の『明日に別れの接吻を』を高評価している。主人公は、凌辱され自殺した妻の復讐として、犯人の男を殺害した。情状酌量が認められ執行猶予となったが、期間中に旧友が「人を殺した」と彼のもとを訪れ、「一緒にいたことにしてほしい」と懇願される。警察に知られたら刑務所に入らなくてはならないという状況下で、次々に周辺人物が殺害されていく。ミッシングリンクも特殊で、最後の最後まで気を抜けないサスペンス作品である。
アリバイトリックの陰に隠れがちであるが、笹沢は密室トリックでも良作を発表している。ベストワンといえる作品が、一九七八年に刊行された『求婚の密室』だ。著者のことばで笹沢は密室トリックに対し「使い古されたトリックの焼き直し」や「安易な機械的トリックにぶつかることが多い」と不満を述べ、本作を「初の密室トリックによる長編本格推理小説」と位置付けている。これまでに密室トリックの登場する作品はあったが、笹沢自身では、密室の謎を解くことが作品の主題ではなかったのであろう。
大学教授が自分の娘の婚約者を公表するために、十三人の男女を招待して、別荘でパーティーを開いた。しかし、翌朝、主催者である大学教授とその妻が、内側から南京錠のかかった地下貯蔵庫で遺体で発見される。死因は服毒死。心中説や他殺説が飛び交うなか、招待客の一人であるルポライターの天知は他の招待客たちの過去を暴いていく。現場に残されたダイイングメッセージの真相が明らかになった瞬間、これまでの伏線が一本の線でつながり、犯人を特定できるという過程が見事である。やはり本作でも、真実が明らかになったあとに浮かび上がる動機が感慨深い。
『求婚の密室』の探偵役である天知は、一九七六年度刊の『他殺岬』にも登場していた。あらすじは以下になる。天知の書いた暴露記事により、独自の痩身美肌法で人気を得ていた美容師が縊死した。さらに、妊娠中の娘ユキヨも後を追うように崖から飛び降りる。ほどなくして、ユキヨの夫と名乗る人物が、保育園に通う天知の一人息子を誘拐し、五日後に処刑すると脅迫電話をかけてきた。息子を助けるため、天知はユキヨの他殺の可能性から事件を追う。本書は金曜エンタテイメントで映像化もされたが、本放送のみで再放送はされていない。
アリバイと同様、笹沢作品に多いのが、誘拐ものにタイムリミットを加えたサスペンス作品だ。誘拐ものでは、一九七二年刊の『真夜中の詩人』で、特異なシチュエーションを手掛けていた。この作品もご多分に漏れず、人間の心理が絡み合うことにより意外性を高めている。
トリックもさることながら、実験的な作品も多く見られる。一九七五年『三人の登場人物』は主要登場人物を三人に絞り、可能性を積み上げて犯罪を成功させる「プロバビリティの犯罪」を成し遂げた。一九八一年刊行の短編集『どんでん返し』、一九八四年刊行の長編『同行者』(『悪魔の道連れ』に改題)は地の文は一切なし、会話だけで構成された物語だ。後者の会話だけで描いた官能場面は強烈なインパクトを与える。一九八一年刊『後ろ姿の聖像』(一九八四年講談社ノベルス版で『もしもお前が振り向いたら』に改題し、一九八八年同タイトルで講談社文庫化。二次文庫版は『魔の証言』に改題)は、謎そのものが変貌する男性バディもの。一九八七年刊『真夜中に涙する太陽 笹沢左保の名探偵』は、著者の笹沢自身が探偵役を務める。一九八九年刊『霧の晩餐 四重交換殺人事件』(『殺意の雨宿り』に改題)は、通常は一対一でおこなわれる交換殺人を、女性四人で企てる異色作だ。
本格に重点を置いた短編では、七つの事件が登場し、対照的な二人の男性刑事の推理劇が映える、一九八〇年発表の連作短編集『セブン殺人事件』がお薦めとして取り上げられているのを時折見かけるが、本稿では一九八四年の『殺人スクランブル』(『シェイクスピアの誘拐』に改題)を推奨したい。「シェイクスピアの誘拐――暗号と殺人」「年賀状・誤配――安楽椅子と殺人」「知る――倒叙と殺人」「愛する人へ――不在証明と殺人」「盗癖――動機と殺人」「現われない――人物消失と殺人」「計算のできた犯行――完全犯罪と殺人」「緑色の池のほとり――怪奇と死体」の八編が収録されている。得意の人間模様を抑え、謎を解くことに重点を置き、どの話も難易度は高い。特に語り手が誰かを当てる「知る」は、叙述トリックを用いた短編のベスト作に選ばれるだろう。「シェイクスピアの誘拐」と「年賀状・誤配」の暗号トリックは異色に感じられるが、一九六六年に刊行された『孤独な彼らの恐しさ』(『凍りつく欲望』に改題)など、文章が謎解きの決め手になる長編も初期の時点で存在している。
本格色の強い作風ではあるが、笹沢作品といえば、やはり「書くべき二つめの要素」でもある、「本格味とロマンの融合」だ。ちなみに「ロマン」とは、「甘美な筋をもった出来事」という意味を持ち、恋愛事件の「ロマンス」も同様に呼ぶ。また、「男のロマン」という表現は「変化に富んだ大冒険や一大事業」を指す。
この「ロマン」が、笹沢が大人気作家となった最大の要因であることは間違いない。例えば、一九六一年『泡の女』や一九六三年『突然の明日』では、これまでごく普通に暮らしていた人物が、身近な人の死によって思わぬ事件に巻き込まれていく。生活感を綿密に描いているので、読者は早期に主人公の視点に同化しやすくなる。殺人事件を追うといった非現実的な冒険の世界にいざなわれ、さらに協力者と恋に落ちるというロマンスも疑似体験できる。この物語構成が、推理小説にさほど明るくない者、たまに推理小説を手に取る者には、馴染みやすかったのだろう。死体を詳細に描かず、生きている人間の描写に力を入れているのも、好まれる理由だったはずだ。「推理小説は怖い」という思い込みから食わず嫌いになっている者にも薦めやすいからである。事実は定かではないが、刊行点数の多さに加え、当時なりの口コミで広く知れ渡ったと推測する。
編集者に指摘を受けた「男より女を描く方が馴れているらしいし、通俗性を持っているのも、ある意味では強味だ」という言葉も、笹沢作品の人気の一つになっているだろう。時代性の表れかもしれないが、笹沢の描く女性たちは、たとえ悪女であっても、淑女ばかりだ。しとやかで、男性を温かく受け入れ、支え、適切な助言をし、はっきりと描かれてはいないが容姿も美しいはずだ。だが、このような女性は実存するわけがない。「男性の理想の女を描くことに慣れている」ことが、笹沢の強味であったのだ。
一方、女性からしても笹沢作品の男性は魅力的に映る。普段はたくましいが、ふとした時に弱みや脆さが表れ、それによって母性本能を揺さぶられる。作中の男性たちに笹沢自身が投影されているのなら、生涯愛人がいたというモテぶりも非常に納得がいく。一九九一年『追越禁止 ドライバー探偵夜明日出夫の事件簿』から始まった代表シリーズのテレビドラマ版「タクシードライバーの推理日誌」で渡瀬恒彦が主役に抜擢されたのも頷ける。また、一九八一年『悪魔の部屋』は、官能小説でありながらも本格の要素をふんだんに使い、さらに性愛描写を使って男性の内側の良さを描いた傑作である。笹沢作品の女性読者をあまり見かけないが、主人公に共感を覚える女性は少なくないだろう。むしろ、笹沢は男性を描く方に慣れていて、男性必読の一冊といっても過言ではない。
ところで、中島河太郎は、角川文庫版『招かれざる客』の解説で、「新本格」をいちばん早く提案した人物は笹沢であるということに触れ、「謎解きだけにとらわれすぎた日本の推理文壇に、さわやかな新風をもたらした」と分析し、別の作品の解説では「天性の本格派」とも位置付けていた。笹沢自身も「謎解き中心主義であった本格推理小説に対し、ロマンと社会性を盛り、人間の設定にリアリティーをもたせた本格物の実現」を目指していたと語る。
だが、笹沢作品をリアルタイムで読めなかった世代ほど、この「新本格」という表現に違和感を覚えるに違いない。「新本格」といえば、一九八〇年代後半から一九九〇年代前半にかけて若手作家が続々とデビューし、出版点数も大幅に高まった一連のムーブメントのほうが馴染み深いからだ。特殊な状況下で、奇々怪々な不可能犯罪が起き、頭脳明晰で破天荒な名探偵が解決するといった作風の旋風が起きた。笹沢の理想とする「リアリティー」とは真逆の流れが生じたのだ。
ムーブメント発生当時、「人間が描けていない」という批判が起きた。一方で、謎解きに関係のない人間模様など不要だと捉える本格読者も一定数いることも事実ではある。しかしながら、どちらの形式も本格の枠組み内であるため、人間が描けているか否かで作品の甲乙をつけること自体がナンセンスだ。笹沢が人間の数だけ事件が存在するかのごとく作品を生み出し続けてきたように、|善し悪しの判断は受け手となる個々人によって異なる。
ただし、角川文庫版『暗い傾斜』の解説で中島が指摘したように、本格には弱点が存在する。中島は詳細に述べていなかったが、謎を解く必然性のことを指しているのだろう。なぜ、謎を解かねばならないのか。この問題に対し、笹沢は人物の行動心理にリアリティーを持たせることで、解答をしている。事件を起こした犯人たちの動機に説得力があり、かつ魅力的であるのも、人間を描いていたからであろう。
一方で、笹沢には探偵役をメインに据えたシリーズが書きにくいという弱点もあった。「取調室」シリーズや先に述べた「夜明日出夫」シリーズがあるが、犯罪に関わりやすい職業、あるいは元職業だからなし得たことだ。ごく普通の人物が数々の事件に巻き込まれることを小説化するのは難しいと、笹沢の歴史を知ると痛感できる。
以上、駆け足で述べてきたが、クイズ番組にレギュラー出演するなど、当時の作家としてはあまりいない流行作家であった。晩年は、木枯し紋次郎の出生地である三日月村との縁を感じ、佐賀県の三日月町の病院で療養生活に入る。退院後は隣接する富士町に自宅を構えて一時的に移り住み、九州さが大衆文学賞(笹沢左保賞)を創設し、運営にも携わってきた。彼を敬愛する有栖川有栖が初代会長を務めた本格ミステリ作家クラブの会員でもあり、本格ないしは小説を受け継ぐことに対して、積極的に活動をおこなってきた。
二〇〇二年、七十一歳で逝去した後もしばらく賞は続き(二〇一七年終了)、富士町の自宅は記念館となっている。全著作三八〇冊の展示に加え、遺稿となった『海賊船幽霊丸』も閲覧できる。親友である森村誠一がそのまま補筆をした原稿用紙は、本格を通じて人間の孤独を描いてきた笹沢への報いが形になったかのように感じられる。
(第4回 おわり)
《ジャーロ No.87 2023 MARCH 掲載》
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
この記事が参加している募集
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
