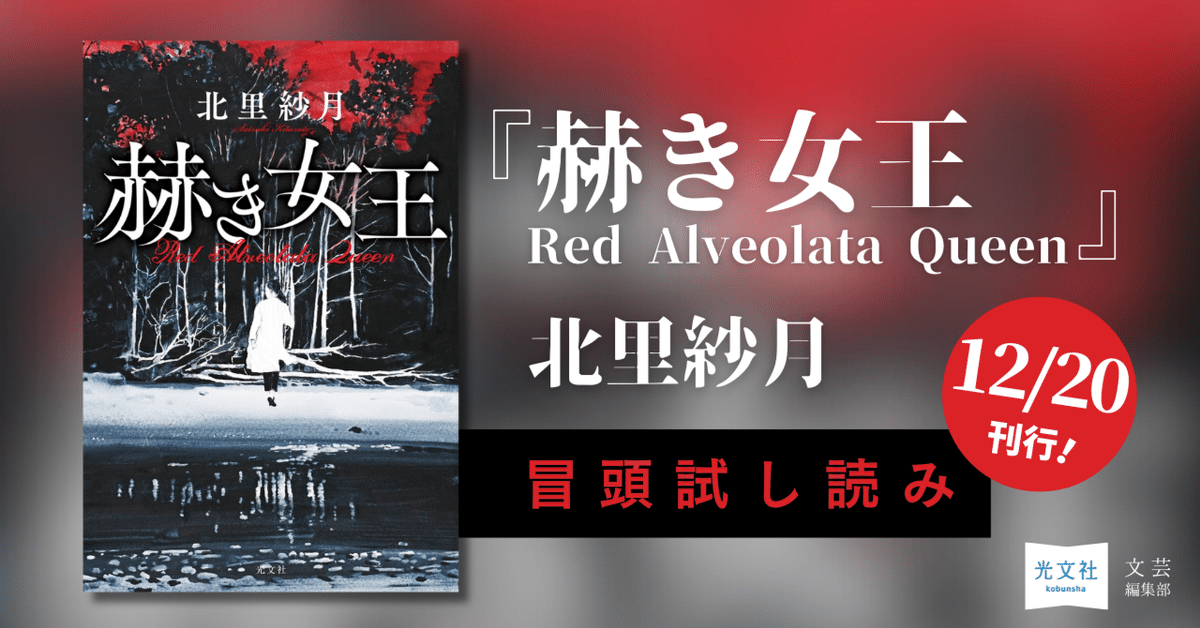
熱帯の無人島で起きた集団怪死事件から始まる、極限のバイオパニックホラー‼【冒頭公開】12/20発売・北里紗月『赫き女王 Red Alveolata Queen』
2023年12月20日(水)発売の新刊『赫き女王 Red Alveolata Queen』(北里紗月・著)より、冒頭を試し読み公開します。

北里紗月『赫き女王 Red Alveolata Queen』
プロローグ
サファリハットを被った男は、目の前に広がる鬱蒼としたマングローブ林の奥に視線を向けた。太陽は昇り始めたばかりだが、左手を流れる川の水面を眩しく照らしている。
森を形成するオヒルギとメヒルギの根元は、むき出しになった太い根が無数の足に見え、まるで木々が歩き出そうとしているかのようだ。さらに男の足元では土中から、いくつもの根が突き出し、空に向かって奇妙な突起を形成していた。
マングローブ林は熱帯地域の汽水域、川と海の合流地付近に広がる特徴的な森林だ。土中から伸びた根は呼吸を行う役割を持ち、よく見ると、その呼吸のための根は全て同じ高さだと気が付く。これは満潮時の水面の高さとほぼ同じになるため、森のどこまで水が入り込んでくるかの目安となる。つまり、男が立っている場所も数時間後には水中に没するのだろう。
男は額の汗を拭うと、右手に持った麻袋を両手で抱え直した。男が抱きかかえる麻袋は、箱型のシルエットをしている。ぬかるみに足を取られているのか、男の表情には疲労の色が濃い。
額から流れる汗は、男の頰を伝って地面に落ちていった。
男は土の上に麻袋を下ろすと、袋の中を魅入られたように見つめ続けている。
その瞳から疲れの色は消え去り、徐々に妖しい熱で満たされていく。どれほどそうしていただろうか、悲鳴のような鳥の声が森に響いた。
男は我に返ったように周囲を見回してから、足元の麻袋をゆっくりと持ち上げた。そして、気力を振り絞るように大きく息を吸い込むと、泥に埋まった足を引き抜き、一歩一歩森の奥へと進んでいった。
熱気を含んだ森の中は男の他に人影はなく、互いの存在を確かめるような鳥たちの歌声で満たされていた。
一章 楽園島
日本最南端の島、瑠璃島。東京から南に千七百キロメートル、九州・パラオ海嶺の中央に位置する、サンゴ礁に囲まれた楽園のように美しい無人島だ。周囲約四十キロメートルの見事な円形の島の中央には、熱帯の木々に覆われた標高四百五十メートルの白山がそびえる。近隣の島や大陸から数百キロは離れているため、これだけの大きさがありながら、大型の哺乳類はいない。捕食者がいないため、瑠璃島は鳥類の楽園でもある。年間の平均気温は二十七度。今日は一月五日だが、昼になれば東京の夏とほぼ同じ暑さになる。
高井七海は緩やかな坂を下りながら、右手に広がるパイライトグリーンの海を眺めた。当然と言えば当然だが、見渡す限り水平線が続く。
砂浜は砕けたサンゴで出来ているため純白で、強い日差しを跳ね返している。
手つかずの熱帯の森と美しい海が広がる瑠璃島は、リゾート開発をすれば大勢の観光客が見込めるだろう。だが、この島にあるのは無機質で華やかさのかけらもない研究所だけ。七海はこの瑠璃島海洋生物総合研究所の准研究員となって九ケ月となる。
国立研究開発法人海洋研究開発機構、JAMSTECが三年前に巨額の費用をかけて建設した瑠璃島海洋生物総合研究所。瑠璃島の中で、唯一船が着岸可能な海岸線の正面に立つ研究所は地上五階建だ。飾り気のない白い建物は中規模の病院によく似ているが、内部には最新鋭の研究機器が設置されている。さらに食堂やシャワー室など、研究員が長期にわたって生活出来るように設計されている。
この研究所は所長に桐ケ谷杏上席研究員を置き、以下二十五名の生物学者がそれぞれの研究を行っている。女性の研究者が施設のトップを務めるのは、日本国内において非常に珍しいだろう。
この研究所が掲げる研究目標は、大きく分けて二つ。一つ目は瑠璃島周辺海域に存在するホットスポットの生態系の解明と海洋生物資源の有効活用。二つ目は大陸から離れた瑠璃島特有の生態系の研究と保全。
ホットスポットとは周辺海域に比べ、生物の個体数や種類が多く保たれている場所を示す。日本周辺の海は、世界的に見てホットスポットが多数存在する貴重な海域だ。
一見すると、環境保全を前面に押し出した研究所のようだが、実際は海洋生物資源の有効活用が主目的となる。多額の資金を出してまで研究所を設立する意味はとても単純で、それ以上の利益を出せるからだ。
つまり金になる。
海に生息する生物が持つ様々な化学物質は有効な薬の材料になる。例えばイモガイが持つ神経毒は種類が多く、ものによってはモルヒネの千倍もの鎮痛作用を持つ。天然材料を元にした薬の多くは植物由来が多いが、海洋天然物は薬としての調査や研究開発の歴史が浅く、莫大な富を生み出す物質が新たに発見される可能性が高い。
海綿動物に含まれる成分から皮膚がんやアルツハイマー病の治療薬、アメフラシ、ホヤ、ソフトコーラルからは抗がん剤、その他にも抗ウイルス薬、抗炎症薬などが発見されてきた。
これらの新規物質を発見するためには、瑠璃島周辺のように、多数の生物が生息していることが有利になる。
桐ケ谷杏は、瑠璃島周辺海域にあるホットスポットを今から八年前に発見した。それだけでも大変な功績だが、その後、杏は次々と新規の有効物質を発見し続けた。ホットスポットの発見から三年後、杏は当時所属していた大学を退職し、JAMSTECに引き抜かれるようにして研究の場を移していった。
杏がJAMSTECに就職した二年後に瑠璃島海洋生物総合研究所が完成した点を考えると、大学を辞める条件が研究所の所長の席だったと考えられる。
七海は理学部生物学科の大学院の博士課程を修了し、昨年の四月より、准研究員として働いている。これは本当に運が良かったとしか言いようがない。
七海はこの研究所に就職するきっかけとなった日のことを思い出していた。
理学部生物学科の大学院で博士課程の道に進んだ七海は、女性の研究者が直面する現実的な問題に頭を悩ませていた。卒業まで半年となった時点で、博士論文用の研究はめどが立ったというのに、その後の就職先が決まらないのだ。
博士課程修了時の七海は二十七歳。女性であれば結婚を意識し、その先に妊娠や出産が控えているとみなされる年齢。七海自身がどのような結婚観を持っていようがいまいがそこはあまり問題にならないようだ。一般的な企業では、どう足搔いても敬遠されてしまう。
研究者の道に進む場合は、大学の教員になるのが一つのパターンだ。こちらは一つ募集がかかれば、数十人の華々しい経歴を持った研究者が集まる狭き門だ。その他には企業や公的な機関が、研究プロジェクトごとに科学者を公募するシステムがある。こちらの場合、給料は非常に良いのだが、雇ってもらえる年数が三年程度と短く次の保証は全くない。
その上、結果が残せなければ役立たずの烙印を押されてしまう。このため、研究職に就く者は泊まり込み、徹夜は当たり前の世界だ。女性の体力では不安が残る、と思われてしまうのが悔しい。
三十六時間までなら、七海でも連続で実験を行うくらい可能なのに。
七海自身は棘皮動物が体内で作り出す、毒性の強いたんぱく質の研究を行ってきた。具体的な研究対象はオニヒトデに含まれるDNA分解酵素なのだが、マイナーすぎて研究の価値をなかなか理解してもらえない。いくら説明しても、オニヒトデしか覚えてもらえないことが多い。
一人暮らしのアパートで、日曜日の朝から鬱々とパソコン画面を見ていた。就職情報ばかりチェックしていると気分が滅入ってしまう。気晴らしにJAMSTECのホームページを開くと、そこに職員募集の文字を見つけた。
春先にチェックした際には、今年度の採用は予定していないと書いてあったはずだ。急いで目を走らせていく。
勤務地は瑠璃島という離島にある研究施設で、正規の職員としてJAMSTECに就職出来る。それ以上に、七海が希望していた研究職でもあった。
ホームページにある募集要項に目を通し終えてから、プロジェクトの内容を紹介しているページに飛んだ。
「母なる海から世界を救う薬品を」
そこに書かれていた文言以上に、白衣を着てほほ笑む女性に目が釘付けになった。プロジェクトリーダー桐ケ谷杏。ショートヘアの黒髪に、わずかに離れた大きな瞳。鼻筋の通ったすっきりとした顔立ちは中性的な魅力があった。
間違いない。七海は本棚に走ると、色が褪せてしまった子供向けの科学雑誌を取り出してきた。全部で十二冊。七海が小学校六年生の頃に、親が定期購読させてくれた雑誌だ。七海は雑誌を開くと、そこに微笑む女性の顔をパソコン画面の横に並べた。髪型こそ違うが、見間違えようもない。生物学者のアン先生だ。
この雑誌の中で七海が夢中になっていたのが、生物学のコラムだった。身近にいる生物の話題や最新の研究まで、子供が分かりやすいように解説されていた。このコラムを担当していたのが、桐ケ谷杏だったのだ。
七海が生物学の道に進むきっかけとなったこの雑誌は、今でも大切に保管してある。あの時のアン先生が、今はJAMSTECの大きなプロジェクトを任されているのだ。鳥肌が立つような感動を覚えた七海は、すぐに履歴書の準備を始めた。
結局、四名の募集に対して三百名を超える応募があったようだ。面接や書類による審査は一般的だが、面白いことに健康診断が必須項目にあげられた。理由としては、島という限られた空間で長期滞在するストレスに耐えうるか、という点らしい。
体力や健康に自信はあったものの、さすがに何の実績もない七海が選ばれることなどないだろう。そう考えて開き直ったのが良かったのかもしれない。
最終的に、桐ケ谷杏は七海を選んでくれた。運命などという非科学的な言葉は嫌いだが、これに関してだけは信じてみたい。
「七海、おはよう。何、ぼうっと海眺めているの。まさか飛び込む気? ウミヘビは陸で休んでいるから大丈夫だと思うけど」
振り返ると、同僚の三上桃子が満面の笑みを浮かべて七海を見ていた。
彼女も七海と同じ採用枠で選ばれた准研究員だ。
艶のある黒髪を一つにまとめ、カーキ色のハーフパンツと真っ白なTシャツから伸びる長い手足が眩しい。化粧はほとんどしていないようだが、猫のようによく動く瞳が印象的だ。
「昨日定期船が食料品を届けてくれたから、何か珍しいものあるかも」
「桃子はいつも食べ物のことばかりね」
そう言って笑うと、桃子は当たり前じゃない、と大げさに両手を広げてみせた。
「この素晴らしき、南の楽園に唯一足りないものは料理人よ。頭脳明晰な生物学者は沢山いるけど、皆料理下手じゃない。日本の研究施設にしては珍しく女性が多いのにさ」
「そうね。所長の桐ケ谷さんも女性だからかな」
「というよりさ、桐ケ谷所長は実力主義でしょ。男だろうと女だろうと仕事の出来る研究者を呼び寄せて、結果を出せないならそれまで。ちょっと近寄り難い時もあるけど、分かりやすくて私は好きよ」
屈託なく笑う桃子を見ていると、ちくりと胸が痛んだ。桃子は生態学者で、専門は鳥類。二十八歳にして既に輝かしい研究成果を上げている。桃子は大学に入学すると同時に持ち前の行動力を生かして、絶滅の危機に瀕しているアホウドリの保護活動を行ってきた。保護と聞くと、ただ見守るイメージがあるが、桃子の活動はより積極的だ。離島に生息するアホウドリの個体数を増やすため、繁殖場所を移動させるなどの介入を行うのだ。
この約十年に及ぶ研究活動の成果が認められた桃子は、種の保全に貢献した研究者に贈られる、日本学士院エジンバラ公賞を昨年受賞した。杏の目に留まるのも頷ける。
「何にせよ、あれは桐ケ谷さんの城だからね」
桃子は坂を下りた先に見える、南の楽園には不似合いな白い建物を指さした。
「さ、早く行こう。私、ちょっと桐ケ谷さんに話があるのよね」
潮の香りを孕んだ湿った風が七海の頰に当たる。やはり今日も暑くなりそうだ。桃子は七海を追い抜いて、坂を下り始めた。
「アホウドリがね、繁殖場所にいないのよ」
「それは何かまずいの?」
「やだ、年に一度の繁殖期よ。だから年末年始もここにいたのにさ。まったく、今この島に残っているのなんて、筋金入りの実験馬鹿しかいないじゃない」
瑠璃島の研究所では、常時二十名以上の研究者がそれぞれの仕事を進めているが、年末に帰宅した者が多く、現在は七海と桃子を入れて十名が残っている。居残りメンバーの顔を思い浮かべ、思わず笑みがこぼれた。
適当な歌を歌いながら歩く桃子の横に並び、二百メートルほどの通勤を終えて研究所を見上げる。他に人工建造物がないので巨大に見えてしまうが、街中にあれば、中規模の総合病院程度の大きさだろうか。正面には大きなガラス張りの自動ドアが設置され、見た目も病院によく似ている。七海たちより先に来ていた男性の職員が入り口の前で何やらカバンの中をかき回している。職員証でも探しているのだろうか。
「高井さん、三上さん、おはよう」
准研究員の真島裕斗が、七海たちに気付いて右手を上げた。真島も七海と同じ採用枠で就職したスタッフだ。年齢は三十歳なので、年上だが気さくに接してくれる。学生の頃ラグビーをやっていたらしく、とにかく体が大きい。身長も百八十センチ近くあり、胸板も厚く、目の前に立たれるとかなりの圧迫感がある。これだけ大柄な真島だが、研究対象は海洋微生物というのもなかなか愉快だ。
「職員証ですね? 今開けますよ」
「いや、悪いね。すぐカバンの中で行方不明になっちゃって」
七海はショルダーバッグから取り出したカードを読み取り機に当てて、自動ドアを開けた。研究所内は空調が効いていて、一気に体に浮いた汗が引いていく。
正面入り口前は五階まで続く吹き抜けのホールになっている。右手に向かうと食堂があり、左手は医務室と休憩室、正面の廊下の両側は多目的室と会議室が続く。廊下の突き当たりは実験動物を飼育する、動物舎になっている。
研究所の二階より上は、研究員が自由に利用出来る実験室がある。瑠璃島海洋生物総合研究所の実験プロジェクトは多岐にわたるため、使用目的に合わせた特殊な実験室も整っている。室内全体を低温に保った実験室、無菌状態の実験室、放射性標識化合物などを使用する区域、人体に有害な病原菌などを扱う減圧室、などだ。最上階の五階には、共用スペースの他に所長室があり、隣接する部屋は杏が使用する個室になっているそうだ。
また、設備面も恵まれていて、塩基配列を決定する次世代シークエンサーや、電子顕微鏡まで設置されている。
七海は毎朝このホールに立ち、施設全体を眺めていると誇らしい思いが溢れてくる。それから気を引き締めて実験に臨むようにしている。
普段は職員が行き来しているのだが、先週からは建物全体が静まり返っていた。
「真島君も、一緒に朝ごはん食べましょうよ。昨日船が着いたから、きっと美味しいものがありますよ」
最後に入って来た桃子の声がホールに響く。食事前の桃子は普段にもまして、楽しそうだ。
「それはいいね。まあ、俺はレトルトのカレーがあればいいや」
「さすがに飽きませんか? 今晩当たり久しぶりに有志で食事作りましょうか」
「三上さんの料理は男気が満点だよね。なんというかキャンプ飯?」
真島と桃子は笑いながら、食堂に向かった。全職員がいる場合は、当番制で食事を用意しているのだが、休みに入ってからは各自が自分の分を用意している。桃子の言うように、料理好きは少ないようで冷凍食品やレトルトばかりに走りがちだ。比較的大きな厨房があるのにもったいない話だ。
食堂の扉を開けると広い空間に、副所長の沖野研と同期の長瀬心美が向かい合わせで朝食をとっているところだった。三人に気が付いた沖野は右手を軽く上げる。研究所内で白衣を着ている職員はほとんどいないのだが、沖野は常にしわ一つない白衣をきっちりと身に着けている。杏より年下で、確か三十代の半ばだったはずだが、やや垂れた目でいつもにこやかにしている姿は年齢より落ち着いて見えた。
沖野と心美は、トーストとコーンスープにカットしたオレンジ、飲み物はコーヒーというお揃いのメニューだ。三人は食堂の奥にある厨房に向かい、各自冷蔵庫とパントリーの中身を漁った。瑠璃島に生活物資と食料品を運んでくる船は、週に一度なので生野菜が不足しがちだ。冷蔵庫にトマトがあったので、それを適当に切ったサラダと、焼いたベーコンとヨーグルトにバターロールを盆に載せ、紅茶を淹れてから食堂に戻った。真島は心美の隣に座り、宣言通りレトルトのカレーライスをせわしなく口に運んでいる。七海は挨拶をしてから、沖野の隣に腰を下ろした。
最後に厨房から戻ってきた桃子の盆には、たっぷりの蜂蜜とバターとチョコレートソースをかけたホットケーキの皿と、冷凍のミックスベリーを入れたヨーグルトの入ったサラダボールと牛乳が並んでいた。さすがに、蜂蜜とチョコレートソースは激しく甘そうだが、桃子にとっては丁度よいらしい。
沖野も蜂蜜の上にかけられたチョコレートソースを見て、驚いている。
「三上さん、それ作ったの? すごいね」
「冷凍ホットケーキですよ。解凍しただけ。先週お願いしといたんです。沢山あるので、皆さんも適当に食べて下さい」
桃子は七海の隣に腰を下ろすと、チョコレートソースと蜂蜜の滴るホットケーキを口に運び始めた。
「桐ケ谷所長は、もう来てらっしゃいますか? 少し相談があって」
「所長室にいますよ。確か、論文をチェックしていたはずだから」
論文という言葉が耳に入り、思わず沖野の顔を見つめてしまった。
杏が今読んでいるはずの論文は、おそらく七海がこの九ケ月かかりっきりになっていた研究のデータだ。オニヒトデから抽出した抗血液凝固因子についての内容で、受理されれば七海が世界で初めて発見した新規物質として認定される。
「ああそうか、七海の論文ね。アクセプトされたらお祝いしないと」
「それはいいね。桐ケ谷所長も、良いデータだと喜んでいたからきっと問題なく受理されますよ」
桃子と沖野の言葉を聞くと、本当に報われた気がする。
心美は持ち上げたコーヒーカップを盆に戻してから、七海を見た。年齢は七海より二歳ほど上だが、身長が百五十センチに届かないため、真島と並ぶと大人と子供のようだ。
「七海さんが同期の中で、一番早く結果を出せそうね。本当におめでとう」
「実は、同じ内容の研究をしているグループがあって、焦っていたんです。昨日、論文をチェックしたからまだ先は越されていないはずです」
科学の世界はどうしても研究内容が重なるので、受理された日付がたった一日違うだけで、発見者の栄誉を取られてしまうのだ。こうなってしまったら、到底諦められるものではない。
真島は、七海にお祝いの言葉を言いながらも、カレーライスを食べる手を止めていない。そろそろ食べ終えてしまいそうだ。
「俺は今日ちょっとこの後、海岸に出てサンプル採集してきます」
「私も、アホウドリの繁殖場所まで行ってくる。何か分かるかもしれないから」
桃子は皿に残ったホットケーキのかけらを次々と口へ放り込み、ヨーグルトを幸せそうに食べ始めた。
全員が朝食を食べ終えてから、食器を洗い食堂を出た。七海は四階にある実験室で、昨日から続けている実験を行う予定だ。
正面玄関前のホールまで桃子を見送り、エスカレーターに向かおうとした時、ショルダーバッグの中に実験ノートが入っていないことに気が付いた。自分の個室の机の上に置いてきてしまったのだろう。エスカレーターに向かう沖野と心美が、七海の様子を気にしている。
「ごめんなさい。ちょっと忘れ物をしたので、一度部屋に戻ります。どうぞお先に」
七海は踵を返すと先を歩く桃子の背中を追った。自動ドアが開くのとほぼ同時に桃子と真島に追い付いた。潮の香りが体にまとわりつく。
「部屋に忘れ物しちゃって」
「ラボ組は暑さ慣れしていないから、外歩きは短時間でも注意した方がいいですよ」
真島の言葉通り、一歩建物から出ると刺すような日差しに目が眩む。桃子は立ち止まって、眩しそうに空を見上げている。
返事を返そうと真島に顔を向けると、突然海から強い風が吹き、金属のバケツが派手な音を立てて転がっていった。
と、次の瞬間、三歩前に立っていた真島の上に大きな影が降ってきた。湿った鈍い音と同時に、土埃が七海の顔に当たる。乾いた土の臭いに混じりかなくさい臭気が加わる。
思わず閉じた目を開けると、動かなくなった真島の上に額が大きく裂けた誰かが覆いかぶさっていた。何が起きたのか、全く理解が及ばない。虚ろな瞳で空を向いている真島の上に、まるで恋人が寄り添うように女性が乗っている。裂けた皮膚の隙間から青白い頭蓋骨が覗き、そこから赤黒い血液が溢れている。鼻は無残に歪んでいるが、よく知っている女性だった。
海洋微生物学者の是永奈緒だ。昨日、帰り際に言葉を交わした。何について話したかどうしても思い出せない。
ああ、間違いなく奈緒だ。真一文字に裂けた額から溢れる血液が、瞼のくぼみに集まり、赤い涙のように頰を伝っていく。奈緒から流れた血の涙が、真島の逞しい首筋にぽたぽたと落ちた。
目の前で起きていることを理解する前に、全身の力が抜けていった。気が付くと血で汚れたコンクリートの上にしゃがみこんでいた。
真島君が動いていない。奈緒さんも、あんなに酷い怪我をして。頭から血を流している。奈緒さんの傷。ああ、二人とも息をしていない。心臓マッサージをして助けを呼んで。血を止めなくちゃ。誰か助けを呼びに戻らないと。
不意に沖野の笑顔が脳裏に浮かんだ。研究所に戻って、沖野を呼ばなければ。
どうしても息が上手く吸えない。苦しい。胸が痛い。
過剰に空気を吸い込む自分の呼吸音が耳に流れ込んでくる。早く助けなければ。二人が死んでしまう。早く。ああ……息が出来ない。どうして……
「七海! 危ない!」
桃子の叫び声と同時に衝撃が走り、突き飛ばされ地面を転がった。世界が回転し、ようやく息を吐く動作を思い出した。
這いつくばりながら視線を上げると、一瞬前まで七海がしゃがみこんでいた場所に男が落ちてきた。重く鈍い音が周囲に響く。
目を逸らす間もなかった。男の頭部がコンクリートにぶつかり大きく歪む。首は衝撃で折れ曲がり、陥没した頭部から流れ出した血液が白いコンクリートに広がっていく。血だまりの中に、青白い骨片がオブジェのように転がっている。
十秒前までは確かに生きていた人間が、今はただの塊と化していた。
女性の叫び声がずっと続いている。桃子だろうか。それにしても、何と凄まじい声だろうか。まるで耳元で叫ばれているようだ。
至近距離から聞こえて来る女性の叫び声が自分のものだと気が付くまでしばらくかかった。これは何。何が起きているの。悲鳴がうるさくて思考が全くまとまらない。叫ばないで。助けないといけないの。でも、頭蓋骨があれほどへこんでしまったら、どうしたらいい。それにあれは骨? 頭蓋骨の一部が欠けてしまったの? 応急処置は……何を優先すれば。いい加減静かにしてよ。沖野を呼ばなければ。
不意に研究所の自動ドアが開き、中から心美が飛び出してきた。目の前に広がる惨状を見た心美が悲鳴を上げる。
「駄目よ! 下がって!」
一瞬上を向いた桃子が、立ち上がって叫び声を上げる。驚いた心美が一歩下がると、そこへ大柄な男が落ちてきた。重量感のある低い音に何かがきしむ、胸の悪くなる音が混じる。鼻を突く血の臭い。心美の金切り声。あれは、あれは誰。地面に頭から落下した男は、首が完全に折れてしまったようで、肩と側頭部が密着していた。彼がこちらを向いていたら、完全に意識を失っていただろう。わずかな時間を置いて、地面に叩きつけられた男の体の下に、血だまりが形成されていく。
心美は地面に転がったまま、甲高い悲鳴を上げ続けた。
ああ……息が上手く吸えない。
肺が焼けるように苦しくなり、喘ぎながら空を見上げると、屋上の柵から身を乗り出し、七海を見下ろす人影があった。黒髪のショートヘアに白い頰。その目は異様に見開き、まるで黒い穴のようで感情が読めない。
間違いない。あれは桐ケ谷杏だ。こちらをじっと見つめていた杏の体は、さらに柵の外に垂れてきた。白く細い腕が何かを求めるようにこちらに向けて伸ばされる。
「止めて……止めて! 桐ケ谷さん! 危ないから止めて下さい! 嫌!」
桐ケ谷杏の体が突然視界から消えた。良かった。
安堵した次の瞬間、白い影が空に舞った。
ロイヤルブルーのフレアスカートが澄み切った空に広がる。なんて美しい。
白衣が、まるで鳥の羽のように風を受けながら、桐ケ谷杏が空から落ちてきた。
医務室のベッドから上半身を起こすと、七海は激しい眩暈に襲われた。目を閉じて膝を抱えてゆっくり呼吸を続ける。屋上から落ちて来る杏の姿を思い出し、激しい吐き気を覚えたが、もはや胃に何も残っていない。
目の前で落下する杏を見た七海は、意識を失ってその場に倒れてしまった。沖野と、桃子が七海を抱きかかえて医務室に連れてきてくれたようだ。わずかだが、二人が七海の名前を何度も呼んでいた記憶がある。
壁に掛けられた丸時計は十一時を指している。あれから既に三時間が経過してしまったようだ。一体、何が起きたのか。真島は無事だろうか。杏はどうなったのだろうか。
不意に扉をノックする音が聞こえ、桃子が入って来た。後ろに沖野の姿もある。
「大丈夫? 具合はもう良くなった」
「あの、真島君の怪我の具合はどうなの?」
七海の言葉を聞いた桃子が、ため息をついて沖野を見た。男性にしては色白の沖野の顔色は疲労の色が濃く、わずかに垂れた優しい目も落ちくぼんで見える。それでも普段と変わらず、しわ一つない白衣を身に着けている姿は七海の心を落ち着かせてくれた。
「残念ながら真島君は助からなかった。気休めにもならないだろうけど、首の骨が折れていたからほとんど即死に近い状態だったのだと思う」
「そんな……桐ケ谷さんは? 桐ケ谷さんはどうしているの」
桃子はベッドの端に座ると、七海の右手を両手で包み込むように握った。沖野は一度短く息を吸い込んでから、覚悟を決めたように七海の目を見る。
「本当に残念だが、桐ケ谷所長は亡くなった。屋上から転落した四名と、巻き込まれた真島君の合計五名が死亡してしまった」
「噓よ……事故ですか?」
知らぬ間に涙が次々とこぼれ落ちて行く。杏が死ぬはずない。
落ち着いて、と桃子が両手に力を込めた。空に広がる白衣が脳裏に浮かぶ。
沖野の目が七海を真っすぐ見つめた。
「桐ケ谷所長たちが転落した理由は私にも分からない。念のため屋上に行って調べたが、争った形跡はなかったよ。東京の本部と警察には電話で連絡してある。三日後には迎えの船が来るから、それまでは静かに待つしかない」
「ご遺体は二階の低温室に運んであるの。私が言うことじゃないけど、少なくとも桐ケ谷さんは自発的に飛び降りたように感じた。理由は本当に分からないけど」
自発的? 噓。心が乱れてしまい、反論の言葉が上手く発せられない。ただ涙だけが頰を流れ、体が震えてしまう。
「大丈夫かい? 無理しなくても良いのだけど、これから小会議室で今後の方針を伝えるから、来てもらえるかな」
「はい。大丈夫ですから」
桃子が差し出してくれたティッシュを受け取り、涙を拭った。呼吸を整えてから立ち上がる。わずかに眩暈を感じたが、どうにか歩けそうだ。
桃子の腕に摑まりながら医務室を出て、同じ一階にある小会議室に向かう。廊下の大きな窓の外は、昨日と何も変わらず明るい日差しと木々の緑で溢れている。その全てに現実感がなかった。
沖野と桃子に続いて小会議室に入る。中央に長机と椅子が十脚置かれただけのシンプルな部屋だ。そこには心美と門前圭吾が並んで座っていた。
植物学者の門前は研究室で最も年上で、若い研究者からも慕われていた。研究の話題になると、まるで小さな子供のように目を輝かせていた門前だが、今はすっかり憔悴しきっている。心美にいたっては、小さな体から魂が抜けてしまったように正面をぼんやりと眺めていた。
沖野が心美の正面に座り、桃子と七海はその両脇の椅子に腰を下ろした。今朝までは十人の職員が確かに生きていたというのに、今この島にはこの五人しかいない。
沖野は全員の顔を見回してから、大きく息を吸い込んだ。
「これから、これまでの経緯と今後の方針について説明する。まず、屋上から落下した四名の職員は、桐ケ谷杏所長、是永奈緒研究員、水野淳研究員、落合俊介研究員。そして落下した職員と接触した真島裕斗准研究員の五名が残念ながらお亡くなりになった。ご遺体は二階の低温室に安置した。この状況は東京の本部と警察に通報してある」
沖野は一度言葉を止めたが、誰からの発言もない。門前はその場に居合わせなかったが、おそらく遺体の移動などを手伝ったことだろう。ここにいる全員があの悲惨な事故を目の当たりにしている。
「私たちを東京まで運んでくれる船は三日後に到着する予定だ。それまでは業務を停止して、各自、可能な限り自室か一階で過ごして欲しい。なお、警察から、遺体と亡くなった職員の個室には近づかないように、とのことだ。今後、何があったのかの調査は一切警察に委ねる。みだりに故人の持ち物に触ることは、証拠保全の観点から控えて欲しいとのことだ」
沖野の事務的な言葉からは、一切の反論を受け付けないとの決意が感じられる。けれど、七海にはどのように考えても杏が自らの意思で自殺をするとは考えられなかった。
「桐ケ谷さんは自ら死を選ぶような人ではないです。桃子も沖野さんも、桐ケ谷さんがどれだけ研究に夢中だったか知っていますよね」
「でも桐ケ谷所長は、明らかに柵を飛び越えて落ちてきたと聞いています」
沖野は桃子を見てから静かに言った。
杏にとって、この研究所は安定した大学の職を辞してまで手に入れた自らの城だ。簡単に放り出すはずはない。
「昨日は桐ケ谷所長と、提出する論文の最終的なデータについて確認作業をしました。そんな人が自殺をしますか?」
聞いて、と桃子が七海の顔を覗き込むように見つめてきた。切れ長の目に涙が浮かんでいる。
「例えばお酒を飲んでいたとか、おかしな薬を間違えて飲んだとか、もしかしたら本当に死にたかったのかもしれない。でもそれは、今ここで確かめられないでしょう。私は少し離れた場所にいたからよく見えたの。屋上から落下した職員は全員、自分の意思で飛び降りているように見えた。誰かが突き落としたのでもなければ、柵が壊れていたわけでもない。これが事実よ」
「違う。お酒も薬も飲んでなんかいない」
不意に言葉を発したのは心美だった。焦点の定まらない瞳を見ていると、こちらの心まで壊されてしまいそうだ。桃子が心配そうに心美を見る。
「心美さん、何か知っているんですか?」
「朝、桐ケ谷所長と是永奈緒さんに会ったのよ。奈緒さんの話だと、島の少し沖合に赤潮が発生したらしくて。屋上に上れば、確認出来そうだと言っていた。それを聞いていた水野さんと、落合さんが興味を持って、四人で屋上に向かったのよ。ただそれだけよ。私も見に行こうとした。でも気が変わって、食事に向かっただけ……何があったの。ねえ、何があったのよ」
心美は言い終えると、子供のように声を上げて泣き始めた。門前が考えない方がいいと心美をなだめている。
四人は偶然屋上に向かっただけ。全身に鳥肌が立った。沖野は表情を変えず、心美の状態を見てから小さくため息をついた。桃子は腕を組んで、心美の様子を見ている。
「島には幻覚作用のあるキノコや野草があるにはあるけど。どう考えても桐ケ谷所長が食べるとは思えない。食べ物は食堂にあるもので済ませるのが原則ですから」
桃子の言葉通り、日々忙しく業務に当たっていた研究者が山野草を口にするとは思えない。仮にも生物学者の集団がそのようなミスをするはずがない。
沖野が全員を見回してから、頷く。
「実際に何が起きたのか、我々では調べようがない。こんな恐ろしい事故が起きたのだから取り乱すのは仕方がないと思います。ただ、警察からも可能な限り、現場を荒らさないようにと言われています。門前さんは長瀬さんについていてあげて下さい。これでひとまず終わりとします。また何かありましたら、連絡します」
「了解ですよ。僕は長瀬さんと、休憩室で休んでいますからね。何かあったら来て下さい」
門前はまだ泣き続けている心美を促して立ち上がらせると、小会議室を出て行った。桃子は心美たちが出て行くのを見届けると、安堵したように息を吐いた。
「私は食堂で休んでいます。あそこが一番落ち着くから。明るいし、食べ物もあるし海も見える。余計な考えに浸らないで済みますからね。七海はどうするの?」
「培養中の細胞を眠らせないと。しばらくここに戻れないなら、貴重な培養細胞は一旦凍結して、液体窒素の中に保存しないといけないの。四階の無菌室にいます」
沖野が納得した様子で頷く。
「私は動物舎を確認して、船に乗せる実験動物の数を調べてきます。その作業が終わったら、二階の事務室にいますので。緊急の連絡が必要な場合は携帯電話で呼び出して下さい」
沖野はそれだけ言うと、小会議室を出て行った。普段の沖野と変わらない落ち着いた態度だが、言葉が必要以上に事務的に聞こえた。沖野にしてみれば、長年協力関係にあった杏を失ったのだから、精神的なダメージは計り知れない。
小会議室を出て、桃子と別れてから正面玄関前のホールに立った。
今からたった四時間ほど前、同じ場所にいた。ほんのわずかタイミングがずれていたら、是永奈緒と衝突していたのは七海だ。そして桃子が背中を突き飛ばしてくれなかったら、落ちてきた水野の下敷きとなって死んでいただろう。
エスカレーターに乗っていると心美の言葉が思い出された。四人が屋上に向かったのはただの偶然。それにもかかわらず、確かに杏は柵から身を乗り出し、しっかりと七海を見ていた。それから勢いを付けて屋上から飛んだ。
頭を振って、余計な考えを追い出そうとするが、杏のロイヤルブルーのフレアスカートが思考に絡みつく。四階に到着したものの、無菌室に足は向かなかった。いつの間にか上りのエスカレーターに乗り五階に到着していた。
職員が共通で使用する実験室は二階から四階にまとまっている。五階はホール、大会議場、資料保管庫などで普段頻繁に足を運ぶ場所ではない。そして、杏が利用している所長室と私室がある。
気が付くと七海の足は所長室に向かっていた。杏は七海の論文を送信してくれたのであろうか。そんな身勝手な思いが頭をよぎり、本当に自分が嫌になる。
学生の頃から続けている研究が、ようやく日の目を見るところまで来たのに。あとは送信さえすればいい。これが上手くいけば、七海だけでなく杏の最後の功績にもなるはずだ。タッチの差で他の研究者に手柄を横取りされては、杏だって本意ではないはずだ。
部屋を荒らす意図はない。送信履歴を確かめたいだけだ。
七海が所長室のドアノブに手をかけると、扉は何の問題もなく開いてしまった。鍵がかかっていないことに動揺した七海は、思わず室内に入り込み扉をそっと閉めた。
所長室は正面に大きな窓が作られ、美しいサンゴ礁の海岸が一望出来る作りになっている。窓の前には杏が使用する大型のデスクが部屋の中心を向くように設置され、中央に四人掛けのソファーとテーブルが並ぶ。部屋の周囲の壁には全て本棚が設置され、多数の本で埋められていた。部屋の最も奥まった場所には、隣室に繫がるドアがあった。
本当に入ってしまった。ただ、沖野が懸念していたように現場を荒らすつもりはない。なるべく何も触らないようにして、論文が送信されているのを確認出来たらすぐに終わりにしよう。
七海は杏の机の上にあるノート型パソコンの電源を入れた。職員番号の後にパスワードを入れるのだが、杏がこの工程を省いているのを以前聞いたことがある。不用心だと思ったのだが、さすがに指摘出来なかった。杏は、行動的で頭の回転が速いのだが、部屋の鍵をかけ忘れるなどややそそっかしいところがあった人だ。杏の笑顔を思い出し胸が差し込むように痛んだ。今は忘れよう。
メール送信履歴をチェックすると、今朝の七時に七海の論文は送信されていた。安堵のため息をつき、メールソフトを閉じた。
ノート型パソコンを閉じようとしたのだが、デスクトップ画面の右上にヒメツバメウオと書かれたファイルがあった。ヒメツバメウオとは魚の名前だと思うが聞いたことがない。
特に杏の研究に関しては、七海は完全に把握しようと努力してきた。だから、ヒメツバメウオを研究対象としているなら、名前に聞き覚えがないのは不自然だ。
問題のファイルを開くと、そこには見覚えのない熱帯の魚の写真が並んでいた。ひし形の体に鮮やかな黄色いひれ。全体的には薄い銀色に近いブルーの体色をしているが、別の写真では鮮やかなピンク色の個体もあった。種類が異なる近縁種なのだろうか。そこには神の入り江と短い言葉が書かれていた。
ファイルの履歴を確認すると最初に記入されたのは、五年前になる。この研究所が完成する以前のものだ。これは何の研究だろう。
どの写真もネットから拾った画像ではなく、実際に実験者が撮影したように見える。五年前に行っていた研究なら、実験ノートに記録が残されている可能性が高い。それはそうなのだが、部屋を荒らしてはいけないと沖野に注意されたばかりだ。
七海は部屋の真ん中に立ち、周囲を見回した。どこかにしまわれていないだろうか。
おそらくこの部屋には杏が毎日記入している実験記録ノートがある。これは、研究内容を記録する目的もあるが、同時に同じ内容の論文が受理された場合、どちらが世界で最初にその結果を出したのか、重要な証拠にもなる大切な資料なのだ。日記のようにプライバシーにかかわる内容は書いていないが、他人の実験ノートを探るなど失礼なだけでなく、データの流用を疑われる行為だ。
そもそも、部屋に入る行為も止められていたのに、これ以上は何もするべきではない。頭で理解していても、目がノートを探してしまう。
どうにも耐え切れず、つい本棚の前に移動してしまった。
壁際に並ぶ本棚を確かめていく。学術書や研究機器のカタログ、様々な外国語の辞書が並んでいる。
指を指しながら棚から棚へと視線を滑らせていくと、ブルーの大学ノートがずらりと並ぶ棚があった。これだ。
杏が手掛けていた研究は、新薬開発に直結する。多くの人にとって有益な内容だ。それに、警察はこの悲惨な状況の捜査をするのだろうが、仮にノートから手がかりを見つけたら隠ぺいするつもりなどさらさらない。さらに言えば、ヒメツバメウオに関する研究が今回の事故と関係する可能性など、限りなくゼロに近い。
一冊抜き出してみると、表紙に日付が記されている。2018.03.01 Ann Kirigayaとあった。ページをめくってみると、やや斜めに傾いた特徴的な文字で多数のデータが記されていた。
一冊の大学ノートが百枚つづりとなっていて、一年分が五、六冊に分かれている。棚から全てのノートを取り出して、机の上に並べた。全部で二十八冊になる貴重な資料だ。
五年前の日付が書かれたノートに軽く目を通してみたが、ヒメツバメウオの文字は全く見当たらなかった。結局、分からずじまいだがこれ以上は止めておこう。
そのまま所長室から出ようと思ったのだが、どうにも自分が入室した痕跡がないか気になってくる。端にある窓際まで移動して、部屋全体を見回した。
ふと足元に目を向けると、杏の机の下に籘で編まれたかごがあった。そこにピンク色の大学ノートが入っている。
改めて杏が行っていた研究に対する好奇心が生まれた。もう教えを乞うことも杏の研究を支えることも出来ない。せめて何を考え、何を最終目標に研究していたのか。どうしても知りたい。
七海は机の下に手を伸ばすと、籘のかごを引っ張り出した。中には四冊のピンク色の大学ノートが入っていた。ほんの一瞬迷ってから全てのノートを取り出すと、かごの底に赤い革製のキーケースが見つかった。ノートの表紙には杏の氏名と日付が記されていた。
2018.02.04
本日より二週間の予定で瑠璃島の調査を行う。西側の海岸より上陸し、比較的平らで風のよけられる五百メートルほど内陸部に宿営地を設置。
初めての長期滞在になる。これからここで行われる研究は私にとって人生をかけたものになるだろう。神に祈るのは嫌いだが、今回ばかりは神仏にすがりたい気分になる。弱気になるとは自分でも驚きだ。時間がない。一つ一つのプロセスに失敗は許されない。私なら出来る。きっとやり遂げられるだろう。
まるで日記のような書き出しに思わず表紙の名前を見直してしまった。表紙には間違いなく杏の名前がある。もとより、先に見つけたノートと筆跡が同じであり、間違いなく同一人物のものだ。やや斜めに傾いた特徴的な文字は杏のものだと知っている。だがノートの内容は七海がまるで知らない研究に移っていく。
2018.02.05
瑠璃島内の生態系を調べるため、生息する生物のサンプル調査を開始。
ノートの内容から、杏はたった一人で島内のマングローブ林を調査していると分かった。島内には毒ヘビも生息しているので、大げさではなく命がけの仕事だ。杏の尋常ではない行動力は知っていたが、この調査は危険と言えるほどだ。明らかに冷静さを欠いている。何が杏をそこまで駆り立てたのだろう。
2018.02.07
汽水域にて体色の異なるヒメツバメウオを発見。通常のヒメツバメウオは青色だが、薄紅色の個体が見つかる。穏やかな湾内であるため、その場で観察を続けることとする。簡易テントと最低限の食料があって良かった。
ついに、ヒメツバメウオの名前が出てきた。五年前、瑠璃島周辺の環境を調べるため、島に生息する動植物の徹底した採集が杏の手によって行われたようだ。その中で杏の目を引いたのがこの特殊なヒメツバメウオだったようだ。
結局杏は、偶然発見したヒメツバメウオの観察を続けるため、入り江付近で三日間留まっている。毒ヘビや、その他どんな危険な生物が潜んでいるか分からない森の中で三日。七海では無理だ。
七海は引き込まれるようにノートの続きに目を走らせた。
本来であればブルーの体色の魚のようだが、発見した個体は薄紅色と記載されている。そして、見た目は正常でありながら行動に異常が見られるヒメツバメウオの個体も発見された。行動異常については、実験ノートを読み進めていくと事細かに記載されていた。
まず、通常では考えられないほどの餌を積極的に食べるのだが、採食行動が攻撃的で他の個体を傷つけることも頻繁に観測されている。さらに、餌の過剰摂取により死亡する個体の記述もあった。
結局この二週間の瑠璃島滞在では、発見された新種らしきヒメツバメウオの観察にほとんどの時間を費やしたようだ。滞在最終日には採取した新種のヒメツバメウオを東京に持ち帰っている。本当に新種であるかの同定を試みたのだろうか。七海は最終日の実験ノートにつづられている文字を再度確認した。
2018.02.18
今日でこの島から一時的に離れる。滞在は予想以上に有意義なものだった。体色異常のヒメツバメウオはラボに戻ったのち、すぐに塩基配列の決定を行う予定。どのような結果が出るにせよ、今後の計画のために有効に使わなくてはいけない。最も貴重な時間を無駄にするな。
この文章も普段の杏とはかけ離れた印象がある。杏の仕事は非常に速い。けれど、この文章からは強い焦りが感じられる。確かに時間は貴重だ。けれど、焦ればかえって失敗に繫がり、冷静な判断が出来なくなる。もとより杏がこの基本を知らないはずがない。なぜこれほど時間を気にしているのか分からない。
手元にあるノート以外にも資料があるのだろうか。
ノート型パソコンにヒメツバメウオの写真があった。この点だけでも杏がこの研究について強い関心を持っている証拠になる。それにもかかわらず一切世の中に発表した形跡がない。これは何を意味するのか。
七海は一度ノートから目を離して、気持ちを落ち着かせた。
研究に関する資料を杏はどこでまとめるだろうか。杏になったつもりで考えてみる。まずはこの部屋で仕事をする。深夜になり、そろそろベッドに入らなくてはいけない。明日に響く。それでも、もう少しと欲が出てつい自分の部屋に仕事を持ち込んでしまうだろうな。
ノートの横に置かれた鍵が目に入った。
室内を見回すと、隣室に繫がるドアに鍵穴を見つけた。試しにドアノブを回してみたが、やはり鍵がかかっている。
心の中で杏に謝罪しながら鍵を差し込むと、予想通り扉は開いた。
扉を開けた瞬間に青紫色の光が飛び込んできた。殺菌灯、UVランプの特徴的な色だ。もちろんUVに色はないが、強い紫外線は角膜を傷つけるため、安全上の理由で点灯中は青紫色の光で確認出来るように作られている。
七海は慌てて目を逸らし、部屋の壁にあるはずのスイッチを手探りで探した。すぐにスイッチを入れると、UVランプは消え、蛍光灯の人工的な光が室内を照らした。
これは一体何なの……
目の前に広がっていたのは、杏の寝室などではなく、思わず息を呑むほどの見事な実験室だった。広い空間に窓はなく、実験室中央には正方形の実験台が置かれている。壁際に細胞培養を行うインキュベーターが並び、その隣には大型の顕微鏡が置かれている。
そしてその横には大型のクリーンベンチ。これだけの装置があれば、様々な研究が可能だ。どうして、このような場所に設置したのか。
あまりに衝撃的すぎて、この部屋に入ってしまった罪悪感が薄れてしまう。
冷蔵庫や薬品棚を通り過ぎ、実験室の奥に向かうと、さらに部屋が続いていた。重い引き戸を開けると、動物が飼育されている部屋特有の獣臭と熱気が七海の顔にぶつかってきた。
思わず一歩足を引く。新鮮な空気を吸い込み、息を止めてから中に踏み込んだ。天井に取り付けられたエアコンが異常な音を出して、熱風を吹き出している。壁に取り付けられているエアコンのコントローラーの設定を見ると、三十度の暖房になっていた。すぐに冷房の強風に切り替えると、頭の上から清涼な空気が流れてきた。
十畳ほどの広さがある室内を改めて見渡すと、棚に並べられたケージの中で多数のマウスが死んでいた。いつからエアコンが故障したのか不明だが、この暑さの中に放置されたらひとたまりもない。
さらに、部屋の端には二メートルはありそうな大型の水槽が設置されていた。見ると、白い湯気が上がり、水槽そのものが白く曇って内部が見えない。
水槽の前まで移動して覗き込むと、三十センチほどのひし形をした魚が五匹、白く変色して浮いていた。これは、ヒメツバメウオだろうか。内部の水がお湯に変わり死んでしまったようだ。
水槽全体を確かめてみると水温を測定するセンサーが、わずかに水面から外に出ている。これではサーモスタットの調整が利かず、延々と水槽の中の水を温め続けることになる。こんな初歩的なミスを杏がするのだろうか。
ひとまず魚はそのままにしておき、マウスを観察する。ケージは十五個あり、その中にいるマウスはそれぞれ一匹のみ。死んでいる十五匹を順に観察していくと、体のサイズが明らかに異常な個体が見られた。
不自然なシルエットの個体を詳しく見ると、腹部が大きく膨れ上がり、ごつごつとした突起状の瘤が目視で分かる。腫瘍が発生しているのだろうか。七海は腹部に膨らみがあるマウスの入ったケージを実験室に運び出した。
全部で六個のケージが実験台の上に並ぶ。
さて、どうしたものか。最早引き返せない状態まで来てしまった。
改めて室内を確認してみると、ここがいかに費用をかけて作られた実験室か理解出来る。顕微鏡と周辺機器だけでも、おそらく一千万円はする。
マウスが何時間前に死んだのか正確な時間は分からないが、放置すればするほど状態が悪くなっていく。刻一刻と貴重なデータが消えていくのだ。マウスを冷凍保存する手もあるが、やはりその前に観察だけは済ませたい。
それに、ここまで行動を起こしてしまったのだから、これ以上やってもやらなくても、お咎めは受ける。ならば、やるまでだ。
七海は実験室の棚や、引き出しを開けて回り、必要な道具を実験台にセットしていった。
マウスを並べるステンレスのバットに解剖に使用するゴムマット。マウスの手足を固定する待ち針。精密な作業に向く眼科用ハサミとピンセット。キムタオル。人畜共通感染症の可能性も考慮に入れサージカルマスクとゴム手袋。
念のために部屋の隅のロッカーから白衣を取り出し身に着けた。全てを実験台の上に並べ、準備は完了。
マスクとゴム手袋を装着してから、ケージの中で死んでいるマウスをバットの上に並べていく。生殖器を確認したところ、六匹ともメスだった。バットの中央に置いたゴムマットに一匹のマウスを仰向けの状態に置き、小さな手足に待ち針を刺して固定する。
ごつごつとした腹部は、妊娠しているにしても不自然な形だ。七海は作業用の椅子に腰を下ろすと、ピンセットでマウスの皮膚を持ち上げて、ハサミで腹部を切り裂いていった。生殖器の少し上から喉元まで刃先を進め、さらに両肩と両足方向にも切り込みを入れてから、皮膚を広げて、待ち針でゴムマットに固定していく。表皮が固定され、ピンク色の筋肉が露出すると、さらに腹部の異常な膨らみがはっきりと見える。
臓器を傷つけないように筋肉をピンセットでつまみ上げながら、刃先を下腹部から正中線に沿って切り開いていく。少し迷ってから腹部の筋層は完全に切除して、バットの上に置いた。筋層の除去が終わり内臓を露にしたマウスの腹部は、薄い茶色の固形物で溢れていた。ピンセットで摘んでみると、固形物はもろく崩れていく。マウスの餌を固めたペレットのようだ。
ペレットをピンセットで摘んで全て取り除くと、ようやく本来の臓器が見えてきた。見ると、食道の先にある胃が、伸び切った風船のように広がり裂けている。かろうじて胃と繫がっている小腸の内部まで未消化のペレットが詰まっていた。このマウスは胃が破裂するまで餌を食べ続けていたのだ。何かの疾患だろうか。七海は他の臓器を確認するため、肋骨も除去し、それぞれの臓器を切り出してバットに並べていった。
心臓に見た目の異常は見られない。胃と小腸は異常な量の餌が流入したことが原因となり、形が歪んでいる。細長い子宮に問題はなかったが、赤い卵巣が通常の大きさに比べてずいぶん大きく見える。念のためサイズを測定しメモしていく。
臓器を取り終えたマウスをゴムマットから外していると、耳の内側に発疹を見つけた。念のため体毛をかき分けてみると、所々に直径一センチほどの赤い斑点が数個見られた。新しいケージからマウスの死骸を取り出し、皮膚を確認するとやはり同じような発疹が確認出来た。
これは何かの感染症だろうか。食欲が異常に増進する感染症などすぐには思いつかないが、例えば食欲に関わる中枢神経が変性すればありえるのかもしれない。
二匹目のマウスの腹部を切り開くと、やはり同様に腹腔内は大量の餌で埋まっていた。杏のノートにあったヒメツバメウオも餌の過剰摂取で死亡した個体に関する記述があった。
そもそも、なぜ杏はこれらの実験を公にせずに行っていたのか。重大な発見に繫がる実験の途中経過を世界に向けて発表したくない、ということならある程度理解出来る。
だが実験室の存在を隠していた経緯を考えると、職員を含めて結果を公表したくなかったという意思の表れだろう。
考えてみれば、この部屋が杏の私室であると伝え聞いただけでこの目で確かめたことはない。他の職員も同じだったのだろう。逆に、本部には所長室も含めて、実験室だと申請すれば良いだけだ。
研究施設の図面と本来の使用方法が異なったとしても、それに気が付く人間などいないはずだ。では、何のために。いくら理由を考えても合理的な結論にたどり着けない。どうして秘密に……
「高井さん、一体あなたは何をしている? それにここは」
突然声をかけられ、心臓が痛むほど驚いてしまった。振り返ると、開け放たれた実験室の扉の先に、呆然とした表情の沖野が立っていた。
「沖野さん。ごめんなさい、これには事情が」
「本当に驚いた。この部屋は……いや、そもそも君はどうして所長室に? 現場の保存をするように伝えたはずだが」
実験室の中に入ってきた沖野は室内を見渡すと、呆気にとられたように七海の手元を見つめた。
七海は慌てて汚れたゴム手袋を外した。突然自分の行為が酷くあさましく感じ、羞恥で頰が赤くなっていく。とっさにキムタオルを被せて、自分が切り刻んだマウスの体を覆い隠した。
「説明は聞くけど、三上さんを呼んでくるから待っていて欲しい。今、落ち着いて話が出来るのは彼女くらいだからね」
沖野はため息を一つつくと、所長室を出て行った。
緊張が解けたせいか、全身の力が上手く入らなくなり椅子に座って項垂れていると、桃子を連れて沖野が実験室に戻ってきた。
桃子は七海や沖野と同様に、室内の様子を見て驚きの声を上げた。
「何、この豪華な実験室。こんなVIPルームがあるとは知らなかったけど、沖野副所長もご存じなかったんですか?」
「ああ、全く知らなかったよ。所長室には入る機会があったけど、隣室は桐ケ谷所長の個人的な居住スペースだと聞いていたからね」
桃子は興奮した様子で実験室内を歩き始めた。実験台の上に並べてあるバットのキムタオルをどかし、解剖したマウスの臓器を詳しく見てから、首を捻って奥にある実験動物飼育室に向かった。七海と沖野もそれに続く。
「この茹で上がった魚はヒメツバメウオですね。サーモスタットの故障かな。私も一回だけ、同じ失敗をしたことがあるな。ヒメツバメウオは特に珍しい魚ではないけど、汽水にしかいないです」
「これは一般的なヒメツバメウオと同じ? 例えば色とか」
「体色? さすがにここまで火が通っちゃったら分からないかな。何か関係があるの」
机の下から見つけたノートの説明をするため、所長室に向かった。七海がここに入った理由も丁寧に説明しなくてはいけないだろう。
沖野と桃子をソファーに座らせてから、七海は二人の前に腰を下ろした。
「本当に身勝手な行動を取ってしまって申し訳ないです」
七海はここに至るまでの経緯を二人に伝えた。
二人は言葉を挟まずに七海の話を聞いてくれたが、沖野は厳しい表情を浮かべている。自分でもどれほど非常識な行動を取ってしまったかは理解出来ている。
「驚いた。七海ってもっとこう、常識に雁字搦めにされる生き方をしているのかと思っていた。私でも感心する行動力ね」
「自分でも呆れている」
沖野は額に両手を当ててから、七海を見た。
「もう少し私のことを信用してくれてもいいんじゃないかな。論文の件だって、事情を説明してもらえれば、私が立ち会って調べても良かった。それから、桐ケ谷所長とは信頼を築いていた。彼女の功績を無駄にするような行動を私が取ると思うのかい?」
「でも、警察から証拠保全のため職員の個室には近づかないようにと指示があったのですよね」
「確かに遺体にはむやみに手を触れないようにと言われている。でも、実験を中断しろとか、どの部屋にも一切入るなとは言われていない。あくまで私の判断だよ」
今さらながら、沖野を理解のない上司のように扱ってしまったことを恥ずかしく思った。最初から沖野と桃子に相談して助けてもらうべきだった。
「反省しています。でも、桐ケ谷所長が五年前から続けていた研究内容が本当に奇妙で。目を通して頂けますか」
机の上に置いたピンク色の実験ノートを沖野と桃子が見えるように開いた。ゆっくりとページをめくりながら、七海も改めて読み込んでいく。
未読部分のノート後半には、採食行動に異常の見られた個体を解剖してみたところ、卵巣が腫れていたとの記載があった。思わず小さな声を上げる。
「卵巣部には有毒性を認め、マウスに対するLD50は150ng/kg。何なのこの数字。とんでもなく毒性が高い……」
桃子がノートに目を落として首を捻った。
「卵巣が有毒? ヒメツバメウオの体は無毒よ。でも、例えば有毒の餌を食べれば本来無毒な生物でも毒を持つ場合はあるけど。ヒメツバメウオは聞いたことがないな」
ノートに書かれている内容は五年前の三ケ月分だけで、マウスの実験に関する記述は一切ない。ノートに目を通していた桃子が小さく唸っている。
「ヒメツバメウオね。胃が破裂するまで餌を食べるのは、脳の異常かしら。これだけじゃ何とも」
「沖野さんは何年前から桐ケ谷さんと一緒に仕事をされていましたか? この内容は全くご存じないでしょうか」
ノートに目を通していた沖野が、視線を上げて七海を見た。
「私が桐ケ谷所長と一緒に仕事を始めたのは、四年前からだね。その時には既にこの研究所の建設は決まっていたよ。残念ながら、このノートの内容はまるで知らない。私の認識ほどには彼女から信頼を得られていなかったようだね」
沖野は小さなため息をついた。杏と沖野が研究上のパートナーとして支え合ってきたのは、七海もよく知っている。
「桐ケ谷さんがここまで研究に成功したのは、沖野さんのサポートがあったからです」
沖野はわずかに笑みを浮かべて、首を横に振った。桃子は、何か言いたそうな目を向けてから、結局何も言わずノートに視線を移した。
しばらく無言のまま、それぞれがノートに目を通し、杏が五年前に行っていた研究内容を共有することが出来た。全てを読み終えた桃子は、顔を上げて沖野を見る。
「さて、沖野さんどうしましょうか。正直内容に関しては、私じゃ分からないことが多すぎて。でも、桐ケ谷所長がどんな研究をしていたかは、警察では分からないと思います。おそらく、私たちじゃないと答えにたどり着けないのではないかと思いますね。少なくとも私は調べたいです」
「私からもお願いします。勝手ばかり言って心苦しいのですが、桐ケ谷所長が何を解明しようとしていたのか、どうしても理解したい」
沖野は眉間に深いしわを寄せてしばらく黙した後、表情を緩めた。
「私がだめだと制したところで、あなた方はたとえ首になったとしても続けるのでしょう。だったら、私が協力した方がまだましです。この実験室についても桐ケ谷所長の研究についても、本部に報告しないわけにはいきませんから、いずれにしても調べる必要があります。ただし、今後は私の許可なく単独での行動は禁止とします。それが協力する条件です」
「もちろんです。以後気を付けます」
頭を下げると、桃子が子供みたいね、と笑った。
「まず、他のノートも探しませんか。きっとどこかにあるはず。隣の実験室を少し探してみましょう」
桃子の声に促されるように、七海と沖野はソファーから立ち上がった。時計は午後三時を指している。はるか昔に起きた事故のように感じるが、杏が亡くなってから七時間しか経過していない。
三人は実験室に入り、実験ノートがないか探し始めた。
「ずいぶん立派な顕微鏡ね。なんだか色々機材が付いている。これ、七海は扱えるの?」
引き出しの中を探っていた桃子が手を止めて、光学顕微鏡を指さした。
「以前にマウスのクローンを作製していた研究室にお願いして、使い方を教わったことがあるから、多分大丈夫だと思う」
「そっか。あの小型冷蔵庫みたいなのは何に使うの」
「受精卵を育てたりかな。他にも生きた細胞を育てる場所だと思って」
桃子は頷きながら、長身を折り曲げて引き出しの中を覗いている。
「……あった。これじゃない?」
桃子が二冊のノートを取り出して掲げてみせた。ピンク色の大学ノートなので、ほぼ間違いないだろう。
桃子が実験台の上にノートを広げ椅子に座り、沖野と七海も両側に腰を下ろした。そこに書かれていた文面は、七海の想像とはまるでかけ離れたものだった。
2018.05.15
体色異常個体。ヒメツバメウオの学名Monodactylus argenteusと赤redから命名し、以後R.Mと表記。ノーマル個体N.Mと表記。
R.Mゲノム解析結果より、N.Mと比較した結果の余剰領域が決定。余剰領域は104Mb. N.Mの全ゲノム800Mbに対して12・5%を占める。この領域104Mbについて詳細を解析した。
データベースを使用して相同性解析を行った結果、渦鞭毛藻の一種Pfiesteria piscicidaと45%一致。さらにアピコンプレクサに分類される熱帯熱マラリア原虫と37%一致。
ノートに目を通していた桃子が手を上げて、七海を見た。
「何が書いてあるのかほとんど分からない。七海、解説をお願い」
「まず、赤い体色をしたヒメツバメウオの遺伝子配列を調べた。その結果、通常の色をしたヒメツバメウオより、そもそも遺伝情報量が多かったみたい。通常が八百メガベースペア、八億個の塩基で全ての遺伝情報が構成されているのだけど、それより一億四百万個塩基が多かったという意味ね」
「OK。そこまでは了解」
桃子も当然ある程度理解しているとは思うが、自分の頭の中を整理する意味でも一つ一つ解説を付けていった方がいいのかもしれない。
「それから、体色が赤いヒメツバメウオR.Mに特徴的な配列をデータベースで検索した。これの意味は桃子も知っていると思うけど、色々な生物の塩基配列はそれぞれの研究者がデータベースに登録する」
「今は生態学者でもラボ系の研究者と共同で研究しているからね。私も新種の鳥かどうか迷う時は、捕獲して調べてもらっている」
この研究所でも、屋外で研究をするいわゆるフィールド系の研究者と実験室内で研究を行うラボ系の研究者は、互いに協力しながら研究を続けている。
「そのデータベースで調べた結果、ある渦鞭毛藻と遺伝子配列が45%一致、さらにマラリア原虫と37%の一致」
「マラリア原虫は理解出来る。それに渦鞭毛藻は分かるのよ。赤潮の原因になる藻類。でもこのPで始まるこれは何? 発音もよく分からない」
「私は渦鞭毛藻についても正直分からない。これについては全く不明ね。桃子でも知らないのね」
沖野に視線を向けると、首を横に振る。幸いスペルが正確に記してあるので、各自が自分のスマートフォンで検索を始めた。
そこに記載されている内容は、七海が抱いている藻類とはかけ離れたものだった。
フィエステリア。渦鞭毛藻に分類され、二本の鞭毛を持つ。淡水に生息し、魚類の体表に外部寄生する。魚が泳ぐ振動に反応し、皮膚に張り付くとペタンクルと呼ばれる針のように尖ったストロー状の特殊な器官で皮膚に穴を開け、体液を吸う。複雑な生活環をしており、状況に応じて三十種類以上の形態的変化を行う。環境が悪化するとシスト状になり長期生存可能。また、体内で揮発性の有毒物質を生成するため、河川で大量発生した場合に被害が出る。症状は肝障害、記憶障害など。このため、バイオハザードレベル3に分類される。
これは本当に藻類なのだろうか。植物が魚の体液を吸うとは想像が難しい。
「渦鞭毛藻は藻類なのよね。寄生する生物なの?」
「うーん。寄生の意味よね。渦鞭毛藻はサンゴやクラゲと共生する場合があるのね。サンゴの色は渦鞭毛藻の色で、海水温が高くなると白化現象が起こるでしょ。あれは内部に共生している渦鞭毛藻が外部に逃げ出すわけ。だから、共生も寄生と言えば、言えなくない。けど、フィエステリアについては知らなかったな。それにさ、熱帯熱マラリア原虫は説明するまでもないけど、人間の赤血球に寄生するでしょ。なんなのこの恐ろしい生物は」
桃子は生態学者なので寄生虫に関しても、七海よりはるかに知識がある。その桃子でも知らなかったのだから、よほど珍しい現象なのだろう。
「フィエステリアと熱帯熱マラリア原虫によく似た生物の遺伝子が、なぜかそっくりそのままヒメツバメウオの遺伝子の中に入っていたってことよね」
「そうなるね。でも、例えば、ホルモンなら複数の生物で同じ場合があるから、似た遺伝子を持っていてもおかしくないの。だけど別の生物の全遺伝子が取り込まれる現象は聞いたことがないかな。ウイルスならこれに当たるけど」
そして杏は、特定のヒメツバメウオに見られた採食行動異常は、何らかの生物の影響によるものと予測を立てた。その後、行動異常が見られたヒメツバメウオの組織を取り出して、薄切標本を作製し顕微鏡で一枚一枚確かめていった。手間のかかる作業だ。
杏は実にこの作業だけで、一ケ月以上を費やしている。
そして数百枚に及ぶスライドガラス標本の観察結果から、杏はついに卵巣組織に寄生したおそらく新種の生物を見つけ出した。
該当するページを読み終えて、桃子が腕を組んで七海を見る。
「執念の一言ね。ラボ系の研究は詳しくないけど、これって普通? 桐ケ谷所長が粘り強い性格なのは知っているし、この執念が結果を生むのかな」
「実験の内容自体は問題ないけど。私が疑問なのはなぜこの作業を行ったかという点」
七海と桃子が会話を続けている間も、沖野は黙々とノートを読み続けている。
「例えば、動物の目の中にある光受容体は、元々植物が光合成に使っていた受容体をクラゲが取り込んだものなの」
「噓。目の中に植物のパーツがあるのね」
「だからね、ここまで執念深く標本を作製して調べるからには、確信があったように感じるの。ないものはここまで時間をかけて探せない」
七海の考えが伝わったのか、桃子が頷く。
「発想が逆だと言いたいのか。寄生性を持つ新種の生物がいるかどうか調べたのではなくて、新種の生物がいるのは知っていて、それを何としてでも発見したかった」
桃子の言葉に沖野が顔を上げた。普段は穏やかな瞳に一瞬激しい感情が表れたように見え、驚いてしまった。沖野が曖昧な笑みを浮かべる。
「桐ケ谷所長はどうして私に話してくれなかったのかと考えてしまってね。相談してもらえたら、もちろん助けになれたと思う」
「どんな事情か分かりませんが、桃子の言うように、桐ケ谷さんがこの寄生生物の存在を先に知っていたとしか思えなくて。ただ、そうだとしても秘密裏に研究を進めていた理由が分からないです」
研究所内で最も信頼していた沖野にまで秘密にする理由とは何か。一番納得する答えがあるが、口にしたくなかった。
生物学における倫理規定に抵触する研究だったからではないだろうか。生物学では倫理上の理由で行えない実験が事細かに決められている。
これを破ったからといって、刑事罰に処されることはないが、科学者としての信頼は一気に失うだろう。ともすれば、所属する学会を追われかねない。
杏のノートには、光学顕微鏡で撮影されたと思われる生物の写真が貼り付けてあった。細長い体の内部には円形の核が見える。さらに体の一端からは、二本の長い鞭毛が伸びていた。
スケールバーから測定すると、大きさは約40マイクロメートル。不定形に近い気はするが、鞭毛が生えているので自由に動き回れるのだろう。これが卵巣に寄生していると想像すると、背筋に寒気が走った。
「私が解剖したマウスの卵巣も、病的に腫れていた。それに、採食行動の異常も重なる……マウスはこの寄生虫に感染していたのかしら」
「うーん。何とも言えないかな。マウスから寄生虫を回収出来ればベスト。鞭毛がある寄生虫は確かにいるけど、形がころころ変わっちゃう場合も多くて。生活環境が悪化すれば、体を丸めて休眠状態に入っちゃうし。見た目で判別するのは難しいかな。そもそも私レベルの知識だと、無理ね。寄生虫の専門家じゃないもの」
ノートには左側のページに写真が貼り付けられ、右側のページには解説が書かれていた。実験台の上に開いたノートの右上には特徴的な系統樹が描かれている。
生物の進化を表す系統樹の大元にはアルベオラータの文字があった。アルベオラータから三つに分かれた枝の先には、渦鞭毛藻、アピコンプレクサ、繊毛虫と文字がある。渦鞭毛藻の隣にフィエステリア、アピコンプレクサの隣に熱帯熱マラリアと赤文字がある。
「桃子、ここにあるアルベオラータって生物は存在するの?」
「いや、いないはず。それは分類上の名前ね。遺伝子解析と構造解析の結果から近縁種だと分かったの。原生生物のグループ名ね。繊毛虫はゾウリムシとかミドリムシとかね。よく知られているでしょ。ただ、かつては共通祖先がいて、そこから枝分かれしたのかも」
桃子は指でなぞりながら説明していく。系統樹の下には杏の文字が続く。
体色異常ヒメツバメウオの卵巣から単離した生物は、ゲノム解析の結果、アルベオラータ生物群の原生生物と重なる遺伝子が多数存在した。この結果から今回発見した新種の生物はアルベオラータ生物群の共通祖先の生き残りである可能性が極めて高い。瑠璃島の特異な環境が功を奏した結果だ。
この生物の名前をRed Alveolata Queen :レッド・アルベオラータ・クィーン。略称レッドと名付ける。
*続きは、12/20発売『赫き女王 Red Alveolata Queen』でお楽しみください。

■あらすじ
「圧倒的知識によって紡ぎ出された、美しくも残酷な生物学的多様性。
悪夢の島でのサバイバル活劇に、息することも忘れてページをめくる。」
――知念実希人氏、熱狂!
日本最南端の無人島・瑠璃島にある海洋生物総合研究所で集団自殺が発生した。研究員・高井七海が調べを進めると、死亡した所長による極秘研究の存在が明らかに。
果たして自殺と研究の関係は。島に生息する動物の異常行動と繋がりはあるのか……。
生物学を究めた医療ミステリーの新星が放つ、トラウマ不可避の会心作!
■書籍情報
『赫き女王 Red Alveolata Queen』
著者:北里紗月
装画:荻野美里
装丁:長﨑綾(next door design)
発売:光⽂社
発売⽇:2023年12⽉20⽇(水)
※流通状況により⼀部地域では発売⽇が前後します
定価:2,145円(税込み)
版型:四六判ソフトカバー
■著者プロフィール
1977年、埼玉県生まれ、千葉県育ち。
東邦大学大学院理学研究科生物学専攻修了。理学修士。
日本卵子学会認定胚培養士、体外受精コーディネーターとして、第一線で生殖医療に携わる。
『さようなら、お母さん』が、島田荘司選 第9回ばらのまち福山ミステリー文学新人賞優秀作に選出され、2017年にデビュー。同作より続く天才毒物研究者・利根川由紀シリーズの『清らかな、世界の果てで』『連鎖感染 chain infection』や、『アスクレピオスの断罪 Condemnation of Asclepius』の著書がある。
■好評発売中です
いいなと思ったら応援しよう!

