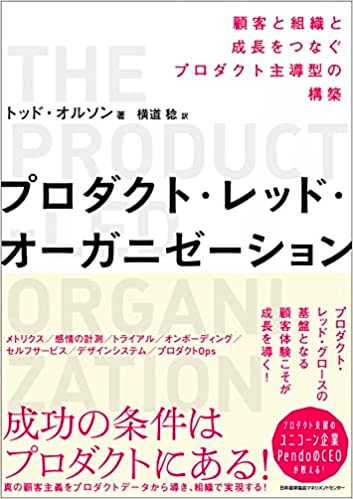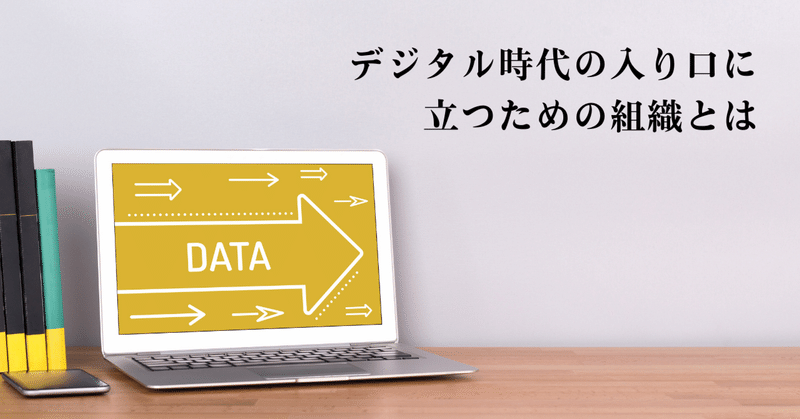
DXを成功させる組織とカルチャー
私たちは今、まさしくデジタル時代の入り口に立っています。
あなたの会社はスタート地点に立っていますか?
DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が日本で普及して久しく、新型コロナウイルスによるパンデミック後、各企業が在宅勤務を実行しようと、様々なデジタルサービスを検討する中、今まで以上にDXをより喫緊の課題と感じた企業は多かったのではないでしょうか。
とはいえ、一筋縄ではいかないのがDXであり、このような疑問や課題を持つ企業も多いかもしれません。
どこから始めたらいいのかわからない
ただサービスを導入すればよいというものでもない
IT人材と経営層の間の理解に乖離がある
本記事では、Pendo Japan カントリーマネージャーの高山さんとカスタマーサクセスマネージャーの大山さんに「DXの成功に必要な組織」について語っていただいたインタビュー動画の一部をまとめ、加筆しています。
ここでは「DX成功に必要な組織」というトピックに対して、「組織論」と「デジタル論」の側面から解説していきます。より詳しい内容をお聞きになりたい方やここでは取り上げられていない部分も気になる方は、動画本編「TTT - DX成功に必要な組織とは」をぜひご確認ください。
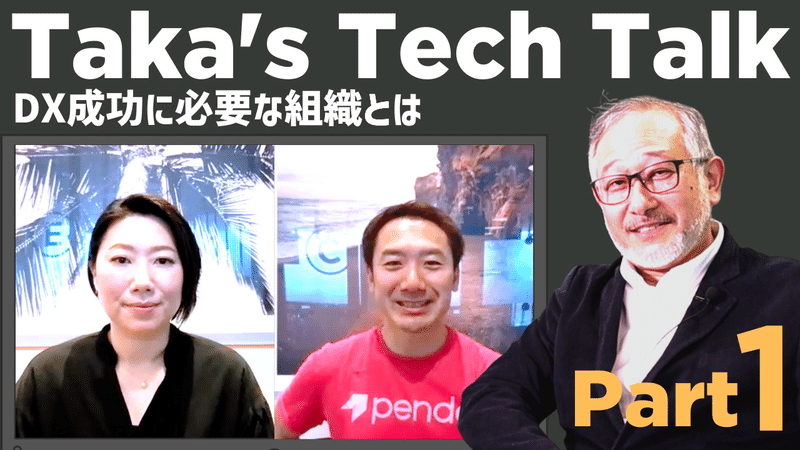
「組織論」編
DXにあたって組織の持つ課題
ハードは買い換えるのにソフトはなかなか変えない
エンジニアが企業側にいない
必要なタイミングで必要なデータにアクセスできない
ハードは買い換えるのにソフトはなかなか変えない

今やあらゆる職種・職業でパソコンは欠かせないツールになっています。パソコンの動きが遅くなるだけで、仕事の生産性と効率だけでなく、モチベーションすら下がります。そのため企業や個人は、必要に応じて定期的にパソコン(ハードウェア)を買い替えます。それなのに外部のシステムエンジニアに依頼して作成したシステムは、動きが遅くなっても、使い勝手が悪くてもなかなか変えないケースが多いです。
テクノロジーの世界のスピードがますます早くなっているというのは、もはや通説になっていて、多くの新しいソフトウェア、アプリケーション、クラウドが日々生まれています。これらこそが、今後の競合他社との大きな差別化となってくるのです。特にクラウドは長期的な導入作戦が不要で、機敏に動くことができる素晴らしいツールです。
クラウドの導入がどういった状況の変化をもたらすのかを考えてみましょう。どのような企業でも安定して変化しないことはあり得ません。どんな会社にも守るべきところと攻めるべきところがあります。
歴史ある大企業にとっては、クラウドなら少ない投資で柔軟なシステムが構築できるため、昔からのIT構築の方法に慣れていて、業態が広がった時に迅速に対応できないといったことがなくなります。
中小企業にとっては、クラウドという大企業と同じ道具を使えることによって、企業規模に関わらずヨーイドンと横並びで競争できるようになります。
エンジニアが企業側にいない
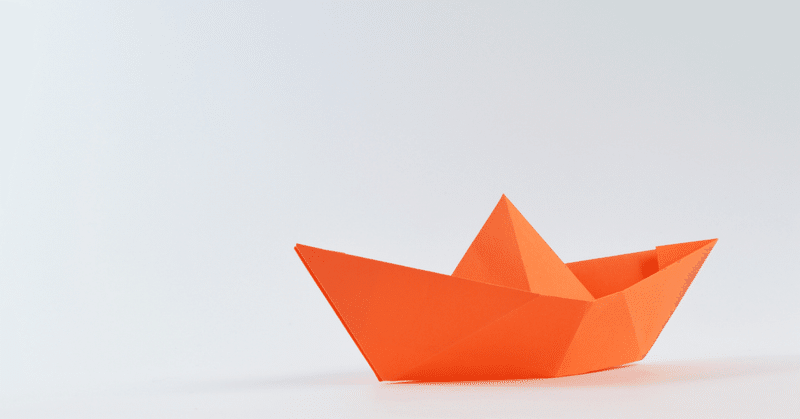
ではそのためには何が必要なのか。それはそれぞれの企業に合った、正しい道具を探して判断することのできる目利きが必要となります。
例えば米国企業のほとんどは自社内にデータサイエンティストやITエンジニアを抱えていますが、一方、日本では約75%の企業が外部のSIer(システムインテグレーター)に任せているのが現状です。つまり、エンジニアのほとんどが企業側にいないことになります。
これではDXという船を漕ぐにも、漕ぎ手がいないまま進むことになります。目利きの人材を育てる、あるいは信頼できるトラステッドパートナーを社内に迎えることは、経営のマスト事項なのです。
必要なタイミングで必要なデータにアクセスできない

だからと言って、全ての人がデジタルのスペシャリストになる必要はありません。モノづくりが経済を支えてきた日本では、デジタルでもプロダクトアウトを考えてしまいがちですが、デジタルの一番のポイントはそこではありません。
今やデータは企業のガソリンと言われており、社内の様々な立場の人が日々の意思決定をする際にデータを見ていると思います。しかし、必要な人が必要なタイミングで必要なデータにアクセスできているでしょうか?
データを水に例えると、必要な場所に水飲み場があり、誰でもそこで水を飲むことができて、蛇口をひねればいつでも水が出てくるというのが理想的な状況です。そうすることで、誰も喉が渇くこともなければ、水飲み場を探し回る必要もないのです。
これを企業で実行するには、正しいソリューションとそれを管理統括するポジションを作ることが有効でしょう。それがデータをオープンにし、データを共通言語とする組織の始まりです。
解決策まとめ
クラウド利用によって全ての企業が等しくチャンスを得る
デジタル前提の人材育成の視点
データをオープンにし共通言語とする組織
「デジタル論」編
ここまでは、DXを成功させるために組織にとって必要な基盤についてお話をしてきました。ここからはDXを進めるコアの部分「デジタル化」についてお話をしていきたいと思います。
デジタル化によって生まれるデジタル弱者

デジタルのポイントは「データが取れること」にあります。ウェブ解析の黎明期から、ユーザーを理解するためにデータ活用が行われてきました。今では全てのサービスがデジタルの要素を含んでいるため、さらにデータを集めやすくなっており、これはビジネスにとってはとてもよいことです。
しかし、デジタル化が進めば進むほど、デジタル弱者(デジタル化から置いてけぼりにされる人)が生まれます。個人レベルで考えてみても、毎年新しいスマホが発売され、毎月のようにソフトウェアや仕様のアップデートがあり、数えきれないほどのアプリが存在して、アカウント作成やログインにも様々な方法があります。良かれと思ってこれらのツールがより新しく、複雑になっていく中、デジタル弱者は、この急速なデジタル化の波に飲まれ、取り残されるのです。
しかし本当のデジタル化にあたっては、このようなデジタル弱者を取り残さないことが重要です。そのためには、デジタルのツールやサービスを使いこなしている人を対象にするのではなく、すべての年代の方に寄り添えるツールやサービスを考える必要があります。
日本が持つ「失敗してはいけない」カルチャー

カルチャーに目を向けてみましょう。日本では「失敗してはいけない」という発想が主流でした。日本では今でもその文化が定着し、1週間、1カ月で導入できるものを1年かけて検証し、結果、時代遅れになって使えないものになってしまうことがあります。日本の経済を支えてきたモノづくりや製造業では欠かせないとても大切な視点です。しかし、サービスが日々進化するデジタルの世界では「失敗を恐れない」という、異なる視点を持つこともまた大切です。
一方、日本は「改善」という考えも持っています。実はこの「KAIZEN」は海外でも高く評価されており、MBAでも学ばれているほどです。そして、企業において改善サイクル (PDCA) を回すには、元となるデータを正しく活用することにあります。
例えば、新たな仮説の検証のために、IT部門に都度依頼したり、待つことなく、自分でデータを取れるようにする。そのための解決策はすでに多く存在し、ノーコード・ローコードはその代表的なソリューションのひとつです。これにより、製品の改善やユーザーとのコミュニケーションなど、改善の好循環をより一層スピーディーにできるようになります。
まとめ
ここまでくれば、DX(デジタルトランスフォーメーション)は成功に近づいていき、企業はより自社の製品にフォーカスをすることができます。つまり、データを元に自社製品に磨きをかけ、他社との差別化をし、顧客によりよい製品や製品体験を提供する「製品主導の組織」となっていくのです。
本記事の元となったインタビュー動画では、これまで明らかになった課題への解決策において「経営者がすべきこと・心構え」や「デジタル化を成功裏に進めるために必要な視点」などについても話していますので、ぜひご視聴ください。
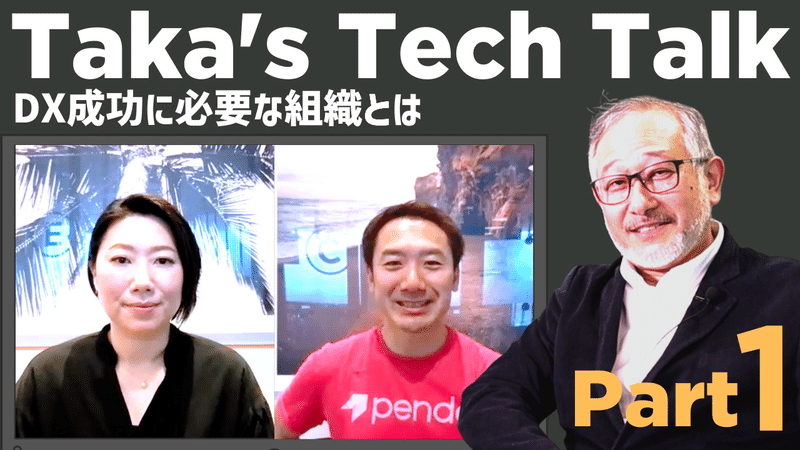
また、製品主導の組織についてより詳しく知りたい方は、Pendo社CEO トッド・オルソン氏の最新著書「プロダクト・レッド・オーガニゼーション 顧客と組織と成長をつなぐプロダクト主導型の構築」をぜひ手に取ってみてください。顧客と組織と成長をつなぐ製品主導型の構築について詳しく書かれており、ここには先に述べたデータが深く関わっています。