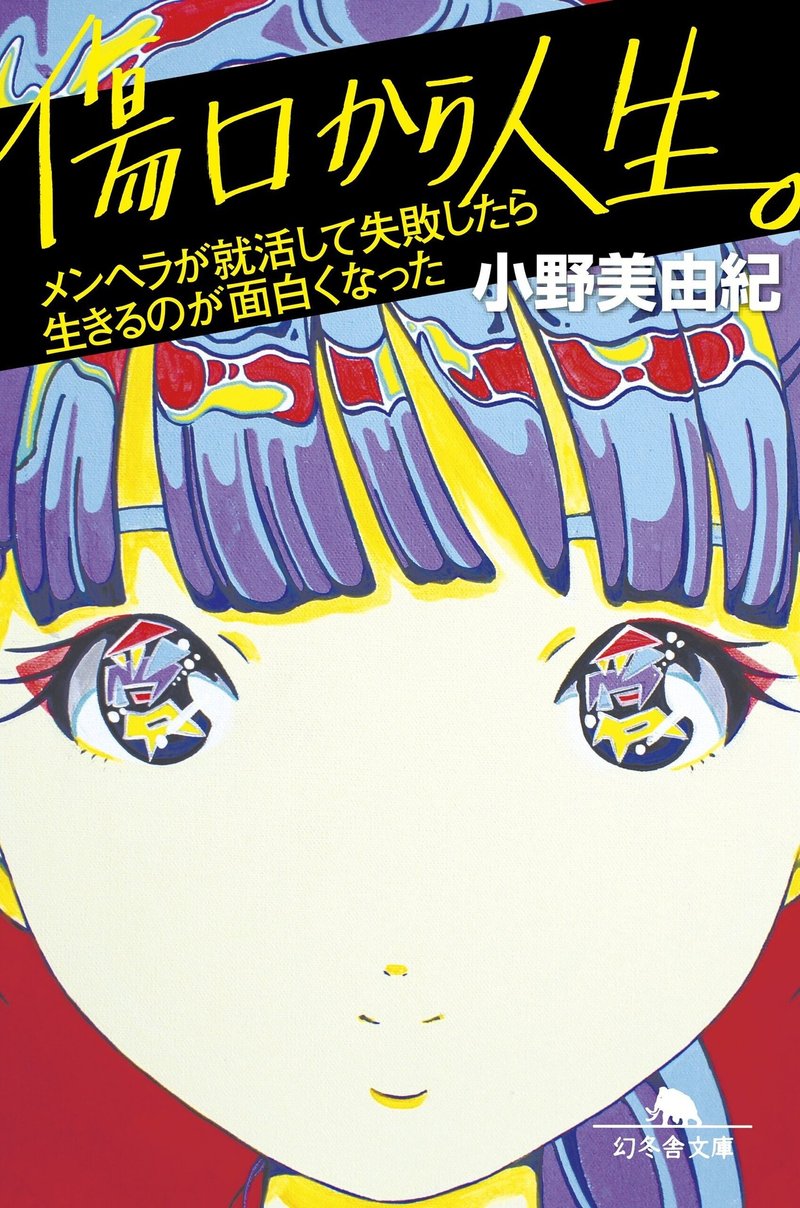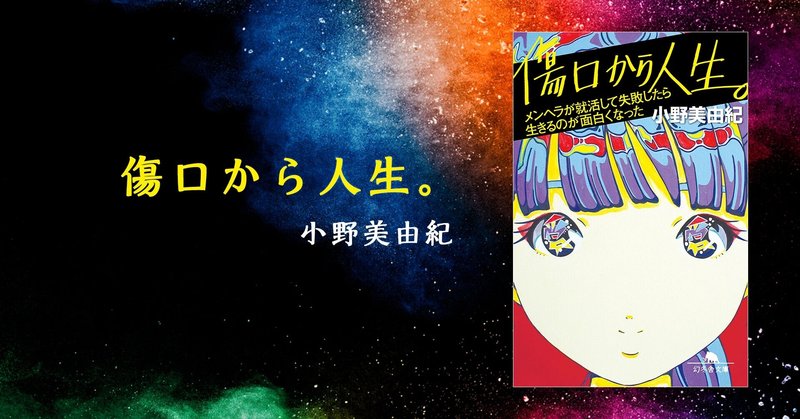
飲み会が嫌で嫌でしかたない…なんで大勢の場に適応できないの? #5 傷口から人生。
過剰すぎる母に抑圧され、中3で不登校。大学ではキラキラキャンパスライフになじめず仮面浪人。でも他人から見てイケてる自分でいたくて、留学、TOEIC950点、ボランティア、インターンなど、無敵のエントリーシートをひっさげ大企業の面接に臨んだ。なのに、肝心なときにパニック障害に。就活を断念し、なぜかスペイン巡礼の旅へ……。
小説家としても活躍している小野美由紀さんのデビューエッセイ、『傷口から人生。 メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった』は、「つまずきまくり女子」の人生格闘記。読めば生きる勇気が湧いてくる、そんな希望にあふれた本書から一部をご紹介します。
* * *
家に帰るとどっと疲れる
大学を卒業してから2年後、運よく離島経済新聞社という小さなWEBの会社に拾ってもらった頃。その時アシスタントをしていた、女社長の鯨本さん(大分出身)にこんなことを言われた。

「25歳まで、誘われた飲み会は全部、断らないで行くようにしてたけん」
私は20代の前半、飲み会が苦手で苦手でしょうがなくて、せっかく誘われた飲み会も、ぎりぎりになって急に嫌になってドタキャンしたりしていた。そのせいか「まともな」人付き合いを覚えるのが、だいぶ遅れてしまったのだが、社会人の切れっ端になった今、それを取り返すがごとく、社長の訓示を遵守し、誘われた飲み会は、全部行くようにしている。
ところが、である。
飲み会に参加すると、その場は楽しいのだが、その後、ひどく落ち込むのだ。
多くの人と話したあとの、あの落ち込み。
飲み会から帰って来て、へべれけな状態で鏡の中の自分の姿を見たとたん、取り憑いたものがすっと離れるように上気した気分がそがれてゆく。飲んではしゃいで楽しく過ごせたはずなのに、次の日、前借りしたものがどっしりと返ってくるように、疲れが残って布団から出られなくなったりする。
別に、人と話すのが嫌とか、酒が嫌いとかではない。それなのに、楽しそうに話し、オーバーリアクションでへーとかほうとかあいづちを打ち、場の対流を崩さないように、かき混ぜてかき混ぜてかき混ぜて盛り上がった飲み会ほど、すごく疲れる。内臓に、どすっと来るような疲れがいつまでも取れない。
この「コミュニケーション・リバウンド」とも呼べるような疲れに、対処のしようがあるのかどうか。
知り合いに聞いたら、
「飲み会がある時は、2~3日前から精神統一してコンディションを整え、それでもしんどくて、でもどうにかして行かないといけない時は、レッドブルを2、3本がぶ飲みしてから行く」と言っていた。
それはただの寿命の前借りである。却下。
なんでだろう。なんで自分は大勢の場に適応できないんだろう。そう思っていたら、精神科医の名越康文先生の本に、ヒントがあった。
「相手を楽しませるために、10の話を100にして話したり、逆に関心も無いのに関心のあるようなリアクションを取ったり、楽しそうに振る舞ったりして、自分を“盛って”しまったりという経験は、誰にでもあると思います。
こういう『舌が勝手につく嘘』は、誰しも身に覚えがあるものだし、ちょっと話を大きくしたり、尾ひれをつけたりするだけであれば、実害はないように感じます。しかし、これを放置しているとボディブローのように、自分の心にダメージを蓄積してしまうんです。
(中略)友人と飲みに行った帰りがけに、えもいわれぬ『挫折感』を覚えた経験はないでしょうか。
たいていの場合、僕らはそれを人と別れる事によるさびしさと理解しがちなんですが、実は、宴席において『舌が勝手につく嘘』を重ねてしまった、後悔による疲れであることが、少なくないんです」
(名越康文『驚く力』より)
たまには試しに黙ってみる
ああ、私はあれが苦手なんだ。
リア充が集まる飲み会の、全員が場の雰囲気を壊さないように、流れを止めないために、大きな一枚の布のすそをひっぱって、うまく落とさないように支えている感じ。流れを途絶えさせないように、壊さないように、絶え間なく気を遣っている感じ。
自分をこの場にふさわしい、朗らかで、好き嫌いがなくて、コミュニケーションの上手な人間のように見せかける。

飲み会が楽しくないのではない。自分が、その場から、滑り落ちなくてすむように、周到に、リア充シールドを張り巡らせて人と接しているから、緊張してエネルギーを消耗しているだけだ。
そっか。適応できないから疲れるんじゃなく、適応過剰だから疲れるのか。
でも、飲み会の場をよく観察していると、流れなんてあるようでいて、実は霧散していることが往々にしてある。
本当は無いはずの流れを壊さないように、おいてきぼりにならないように、と、つい浮き足だって、布の端っこを摑んでしまうから、自分で作り出した、よく分からないイキオイについつい飛ばされて、名越先生の言うような状態になってしまうんだろう。
キャバ嬢と飲んでも安らげない人は、たぶん、このタイプだ。気を遣う人に気を遣ってしまって疲れるのだ。飲み会に参加したら、全員の布を落とさないように一身に引き受けてしまう。布をつい、落としてしまいそうなあぶなっかしい人のことまで、なぜか気にかけてしまう。
結果、消耗して自分の中に、大きなクレーターを残してしまう。
反対に、空気も読めず、コミュニケーションの下手な「コミュ障」ばかりが集まる飲み会は、とっても気楽だ。誰も気を遣えないから、疲れもへったくれもないのである。全員がリア充ぶり、いかにもコミュニケーションが上手そうにふるまう綺麗すぎる飲み会ほど、とても疲れるわりに全然楽しくないけれど、そんなところに、コミュ障が一人いると、なんだか全員がほっとする。
コミュ障は、全員が、やぶらないようにやぶらないようにしている布に、容赦なく裂け目を入れる。だからちょっとだけ、安心する。全員が、演技するのをちょっとだけ止められる。コミュ障は、ヘタなコミュニケーション強者より、よっぽどコミュニティの潤滑油だ。
最近、飲み会でもうあんまり話さなくなった。飲み会で、ああ、自分は今、勝手に嘘をついてるなあと思ったら、試しに黙ってみる。黙ってぼーっとする。ぼーっとしていると、会場の中の、なんとなく流れのほころびのようなものが見える。ほころびの中に、自分と同じようにぼーっとしている人がいる。そういう人と、ぽつんぽつんと話してゆくと、さっきまでとは違った場所に、二人の輪ができる。ぽっと三月兎の穴が開いて、みんなが保とうとしているシーツの下の秘密の世界に、行けるんである。
みんながわいわい盛り上がっているところに一生懸命ついていこうとするから疲れるのだ。
話そうと思って一生懸命話している中に、コミュニケーションは生まれない。コミュニケーションは、自分に「待て」を課したところ、止まったところから、いきなり生まれるのである。
◇ ◇ ◇