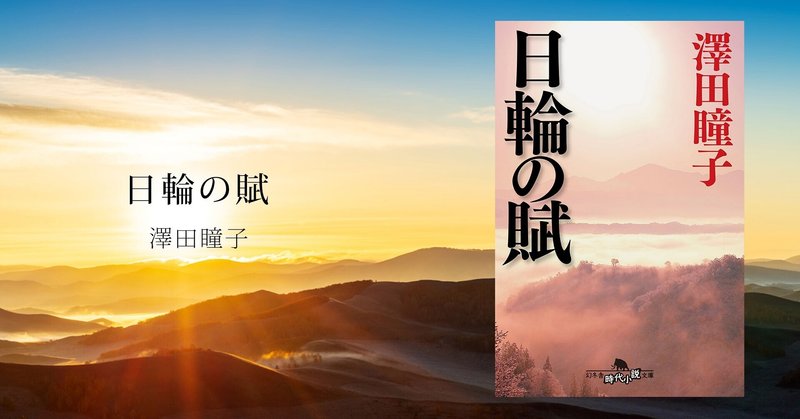
古代日本の最新都市・藤原宮へ…壮大なスケールで「日本誕生」を描いた歴史エンターテインメント #4 日輪の賦
7世紀終わり。国は強大化する唐と新羅の脅威にさらされていた。危機に立ち向かうべく、女王・讃良(さらら)は強力な中央集権国家づくりに邁進する。しかし権益に固執する王族・豪族たちは、それに反発。やがて恐ろしい謀略が動き始める……。
昨年、『星落ちて、なお』で直木賞を受賞し、一躍注目を集めた澤田瞳子さん。『日輪の賦』は、壮大なスケールで「日本誕生」を描いた歴史エンターテインメント。その冒頭部分を、ご紹介します。
* * *
「おい、そこな奴(やっこ)。荷はわしが運んでつかわそう。おぬしの身体つきなら、主をおぶって山を下ることもたやすかろうて」
言うなり人麻呂(ひとまろ)は狗隈(いぬくま)の背から、強引に荷を奪い取った。半白の髪やひょろりと細い体軀(たいく)には似合わぬ、敏捷(びんしょう)な動きであった。

「ありがとうございます。ですがそのお年で荷など負われて、大丈夫ですか」
「中身はせいぜい、着替えと道中の米程度でしょう。これでも昔は戦に加わり、野面や森を駆け回った身。老いたりとはいえ、平気でございますよ」
言葉にたがわず、人麻呂はさっさと包みを背負い、軽い足取りで山道に踏み出した。忍裳(おもし)の姿はすでに、深い藪笹に覆われて見えない。
「やれやれ、この年になって坊ちゃまに背を貸すとは、夢にも思いませんでしたぜ」
ぼやきながらもよっこらしょと廣手(ひろて)をおぶい、狗隈は主従の後を追った。
放埒(ほうらつ)に繁った笹の根のおかげで、足元は悪くない。忍裳は苦もなく追いついてきた狗隈に、切れ長の目をちらりと振り向けた。
木漏れ日に紗の冠が透け、薄い影が白い項(うなじ)に落ちている。真っすぐに背を伸ばして手綱を握るさまがいかにも端正だが、女としての華やぎは微塵もない。男とも女ともつかぬ、実に不思議な容姿であった。
「里に着いたら、いずこかで馬を借りましょう。さすれば夕刻までには宮城に着けるでしょう」
「ここから里まではどのぐらいかかるのでしょうか」
「もはや峠はそこです。山を下るだけなら、半剋(はんとき)もかかりますまい」
このとき不意に、道の両側に覆い重なるように繁っていた木立が切れた。それと同時に眼下に開けた平野のあまりの美しさに、廣手は狗隈の背で息を呑んだ。
凪いだ海のようになだらかな盆地のところどころで、こんもりとした丘が早緑に煌(きら)めいている。平野部には大路小路が縦横に走り、びっしりと並んだ建物を区切っていた。
道行く者がまとう綺羅(きら)であろうか。芥子粒(けしつぶ)ほどの人影が街衢(がいく)を行き交うたび、そこここで小さな輝きが砕ける。そうでなくとも大路に敷き詰められた白砂のためか、眼下に広がる街並み全体が、薄い光を放っているかのようである。
(これが、新益京――)
「京の中央、あの大垣と濠(ほり)で囲まれた一画が、大王(おおきみ)の住まわれる宮城でございますわい。まこと世に二つとなき、美しい宮でございましょう」
あまりの偉容に言葉もない廣手と狗隈を振り返り、人麻呂が説明した。
宮城の大きさは、方十町(約一キロメートル)。白土の塁壁と濠が巡らされ、十二の門が四囲に開かれている。
大小の官衙(かんが)が建ち並ぶ中、際立って豪壮な二層の建物は、宮城の中核を成す大極殿(だいごくでん)であろう。相当の距離があるにもかかわらず、柱の一本一本までが手に取るように見えるのは、それだけ規模が壮大だからに違いない。正殿の屋根には金色に輝く鴟尾(しび)が置かれ、柱の鮮やかな丹(に)の色と相まって、まるで燃え上がる焰(ほのお)の如き雄渾(ゆうこん)さであった。
大極殿の南には、十二の細殿が二列になって連なっている。その規律正しさに廣手はふと、天の星々が北辰(北極星)に扈従(こじゅう)する様を思った。
なるほどこれは決して、大小の豪族と協調して政務を執る、古の大王の宮殿ではない。
大王を中心とする新たな国家――父の言葉の意味が、目の前に明確な姿を取ったが如き堂々たる殿堂がそこにあった。
「藤原の 大宮仕(おおみやつか)へ生(あ)れ付くや 娘子(おとめ)がともは 羨(とも)しきろかも――他国から京に来られた方はみな、ここで一様に立ちすくみ、溜息をつかれますわい。大陸には『周礼(しゅうらい)』と申す書物がございましてな。方形の羅城の中を東西南北に走る、九条九坊の街路。中央に王城を配し、北に市、南に社稷(しゃしょく)。まさに大陸の方々が理想となさる都城を実現したのが、この京なのでございます」
藤原の宮に奉仕するため、生まれてくる少女たち。あのような美しい宮にお仕え出来るとは、実に羨しいことだ――とのびやかな声で歌い、人麻呂は誇らしげに胸を張った。
十年の計画・工事期間を経て、飛鳥からここ藤原に京が移されたのは一昨年の冬。古くからの官道である上(かみ)ツ道・中(なか)ツ道・下(しも)ツ道、丹比道(たじひみち)(横大路)を内包する新京は、交通の要衝であるとともに畿内の中心地。京人(みやこびと)からすれば、何より誇らしい最新都市であった。
だが見慣れているのか、忍裳だけは廣手たちには構わず、先に道を下り始めている。急いで後を追ったが、険しい山道をどう駒を急がせたのか、沼の傍に数軒の家が建ち並ぶ集落に出た頃には、彼女の姿はかき消したように失せていた。

「先に宮城に戻られたに違いありませぬ。ここまで来れば、京は目と鼻の先。まだ日も高うございます。あとはゆるゆると参りましょうぞ」
人麻呂はそう言って里長の家で馬を借り、廣手を鞍に移して轡を握った。それが当然といった面持ちであったが、おそらく人麻呂は大舎人(おおとねり)。つまり廣手には、大先輩である。
「よしてください、人麻呂どの。腹が痛いとはいえ、馬ぐらい一人で乗れます」
「遠慮なさらずともよろしゅうございます。これは臣(やつがれ)の常の務め、むしろ手ぶらでのんびり道を歩くのに慣れておりませぬのじゃ。せめて轡ぐらい取らせてくだされ」
幾度も水をくぐったらしき官服はくたびれているが、汚れ一つ見当たらない。板を入れたようにまっすぐな背筋といい、飄々としながらも折り目正しい物言いといい、いかにも叩き上げと覚しき老舎人であった。
「阿古志連(あこしのむらじ)家と申さば、紀伊国の由緒正しき豪族ですな。臣なぞ凋落(ちょうらく)した古い氏族の出ゆえ、この年になっても浮かぶ瀬がございません。ですが廣手どのは当初こそ大舎人でおられても、すぐにどこぞの官司に転属なさいましょう。いやはや、羨しい限りでございます」
「人麻呂どのは畿内の出でいらっしゃいますか」
「さよう、生まれは倭国添上評(やまとのくにそふのかみのこおり)。七、八代昔までは、大王に妃(みめ)を奉るほどの家でございましたが、まあ世の潮流には逆らえませぬわい」
そう言いながらも言葉つきは悠長で、一族の没落を嘆く気配はない。小さな欠伸を漏らし、人麻呂はどこか浮世離れした口振りで続けた。
「とは申せ、好きな歌を詠み、好きな酒を飲めるこの暮らし。これはこれで、わしはけっこう気に入っておりますのじゃ」
春日(はるひ)すら 田に立ち疲る 君は悲しも――と朗詠する彼の声を聞きながら見回せば、いつの間に官道に戻ったのだろう。大路は美しく掃き清められ、塵一つ落ちていない。桑の葉の入った籠を担う農婦や、官吏に率いられた仕丁の集団が、汗ばむほどの陽射しを受け、東へ西へと足を急がせていた。
溝で足をすすぐ旅人、乞食(こつじき)帰りらしき僧侶に目を注ぐうち、青草が繁るばかりであった道の左右は、見渡す限りの田畑に変わった。その狭間にぽつぽつと草葺(くさぶき)の民家がのぞいたかと思うと、ほんの数町で辺りは眼もくらむばかりの雑踏に変じた。新益京の京域に入ったのである。
「ここは横大路と下ツ道の辻。どちらも京の目抜き大路でございます」
京の羅城は方一里十二町(約五・二キロメートル)。遷都からまだ日が浅いため、行く手をふさぐように聳(そびえ)え立つ宮城の殿舎はもちろん、軒を連ねた家々までが真新しく、柱の丹も艶々としている。
人麻呂は大路を通り抜け、二人を宮城に導いた。日焼けした門番が人麻呂を見て、厳めしい顔を親しげにほころばせた。
「なんだ、忍裳さまはとっくにお戻りというに、おぬし一人、どこで道草を食っておった」
海犬養門(あまいぬかいもん)――と淋漓(りんり)たる筆で記された額が掲げられた門は、桁行五間。紀伊では国衙(こくが)の政庁にしか用いられぬ瓦が葺(ふ)かれ、どこの官衙かと見まごう豪壮な構えであった。
「ふむ、忍裳さまはそんなに早くお戻りになられましたか」
「おお、横大路の雑踏を駆け通して来られたようで、馬も御身も汗みずくでおられたわい。されどさような無茶をなさっても、道行く者に誰一人怪我を負わせぬのだから、まったく女子の身でたいしたお方じゃ」
宮城内は小路で区切られ、大小の曹司(ぞうし)が櫛比(しっぴ)している。その間を官人や宮人(くにん)(女性官吏)が忙しげに行き交う様に、廣手は馬から下りるのも忘れ、呆然と眼を見張った。
視界に入る人々の大半は、深縹(こきはなだ)色や浅縹(あさはなだ)色の官服を着した下級官吏。だが中にはごく稀に、緋色(ひいろ)や深緑色の官服姿の人物もいる。いずれも紀伊国宰以上の高職にある顕官であった。
御牧(みまき)から貢上されてきたのであろう。逞しく肥えた黒駒を曳(ひ)いた馬丁が、廣手の乗る農馬に眼を投げ、小莫迦(こばか)にしたように鼻を鳴らした。
「ではとりあえず、外薬官(とのくすりのつかさ)に参りましょうかな」
幾度も角を曲がってたどりついた官衙では、数人の官吏が籠や笊(ざる)を手に走り回っていた。切石の上に漆喰(しっくい)で土壁を築いた小房が庭を囲む様は、一見、大蔵(倉庫)にも似ているが、どの高窓からも盛んに湯気が噴き上がり、つんと薬臭い匂いが界隈にたれ込めている。そのうちの一つの扉を、人麻呂はほとほとと叩いた。
「詠(えい)先生、おいででございますか。すみませぬがお一方、診て差し上げてくだされ」
「その声は人麻呂どのか。今、手が離せぬゆえ、勝手に入ってこられよ」
胴間声に促されて馬を下りると、土間に広げた莚(むしろ)の上で、いかつい体つきの中年男が、石臼を回している。散らかり放題の房の隅では、鉄鍋が竈(かまど)の上でぶくぶくと沸き立っていた。
「患者はその若者か。とりあえず横になれ」
男は壁際に設えられた寝台を、四角い顎で指した。わずかな訛りのある、太い声であった。
ぎょろりとした金壺眼(かなつぼまなこ)に大きな唇。布衫(ふさん)の胸を無造作にはだけ、真っ黒な剛毛をもじゃもじゃとはみ出させている。五分ほどにそり上げた頭の鉢が秀でた、何とも奇妙な顔立ちの男であった。
ちりん、というあえかな音に見回せば、男の腰に下げられた碧色(へきしょく)の玉鐸(ぎょくたく)がかすかな音を立てている。青磁よりもなお冴えた澄明な肌合いを持つ玉の響きは、暫時、廣手に腹の痛みを忘れさせた。
◇ ◇ ◇
連載一覧はこちら↓
日輪の賦 澤田瞳子

