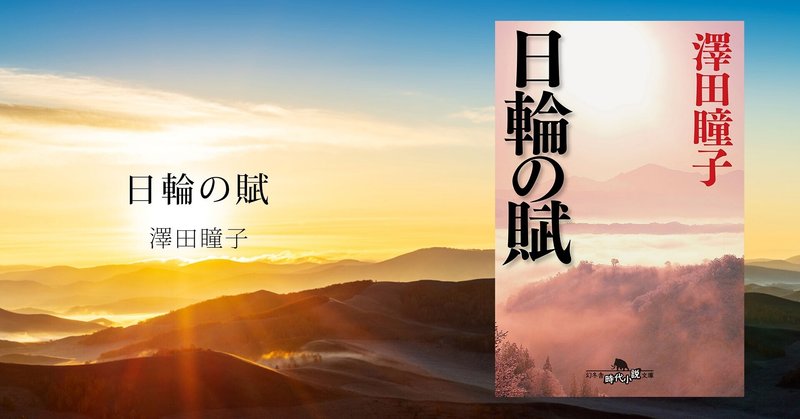
やがて恐ろしい謀略が動き始める…壮大なスケールで「日本誕生」を描いた歴史エンターテインメント #5 日輪の賦
7世紀終わり。国は強大化する唐と新羅の脅威にさらされていた。危機に立ち向かうべく、女王・讃良(さらら)は強力な中央集権国家づくりに邁進する。しかし権益に固執する王族・豪族たちは、それに反発。やがて恐ろしい謀略が動き始める……。
昨年、『星落ちて、なお』で直木賞を受賞し、一躍注目を集めた澤田瞳子さん。『日輪の賦』は、壮大なスケールで「日本誕生」を描いた歴史エンターテインメント。その冒頭部分を、ご紹介します。
* * *
「腹が差し込むとな。旅の末となると、水あたりか食あたりが相場じゃが。ふむ腹を下してはおらぬのか。――なれば、これはどうじゃ」
いきなり脇腹を強く圧迫され、廣手(ひろて)は思わず小さく呻いた。それに満足げにうなずき、男は人麻呂(ひとまろ)を振り返った。

「心配はいらぬ。旅疲れで六腑(ろっぷ)が弱り、食い物がこなれずに腹中で蟠(わだかま)っておるだけじゃ。人間の体は十六、七歳が盛り。二十歳を過ぎた頃には、少しずつ衰えが始まっておる。若いと申して、無理な旅をしたのが祟(たた)ったのであろう。後ほど曹司に薬を届けさせるでな。姓名と官職をそこに書いてまいれ」
「それが詠(えい)先生、まだ配属先がわからぬのです。なにせ大舎人(おおとねり)になるべく、たった今、故郷(くに)より出てこられたばかりゆえ」
「なんじゃ、新参者か。法官(後の式部省(のりのつかさ)。人事を司る)へ出頭するよりも早くここに担ぎ込まれるとは、何とも珍しい話じゃわい」
大口を開いて笑い、医師は腰に下げた布きれで手を拭った。またしても帯に吊るされた玉鐸(ぎょくたく)が小さく鳴る。もとは相当な名品であろう。長い年月のせいか、ところどころ脂曇りしているのがなんとも惜しまれた。
「そういうわけでございますから先生、手当が終わられましたら、法官の場所を教えて差し上げてくだされ。臣は御用もありますゆえ、ここで失礼いたします」
そそくさと人麻呂が出ていくと、医師は横たわったままの廣手をじろりと振り返った。
詠という名や端々の訛りから察するに、どうやらこの国の生まれではないらしい。
三十年前、百済国が大唐・新羅連合軍によって滅ぼされると、倭には万を超える亡命者が渡来した。朝廷はその大半を開拓途上の東国に移住させる一方、貴族や卓越した学識・技術を備えた者を畿内に留め、彼らから様々な知識を吸収するべく努めた。
このため国内には現在百済人はもちろん、唐人や新羅人、更には大陸経由で渡来した吐蕃(とばん)人など、多種多様な人々が居住している。廣手もこれまで国衙(こくが)などで他国人に接してきたため、目の前の男の出自にはさほど興味をそそられなかった。
むしろ驚いたのは、問われるままに姓名を答えた途端、
「するとおぬしは阿古志連八束(あこしのむらじやつか)の弟か。なるほどそう思って眺めれば、面差しがよく似通っておるわい」
と詠が応じたことであった。
「あ、兄をご存じでおられるのですかッ」
大声を上げて寝台から起き直った廣手の額を、詠はぺしっと叩いた。
「おお、知っておるとも。これでもわしは、外薬官(とのくすりのつかさ)きっての鍼(はり)の使い手。高市(たけち)さまの母君には、いつも贔屓(ひいき)にしていただいておる。あやつが高市王家の大舎人であった折には、お屋敷でしばしば顔を合わせたものじゃ」
高市王子(たけちのみこ)は四十三歳。大海人(おおあま)の長男として生まれながらも、母の出自の低さゆえ王位争いから脱落。それでも世を拗ねもせず、太政大臣として義理の母・讃良を支える篤実な人物である。
太政大臣は大王の補佐を任務とする最高官。いわば高市は讃良の王太子として、次なる王位を約束された男でもあった。
「わが兄は高市さまの舎人だったのですか」
「なんじゃ、そんなことも知らなんだのか。その聡明さゆえ高市さまにひどく気に入られ、あれこれ身の回りのお世話を務めておったわい。されどそうでなければ、営造半ばの新益京に遣わされ、かような事故に遭いはせなんだのにのう」
詠の声がわずかに沈んだ。
「確か兄は作事場で、崩れてきた材木の下敷きとなったと聞きましたが」
「うむ、さようじゃ。かく申すわしが看取ったのじゃから、間違いはない」
「あなたさまが兄を――」
詠によれば、八束は卓越した武芸の腕を信頼され、高市から臣僚の一人として遇されていた。朝参の供はもちろん、造作中の新益京に派遣され、工事の進捗状況を報告する務めまで任されていたという。
事故が起きたのは、右兵衛府(みぎのつわもののとねりのつかさ)の兵庫(ひょうご)(兵器庫)に近い一画。土塀に立てかけられていた十数本の檜材(ひのきざい)が崩れ、乗っていた馬もろともその下敷きになったのだ。物音に気付いた役夫たちが急いで助け出したが、磚(せん)で頭を打った八束は意識を取り戻すことなく、二日後の朝、帰らぬ人となった。
「故郷には形見の品を送ったと聞いたが、死の詳細は告げられておらぬのか」
なるほど牟婁(むろ)には八束の遺髪が一束と、大刀を含めた形見数点が届けられた。だが書簡に記された死の経緯はあまりにそっけなく、詳細はほとんど述べられていなかった。それだけに兄の最期を知る医師との出会いに、廣手は数奇な巡り合わせを感じた。
「先生、もしよろしければ日を改めて、兄の話をお聞かせいただけませんか。なにしろ京に出てからこの方、八束は何の便りも寄越さず、僕は兄の暮らしぶりを皆目知らぬのです」
「おお、よいとも。されど日を改める必要などないぞ。おそらくおぬしとはこれから毎日、顔を合わせようでな」
意外な言葉に眼をしばたたくと、彼はなんだ知らなかったのか、と厚い肩を揺すり上げた。
剃り上げた頭から察するに、おそらく本業は僧侶だろう。さりながら太い声やいかつい体軀は、礼仏(らいぶつ)読経とはまるで縁がなさげであった。
「わしは外薬官の医師をしておるが、身柄は葛野王(かどのおう)家の懸人(かかりゆうど)。そしておぬしは大舎人として、その葛野王の許(もと)へ配属されると、すでに決まっておる。つまりおぬしとわしは今後、同じ屋根の下で暮らすのじゃわい」
「葛野王の――」
それまでの昂揚(こうよう)していた気分が突然、しゅんと音を立ててしぼんだ。八束が太政大臣高市に仕えていたと聞いた直後だけに、なおさらであった。
「なんじゃ、その不満面は。冷や飯食いの王家の舎人など、ご免蒙(こうむ)りたいと言いたげじゃな」
「い、いいえ。滅相もありません」
否定したものの、詠の言葉は図星であった。
なにしろ葛野王は、壬申の乱の際に自害した大友王子(おおとものおうじ)の一人息子。身分こそ王族だが、要は敗者である近江朝廷の生き残りである。

乱後、まだ幼児だった葛野は、母の十市王女(とおちのひめみこ)もろとも大海人の許に引き取られた。十歳で母を失ってからは、広大な屋敷と従者を与えられ、諸王の一人に列せられている。
血筋で言えば、讃良の甥(おい)。爵位だけは他の王族並みに高いものの、二十八歳の働き盛りにもかかわらず宮城では無官。ほとんど世捨て人に近い王親であった。
有体に言って、高市王子とは月と鼈(かわかめ)。空の綺羅星(きらぼし)と地上の小石ほどの隔たりがある。
(そりゃ僕は、八束に比べれば出来は悪いけどさ……)
官人の出仕には様々な階梯(かいてい)があり、宮城の警備をする兵衛や、各役所の雑用を果たす使部(つかいべ)(雑用係)に比べれば、貴人に仕える大舎人は格が高い。そう思えば落ち込む必要はないのだが、やはり出仕早々、貧乏くじを引かされた気分は否めない。
肩を落とす廣手を面白げに眺め、詠は分厚い唇を一方に引き歪めた。
「葛野さまは確かに、世から忘れ去られたお方。おぬしの如き若者には、頼りない主と映るやもしれぬ。されど古王子(ふるみこ)は古王子なりに、お仕えする喜びがあるのじゃぞ」
「はあ……」
生返事の廣手にはお構いなしに、彼は竈の鍋を下ろし、薪に灰をかけた。
「まあ、ここでわしと巡り合ったのも、何かの縁。今日はもう、新たな患者も来ぬようじゃ。退出には少し早いが、今よりともに葛野王家に参ろうぞ」
壁際に置いてあった雑囊(ざつのう)を担ぎ上げる詠の裾を、廣手は寝台の上から慌てて摑(つか)んだ。
「ま、待ってください、詠先生。まだ腹の痛みが癒えておりません」
「おお、そうじゃった。薬を与えておらなんだな。それ、とりあえずはこの丸薬を含んでおれ。王家に着いたら、薬を煎(せん)じてやるわい」
懐の竹筒から振り出された丸薬を三粒口に含むと、なるほど腹の痛みが薄らぎ、涼しい風でも吹き通ったかのように体が軽やかになった。現金なものでそうなると、目の前の医師を品定めする余裕すら湧いてくる。
(ひどく身勝手な御仁だが、この先生、実はなかなかの名医じゃなかろうか)
外では狗隈(いぬくま)が手持ち無沙汰な顔で、垢まみれの胸元をぼりぼりと搔いていた。その姿に、詠が軽く鼻を鳴らした。
「奴連れで宮仕えとは、さすがは評督(こおりのかみ)の坊ちゃまじゃな。まあ、よい。幸い葛野王家の奴婢溜まりには余裕があるわい。家宰(かさい)どのも小言は言われぬじゃろう」
元来た海犬養門(あまいぬかいもん)をくぐると、詠はそのまま真っすぐ大路を北上し、ひときわ繁華な町辻へ向かった。
小狭な店々が軒を連ねているところからして、ここが北の市なのだろう。売り手、買い手のかしましい大声と人いきれ……竹筵の上に蔬菜(そさい)を積み上げた脇では、魚や蝦(えび)がうごめく桶が、所狭しと並んでいる。買い物客目当ての煮売り屋台では、幾段にも積み上げられた蒸籠(せいろ)が盛んに湯気を上げ、周囲にうまそうな匂いをふりこぼしていた。
馴れているのか、詠は恐ろしく足早に人混みをすり抜けて行く。そのたびに鳴る腰の玉鐸が、遅れがちな廣手たちを急かしているかのようであった。
「どけどけ、ぼうっとするな」
小脇に油壺を抱えた男が、人々を突き飛ばす勢いで駆け抜ける。
うかうかしていると肆(いちくら)(店)につんのめりそうなほど、道は狭い。肩と肩が触れ合い、騒然とした熱気がそこここに充満していた。
「ところでおぬし、柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)とはかねてよりの知己か」
じゅうじゅうと煙を上げて焼かれている獣肉の串を三本求めた詠は、うち二本を廣手たちに投げて寄越した。
「いいえ、道中でたまたまお会いし、宮城にお連れいただいたのです。人麻呂どのの姓(かばね)は、柿本と言われるのですか」
受け取ったはいいが、いったいこれは何の肉だろう。いやそれ以前に、肉食は僧侶の禁の一つではないか。廣手の奇異の目にはお構いなしに、詠は行儀悪く串を横ぐわえし、さようか、とうなずいた。
「それで納得いたしたわい。おぬしのような田舎者が、京一の名物舎人と知り合いのはずがないでなあ」
「名物舎人ですか」
「さよう、人麻呂は爵位こそ低いが、その歌才たるや卓越非凡。しかも名誉栄達を望まず、行雲流水の態で生きる男じゃ。京に出てきた早々、あやつと近づきになるとは運がいい。されどどういう仔細(しさい)で、道中一緒になったのじゃ」
「はい、実は竹内峠近くで賊に襲われそうになったところを、忍裳(おもし)さまと仰られるお方とともにお助けいただいたのです」
その途端、詠は肉を咀嚼(そしゃく)していた口をぴたりと止めた。
「――忍裳さまじゃと。おぬしが申しているのは、三宅連(みやけのむらじ)忍裳どののことか」
「姓は存じませぬ。ただ常になき漆黒の官服を着した、年の頃、二十三、四の女性(にょしょう)です」
詠は残っていた肉を、無言で口に押し込んだ。まずいものをかみ砕くような顔で二、三度大きく口を動かすと、串を後ろ手に投げ捨て、「行くぞ」と顎をしゃくった。
あまりの彼の豹変ぶりに、廣手と狗隈は顔を見合わせた。何がなんだかわからぬまま、肉の串を握りしめて後を追う。
◇ ◇ ◇
連載一覧はこちら↓
日輪の賦 澤田瞳子

