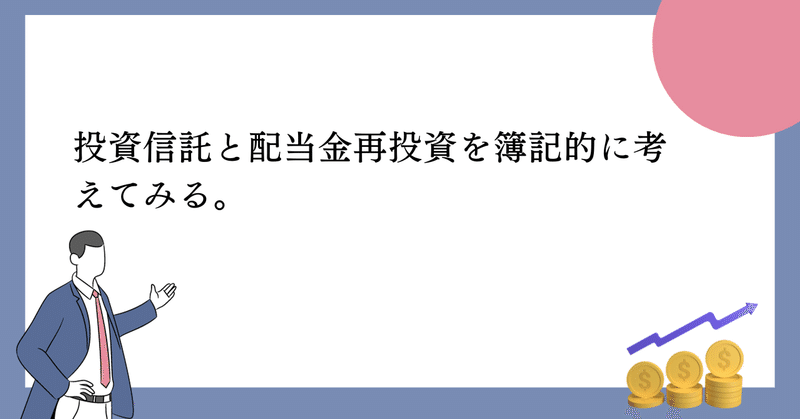
投資信託と配当金再投資を簿記的に考えてみる。
株式と投資信託を取得してから売却までの流れをあえて簿記の仕訳で考えて見ようと思います。あくまでも企業会計をベースにした考え方で、細かい設定はご容赦ください。
■株式(ETF含む)
株式を100万円購入し、配当金を3%(税率20%と仮定)で貰う。その後売却
・株式取得時
株式 100 / 現金 100
・配当金受取時
現金 2.4 / 配当金 3
税金 0.6
・売却時(配当権利落ちと時価=簿価と設定)
現金 100 / 株式 100
■投資信託
投資信託を100万円購入し、配当金を3%分がファンド内で再投資(税率20%と仮定)
・株式取得時
株式100 / 現金 100
・配当金ファンド内再投資(期末後再振替して消す)
株式 3/ 有価証券評価差額金2.4
繰延税金負債 0.6
・売却時
現金 102.4/ 株式 100
税金 0.6 売却益 3
この違いにどういった性質があるのかというと、配当金を貰うと実現損益になりますが、ファンド内での再投資だと未実現利益になります。
税金がとられない分有利になるのではないかという考え方もありますが、繰延税金負債というものが将来の税金に代わります。そして投資信託では売却時に課税されます。
投資信託では、ファンド内で再投資された分が複利効果を呼び、ズンズン資産形成がなされていきます。配当金を再投資しても税金分の0.6が不利になってしまいます。
この仕組みを理解していると、NISA制度では、税金と繰延税金負債がなくなり、配当金を再投資しても一緒の結果になります。
しかし、成長投資枠では,1,200万円の上限があるために、配当金再投資はNISA枠を新たに消費することになり、1,200万円非課税効果を最大限受けることが出来なくなってしまうという事になります。
でここで、「新NISAでは高配当投資をするな!」みたいなフレーズが生まれるわけです。
これには少し限定されることがあって、成長投資枠が埋めきれる自信のある方は「新NISAでは高配当投資をするな!」そうじゃないと非課税効果を最大限受け取れなくなる。というと理解しやすいと思います。
もちろんこれは、米国ETFのVTと全世界型の投資信託や、VOOとS&P500連動型の投資信託でも同じ構図が成り立ちます。
だけど、単身で1,200万円の成長投資枠、夫婦で2,400万円分の成長投資枠を埋めれる世帯はどれだけあるのでしょうか?ましてや積立投資枠を含めると一人で、1800万円です。
仮に資金があったとしても、比較的多額の資金をリスク資産にシフトさせることがいいのかよくわからない。
新NISAが始まって、煽り報道があるので、焦ったりせずに投資する方は投資した方がいいと思う。焦りは正常な判断ができなくなる可能性があります。
お金の向き合い方、投資との向き合い方は人それぞれだと思うし、違っていいと思う。
自分が心地いい投資(投資しない事含めて)を長期で出来ればと思う。
もしよろしければスキやフォローお願いします。
励みになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
