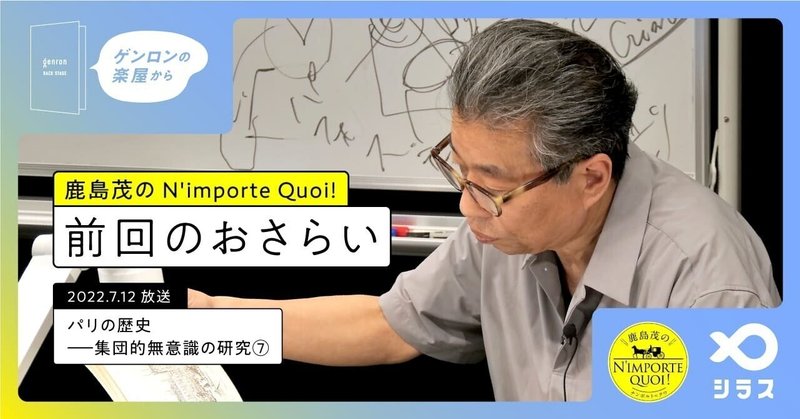
盛り場西漸説の検討──鹿島茂のN'importe Quoi!「前回のおさらい」
シラスで好評配信中の、フランス文学者鹿島茂先生による講座チャンネル、「鹿島茂のN'importe Quoi!」をご覧のみなさんも、そうでないみなさんもこんにちは。このチャンネルで聞き手を務めさせていただいております、ゲンロンの野口です。
みなさんは「盛り場」と聞いてどんなイメージを持ちますか?わたしがパッと思いつくのは、バンバンバザールというバンドの「盛り場に出ていこう」という曲です(※バンバンバザールには同じくシラスでチャンネルを運営している丸山朝光さんもライブメンバーとしてよく参加されています!)。
曲の中で♪銀座~赤坂~六本木~……♪と街の名前が出てきますが、はて、どの街が「盛り場」なのかはどこかに定義があるのかしら?と調べてみると、警視庁のサイトに「東京都内における主要な盛り場」というページがありました。へぇー。
さて、こちらの記事ではそんな「盛り場」がテーマであった7月12日の「盛り場西漸説の検討【パリの歴史──集団的無意識の研究・第7講】」をおさらいしていきましょう!

1.「盛り場」の定義
さて、まずはそもそも「盛り場」って何だろう?というところから考えてみましょう。
先ほどの警視庁の「東京都内における主要な盛り場」では、新宿歌舞伎町地区について「多くの娯楽・商業施設、飲食店等が乱立する『眠らない街』」と紹介されています。しかし鹿島先生は単に人が大勢集まり、飲食店や歓楽街がある……だけでは足りないのではないか、といいます。「盛り場」足るにはその場における「階級の混在」とそれがもたらす「階級移動の夢」があること。それが盛り場の条件であり、それがパリにおいて成立するのは18世紀後半から19世紀にかけてではないか、というのです。
では18世紀後半からと、それ以前で「人が大勢集まる場」はどう違ったのでしょうか?
人が集まる場所としての”市”や”商店街”は古くから存在していました。例えばフィリップ・オーギュストの時代に成立した様々な”市”の集合体(「レ・アル」(パリ中央市場)として1969年まで維持されたそうです!)。あるいは橋の両側に建物が建てられ、Le Pont Au Change(ル・ポント・オ・シャンジュ シャンジュ橋)と呼ばれた両替商や貴金属商などが集まったいわば橋上商店街。


いまのパリには残っていませんが、フィレンツェのポンテベッキオ橋を思い浮かべていただくと
雰囲気がつかめるかもしれません……
『19世紀パリ時間旅行──失われた街を求めて──』(鹿島茂、青幻舎 P45)より
しかし、前者で行われていたのはあくまでも等価交換としてのやり取りであり、後者は未だ度量衡がフランス全土で統一されていなかった時代にパリに集まってきた人々のためであったり、逆に遠方にお金を送るために必要な為替のやり取りであったり、と必要に応じて生まれた場所でした。そこでは「階級の混在」も「階級移動の夢」ももたらされてはいません。
では、18世紀後半の取引では何が変わっていたのでしょうか?1つのヒントとなるのが、鹿島先生も伝記をまとめたイタリア出身の色男、カサノヴァの残した記録。18世紀にパリを訪れたカサノヴァが目にしたのは大繁盛の香水屋(帽子屋だったかもしれない)。人々がこぞって求めるその理由は「オレルアン公の妻がひいきにしているから」でした。
こういった購買動機を鹿島先生は「ヴェルサイユを買う」と表現します。人々は、それを買った分だけオレルアン公に、あるいはヴェルサイユに近づける、というような幻覚を持つようになる……なぜこういう幻覚を持てるようになったのか、その背景についてはぜひ動画でご確認ください!
2.階級が混じりあう「犯罪大通り」
さて、同じころ盛り場成立の条件にあった「階級の混在」が実際に起きていた場所があります。それがシャルル4世の城壁が取り払われたあとに作られた「タンプル大通り」、通称「犯罪大通り」です。

タンプル大通りの様子と天井桟敷の人々。
そもそも「タンプル大通り」と名付けられたのはこのあたりがテンプル騎士団の領地だったからなのですが、気になるのはこの非常に物々しい「犯罪大通り」という別名です。その名づけの理由となったのは、この通りに数多く立ち並んだある娯楽施設でした。
タンプル大通りは1760年代から発展が始まり、シャトー・ドーという階段状の噴水や、Vaux Hall(ボックス・ホール)と呼ばれる一種の遊園地的なもの、さらにダンスホールやレストランも並ぶようになりました。さまざまな遊興施設のなかでも欠かせなかったのは、当時人々に人気の娯楽だった演劇を行う劇場です。
タンプル大通りの劇場ではさまざまなメロドラマが上演されていました。この「メロドラマ」という言葉の語源についても講義の中では解説されているんですが、どの芝居でも必ず犯罪が起こる、ということから「犯罪大通り」と呼ばれるようになったそうです。当時の様子を知るのに最適なのが1944年に公開された名作映画『天井桟敷の人々』。街の雰囲気はもちろん、劇場の様子、人々の暮らしもわかるので、ぜひお時間あるときにご覧ください!
※Amazon Prime Videoでも字幕版が見れます!(2022年8月現在)
さてこのタンプル大通りは、おもに通りの北側は劇場やボックスホールのある大衆街、南側は高級レストランやダンスホールなどそれまでヴェルサイユにいた貴族たちや革命後に力を持った上流階級の人々向けの施設が並んでいました。
しかし、通りを挟んだ向こう側とこちら側、ぐらいのレベルの距離感。上流階級の人々もボックスホールに遊びに行ったり、劇場のボックス席(舞台そのものは見えづらいけれど、客席からはよく見える、むしろ客席の人々にアピールするためのドーダ!用の席です!)にも行きますし、逆に南側のレストランにも大衆たちがハレの日に行く、といったような混在が起こるようになっていきました。

この冊子、ほしい……
このタンプル大通り、実は現代のパリにはほとんどその痕跡は残っていません。この講座でも何度がご紹介しているオスマンのパリ大改造によって、なくなってしまったのです。
3.そして盛り場は西へ
このように、オスマンの大改造によって……ではなく、その数十年前、19世紀前半頃からシャルル4世の城壁のあとに作られたブールヴァールを西に行った、ブールヴァール・デジアリアン(des Italian)のほうへ移っていきます。1820年にはオペラ座も移転してくるなど、賑わいを見せます。
そこで栄えたのがルイ15世広場(現:コンコルド広場)につながるロワイヤル通り。そこからさらにシャンゼリゼを経て、エトワール凱旋門を越え、時にはトロカデロ広場のほうまで馬車でめぐる「ロンシャン」が流行ったそうです。

さて、ここでいうロンシャンとは、現代のパリの西、ブローニュの森を越えた先にある、ロンシャン競馬場のことではありません。そこで指されているのは中世に建設された女子修道院。鹿島先生曰く「貴婦人たちの高級養老院」というこの修道院には、夫と不仲になったり、未亡人になった上流階級の婦人たちが優雅に暮らしていました。暇と金を持て余した彼女らと修道女は自分たちで演劇を始め、徐々に本格化。いつしかパリ市内から本業の役者を招いたり、修道院の中に劇場をつくったり、と活発な活動をするようになったのです。それを見に行く、ということで上流階級の人々は馬車に乗ってロンシャンの修道院に向かうようになります。
いつしかこれが毎週になり、最新の馬車に乗り、最新のファッションに着飾って、通りから眺める人々に向けて行われた「習慣化された富の衒示」を「ロンシャン」と呼びました。途中、日光浴が行われたテュルイリー公園や、ロワイヤル通りの北にできたジェラート屋、Cafe Tortoni(カフェ・トルトーニ)は貴婦人たちのたまり場になっていったといいます。

見ている若者の中には「俺も馬車が買いたい!あの列に加わりたい!」とあこがれる若者もいたことでしょう。テュルイリー公園ではバルザックの『ゴリオ爺さん』に描かれている青年・ラスティニヤックよろしく、成り上がり願望のある若者たちが、貴婦人たちの目に留まるべくお金をかき集め、一張羅のスーツを仕立てて歩いたり、ナンパしたりといった、ある種の恋愛の脱階級化も行われていたそうです。
また、西に移った盛り場では「アングロマニア」と呼ばれる「イギリスかぶれ」のスタイルが流行します。中心地となったのはCafe de Paris(カフェ・ド・パリ)。そこには逆に「フランスかぶれ」であったイギリスのシーモア卿が屋敷を構え、博打で財産を失い、その1階を貸し出す、といういつかのパレ・ロワイヤルで聞いたような流れがあり、そのテナントに入ったのがカフェ・ド・パリでした。
カフェ・ド・パリは、イギリス式にモラルにも厳しい超高級レストランだったようなのですが、それでは納得がいかないのがパリの人々。付近にはメゾン・ド・レ、カフェ・リッシュ、マキシム・ド・パリといった新たなレストランがオープンし、深夜営業、個室、そして高級娼婦というセットで営業したといいます。
そこで無限にお金を使って遊んでいたのが、のちのイギリス国王エドワード7世、当時はまだプリンス・オブ・ウェールズ、皇太子でした。彼が残した伝説も色々あるようなのですが、重要なことは彼のような金持ちにあこがれて人々が集まり、その伝説が小説などを通して再生産され……というサイクル。さきほどのテュルイリー公園の話でも、実際に貴婦人の愛人となって出世したやつがいる!となれば、またそれにあこがれる若者が再生産されていきました。
こうして人々のあこがれや願望など、さまざまな欲望を飲み込むパリの盛り場は、20世紀前半、第一次世界大戦のころまで大きな賑わいを見せていくのでした。

4.次回放送は8月9日!今度はシャンゼリゼ。
さて、鹿島茂のN'importe Quoi!は、7月から第2シーズン!ということで、引き続きパリの歴史に関する講座と、エマニュエル・トッドの家族人類学に関する講座をそれぞれ月1回ずつ配信中。毎回さまざまなテーマでお送りしています。
次回の放送は明日8月9日!引き続き「盛り場」をテーマに、まずはシャンゼリゼ通りを取り上げます。どうぞご期待ください!
また、先月末に放送した講義回とは別のシリーズ、稀書探訪シラス版#5 「パスカルで読み解く PASSAGEの愉しみ」が、図らずもいい具合にN'importe Quoi!の雰囲気を感じてみるのによい!というコメントもいただきました。税込330円とお求めやすい価格となっておりますので(と、言っても鹿島さんの講座3時間分が1100円というのもかなり破格だと思うのですが……)、どんな感じの放送なのかな、開始ちょっとよりももう少し長めに聞いてみたいな~という方は、こちらもぜひお試しください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
