
口の悪い少女 シゲカズです
信頼と実績のシゲカズと申します。
三か月お世話になった口の悪い少女の物語も最後となりました。
第三話はこれを書きたいが為に始めたと言ってもいいくらい最初から書こうと思ってたお話です。
ぼくは超絶おばあちゃん子ですがおばあちゃん子に特におすすめです。
この話だけ見た人でも多分楽しいとは思いますが、第一話から見ると10倍は楽しいと思います。
読んだ事ない方もほぼ忘れてしまった方も絶対にこれしか読まないと決めている方も、
少女はイライラしている時は鼻をピクピクさせ、
楽しい時は頬っぺたを膨らませたりするという事だけ知っといてもらえれば大丈夫です。
それではこれをお読みになられたあなた様の日々が少しでもマシになったら幸いです。
祖母
3月27日
「絶対見舞いに決まってるやろアホなんか」
ナースステーションを通り過ぎる時
「今日はどうしたの?」
と話しかけてきた看護師に、私は鼻をピクピクさせながらそう言い返す。
驚いた看護師が何か言いたそうにしているのを無視して個室病棟にある501号室に向かう。
病室につきドアを開けると、ベッドを半分ほど起こし、窓の外の風を浴びながら祖母が眠っていた。
家から持ってきたカバンをサイドテーブルに置き、寝ている祖母に話しかける。
「着替え持って来たったぞクソババア起きんかい」
少し間があって祖母が目を開き体を寝かしたまま私の方を見て、ゆっくりと諭すように話しかけてくる。
「遅いねんほんまトロいガキやの」
私は小学校でも口が悪すぎて伝説になるくらい口が悪いとよく言われるが、そうなったのは間違いなく祖母の影響だ。
両親が共働きでほとんど家にいないせいで、私は生まれて間もない頃から同居している祖母に育てられてきた。食事はもちろんお出かけや習い事の送り迎えや授業参観なども全て祖母がやってくれていた。
祖母は家事全般や子育てはうまかったので、私は何不自由なく、すくすくと育ってきたつもりだが、とにかく口が抜群に悪かった。
一番古い記憶は7年前私が3歳の時に、黒い線がぐちゃぐちゃになってるだけの祖母の似顔絵を描いて
「ババア、アゲル」
と渡した時、
「こんなもん陰毛やんけなめとんかい」
と最低の感想を言われたことだ。
他にも折り紙でウサギを作って渡した時も
「ババア、アゲル」
「紫のウサギて色考えろやきしょいねんドチビ」
と瞬時に言い返される。
その最強に口の悪い祖母の言葉使いで人間の言葉を覚えた私は、ネイティブに悪口を言える生き物に成長していったのだ。
「ガリガリすぎ。孫に気つかわすなよザコが」
「お前みたいなゴミは話してもらえてるだけで感謝せえよ」
病院の中庭で祖母が乗っている車椅子を押しながら二人でいつものように会話をする。
少しの時間でも外に出ると祖母の体調が良くなるので毎日の日課になっている。
遠くから優しい目で見てきているおばさんは、素敵ねウフフ、みたいな感じでこちらを見てきているがまさか悪口の応酬をしているとは思ってもいないだろう。
といっても私達にとっては別に喧嘩をしてるわけではなく
「おばあさん。きれいなお花が咲いてるわね」
「本当にきれいねえ」
みたいな会話をしているのと同じようなものなのだが、
以前もファミレスで
「しわしわの顔見ながら飯食うのまずいねんどっか行けや」
「お子様ランチ食いながらイキんなよ小娘」
といつも通りの会話をしていたら、店員が心配そうに駆け寄ってきた事もあった。
入院しても毎日私と無限にラップバトルをしているように悪口を言い合う祖母は、もうすぐ死ぬらしい。
数日前母に「覚悟しといてね」と言われた時は、ほぼ死ぬって言ってしまってるやんけとびっくりしたが、
「誰も面倒見てくれんからって私にばっか頼んなよ老害」
「貴様は死ぬまで一人やけどな」
と変わらないやり取りをしているとよくわからない不思議な気持ちになる。
祖母には私の両親以外に身寄りはないのでお見舞いにはほとんど誰も来ない。私が生まれる前には祖父は亡くなっていたし、友人もゲートボール仲間のおばあさんが一人いてその人がたまに顔を出すくらいで、それ以外は私は見た事がない。別に祖母は全く気にしていないし、むしろ
「めんどい人間関係なくて最高の人生」
とよく言っている。
私自身も友達はできないとあきらめていたが、奇跡的に心が許せる友達が一人いる。どこにでも一人は寛容な人間がいるらしい。
病室に戻ろうと色とりどりの花が並んでいる花壇を通りすぎる。
そういえば数年前鮮やかな青色の花を見つけたので持って帰り、
「ババア、貴様ごときにもったいないがくれてやる」
「花とかもらってどうしたらええねん。捨てるのも気悪いしゼロ点」
と言われた事もあったななどと考えながら病室に戻ると、唯一の友人、名付けてゲートボールババアがベッドの横の椅子に座っていた。着物を着て年寄りとは思えないほど姿勢が良く、見るからに上品そうな雰囲気だった。
そんなゲートボールババアを見て、祖母が頬をぷっくりとしながら口を開く。
「病院で着物て、ババアやのにまだイキるやん」
ゲートボールババアは嫌そうにするわけでもなく優しく言い返す。
「やめて、トリちゃん」
祖母とゲートボールババアがババア特有の昔話をしている。
どうやらゲートボールババアはユウという名前で、祖母の小学校からの幼馴染らしく、昔転校して行ったが、結婚して再びこの街に帰ってきたという事らしかった。ゲートボール昔話は信じられんくらいどうでもいい話だったので、あまりの長さに無意識に鼻をピクピクさせる。イライラするとついしてしまうこの仕草も祖母がやっているのが自然と移ってそうなった。
「ほんま飛鳥ちゃん、小さい時のトリちゃんにそっくりね」
「なれなれしく話しかけんな下等生物」
「お年寄りに下等生物とか言ったらだめよ」
少し話をした後、ゲートボールババアは腰を上げる。
「じゃあねトリちゃん。また明日来るわ」
「明日がいつもあると思うなよ」
吐き捨てるように祖母に言われ、ゲートボールババアは何かを懐かしむ顔をした後笑った。
笑いすぎたのか目が潤んでいるように見えた。
私はその場でお別れするのもいやらしいので、祖母を病室に残し、一応エレベーターまで送ることにした。
エレベーターに乗り込む際に話しかけてくる。
「トリちゃんは、いっつも飛鳥ちゃんの話ばっかりするのよ。飛鳥ちゃんが好きで仕方ないのね。だからできるだけそばにいてあげてね」
「ゲートボールババア……」
「ゲートボールババア?」
ゲートボールババアを見送って病室に帰り、ゲートボール土産の桃を食べ終えたら今日は帰ろうかなと思っていたが結局帰れなくなった。
祖母の容体が急変したのだ。
ピッピッピッピッ
窓の外はいつのまにか薄暗くなり心臓の機械の音だけが病室で鳴っている。今にも止まりそうな弱弱しい勢いだ。
仕事場から駆け付けた両親が先生と話をしている。
先程まで悪態をついていた祖母は鼻には管をつけ、口には人工呼吸器がつけられている。
私はベッドのすぐ横にある椅子に座り、どうしていいか戸惑いながら、祖母のやせ細った手を離さずにずっと握っていた。
母が近づいてきて私に話しかける。
「おばあちゃんにお別れの挨拶をしなさい」
そう言われて祖母の方を改めて見て、話しかけようとする。
死なんといてや。
もっとご飯作ってや。
もっと遊んでや。
もっとしゃべろうや。
一緒に寝ようや。
一人にせんといてや。
心の中では色々な感情が沸き起こっているがどうしても言葉にする事ができない。
育ててくれてありがとう。
一緒にいてくれてありがとう。
遊んでくれてありがとう。
ただ何も言うことはできず手を強く握る。
するとほんの少しだけ祖母の指に力が入る。
そのかすかな感触を感じた瞬間、私はようやく口を開くことができた。
「ババア鼻に管付けて最後めっちゃキモいやん」
いつものように、吐き捨てるように、いつものような事を言った。
祖母の目が少しだけ開いた。すぐさま私は泣いているというよりびちゃびちゃの顔を、しわしわの祖母の顔に近づけると祖母はゆっくりと口を開いた。
「鳥に……生まれ変わって……絶対お前に……フン落としたるから……覚えとけよクソガ……キ」
「名前が鳥やからややこしいねんボケてんか」
私のその言葉には返事はなく、再び眠るように目を閉じ、微笑むかわりに頬っぺたを膨らませながら、祖母は私のいない世界に飛んで行った。
3月29日
葬式を終えた後、私が祖母の部屋の遺品整理をする事になった。
きれいに整頓されている祖母の部屋を色々と物色する。金庫があったので取り出し、事前に聞いていた番号を入力しカギを開ける。
中にはまあまあの札束やでかめの宝石などが入っていた。そういえば昔、祖父が泥棒だからうちは金持ちなんだと言っていた。あの時はさすがに冗談だと思ったが、もしかしたら本当だったのかもしれない。
きらびやかな宝石やお金と一緒に、国語辞書くらいの大きさの箱があったので取り出してみる。ふたを開けると中にはくすんだ色のものが目に付く。
黒い線ばかりの、陰毛と言われた似顔絵。
紫色の折り紙で折られたウサギ。
元々は青だが枯れ切ってしまった押し花。
私が小さい時にあげたものばかりだった。
そして一番下に、
飛鳥へ
と書かれた手紙が入っていた。
封筒から勢いよく紙を出し目を向けると真ん中に短く一行だけ書いてあった。
「お前がくれたもん残してるからって調子乗んなよマジで。いやマジで」
私はその紙を笑いながらおもいっきり投げ捨てた。
遺品整理がひと段落し、私は祖母とよく行っていた公園に行く事にした。
公園ではいつもの年より少し早く、桜が満開に咲いている。
それを見上げながら歩いていると、ふいに頬っぺたに冷たい感触を感じる。花びらかなと思い触ってみると花びらではなく鳥のフンだった。
空を慌てて見てみると、一羽の見たこともないような鮮やかな色の小鳥がちょうど私の上をくるくる飛び回っている。
それを見て私は頬っぺたを膨らませながらつぶやいた。
「生まれ変わるん速すぎるやろクソババア」
終
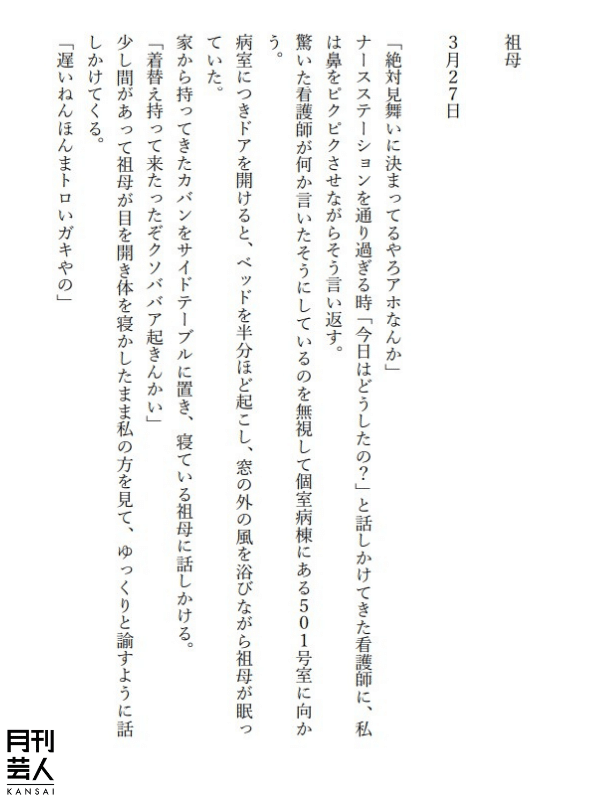
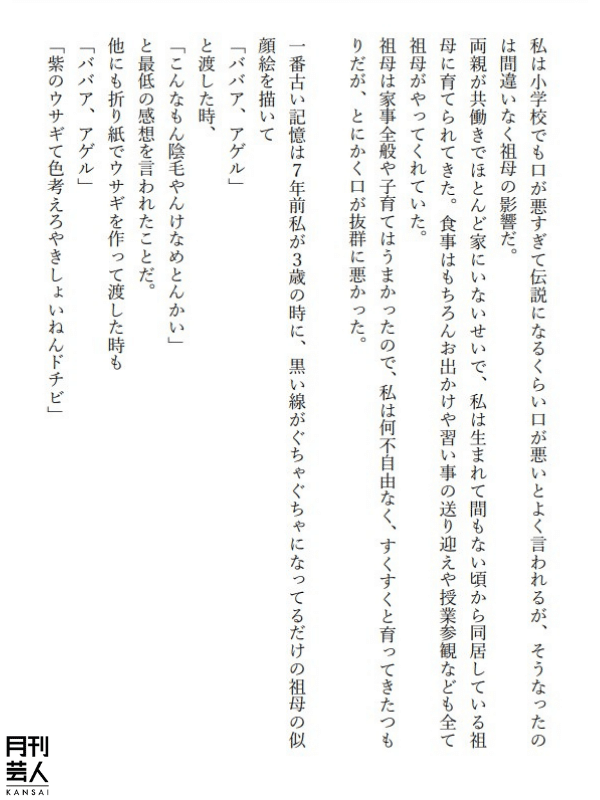
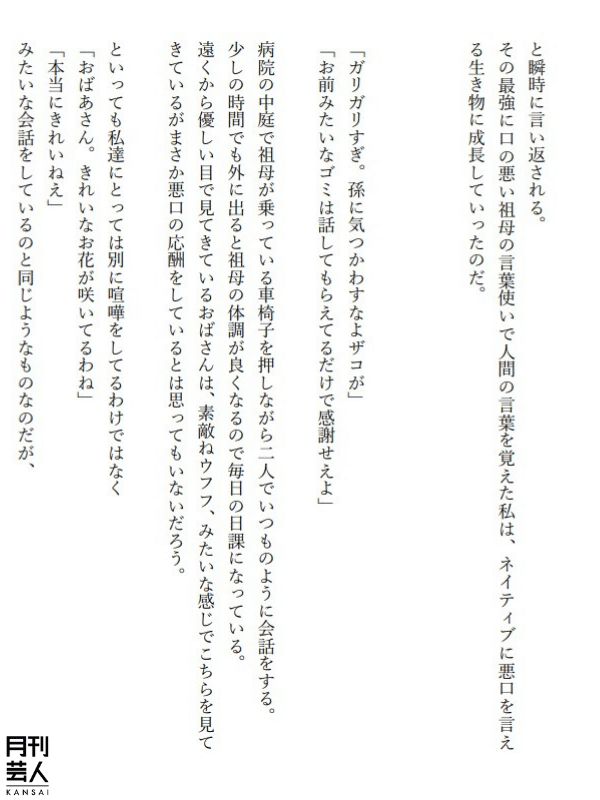
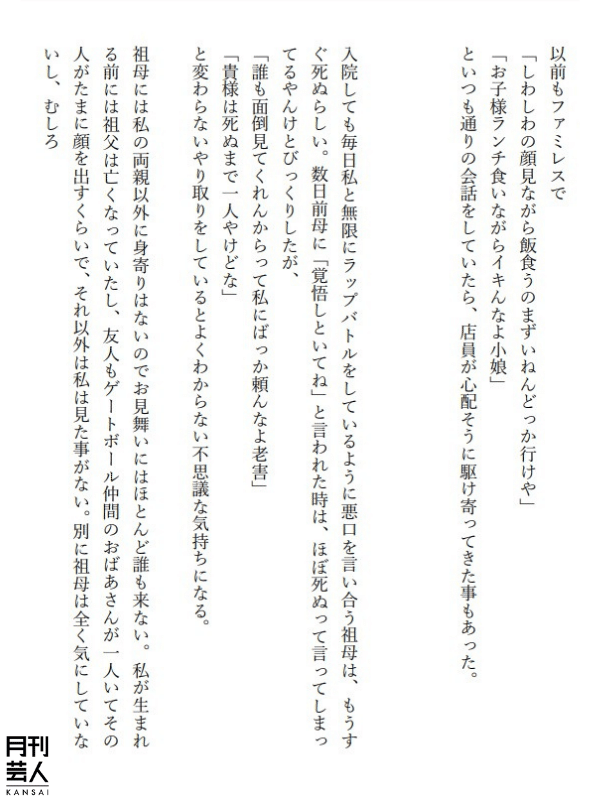
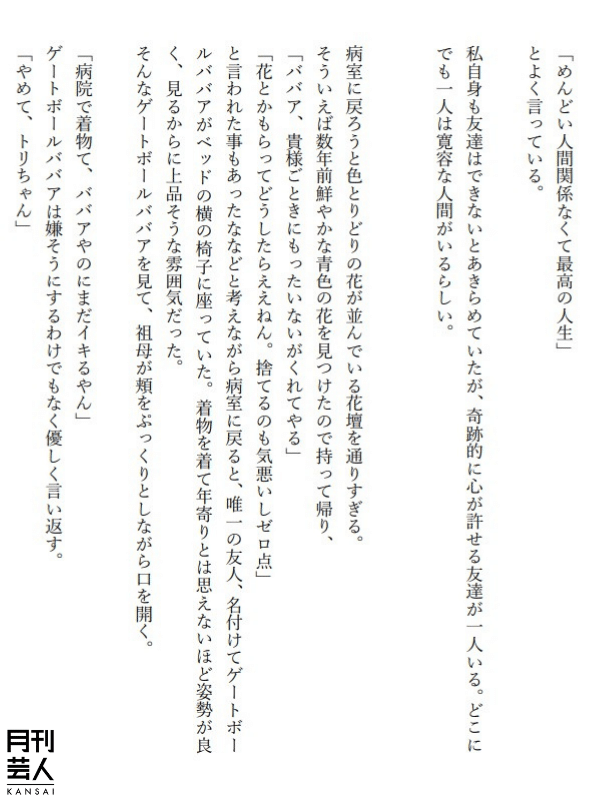
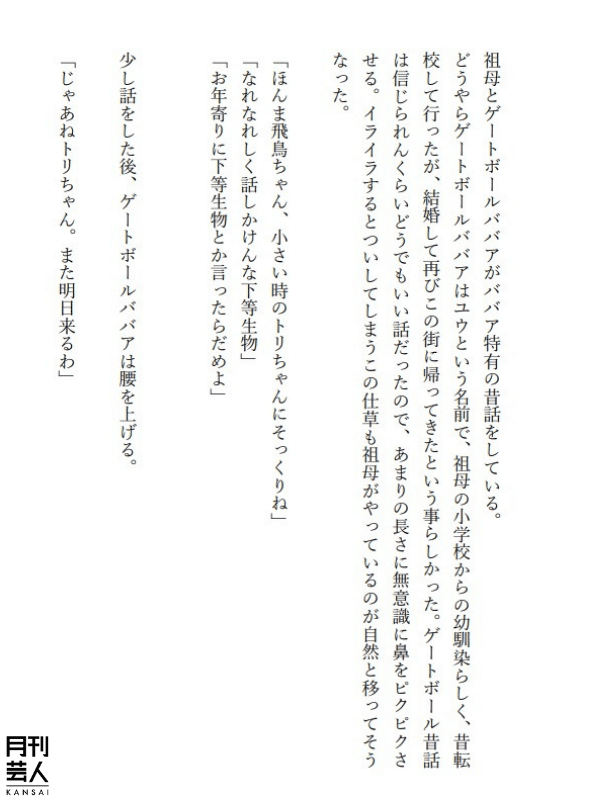
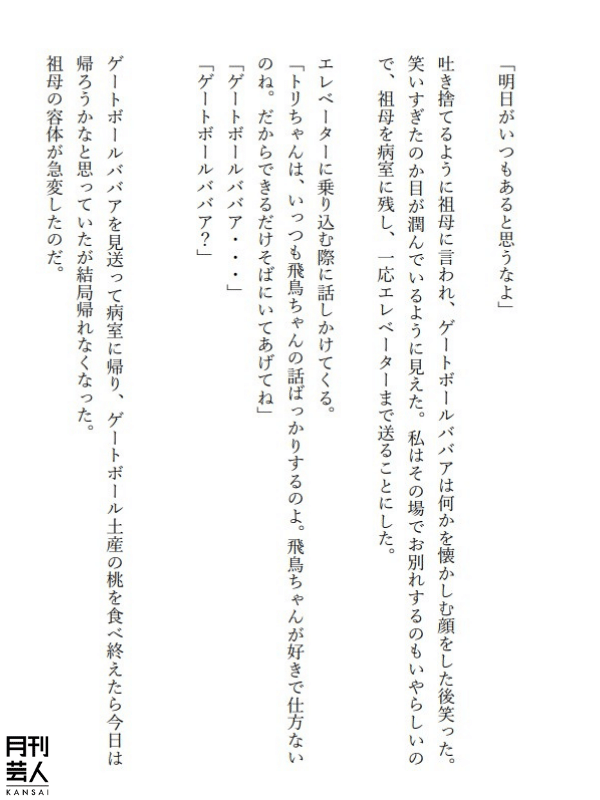
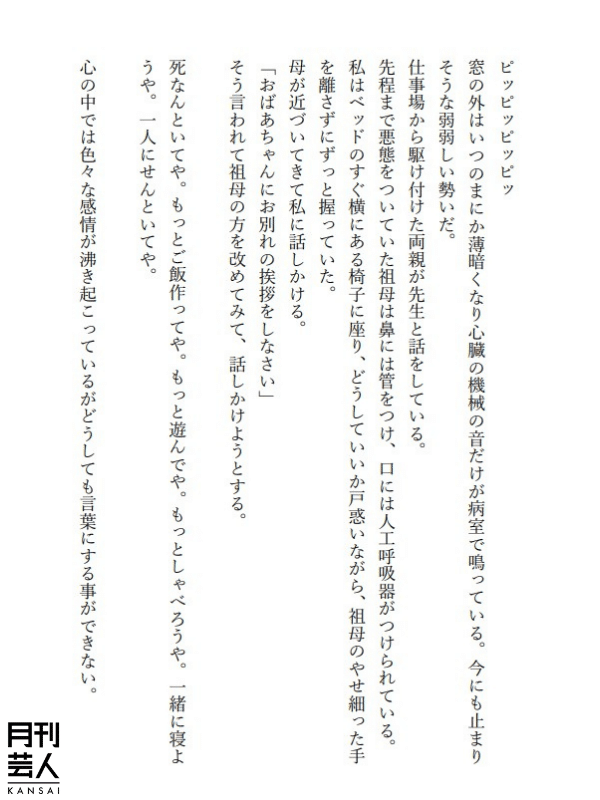
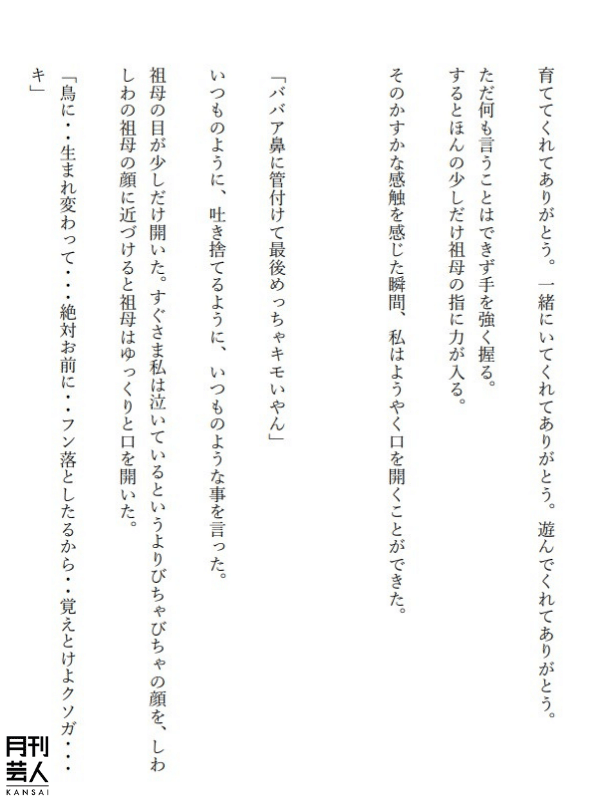
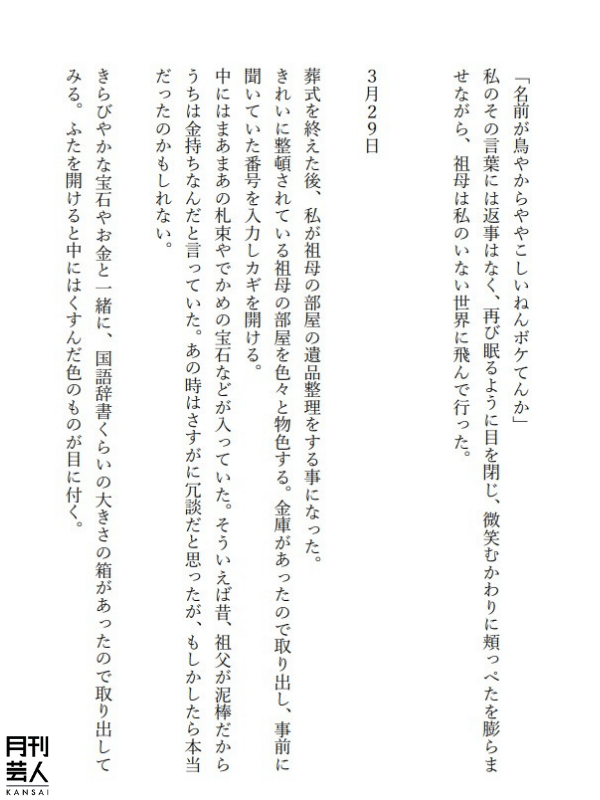
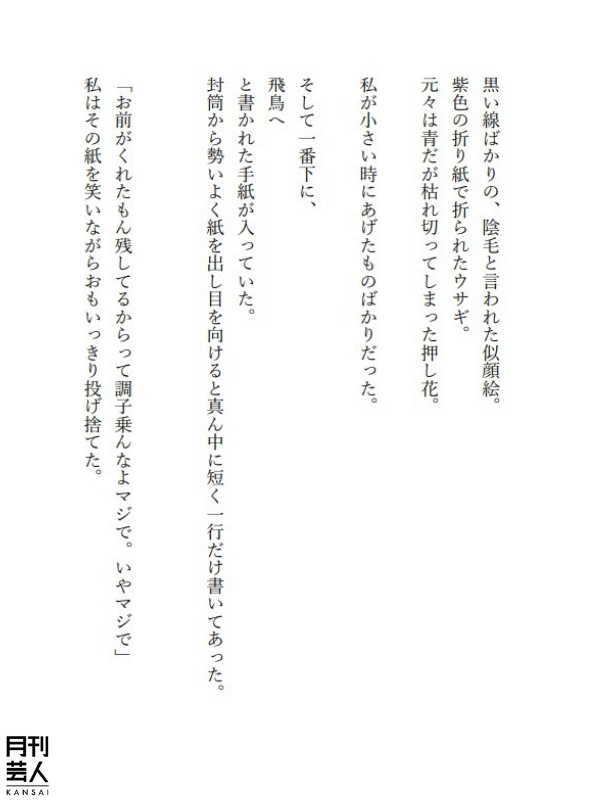
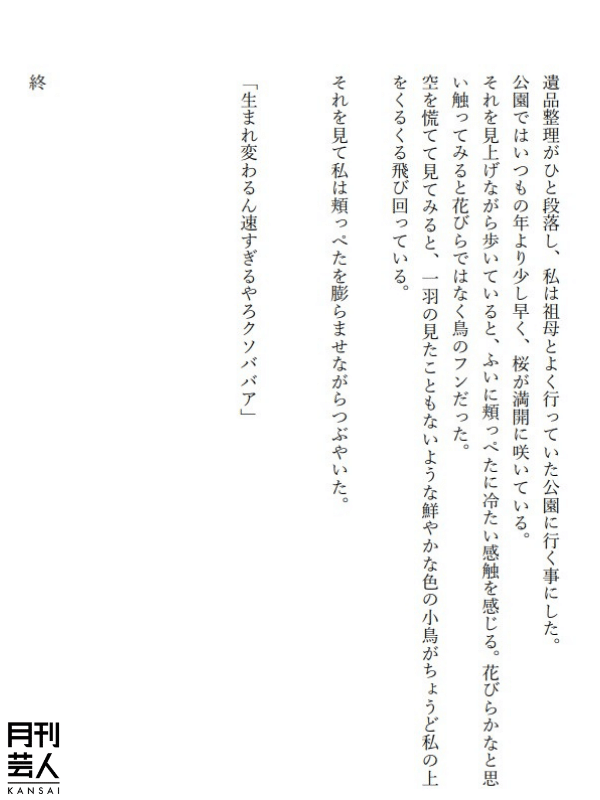
■シゲカズです プロフィール
NSC大阪校 31期生。
趣味は散歩、温泉巡り。特技はイラスト、気持ち悪い人と友達になれる。
シゲカズですINFO
著者/シゲカズです
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
