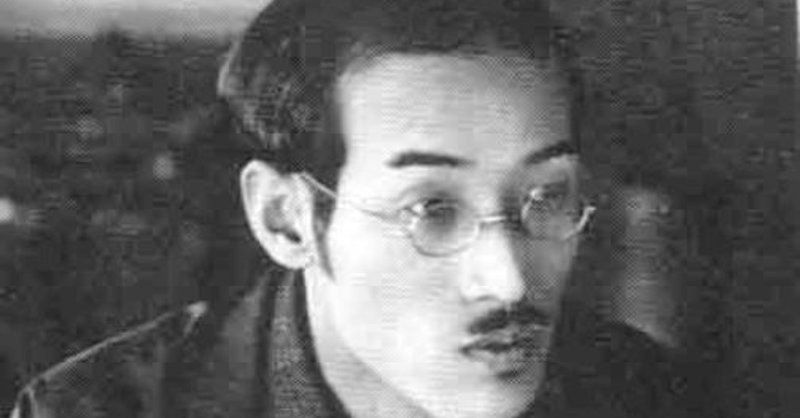
【短篇小説千本ノック1】誤読に誘う狂いのしぐさ――宇野浩二「蔵の中」
そして私は質屋へ行こうと思い立ちました。私が質屋に行こうというのは、質物を出しに行こうというのではありません。私には少しもそんな余裕の金はないのです。といって、質物を入れに行くのでもありません。私は今質に入れる一枚の著物も一つの品物も持たないのです。そればかりか、現に今私が身につけている著物まで質物になっているのです。それはどういう訳かというと、……(宇野浩二「蔵の中」以下太字部分は同作の引用)
こんな人を舐めくさった書き出しからはじまる「蔵の中」という小説は、質入れした着物の虫干しをめぐる語り手「私」の奇矯なふるまいを綴っていくかに、ひとまずはみえます。が、実のところその語り起こしとは、それ以降、確信犯的な千鳥足ともいうべき文体で縷々紡がれゆく脱線行のフックにすぎず、あたかも作者は、小説という形式そのものを煙に巻こうとしているかのようです。
「蔵の中」の語り手たる「私」(山路さんと呼ばれています)は、一応のところ作家として生計を立てている独身の四十男です。作家とはいえ、作中、彼は特段作家らしいことをしない。起床し、朝食をとると、昼頃には女中に起こされて昼食を済ませたかとおもえば再び万年床に潜り込み、夕餉の時刻にはまたぞろ女中に起こされ……というあんまりなルーチンで成り立っています。日がな一日遊んでいるのですから、無論、お金がない。質屋の常連なのです。
そんな「私」が唯一活動的になるのが夕飯後のそぞろ歩きですが、それとて目的はどうにも下衆じみており、要するに手元不如意がため、頻々と通うこともかなわぬ芸者街を彷徨しては、その辺にいる芸妓や半玉の顔貌や髪型、着物の恰好を観賞するのが楽しみなわけです。浅間しい人です。
どんなに目鼻立ちのわるい女でも、芸者と名のつくかぎり、どこかその著物や髪形に取り得があるものです。また、若い女というものには、何となく優しい、何となく色気があるものです。あれが何ともいえません。いや、恥じをかまわず申すのです。若い女に限りません。女は、あれのある間の女は、たとい顔が感心できなくても、恰好がいいとか、恰好が余りよくなくても髪形が綺麗だとか、髪形もわるく、どこも取り所がなくても、著物が綺麗だとか、とにかく私にとっては、世の中に、あれのある間の女に捨てる女は一人もありません……
ここで小説は、冒頭に出てきた着物の話に接続されます。いったいにこの「私」は女好きもさることながら、彼女たちが装う着物にも非常な関心を持っていて、曰く、「女が好きなのと優るとも劣らぬくらいに、私はまた著物が好きで好きでたまらないのです」。
この着物好きは「私」自身にも適用されるもので、時間を持て余したときなどは(まあ、いつもなんですが)、持っている着物をとっかえひっかえしては、ひとりファッションショーを開催したりしています。どこまでもヒマな人ですが、再三述べるように彼には経済的余裕がない。そのため、新しい着物を購っては、次のシーズンにはもう質に入れている。そうしてあぶく銭が入ると、懲りずにまた着物を新調する。そんなこんなで質屋の蔵には、彼専用の衣装箪笥まで置かれてあるのでした。
とはいえ、貧乏たらしく、ナマケモノで、ナルシシストで、物質主義で、女とみると脊髄反射的によだれを垂れ流す「私」は、この時代の文士の例に漏れず、なかなかどうしてモテるらしい。現に進行中の物語のなかでも、質屋の旦那の妹(出戻りのヒステリー美人)とちょっといい雰囲気になっている。実際、作家・宇野浩二の女性遍歴はそれなりにきらびやかなもので、幾人かの愛人たちと浮名を流しています。そういうわけで、このあたりの事情にある程度通じている人ほど、ああ成程、それではこの「私」とは宇野浩二自身のことなのだな、と思い込んでしまう。それが本作の、小説としてのしたたかさです。
『思い川・枯木のある風景・蔵の中』(講談社文芸文庫)に収められた水上勉の解説によると、この「私」のモデルは、書生時代の近松秋江だそうです。宇野は近松の質屋通いのエピソードを親友の広津和郎から聞いて「蔵の中」の着想を得たようですが、いずれにせよ「私」に作者自身の影が反映されているのは間違いない。否、むしろ、先にも述べたように、そうした「私」=作者という読者側の誤読を誘発する構造と文体こそが、この短篇に仕掛けられたブービー・トラップなのです。
今、私は著物とその思い出についてなど、と、しかつめらしい言葉をはきましたが、実をいうと、この縦横の綱にぶらさがっている著物の一つ一つを一と目見ただけで、私には、思い出すべからずと禁ぜられても、何一つ女の思い出を呼びおこさぬものはありません。たとえば、私のすぐ頭の上にぶらさがっている越後上布の絣の帷子と、紺地に夜目にはほとんど見えないような藍の瀑縞の絹縮と、濃鼠の立絽の薄羽織と、それから薩摩上布との一と組です。それに、この一と組に属するのですが、引き出しの所属がちがっていますので、この中には見えませんが、お召セルの袴とです。
これ以降、物語は「私」とその着物にまつわる女性たちの思い出にするすると移行していくのですが、それはさておき、小説という形式において、作者はいくつもの「私」を使い分けています。たとえるなら、着物をとっかけひっかえしているようなものです。読者はといえばそうした作者の分身(のように思われている作中人物)の言動や思想に触れ、あたかも作者自身の人となりを知った気になるわけですが、それは先ほどした引用のなかで、寝そべった「私」が虫干しした着物を見上げつつ、その着物に付随する思い出を想起している状態に似ています。あくまでそれは着物です。形骸です。「私」そのものでは、決してない。この「蔵の中」という作品は、目に余る脱線と逸脱によって小説の形式を茶化しつつ、似て非なる「私」と着物とを、読者の目に巧みに混同させる、きわめて批評的な小説であり、一見すると無造作にみえる宇野の筆致は、実は精緻な計算に基づいたものなのです。
宇野浩二といえば、突如発狂して友人の芥川や広津和郎に大きな動揺を与えた逸話が思い起こされますが、斯様な小説をおそらくは満面のドヤ顔で書いていたにちがいない男の狂いのしぐさを、果たしてどこまで信用していいものか。後藤明生や町田康など後続の作家にも明らかな影響を与えた、佯狂の傑作といえるでしょう。
☆ 今回読んだ本
宇野浩二『思い川・枯木のある風景・蔵の中』(講談社)
☽ おまけの一冊
ゴーゴリ / 平井肇訳『外套・鼻』(岩波文庫)
⇒ 宇野に大きな影響を与えた<脱線>の開祖。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
