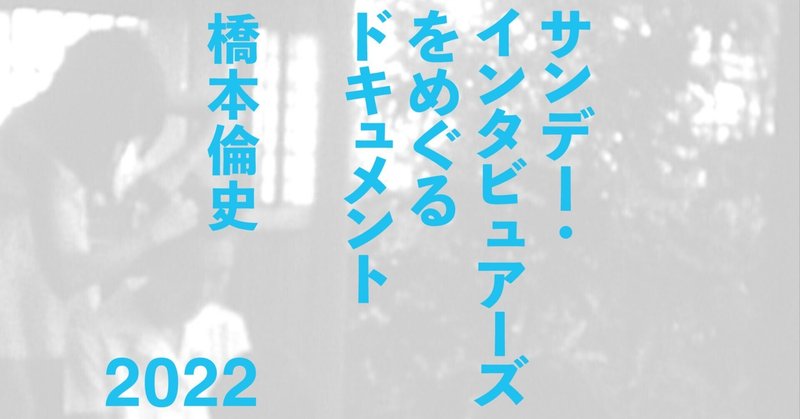
第9回「懐かしさを感じるために止まらないといけないのか」
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムの映像を手がかりに、“わたしたちの現在地”をさぐるロスジェネ世代の余暇活動「サンデー・インタビュアーズ」。月に1度オンラインで集い〈みる〉〈はなす〉〈きく〉に取り組みます。2022年度に公募で集まったメンバー6名による活動記録。ライターの橋本倫史さんのドキュメントです。
連載最終回(全9回)
2022年12月25日。
クリスマスの日に、2022年度の「サンデー・インタビュアーズ」のワークショップは最終回を迎えた。最後のしめくくりに、今年度のワークショップを通じて印象的だった映像と、このワークショップを通じて考えたことを語り合うことになった。
まるやまたつやさんが印象深かった映像のひとつは、No.69『新百貨店落成式など』だ。その映像の中で、強いてどこかの場面を挙げるとすれば、最後に映し出されるプールのシーンが印象的だったという。

「この8ミリフィルムの映像は、全体としてひとつのまとまりを意識されているのかなと感じさせる内容だったんです。最初は新しい百貨店が開業するところから始まって、落成式の様子が映し出されて──フィルムの最後のところになると開業から10年が経っていて、百貨店の屋上が、こどもたちがプールで遊ぶ場所になっている。それがすごくロードムービー的だな、と。単に撮影しただけじゃなくて、ひとまとまりの作品としてまとめていく意志を感じたので、すごく印象に残っています」
『新百貨店落成式など』には、途中でタイトルのように文字が挿入されたり、8ミリフィルムの編集機が部屋の片隅に映り込んでいたりと、単に家族のすがたを記録したというだけではなく、「編集」という視点を感じさせるフィルムだった。この映像を見たことが契機となって、『世田谷クロニクル1936-83』に収録されている8ミリフィルムも、少し見え方が違ってきたのだとまるやまさんは振り返る。
「最初のうちは『純粋な記録として残されたもの』という印象が強かったんですけど、『どうやって残すのか?』という視点が含まれていたり、誰かと一緒に見て楽しめるように撮影されたフィルムもあったりして、『誰かに伝える』という要素も多分に含まれているなと感じるようになりました」
まるやまさんは映像制作を専門とされている。だから余計に、撮影者の視点に興味が向いたのだろう。数十年前に撮影された8ミリフィルムを視聴することで、今この時代に撮影されている映像がどんなふうに残されていくのかと考えさせられたのだと、まるやまさんは語っていた。
「いま撮影されている映像は、たとえばInstagramのフィードで公開される映像って、誰かとシェアすることが前提になっていると思うんです。ただ、世田谷クロニクルの映像を見ていると、当時の8ミリフィルムも誰かと一緒に見ることを前提にしてるのかもしれないなと思ったんですよね。ただ、いま撮影されている映像って、SNSにシェアされたものは残るけど、それ以外のものは撮影した人が亡くなったらどうなっちゃうんだろうということも考えたんですよね。世田谷クロニクルにアーカイブされている映像って、撮影したことも忘れられていたものが、たまたまモノとして残さされていたから、こうやって見ることができるんじゃないか。そう考えると、8ミリフィルムというストレージが持っている意味についても考えさせられますし、デジタルの記録はどうなってしまうんだろうなってことを考えました」
aki maedaさんの場合、8ミリフィルムの映像以上に、オンラインワークショップの映像が印象に残ったのだと振り返る。それもまた、『新百貨店落成式など』の映像がテーマとなった回の映像だった。
「今日は欠席されてますけど、小島和子さんが発表されたときのことがすごく印象に残っているんです。そのときのワークショップで、『新百貨店落成式など』の中に出てくる、ボートを漕いでいる女性を撮影したシーンについて小島さんが話をされていて。8ミリフィルムを撮影している人は、ボートを漕ぐ女性のことを映していて、その女性がこちらにカメラを向ける──そのシーンのことを取り上げながら、小島さんが最相葉月さんの『れるられる』を紹介されていて。その話を聞いた瞬間にもう、ちょっとフィクションの映像を見ているような気分になったんですよね」

湖でボートを漕ぐ場面というのは、家族旅行で静岡県の一碧湖を訪れたときに撮影されたものだ。そこに切り取られているのは、ごく個人的な記録だ。それがフィクションのように見えてくるというのは、一体どういうことだろう。そこそもここで「フィクション」とは、何を指しているのだろう?
「aki maedaさんが『フィクション』と呼ばれているのは、映像のつなぎかたがフィクショナルに感じられたということでしょうか?」松本篤さんが尋ねる。「そこに記録されている事実は全部ほんとうなのに、映像のつなげかたがフィクショナルに感じられるということでしょうか?」
「事実というのは──なんだろう、『言えないこと』っていう感じがあります。フィクションの物語の中だったら、こういうことがありましたって言うこともできるけど、事実というのは人には言えない、というか。記録映像というのは、そこに映っているのは“事実”なんですけど、見ているわたしたちからすればフィクションとしても見れると思うんですよね。でも、事実というのは、言いたくても言えないことって感じがします。事実だから言えなくて、フィクションだから言えるのかなって、私の中では勝手にカテゴライズされてるのかもしれないです」
「わたし」の人生は、たった一度きりの、誰とも置き換えることが不可能なものだ。そこにはひとつずつ別個の生があるだけで、共感というのは本来成立しないものだ。だからこそ、その「わたし」の身にふりかかったことや、「わたし」が置かれた境遇のことを、誰にも話せなくなってしまうときがある。ただ、フィクションはそうした壁を超えて、誰かに何かを届けることができる。8ミリフィルムに記録された映像も、いつかの時代を生きた誰かのたった一度きりの瞬間を映したものであるはずなのに、わたしたちは映像の余白に何かを見出し、何かを受け取ったり何かを感じたりする。
「印象的だったのは、最初に見た『東京転勤』で、家族が引っ越していくところですかね」。たにぐちひろきさんが言う。「世田谷が昔、田園地帯だったというのは情報として知っていたし、写真を見たこともあったんですけど、そこにどうやって住んでいたのか、いまいちイメージできてなかったんですね。『昔は田園地帯だった』と言われても、東京だと農村の暮らしとは違うんじゃないか、と。そこで『東京転勤』の映像を見て、お父さんはおそらく都心に通勤して、こどもたちはわりと自然あふれるところで暮らしてる風景というのが、なんとなくイメージできたところがありました」

たにぐちさんが言うように、世田谷の昔の風景というだけであれば、これまでにも写真で目にしたことがあった。ただ、写真に比べると、映像に記録された風景というのは現在とどこか地続きものとして見えてくる。
「印象的だった映像で言うと、私も『東京転勤』です」。アキさんが言う。「最初のワークショップだったということもあって、映像を見ることについて考えた回だったなと思うんですよね。映像を一時停止すると、そこからいろんなことが読み取れるんですけど、そういう見方はあんまり映像的じゃないな、と」
では、映像的とは、どんな見方なのだろう。
そこでアキさんが例に挙げたのは、目の見える人と見えない人が一緒に8ミリフィルムを鑑賞するオンラインプログラム「エトセトラの時間」だった。このプラグラムもまた、『世田谷クロニクル1936-83』としてアーカイブされた映像を用いたもので、第1回で使用された映像というのは、今年度のサンデーインタビュアーズでも課題に選ばれた『新幹線試乗』だった。

「この『エトセトラの時間』に参加させてもらったときは、映像を見ながら、気づいたことをひたすら話していったんですね。その体験がとても映像的だったんです。画面に映し出されるものをひたすら言葉にしていくんですけど、言葉が映像に追いつかなくて、どんどん置いていかれてゆく。静止画であれば、そこに写っているものについて何か語ることもできるんですけど、映像だと途中から黙ってしまったり、追いつけなくなってしまったりする。そうやって『ここに何が映っている』とははっきり言えないようなものが、映像を見るという体験に近いのかなと思いました」
写真というのは、わたしたちが生きている時間を一時停止するかのように、一瞬を切り取ることができる。映像もまた、私たちが生きている時間をフィルムに焼きつけることができるのだけれども、映像の中でも時間は止まることなく、わたしたちの人生と同じように、流れ、過ぎ去ってゆく。だから映像に記録された過去は、現在と地続きに感じられるのだろうか?
「サンデー・インタビュアーズの説明会のときに、『過去に撮影された8ミリフィルムの映像を、なぜ今懐かしいと感じるのか考えていきたい』とおっしゃられていたと思うんです」と、アキさんは話を続ける。「最初のうちは、モノクロ映像だから懐かしいのかなと思っていたんですけど、回を重ねていくうちに、どうもそういうことじゃないなと思うようになって。そういうことを考えていると、森山大道さんの『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』という言葉があらためて気になってきたんです。写真に写っている過去が新しく見えてくるというのは共感できるんですけど、未来が懐かしいというのはどういうことなんだろうな、と。映像は流れていくものだということを考えると、懐かしさを感じるためには止まらないといけないのか──そのあたりはまだ、うまく言葉になっていないんですけど、そのあたりのことは継続して考えていけたらなと思っています」
わたしたちの人生は、生きている限り止まることはなく、流れ続けてゆく。たえず流れ続けてゆく時間軸に棹さすように、少しだけでも立ち止まってみようとする試みが、映像に記録するということなのかもしれない。そして、誰かがかつて記録した映像を見つめるということもまた、わたしたちの人生について想像を巡らせることと繋がっている。
サンデー・インタビュアーズというプロジェクトは、2022年度をもって一区切りとなった。ただ、『世田谷クロニクル1936-83』としてアーカイブされた映像は、これからもウェブ上に残り続ける。この映像をめぐる取組もまた、途切れることなく続いていく予定だ。
サンデー・インタビュアーズをめぐるドキュメント2022
第1回「時間が経てば経つほど、見えないものが見えてくる」
第2回「結婚の挨拶に行くと、びしっとスーツを決めていて」
第3回「テーマを持って作品を作ろうという意識がおありなんだろうな」
第4回「個人的なもののはずなのに社会的なことを考えてしまう」
第5回「ボストンバッグに修正液でナイキのマークを描いていた」
第6回「電子レンジがあるはずなんだけど、ないんだよね」
第7回「手で牌を混ぜる音が1階まで聞こえていた」
第8回「カメラを通して住んでいる環境と向き合える感じがあったんです」
第9回「懐かしさを感じるために止まらないといけないのか」(最終回)
文=橋本倫史(はしもと・ともふみ)
1982年広島県生まれ。2007年『en-taxi』(扶桑社)に寄稿し、ライターとして活動をはじめる。同年にリトルマガジン『HB』を創刊。以降『hb paper』『SKETCHBOOK』『月刊ドライブイン』『不忍界隈』などいくつものリトルプレスを手がける。近著に『月刊ドライブイン』(筑摩書房、2019)『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』(本の雑誌社、2019)、『東京の古本屋』(本の雑誌社、2021)、『水納島再訪』(講談社、2022)。
サンデー・インタビュアーズ
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムを手がかりに、“わたしたちの現在地” を探求するロスト・ジェネレーション世代による余暇活動。地域映像アーカイブ『世田谷クロニクル1936-83』上に公開されている84の映像を毎月ひとつずつ選んで、公募メンバー自身がメディア(媒介)となって、オンラインとオフラインをゆるやかにつなげていく3つのステップ《みる、はなす、きく》に取り組んでいます。本テキストは、オンライン上で行うワークショップ《STEP-2 みんなで“はなす”》部分で交わされた語りの記録です。サンデーインタビュアーズは「GAYA|移動する中心」*の一環として実施しています。
https://aha.ne.jp/si/
*「GAYA|移動する中心」は、昭和の世田谷をうつした8ミリフィルムのデジタルデータを活用し、映像を介した語りの場を創出するコミュニティ・アーカイブプロジェクト。映像の再生をきっかけに紡がれた個々の語りを拾い上げ、プロジェクトを共に動かす担い手づくりを目指し、東京アートポイント計画の一環として実施しています。
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]
