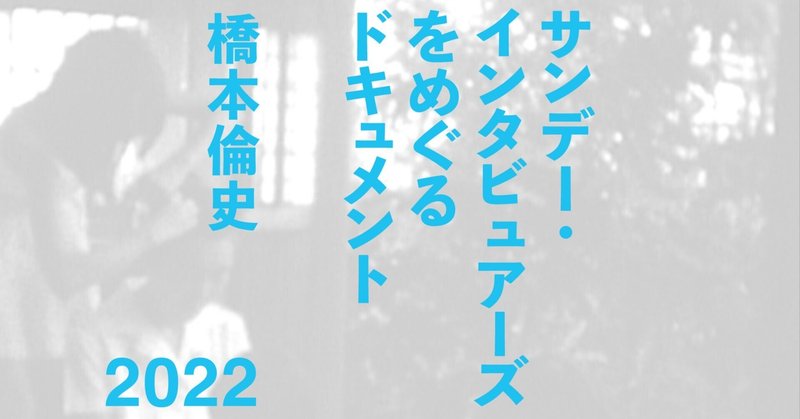
第8回「カメラを通して住んでいる環境と向き合える感じがあったんです」
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムの映像を手がかりに、“わたしたちの現在地”をさぐるロスジェネ世代の余暇活動「サンデー・インタビュアーズ」。月に1度オンラインで集い〈みる〉〈はなす〉〈きく〉に取り組みます。2022年度に公募で集まったメンバー6名による活動記録。ライターの橋本倫史さんのドキュメントです。
連載第8回(全9回)
2022年度のサンデー・インタビュアーズで、最後の課題として取り上げられたのは、『No.1』というタイトルの映像だった。11月27日のワークショップで、この映像をテーマに「みんなで“はなす”」時間を設けたとき、口火を切ったのはたにぐちひろきさんだった。
「私がタイムコードを切ったのは、00:13──日比谷公園と日比谷の街が映ってるところです。ここに日生劇場が映っているんですけど、それ以外の建物は建て替わっているものが多くて、今は帝国ホテルも高いビルになってますし、ミッドタウン日比谷ができてますよね。日比谷公園も、樹の高さが今より低いなと思ったんです。だから今より開放感がありますし、まわりのビルと樹が両方見える景色というのは、今と違って面白いなと思いました」

前に『新百貨店落成』の映像を扱ったときも、たにぐちさんは映像に映る環七沿いのビルが数年前まで残っていたことを手掛かりに、8ミリフィルムが撮影された時代と現在の東京の姿とを比較しながら発表していた。たにぐちさんの視点を通じて、東京という都市を俯瞰しているような心地がする。
昭和38年11月から12月のかけて撮影された映像だ。フィルムの提供者は当時、映画の配給会社に勤めており、8ミリフィルムを始めたばかりの頃に撮影したものだという。フィルムの中には、日比谷公園や有楽町のパチンコ店、世田谷区は三宿にあった会社の寮が記録されている。
「映像とは直接関係ないんですけど、私自身、去年まで三宿に近いところに住んでいたんですね」。皆で『No.1』の映像について語り合った翌月、12月に開催されたワークショップで、たにぐちさんはそう切り出した。「三宿のあたりって、どの駅からも10分以上歩くようなところで、交通の便がよくないんです。そのぶん落ち着いているところではあるんですけど、どうしてそんなところに会社の社員寮が建てられたのか、気になったんです。調べてみると、この映像が撮られた時代だと、東急玉川線が走っていて、三宿にも駅があったそうなんです。それがあれば都心に通勤するのも不便じゃなかったでしょうし、三宿の街自体も、今の静かな感じとはまた違ったのかなと思いました」
東急玉川線は路面電車として運行していた。モータリゼーションが進んだ時代に、渋滞を解消するべく東急玉川線が廃止されたのは、1969年のこと。これに代わる路線として建設された地下鉄が「新玉川線」(現在の東急田園都市線の一部)だった。新玉川線は、東急玉川線のルートを引き継いではいるものの、路面電車に比べると停留所の数は少なくなり、三宿駅は消滅した。こうして三宿は、電車だとアクセスしづらい場所になった。だが、それが街に変化をもたらす。電車だとアクセスが悪くとも、三宿には幹線道路である国道246号が走っており、車でのアクセスは良い場所だ。バブルから90年代にかけて、鉄道だとアクセスの悪い場所──三宿の他にも、西麻布や、大江戸線が開通する前の麻布十番といった街──は隠れ家的な場所として、芸能人が集まる場所というイメージも醸成されてゆく。
「今の三宿って、若者が住む安めのアパートみたいなのはあんまりなくて、大きい家が多くて、高級感のある街だって感じはすごく感じていたんです」。たにぐちさんは三宿の近くに暮らしていた頃を振り返ってそう語る。その一方で、三宿には古い町中華もあって、そこには『No.1』が撮影された時代の名残りを感じた──と。
「これは私が住んでたときの印象なんですけど、街からの疎外感みたいなものを少し感じたんです。そこに引っ越す前に住んでいたのは武蔵小杉だったんですけど、そのころ武蔵小杉にはちょうどタワーマンションが建ち始めて、いろんな人が流入してくる時期だったから、疎外感というのは感じなかったんですね。あるいは、その前に住んでいた早稲田も学生街だったから、外から入ってきた人が多い地域だったんです。でも、三宿のあたりは地元で長く住んでる人が多くて、最近になって住み始めた自分に対して違和感を感じることがありました」
東京への転入超過がピークを迎えたのは、東京オリンピックが開催された時期のこと。それは「No.1」の映像が撮影された時代でもある。増え続ける人口に対応するべく、田園地帯だった世田谷も宅地化が進み、外から高度成長期の60年代のこと。その時代を起点に考えただけでも、すでに60年ほどの歴史が堆積している。新たにひらかれた土地も、やがて誰かの地元になってゆく。開拓第一世代としてではなく、あとからやってきた世代は、そこにどうやってなじむことができるのだろう。そもそも、「自分はこのまちの住人だ」という意識はどこから生まれるのだろう?
「以前、建築ユニットの『ミリメーター』という方たちのワークショップに参加したことがあるんです」と、事務局の水野雄太さんが切り出す。ミリメーターは、空間と社会の規範を解きほぐし、都市に関わる視点や空間を提示する活動を続けているユニットだ。水野さんが参加したワークショップは、「街を掃除してみる」という内容だった。自分が暮らしていない街でも、掃除をすることで街のディティールが把握できたのだと、水野さんは振り返る。今は北国に暮らしている水野さんは、「雪かきをするようになって、勾配や地形を意識するようになって、この土地に住んでいるという体感が生まれた」のだと語る。
ワークショップが開催されていた時期は、記録的な大雪に見舞われていた時期だった。雪が降り積もる地域に暮らすまるやまたつやさんもまた、雪かきを通じて場所を意識するようになったのだと言う。普段から近所付き合いがあるわけではないけれど、隣近所とのあいだにある曖昧な領域まで雪かきをすることで、土地を意識するようになったのだ、と。
同じような経験はアキさんにもあった。
アキさんが暮らす町には竹藪があった。その竹藪は私有地だったが、所有者はこの町を離れて暮らしていた。この竹藪の環境を整えるべく、年に一度、町内会総出で清掃作業をおこなっていた。あるとき、この場所に開発の手が伸び、竹藪は伐採されてしまった。皆で清掃作業をおこなう時間がなくなってみると、「地域の住民が総出で何かに取り組んでいる」と感じられる時間もなくなってしまったのだと、アキさんは語る。
「町の共有地を掃除しているだけだったら、『皆で一緒になにかをやってる』って意識は生まれない気がするんですよね。自分の土地でもなければ、共有地でもなくて、よくわからない場所を一緒に掃除してるから、『皆で団結してやっている』という感覚が芽生えてたような気がするんです。昔は山に『入会』(いりあい。地域の住民が草や薪を採取するための共有地)がありましたけど、所有者がよくわからないところを皆で管理していると、団結や住人という意識が生まれるのかもしれないなと、今の話を聞いてて思いました」
共有地にかかわることで、その土地に暮らす住人だという意識が生まれる──これはシンプルな話だ。ただ、よくわからない土地にかかわることから住人という意識が芽生えたのだと、アキさんは語る。
もしも「道路の清掃作業をするから、×月×日は地域住民で清掃作業をします」と回覧板がまわってきたとする。そこではもう、共有地にかかわることは決定事項であり、決められた作業に従事するだけだ。ただ、誰の土地だかわからない場所にかかわるためには、まずは自分はそこにどのようにかかわるのか、自分自身で考えることが求められる。そうして主体的にかかわることが、「住人」という意識につながるのだろうか──?
「まるでサンデー・インタビュアーズの取組みたいですね」と、松本篤さんが言う。「もちろん、『世田谷クロニクル1936-83』にアーカイブされている8ミリフィルムには、その映像を撮った誰かがいるんですけど、かつて撮影された映像を見るっていうのは、その映像の所有者は誰なのかということを曖昧にさせるところがあるのかなと思いながら聞いてました」
人間の感覚はつくづく不思議なものだと思う。まちは誰のものでもないのに、「ここは自分のまちだ」と感じたり、「このまちには自分の居場所がない」と感じたりする。あるいは、自分が生まれ育ったまちを「故郷」や「地元」と呼び、そこに特別な親しみをおぼえることもある。ただ、「故郷」はわたし自身が選んだ場所ではなく、たまたまそこに生まれただけの話だ。わたし自身はまるで無関係だったはずの土地に、人はどのようにしてかかわりを持ちうるのだろう?
「自分は大阪で生まれて、高校生まで福井で育ったんですけど、当時は福井から出て行きたいという気持ちが強かったんです」。まるやまたつやさんはそう切り出した。「その当時は、『自分はこの街の住民じゃないんだ』という意識があったんですけど、大人になった今、自分の故郷はどこかというと、福井だなと思っているんですよね。あるいは、福井を出て別の街に暮らし始めたとき、そこに行きつけのお店ができたり、自分が居心地のいい場所を見つけられたら、『住人』とまではいかなくても、ここは自分の街だという意識が芽生えてくるのかなと思いました」
ところで、最後の課題となった『No.1』の映像の中で、まるやまさんが気になったポイントのひとつは、1:30のあたりだった。8ミリフィルムには、撮影者が暮らす部屋の様子が映し出されている。映像制作を専門とする丸山さんは、その映像を目にしたとき、自分自身が初めてビデオカメラを手にしたときのことを思い出したのだという。

「初めてビデオカメラを手にしたとき、僕も自分の部屋をズームで撮ってみたりしてたんです。あるいは、当時自分はベースギターをやっていたので、弾いているところを自撮りしてみたりして。液晶モニターをひっくり返して、カメラを自分の側に向けてみると、自分がどういうふうになっているのか見れるじゃないですか。そうすると、カメラを通して自分が住んでる環境みたいなものと向き合えている感じがあったんですよね。たにぐちさんがおっしゃっていた『疎外感』とも繋がってくるんですけど、『ここは自分の街じゃない』という意識があったころって、自分の部屋に自分の好きなもの並べて、それをビデオカメラで撮影することで、『この部屋の中だけは自分の居場所だ』と思っていたのかもしれないなと思ったんですよね。福井を離れたあとも、自分が行きつけにしている場所をビデオカメラで撮っていたような記憶があるので、疎外感とカメラはセットなのかもしれないなと思いました」
わたしたちは、生きていく中で“鏡”を必要とする。
社会というものの規模が大きくなった時代に「新聞」が生まれ、わたしが暮らしている社会で何が起きているのか、メディアを通じて把握するようになった。このメディアというのもまた、ひとつの鏡だ。あるいは、ドラマや映画を見るのも、わたしのたった一度きりの人生を鏡越しに見つめているような心地がする。
「世田谷クロニクル1936-83」の映像を見ることも、どこか鏡を見るような感覚がある。
そこにアーカイブされている映像の大半は、わたしが生まれる前に撮影されたものだ。だから、そこに記録されている映像は、私とはかかわりのない時間ばかりだ。ただ、この世界には、わたしが生まれるずっと前から存在していて、そこには気が遠くなるほど連綿とした営みが続いてきた。生まれた瞬間にはまだ、わたしはこの世界とは無関係だった。その無関係だったはずの世界に、自分の居場所を棹さすように、8ミリフィルムの映像にタイムコードを切る。
サンデー・インタビュアーズをめぐるドキュメント2022
第1回「時間が経てば経つほど、見えないものが見えてくる」
第2回「結婚の挨拶に行くと、びしっとスーツを決めていて」
第3回「テーマを持って作品を作ろうという意識がおありなんだろうな」
第4回「個人的なもののはずなのに社会的なことを考えてしまう」
第5回「ボストンバッグに修正液でナイキのマークを描いていた」
第6回「電子レンジがあるはずなんだけど、ないんだよね」
第7回「手で牌を混ぜる音が1階まで聞こえていた」
第8回「カメラを通して住んでいる環境と向き合える感じがあったんです」
第9回「懐かしさを感じるために止まらないといけないのか」(最終回)
文=橋本倫史(はしもと・ともふみ)
1982年広島県生まれ。2007年『en-taxi』(扶桑社)に寄稿し、ライターとして活動をはじめる。同年にリトルマガジン『HB』を創刊。以降『hb paper』『SKETCHBOOK』『月刊ドライブイン』『不忍界隈』などいくつものリトルプレスを手がける。近著に『月刊ドライブイン』(筑摩書房、2019)『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』(本の雑誌社、2019)、『東京の古本屋』(本の雑誌社、2021)、『水納島再訪』(講談社、2022)。
サンデー・インタビュアーズ
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムを手がかりに、“わたしたちの現在地” を探求するロスト・ジェネレーション世代による余暇活動。地域映像アーカイブ『世田谷クロニクル1936-83』上に公開されている84の映像を毎月ひとつずつ選んで、公募メンバー自身がメディア(媒介)となって、オンラインとオフラインをゆるやかにつなげていく3つのステップ《みる、はなす、きく》に取り組んでいます。本テキストは、オンライン上で行うワークショップ《STEP-2 みんなで“はなす”》部分で交わされた語りの記録です。サンデーインタビュアーズは「GAYA|移動する中心」*の一環として実施しています。
https://aha.ne.jp/si/
*「GAYA|移動する中心」は、昭和の世田谷をうつした8ミリフィルムのデジタルデータを活用し、映像を介した語りの場を創出するコミュニティ・アーカイブプロジェクト。映像の再生をきっかけに紡がれた個々の語りを拾い上げ、プロジェクトを共に動かす担い手づくりを目指し、東京アートポイント計画の一環として実施しています。
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]
