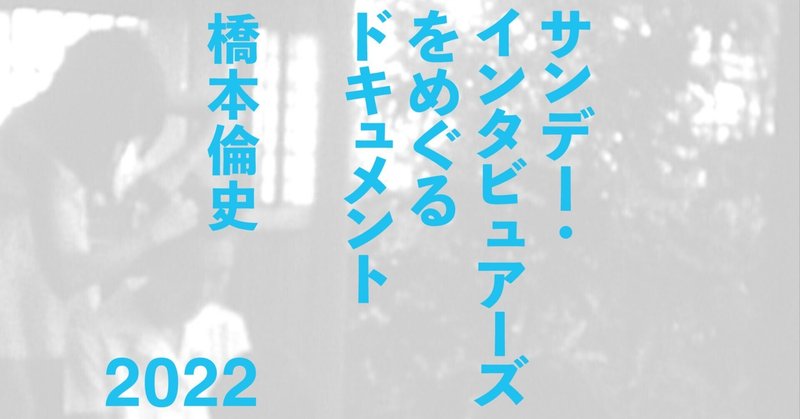
第7回「手で牌を混ぜる音が1階まで聞こえていた」
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムの映像を手がかりに、“わたしたちの現在地”をさぐるロスジェネ世代の余暇活動「サンデー・インタビュアーズ」。月に1度オンラインで集い〈みる〉〈はなす〉〈きく〉に取り組みます。2022年度に公募で集まったメンバー6名による活動記録。ライターの橋本倫史さんのドキュメントです。
連載第7回(全9回)
家族の姿をフィルムに収める。
それは、昭和の時代にはごく“当たり前”の光景だった。旅行に出かけたとき、こどもの入学式や運動会のとき、新しい車が我が家にやってきたとき、お正月を迎えたとき。なにか行事があれば、父親がカメラを構えて家族を写すというのが、“当たり前”だとされていた。ただ、その“当たり前”も、細かく見ればひとつずつ違っている。
10月23日に開催された4回目のオンライン・ワークショップで、あらたな課題となったのは、映像No.24『井の頭公園』だ。このフィルムは、井の頭公園で家族の団欒のときを過ごしたり、多摩霊園まで家族でお墓参りに出かけたり、世田谷区の船橋にある自宅で過ごす家族の姿が記録されている。このフィルムは、「世田谷クロニクル1936-83」にアーカイヴされた映像の中でも、他のフィルムとはまたちょっと違った趣向が凝らされている。逆再生を利用して、兄の姿が消えたかのように見せたり、祖母が手品をしてみせたかのように見えたりする映像を撮影しているのだ。
アキさんがタイムコードを切ったのは00:14、家族が並んで並木道を歩くところだ。

「このフィルムは、皆がすごく楽しそうに撮影している感じがありますよね。この0:08のところも、映画みたいな出だしだなと思いました。全体的にすごく作り慣れている感じがあったので、家族皆で映像を撮ったり、その映像を一緒に見たりする文化があったんだろうなと思いました」
たしかに、被写体となる家族は皆、撮られ慣れている感じがする。3人のこどものうち、一番上のお兄ちゃんは学生服姿だ。それぐらいの年頃になると、家族と一緒に出かけたり、あるいはカメラを向けられたりすることを嫌がり始めても不思議ではないけれど、カメラに笑顔を向けている。あるいは、お墓参りのときにカメラをまわすのも、どちらかといえば珍しいほうではないだろうか。
「あと、個人的には、10:04のところ、家族で麻雀をしているところが印象的で」。アキさんが話を続ける。「というのも、私も小さい頃、おじいちゃんたちと一緒に麻雀やってて、すごく楽しかった思い出があるんですね。それを他の人に言うと『家族で麻雀なんかしないよ』って言われるんですけど、ああ、ここにも家族で麻雀やっている人たちがいた、って嬉しくなりました」

フィルムの中に映る家族は、床の間のような場所でテーブルを囲んでいる。こたつの台の上に、絨毯のような柄の布をかけて、麻雀を楽しんでいる。映像提供者によると、その麻雀牌は父の手作りだったそうだ。母の竹細工の花器を割り、セルロイドの下敷きが貼られ、牌には手彫りの字や絵があつらえてあったのだという。
10月のワークショップが終わると、翌月のワークショップまでのあいだに、参加者はそれぞれステップ3の「だれかに“きく”」を実践して、その内容を“ポストムービー”としてまとめる。この課題は思った以上に難しく、まずは誰にきけばよいのか、きいた話をどんなふうにまとめればよいのか、悩ましいところがある。そこで事務局の水野さんは、まとめかたの例として、2021年度の参加者のポストムービーを共有した。そのひとつは、映像No.74の『松陰神社、双葉園、雪の日』を見たあと、ラナさんが作成したポストムービーだ。

『松陰神社、双葉園、雪の日』にも、麻雀に興じる家族の姿が記録されている。その映像を見て、ラナさんは「自分に“きく”」という形で、自分自身の記憶を深掘りした。トロント大学の学部生時代、レジデンスに暮らすルームメイトの中には日本と上海からの留学生たちがいて、麻雀の遊び方を教えてくれたのだという。留学生たちはさまざまな地域からトロントにやってきていたので、時々ルールについて言い争うこともあった。ラナさんが自分の部屋で勉強しているときでも、洗牌の「ジャラジャラ」という音が聞こえてきたのだと、ラナさんは綴っていた。
この「自分に“きく”」という方法を援用して、アキさんもまた、自分自身の記憶を深掘りした。ポストムービーのタイトルは「家族と麻雀。」だ。
「家族で麻雀をやった時間は、めちゃくちゃ楽しかった思い出があるんですね」。11月27日に開催されたワークショップで、アキさんはそう切り出した。「うちは家族でボードゲームをする機会も多くて、いろんなゲームもあったんですけど、麻雀は格別だったんです。なんで格別だったのかなと考えたら、やっぱり麻雀だと時間もたっぷりあって、やりながらいろんな話ができたんですね。麻雀の牌自体も、手触りといい、彫りといい、特別感があったんです。あと、麻雀をやった時間は、祖父との思い出にもなっていて。祖父とは年が離れているので、麻雀以外では一緒に遊ぶことは考えられなかったんですけど、同じ遊びをやったということで印象的だったんだと思います」
他のボードゲームだと、こどもが大人に混じってもかなわないけれど、麻雀だと初めに配られた牌次第では、こどもも大人に勝つことができる。しかも、将棋やチェスのように、ずっと頭を使い続ける必要もなく、談笑しながら遊ぶことができる。そんなふうに「ひらかれたゲーム」だったから、こどもながらに楽しかったのではないかとアキさんは振り返る。
「家族と麻雀」というタイトルでポストムービーをまとめたのは、アキさんだけではなかった。実はまるやまたつやさんもまた、まったく同じタイトルでポストムービーをまとめていた。
「私はこの『井の頭公園』の映像を見て、ちっちゃいこどもとおばあちゃんが一緒に麻雀をしているのを見てびっくりしたんです。小さい頃に家族でドンジャラをやったことはあるんですけど、こどもが麻雀をするっていうのが想像できなかったんです」
ただ、一緒に遊ぶことこそなかったものの、まるやまさんの祖父は麻雀好きだった。祖父は現在施設に入っていることもあり、まるやまさんは父を焼肉屋に誘い、祖父と麻雀について話を聞いてみたのだという。
「うちの父も、家族で麻雀をやったことはなかったみたいなんですけど、実家の2階が祖父の部屋になっていて、そこに同僚や友達を連れ込んで、夜な夜な麻雀をやっていたみたいです。こどもが入れない雰囲気があったから、どういうことをやっていたかはわからないけど、手で牌を混ぜる音が1階まで聞こえてたそうです。父自体は麻雀をやったのかっていうと──やるにはやったみたいなんですね。『当時のサラリーマンは、麻雀とゴルフと酒に付き合えないと、コミュニケーションが成り立たなかったんだ』みたいなことを言う一方で、『勝ったままでは終われない』とか、『負けても「もう一回!」ってなる』とか、あんまり良い終わりかたをしないイメージがあったみたいで、そこが面白かったです」
まるやまさんの祖父は自由奔放な人だったらしく、カラオケ喫茶と焼き鳥屋を営んでおり、焼き鳥屋の個室を雀荘のようにして、そこで麻雀ばかりやっていたのだそうだ。そうやって友人たちと麻雀に興じてばかりで、家族サービスをしてくれなかったこともあって、父は麻雀に対していいイメージがなかったんじゃないか──と、まるやまさんは話を続けた。
「私は家族皆でやってたから、家族の団結が深まったのかなって、今の話を聞いていて思いました」とアキさんは言う。
昭和の時代は、「一億総中流」という言葉とともに語られることもある。誰もが中流で、同じような生活を送り、同じものに熱中し、暮らしていたのだ──と。
「麻雀」というチョイスは珍しいとしても、正月に親戚一同が集まってゲームに興じるというのは、昭和の時代には「普通」の光景だったように感じる。トランプに花札、人生ゲーム。将棋にオセロ、UNO。そういったゲームで遊んだ経験を持つ昭和の家族は多いはずだ。
それに比べて、平成生まれのたにぐちさんは、「麻雀含めて、家族で遊ぶことがなかった」と振り返る。
「家にはトランプがあったり、お土産で買ってきたボードゲームがあったりしたんですけど、それに触ることはなかったですね。テレビゲームも、父親が買ったファミリーコンピュータはあったんですけど、それもあんまりやってなくて。ゲームが好きっていうより、流行ってたから買ってみた感じだったのかなっていう気がします。母方の叔父はゲームが好きで、僕にもゲームを買ってくれたんですけど、ひとりで遊ぶゲームが多くて、一緒にやろうって話にはならなかったです。もしかしたら、一人で遊ぶのが好きな家系だったかもしれないです」
こうした傾向は、昭和から平成、令和と時代が下るにつれて加速していったのだろう。コロナ禍となったことで、お正月に親戚で集まるということ自体、珍しいことになりつつある。
ただ、昭和の時代にも、正月だからといって集まることのない家族もいたはずだ。一緒にゲームで遊んだ経験のない家族もいたはずだ。写真をほとんど撮ることのなかった家族だっていたはずだ。どんな時代にも、“当たり前”の外側にいる家族は存在する。ひとつの映像をきっかけに、出身地も世代も少しずつ異なるメンバーが集まって語り合うことで、わたしたちが“当たり前”だと思い込んでいることを揺るがすことができるのだ。
サンデー・インタビュアーズをめぐるドキュメント2022
第1回「時間が経てば経つほど、見えないものが見えてくる」
第2回「結婚の挨拶に行くと、びしっとスーツを決めていて」
第3回「テーマを持って作品を作ろうという意識がおありなんだろうな」
第4回「個人的なもののはずなのに社会的なことを考えてしまう」
第5回「ボストンバッグに修正液でナイキのマークを描いていた」
第6回「電子レンジがあるはずなんだけど、ないんだよね」
第7回「手で牌を混ぜる音が1階まで聞こえていた」
第8回「カメラを通して住んでいる環境と向き合える感じがあったんです」
第9回「懐かしさを感じるために止まらないといけないのか」(最終回)
文=橋本倫史(はしもと・ともふみ)
1982年広島県生まれ。2007年『en-taxi』(扶桑社)に寄稿し、ライターとして活動をはじめる。同年にリトルマガジン『HB』を創刊。以降『hb paper』『SKETCHBOOK』『月刊ドライブイン』『不忍界隈』などいくつものリトルプレスを手がける。近著に『月刊ドライブイン』(筑摩書房、2019)『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』(本の雑誌社、2019)、『東京の古本屋』(本の雑誌社、2021)、『水納島再訪』(講談社、2022)。
サンデー・インタビュアーズ
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムを手がかりに、“わたしたちの現在地” を探求するロスト・ジェネレーション世代による余暇活動。地域映像アーカイブ『世田谷クロニクル1936-83』上に公開されている84の映像を毎月ひとつずつ選んで、公募メンバー自身がメディア(媒介)となって、オンラインとオフラインをゆるやかにつなげていく3つのステップ《みる、はなす、きく》に取り組んでいます。本テキストは、オンライン上で行うワークショップ《STEP-2 みんなで“はなす”》部分で交わされた語りの記録です。サンデーインタビュアーズは「GAYA|移動する中心」*の一環として実施しています。
https://aha.ne.jp/si/
*「GAYA|移動する中心」は、昭和の世田谷をうつした8ミリフィルムのデジタルデータを活用し、映像を介した語りの場を創出するコミュニティ・アーカイブプロジェクト。映像の再生をきっかけに紡がれた個々の語りを拾い上げ、プロジェクトを共に動かす担い手づくりを目指し、東京アートポイント計画の一環として実施しています。
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]
