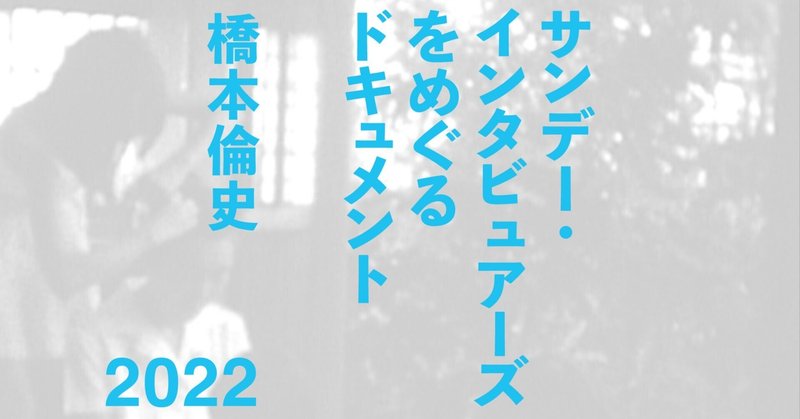
第5回「ボストンバッグに修正液でナイキのマークを描いていた」
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムの映像を手がかりに、“わたしたちの現在地”をさぐるロスジェネ世代の余暇活動「サンデー・インタビュアーズ」。月に1度オンラインで集い〈みる〉〈はなす〉〈きく〉に取り組みます。2022年度に公募で集まったメンバー6名による活動記録。ライターの橋本倫史さんのドキュメントです。
連載第5回(全9回)
わたしたちの目は、何を捉えているのだろう。
サンデー・インタビュアーズの活動をドキュメントとして書き綴るうちに、そんなことを考えるようになった。
月に1度開催されるワークショップで、参加者は課題となる映像を見て、タイムコードを切る。同じ映像でも、注目するポイントは十人十色だ。
「えっと、私がタイムコードを切ったのは、3:43です」。参加者のひとり、aki maedaさんが語ると、Zoomの画面の中に映像が映し出される。今回課題に選ばれたのはNo.51『新幹線試乗』だ。そのフィルムには、時速をあらわすメーターが200キロを超えた様子が映し出されている。カメラはやがて横に振られ、車窓の景色を眺める人たちの姿が捉えられている。
「この03:54のところで、窓際に花瓶みたいなのが置かれてますよね。これ、どういうものなんだろうって気になったんです。窓に花瓶って、私が新幹線に乗ったときにはもう置かれてなかったと思うんですよね。食堂車だから置かれていたのかなとも思ったんですけど、窓際に置いていて割れたりしないのかなって気になりました」

この8ミリフィルムが撮影されたのは、昭和39年10月1日のこと。東海道新幹線が開業する直前に、国鉄関係者や新幹線の開発に携わった技術者たちが招かれ、試乗したときの様子がフィルムに収められている。通常の運行ではなく、試乗だったから花瓶が置かれていたのだろうか。あるいは、この時代の食堂車やビュッフェ車には、花瓶が置かれていたのだろうか。おもてなしのように飾られる花は不思議な存在だ。花が飾られている公衆トイレに出くわすたび、そんなことを考える。
「もしわかるようであれば、当時のビュッフェ車の内装について調べたら面白いかもしれないですよね」と、松本篤さんが言う。「もしかしたら、揺れないことの証のように置かれてたのかもしれないですよね」
この日は仕事があって欠席されていたまるやまたつやさんも、このあたりでタイムコードを切っていたのだと、事務局の水野雄太さんが話を切り出す。「まるやまさんは3:15でタイムコードを切られていて、『新幹線だからか手ブレが多い』と指摘されてました。『新幹線の揺れって、今とどれぐらい違うんだろう?』と」
その指摘は、映像制作を専門とするまるやまさんならではの指摘だと思う。あるいは、都市や町並みの変化に関心があるたにぐちひろきさんがタイムコードを切った箇所も、たにぐちさんならではの視線を感じるものだった。
「00:16のところで、新幹線のホームが映ってますけど、この圧迫感のあるY字型のホーム屋根って、今とほとんど変わらない気がするんですよね」と、たにぐちさん。「Y字型でホームの真ん中がへこんでるか、山形でホームの真ん中が膨らんでるか──どちらも圧迫感があって、正直好きじゃないんです。東京駅や品川駅、新橋駅みたいな大きな駅って、この頃から変わってないんじゃないかって気がします。最近、大阪駅が大きな屋根を作って、それはすごく広々した感じがして良かったので、東京の駅もそういうことをやってくれたらいいのになと思っていたところです」

こんなふうに、同じ映像を見ていても、それぞれの関心によって注目するポイントは異なってくる。「同じ映像」だけでなく、「同じ瞬間」であっても、目が何を捉えるかは違ってくる。aki maedaさんと、たにぐちさんが共通してタイムコードを切ったのは、0:55、新幹線の客席を前方から移した映像だ。そこには談笑する乗客の姿が映し出されている。

「この場面を見たときに、思わずスマホの音量を上げてしまったんです」とaki maedaさん。「この8ミリフィルムには音声がないんですけど、情景を見ていて思わず音量を上げたくなったことが、他の映像のときにも何度かあったんです。たとえば口が動いていたら、『何をしゃべっているんだろう?』と思うし、『この景色の音を聞いてみたい』と思って思わず音量をあげちゃう瞬間は結構あります。これ、もともと音声は入ってなかったんですよね?」
「もともと入ってなかったです」と松本さん。「たしかに、しゃべっている会話が残っていたら面白かったかもしれないですね」
「でも、声が入っていたら、その内容に意識が向いちゃうと思うんです」とaki maedaさん。「音声がないほうが、映像にだけ集中できるので、映像の記録としてはこっちのほうがいいのかなと思いました」
同じ場面を見て、たにぐちさんが注目したのは新幹線の網棚だった。
「なんとなく、網棚を見るのが好きなんです」と、たにぐちさん。「古い車両の展示とかがあると、網棚が網なのか、金属なのか、つい見ちゃうんですよね。これは新幹線だけど、網棚がほんとうに網で出来ていて、これだと絶対スーツケースは積めないよなと思ったんです。この時代だと、皆さんボストンバッグとかで旅行されてたんだと思いますけど、持ち物の変化も気になるなと思いました」
この『新幹線試乗』の映像に関して、ステップ3の「だれかに“きく”」では、ボストンバッグに関する話が相次いだ。たにぐちさんは、自分の両親に、旅行の時にどんな鞄を持って出かけたのかをきいていた。
「うちには革のボストンバッグがあるんですけど、これは父が40年ほど前に購入したとのことなので、やはり『ボストンバッグは昭和のもの』というイメージ通りでした。父は独身時代、バイク旅行を趣味にしていたようなので、ボストンバッグだとバイクに載せやすいというのがあったのかもしれません。我が家に初めて導入されたスーツケースは、90年代に父親が引き出物でいただいたもののようで、ほとんど父の海外出張用でした。私が小さい頃は、スーツケースといえば海外旅行で使うもので、ビジネスマンかお金持ちの家のものといったイメージでした」
たにぐちさんは80年代生まれだ。だから、自宅にスーツケースがやってきた90年代にはまだ小学生で、自分が使う道具ではなかったのだろう。一方、90年代にはもう大人になっていたアキさんにとっても、当時スーツケースは縁遠い物だったという。
「私は90年代ぐらいからたまに海外に行っていたんですけど、そのときまわりはほぼスーツケースだったんです。でも、私は絶対ボストンバッグでした。というのも、当時のスーツケースはめちゃくちゃ重かったんですね。ツアー旅行で海外に行く場合はスーツケースでいいんですけど、個人旅行で、向こうで宿を決めるような旅をしていると、スーツケースだと大変だったんです。特にヨーロッパは石畳なので、ほんとに大変なんですよね。そのあと軽くて小型のスーツケースも出てきて、タイヤの性能も優れたものが普及するようになってから、国内旅行でもスーツケースを使うようになったので、性能の問題がすごく大きかったイメージがあります」
こうした話の流れを受けて、小島和子さんもボストンバッグの思い出をきかせてくれた。
「私が中学生や高校生のころに、ちょっと半円型になっているボストンバッグがすごく流行って、鞄といえばそれしか思い浮かばないような時期があったんです。世代が違う方だと、全然流行も違ったと思いますけども、自分にとってボストンバッグといえばその形だったな、と。優等生からツッパリくんまで、皆その形のボストンバッグを使ってましたね」
「僕の学生時代だと、運動部の人たちはツヤのあるエナメルバッグを使っていたイメージがありますね」と水野さんが言えば、「言われてみたら、中学生の頃だと、こういう半円型のボストンバッグを皆使ってて、修正液でナイキのマークを描いている同級生とかいた気がします」と松本さんが言う。僕は水野さんや松本さんと同世代だからか、ふたりの話を聞いていると、中高生だったころの教室の風景がありありと甦ってくるような心地がする。
もしも60年代を舞台にした映画が撮影されるときに、スーツケースを引いて上京するシーンが描かれると、当時を知る世代は「リアルじゃない」と感じるだろう(あるいは、その登場人物は浮世離れしたキャラクターとして受け止められるだろう)。そこはやはり、ボストンバッグだ。
それと同じように、ある時代の高校生の姿を思い浮かべると、そこにはエナメルバッグがしっくりくる。あるいは、ナイキのボストンバッグを買うのではなく、修正液でナイキのマークを描いていたといういじらしさにも、強烈なリアリティを感じる。そこには、90年代のナイキが持っていた特別な輝きも、織り交ぜられているような心地がする。わたしたちが「リアル」を感じるのは、こうした部分だ。
サンデー・インタビュアーズをめぐるドキュメント2022
第1回「時間が経てば経つほど、見えないものが見えてくる」
第2回「結婚の挨拶に行くと、びしっとスーツを決めていて」
第3回「テーマを持って作品を作ろうという意識がおありなんだろうな」
第4回「個人的なもののはずなのに社会的なことを考えてしまう」
第5回「ボストンバッグに修正液でナイキのマークを描いていた」
第6回「電子レンジがあるはずなんだけど、ないんだよね」
第7回「手で牌を混ぜる音が1階まで聞こえていた」
第8回「カメラを通して住んでいる環境と向き合える感じがあったんです」
第9回「懐かしさを感じるために止まらないといけないのか」(最終回)
文=橋本倫史(はしもと・ともふみ)
1982年広島県生まれ。2007年『en-taxi』(扶桑社)に寄稿し、ライターとして活動をはじめる。同年にリトルマガジン『HB』を創刊。以降『hb paper』『SKETCHBOOK』『月刊ドライブイン』『不忍界隈』などいくつものリトルプレスを手がける。近著に『月刊ドライブイン』(筑摩書房、2019)『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』(本の雑誌社、2019)、『東京の古本屋』(本の雑誌社、2021)、『水納島再訪』(講談社、2022)。
サンデー・インタビュアーズ
昭和の世田谷を写した8ミリフィルムを手がかりに、“わたしたちの現在地” を探求するロスト・ジェネレーション世代による余暇活動。地域映像アーカイブ『世田谷クロニクル1936-83』上に公開されている84の映像を毎月ひとつずつ選んで、公募メンバー自身がメディア(媒介)となって、オンラインとオフラインをゆるやかにつなげていく3つのステップ《みる、はなす、きく》に取り組んでいます。本テキストは、オンライン上で行うワークショップ《STEP-2 みんなで“はなす”》部分で交わされた語りの記録です。サンデーインタビュアーズは「GAYA|移動する中心」*の一環として実施しています。
https://aha.ne.jp/si/
*「GAYA|移動する中心」は、昭和の世田谷をうつした8ミリフィルムのデジタルデータを活用し、映像を介した語りの場を創出するコミュニティ・アーカイブプロジェクト。映像の再生をきっかけに紡がれた個々の語りを拾い上げ、プロジェクトを共に動かす担い手づくりを目指し、東京アートポイント計画の一環として実施しています。
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、公益財団法人せたがや文化財団 生活工房、特定非営利活動法人記録と表現とメディアのための組織[remo]
