
ほぼ独学で東大に合格できた教材を紹介します
前回は勉強法の話をしたので、今回は各教科でどんな教材を使っていたかを紹介します。未読の方は先に下のリンクの記事をご覧ください。
まず前提として、各教科のセンター(現・大学入試共通テスト)過去問と、東大過去問(赤本)15~25年分は必須なので用意しました。
以下ではそれ以外で各教科使ったものを紹介していきます。
今の受験用としても使えるものばかりですが、一部内容が新しくなったものは別途取り上げています。
国語
現代文は元からある程度実力はあったので、センターと東大の過去問だけ演習しました。(現代文が苦手な方には出口旺のレベル別問題集がオススメです)
古文は日栄社の古典文法と、読解用で初級、中級、上級の3冊の問題集を使いました。漢文も基礎の復習用で日栄社のを使いましたが、ここは店頭に並んでいるもので自分にとってやりやすいと思うものなら何でもいいと思います。
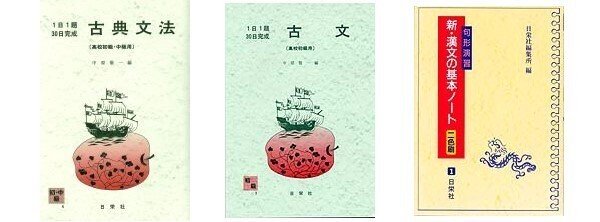
古文単語は教学社の「風呂で覚える古文単語」を使いましたが、これも自分にとって見やすければ何でもいいと思います。
あと、漢文は数研出版のチャート式を使いました。これは文法もそうですが、文法や句形、有名な文章や漢詩の詳しい解説だけでなく、中国史や文化などの背景知識も色々とつくのでオススメです。特に漢詩の見方が分かりやすく、個人的には東大2次でもかなり役に立ちました。

以上の教材を経てセンター、東大過去問へと無理なくステップアップできました。
数学
数研出版のチャート式の白(基礎~センターレベル)と青(難関大入試レベル)をⅠAとⅡBでそれぞれ用意し、3周ずつしました。その後センター過去問 → 東大過去問です。
学校で採用されている数学の問題集は4STEP や Focus Gold など色々ありますが、個人的には解説が丁寧で、難易度がスモールステップで上がっていくチャート式がオススメです。
これでセンターは十分通用したものの、東大過去問はかなり難しく感じた(もともと数学は得意ではなかった)ので、東京出版の「大学への数学 1対1対応の演習」など、もう1ステップ何かの教材を挟んでから東大過去問へ挑んだ方がよかったかなと感じています。
3年間の受験で数学の二次試験の点数は20点 → 27点 → 43点(80点満点)でかなり足を引っ張ったので、戦略ミスでした。
英語
英語は元々得意だったので、センターは発音・アクセント問題対策の参考書を1冊用意しただけでした(共通テストでは不要です)。
2次対策は桐原書店の「英文法ファイナル問題集 難関大学編」と、共学社の「東大の英単語(鬼塚幹彦著)」を買いました。前者は文法単元別に実力判定でき、問題のレベルも秀逸でした。後者は知っている単語でも新しい視点から学べることが多いので、読む価値がありました。

文法問題集の中には選択式の問題しかないものもありますが、個人的には空欄補充や和文英訳など、自分で1から考えて答えを導き出す形式が含まれているものの方が実力がつくと思います。
世界史
小学生の頃から歴史の授業が嫌いだったので、世界史が全教科で一番苦労しました。他の教科は参考書や問題集を合わせて1~4冊程度で済みましたが(過去問除く)、世界史は最終的に計8冊買いました。どれを読んだり解いたりしても、それぞれの教材からわずかずつしか自分の頭に入ってくるものがなかったので、数が増えました。
最終的に既存の教材では満足できなかったので、分かりにくいところは自分で Excel を使って年表や一覧表にまとめて覚えました。当時のファイルが残っていたので、参考画像を下に載せます。



世界史はどうしてもタテの流れ(1つの国や地域の歴史)にヨコ(同時代に別の地域で起きたこと)が混じりがちなので、自分で分かりやすいようにまとめた方が早かったです。
地理
センターは「村瀬の地理Bをはじめからていねいに」の系統地理編と地誌編(ともに村瀬哲史著)を読んで、後は過去問を解いただけです。非常に分かりやすくまとめられているので、これだけで8割以上取れました。
現在は内容が新しくなって、「村瀬のゼロからわかる地理B」のタイトルで同様に系統地理編と地誌編が出ています。

二次の記述対策には「大学入試 地理B論述問題が面白いほど解ける本(宇野仙著)」を買いました。こちらも東大レベルまで対応しており、過去問と合わせていい練習になりました。
理科
センターの理科は地学基礎と化学基礎を選択しました。地学は覚えることが少なく、問題のパターンも限られているのでコスパが良いことが決め手でした。ただし選択する人が少ないので、店頭に並ぶ参考書や問題集も種類が少ないです。
私は中経出版の「決定版 センター試験 地学Iの点数が面白いほどとれる本」を買って、後は過去問で対策しました。現在は「大学入学共通テスト 地学基礎の点数が面白いほどとれる本」のタイトルで販売されています。過去問だけで不安なら問題集も購入してもいいと思います。
化学基礎の方は、物理は嫌いだし生物は覚えることが多いしということで、消去法で選択しました。参考書は東進ブックスの「鎌田の化学基礎をはじめからていねいに」を使いました。また、化学基礎の方は計算問題がちょくちょくあるので問題集が必要だと思い、文英堂の「シグマ基本問題集化学基礎」が薄くてよくまとまっていたので購入しました。
これで両方とも8割以上取れました。
○○基礎のレベルであれば、理科も自分がやりやすいと思うものなら何でもいいと思います。
補足
東大受験となると大量の参考書や問題集を使ったと思われるかもしれませんが、自分の弱点と目的がはっきりしていれば、手当たり次第にあれやこれやと手を出すことはありません。
現代文や英語ははじめからある程度出来たのもありますが、全体として割と少ない冊数で済んだかなと思います。世界史だけは迷走しましたが…。
あと、タイトルに「ほぼ独学」と書いたのは、受験1年目の2次試験直前だけ、東進の東大対策の映像授業で国語と数学を受けたからです。1年目はセンターでコケたので、何とか巻き返したいと思い受けました。国語は非常に有益な内容(現代文は林修先生)でしたが、数学の方は当時の自分のレベルが低かったのであまり実力アップには繋がりませんでした。
これ以外は3年間で他者から勉強の指導は受けていないので、「ほぼ独学」としました。私は入学後に周りの子に受験勉強の内容について色々聞きましたが、地方出身の子を中心に、塾や予備校に行かずに自分で勉強して東大に合格した人が一定数いました。都市部と違い、地方だとそもそも大手の塾や予備校がなく受験に不利な環境であることは否めませんが、取り組み次第でいくらでも可能性は広がるはずです。
この記事の内容がこれから受験に向かう方の、何らかの参考になれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
