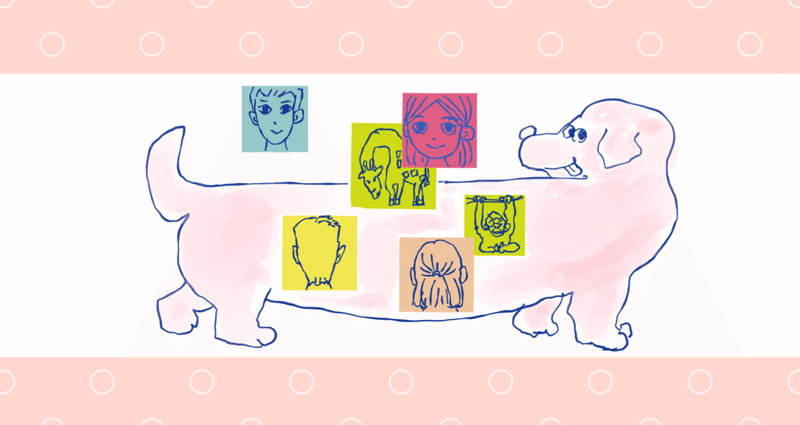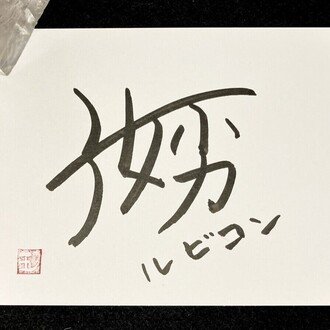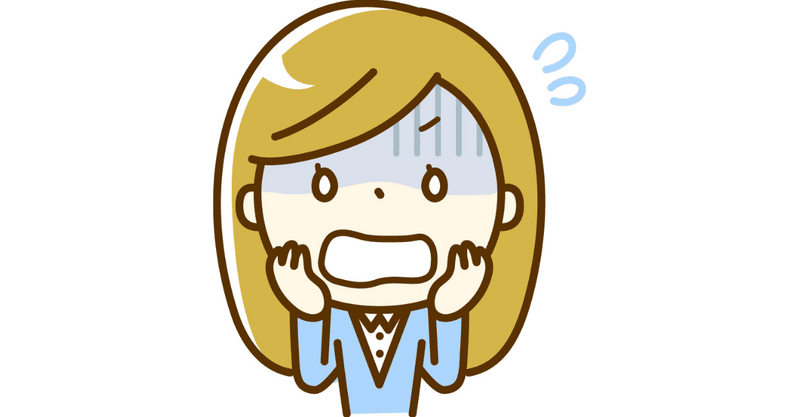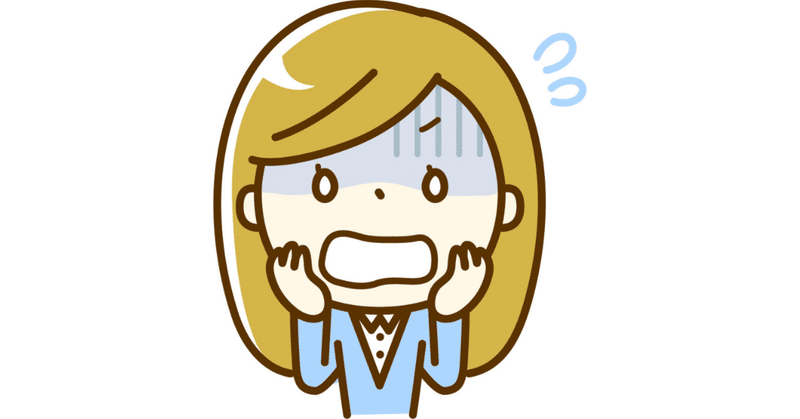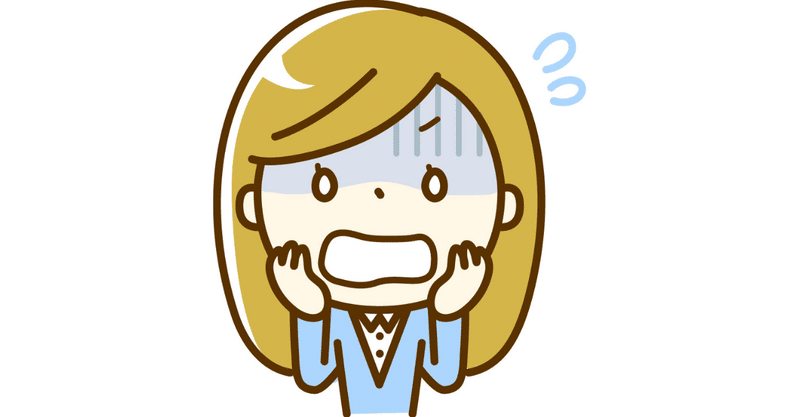#小論文を学ぶ
ローレンス・シルバーマン(2) ー ブラジャーよさらば !ー
オイラが中学生の頃(1960年代末)なんて、アメリカがベトナム戦争にのめり込み、フランスでは社会変革を求める5月革命が、そして日本では全共闘運動が暴れるという物騒な時代。
70年代、マス・メディアはオイラたちの気質を、無気力・無関心・無責任の三無主義と呼び、オイラたちの世代を無共闘世代とかしらけ世代と呼びました。
でも、もし洒落た言い回しがしたいのなら、過激を好まない穏健世代、あるいは中庸(ち
ローレンス・シルバーマン(1) ー 論理的推論 ー
これから何回かに分けて、ローレンス・シルバーマン連邦高等裁判事(85歳)の主張の前フリの記事を投稿しちゃうことにします。なぜって、それはオイラの思考回路を理解してもらうため(笑)。
◇ ◇ ◇ ◇
英語の induction は「duc-」「 duct-」(ラテン語の「ducere = to lead(導く)に、接頭辞の「 in(中に、上に)」 が付いて帰納