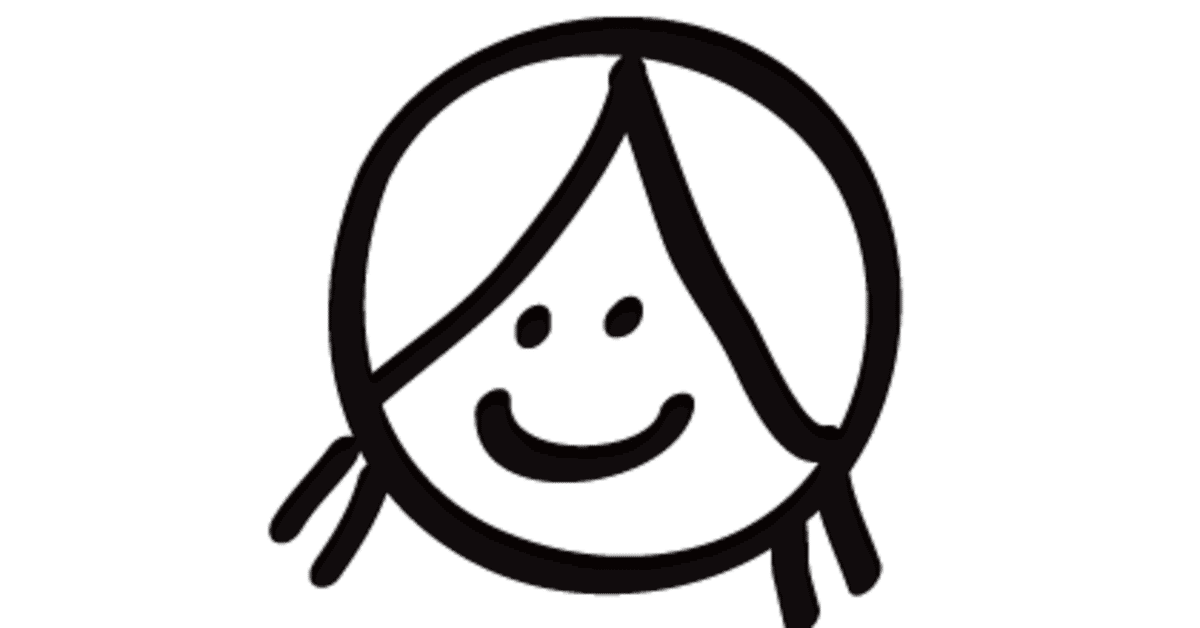
教員の理不尽な指導をもたらす背景は、懲戒権にある③
不登校30万人の現実が示す
学校教育に潜むさまざまな課題
教員が個人の判断で子どもに懲戒を加えることができる現行制度は、学校の安全を守る上で一定の効果をもたらしています。そして同時に、見過ごすことのできない弊害をもたらしています。その一つが、いわゆる不登校問題です。
ここからは、不登校の観点から懲戒の問題を見ていきたいと思います。朝日新聞の記事がもとになりますが、少しその話をしていきたいと思います。
不登校の理由「先生の多忙さと関係」
文部科学省が毎年行う「児童生徒の問題行動・不登校調査」の結果によると、2022年度に不登校だった子どもは小中学生だけで29万9048人。前年度から22.1%増え、10年連続の増加になった。
2023年11月26日付 朝日新聞
問題行動調査は、さまざまな事柄について学校側の認識を問う統計です。記事によれば、不登校の原因で最多は「無気力、不安」の51.8%。学校は、こう認識していることがわかりました。
一方、特定非営利活動法人多様な学びプロジェクトが、すでに不登校状態になっている子どもの保護者を対象として調査したところ、「最初に不登校になったきっかけは何ですか?」という問いに対する答えでは、「先生との関係」が33.5%。これは、先生と合わなかったとか先生がこわかった、そういった理由です。そして、この調査の自由記述の中にはこんなことが書かれていました。
「先生がいつもピリピリして怒鳴る場面もあり、息子は怯えたり、先生の理不尽な言動に怒ったりしていました」。これは、小学校6年生の母親の回答です。
小学校5年生の児童の母親は、「学校が忙しすぎる。とにかく急がされるので子どもが疲弊している。先生が忙しすぎてその大変さが子どもに伝わる」と答えています。
さらに、最初に不登校になったきっかけの2位は、「学校のシステムの問題」26.2%、3位は、「勉強は分かるけれど授業が合わない」の20.3%となっていました。
文科省の調査とは
大きくかけ離れた結果になる理由
文科省の問題行動調査では、「無気力、不安」が51.8%、「生活のリズムの乱れ、あそび、非行」が11.4%、「いじめを除く友人関係を巡る問題」が9.2%。と「多様な学びプロジェクト」による調査結果と大きく乖離しています。もちろん単純に比較できるものではなく、たとえば問題行動調査の場合にはあらかじめ選択肢があり、そこから選んでいくために差が広がっているのは無理もないかもしれません。もともと問題行動調査は、学校から上がってくる数字を文科省が足し算しているだけなので、これを調査と言っていいのか、統計と読んでいいのか、私は疑問に思っています。
この「多様な学びプロジェクト」の調査で、不登校の理由の1位が「先生との関係、33.5%」となっている理由は、懲戒権の問題がどこかに影響しているのではないかというのが私の推測です。
もしそうだとするならば、不登校というのは子どもの避難行動ではないか。子どもが、あるべき姿を強要されて、それについていけない、あるいは理不尽な叱責を受ける、そのことがとてもつらい。そう感じた子どもたちが学校から避難している姿が、いわゆる不登校なのではないか。あるいは学校教育の矛盾や嘘や、そういったものに気づいた子どもが教育を見限っている、そういった状況が不登校なのではないか、とも想像できるわけです。
あるべき姿を執拗に求めるのは
ありのままの子どもを受け入れられないから
「まぼろしの子ども像」というエピソードを紹介したいと思います。これは教育ジャーナリストの青木悦さんがご自身の著書『孤独な、なかよし』という本の中で、おとなが期待とともに描きだしてしまう「まぼろしの子ども像」について触れた部分です。
親の持っている「まぼろしの子ども像」は、すさまじいものです。たとえば「理想的な子ども」として親が描くのは、
「朝はひとりでさわやかに飛び起きて、前の晩自分で用意した清潔な衣服を順番を間違えずにすみやかに身につけて、朝から生野菜でもなんでも好き嫌いなくモリモリ食べて、忘れ物の一切ないカバンを持って元気に飛び出し(けっして、学校に行く時間がきたらトイレにこもったり、イヤだといって玄関にうずくまったりすることなく)、近所の人に出会ったらむこうからあいさつされる前に『おはようございます!』とさわやかにあいさつをして、学校に行ったら体調が良かろうと悪かろうと常に積極的にハキハキと、全教科まんべんなく関心を持ち(本当は全教科できてほしいんですが、全教科できることはなかなかむずかしくてできないから、できないことはよく分かっているから、せめて関心を持ってほしい、となります)、友だちにもやさしく、校庭の隅っこに咲いている小さな花に感動する心も持ち、夜はテレビを見ないで早く寝る」
といった子ども像です。
これが「まぼろしの子ども像」です。この一節を講演などで紹介すると、会場で笑い声が起こります。あまりの極端さに対する笑いかもしれませんし、あるあると思っての笑いかもしれません。
青木さんは、「まぼろしの子ども像」を示す前に、大事な断り書きを添えています。
ここでいう『親』の中には、学校の先生も保育士の方も教育関係の学者も児童館の職員も含まれます。
と。
なぜ私たちは、これほどまでに子どもに「あるべき姿」を求めるのでしょうか。おとなの基準を無理やり子どもに押し付けるのは、私にはある種の虐待と思えるのですが。
to be continued.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
