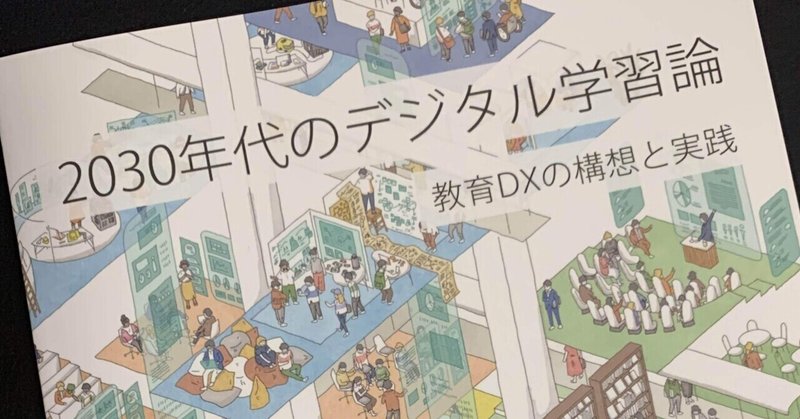
教育DXってなんなのよ(智場#124 2030年代のデジタル学習論)
私生活がバタバタしまして、大変久々な投稿になってしまった10月。そこからまた3カ月も経ってしまいました,,,しかし、緩くでも続けていきます。ご一読いただけたら嬉しいです。さて、3ヶ月前に書いたのはこちら。教育DXという言葉がやたら飛び交い始めていますが、どこに向かうのかとモヤモヤします。
というわけで、こちらの本を読みつつ、どうトランスフォーメーションするのかを考えてみたいと思います。
本日の本
さて、DXという言葉に初めて触れたのは2019年だったように記憶している。所属企業の中期計画の議論に参画した際、デジタルを軸にした抜本改革が必要で、本気でDXを考えるべきではないか、と言う話であった。その後2020年頃から、コロナ禍という背景もあり、メディアで盛んにDXというワードが飛び交うようになる。DXとは何なのか?どうなればDXできたとなるのか?DXに成功した企業はどこか?これら当たり前のことすらよくわからないまま、もはやバズワードと化していた。
そして、ついに教育DXである。巻頭論文で、豊福先生自身もこのワードの実態の無さに言及しつつ、有識者及び実践者の寄稿・対談から、「2030年代のデジタル学習論 - 教育DXの構想と実践 -」を考えようと言うのが本書である。
トランスフォーメーションで、
何が何に変わるのか?
教育DXが遂行されると、どのような変化が起こるのだろうか。これが最もわからない点である。新学習指導要領やGIGAスクール構想もあり、なぜ新しい教育が必要か?という発信は様々な場で見聞きするようになった。いわゆる「Society5.0の時代を踏まえると,,,」「一人一人のウェルビーイングを実現するためには,,,」というやつである。次に来るのは、「だから〇〇が必要だ」だ。例えば新たな学びとして探究,STEAMの学びが必要、学習環境として1人1台端末と高速回線が必要、労働環境として教員の働き方改革が必要、これらを成すために学校を支えるエコシステムが必要…確かにどれも必要とは思うが、ではトランスフォーメーション、すなわち何から何に変えるためなのか?と言うとよくわからない。
あるあるトランスフォーメーションを考える
教育DXで何が何に変わるのか?それを考える上で、最近言われるAからBへを考えてみたい。
『コンテンツ』から『コンピテンシー』へ
新しい学習指導要領に代わる際、資質・能力への転換について言われるものがこれである。目的と手段を考えると当然と思う。すなわち、「コンピテンシーを育むために、〇〇のコンテンツを学ぶ」で考えれば妥当と思うのだ。一方で、コンピテンシーは身についたかどうか、評価が難しい。また教員側がコンピテンシーを育もうとしすぎて、児童生徒が受動的になるのも望ましいとはいえない。このように留意すべき点はあるが、教育活動が児童生徒に意味あるものになるためにも、『コンピテンシーのためのコンテンツ』と考えることは大切なように思う。以下は参考。
コンピテンシーを重視すると言っても、そのことが、各教科等のコンテンツを軽視するものではないということである。コンテンツを学習する過程において、コンピテンシーが育まれるのであるし、より高次のコンピテンシーを獲得することにより、さらに多くのコンテンツをより深く理解することが可能になる好循環が働くのである。したがって、コンピンテンシーを重視するとしても、コンテンツとコンピテンシーが二項対立で捉えられてはならないことについては、改めて留意が必要であり、一つ一つのコンテンツをしっかりと学習していくことの重要性が変わるものではない。大切なのは、コンテンツを学んだことで、どのような資質・能力が身についたかという学習の成果を意識することである。
https://www.saitama-city.ed.jp/04kanko/saitama/31/31/06-09.pdf
『相対評価』から『絶対評価』へ
生き方,活躍の仕方がますます”人それぞれだよね”となる中、同一規準に児童生徒を並べ、相対評価でできるできないを伝えていくことの価値は弱くなっているだろう。他方、絶対評価にすればOKというのも違和感がある。なぜなら、児童生徒からすれば、絶対評価の結果を渡されても周囲と比較しさえすれば、絶対評価の結果を相対的に扱うことになるためである。また評価者が絶対評価を行う際に、評価規準と評価対象だけでは判断しきれない場合、相対的な判断を下して絶対評価をつけることも多いのではないか。
そう考えると、絶対評価はあくまで手段であり、児童生徒が周囲を意識しすぎずに成長を実感し、その後の学びを考える機会こそ大切であることに気づく。ただし、ここにも落とし穴は存在する。絶対評価の規準である。児童生徒がその規準が絶対と過度に思わないよう、留意する必要がある。評価規準を駆け上がるための学びは悲しい。絶対評価は”到達度評価というより成長評価”といった方が狙いが明確になると思うが、その成長を見取る規準もあくまで1つの規準でしかないことに常に自覚的になるべきである。
『履修主義』から『修得主義』へ
明らかに生徒間の習得度合いに差があるのに、教室内で全員に同じ授業をするのはいかがなものか?このような問題意識から、一人ひとりの習得度合いに応じた学びに変えるべきと言う意見がある。さらにここでデジタルの出番、「AIを活用すれば、最適な学習コンテンツを一人ひとりに提示できる」というやつである。
理想としては正しいように思うが、それにより失うものも議論すべきだろう。隣の席の友人が二次関数を解いている中、自分は九九で苦労している。隣の席の友人が海外の英語ニュースを読んでいる中、自分は疑問詞を学んでいる。そこでは残酷なまでに”能力差”が浮かび上がる。もちろん、こうした点への留意が、過度な平等主義をもたらしていたとも言えるが,,,もう一つ。習得度合いを把握できる学びは非常に限定的ではないか。これから目指すべき学びは、むしろ習得度合いが把握しづらい学びではないか?
履修主義は裏がえせば教室内での共通体験、習得主義は教室内での個別体験である。次に挙げる対話的な学びを標榜するのであれば、履修主義の方が相性が良いようにも思う。もちろん、ただ履修すればオッケーというわけではないことは添えておく。共通の履修内容をもとに対話的に学びを深めるイメージだ。
『講義型授業』から『対話型授業』へ
私はこれに賛成である。講義型の学びの作り手は、教員だ。しかし、対話型の学びの作り手は教員と児童生徒の両者である。より良い学びのためには、自ずから児童生徒自身の関わりが重要になる。だからこそ学びを得られた際の手応えも大きい。対話的な学びの方が、得られる学びの総和は大きくなると考える。
一方、教授者側からすると、授業は講義型の方が設計しやすいのではないか。対話型はどのような学習成果が得られるか計画しづらいように思う。対話はどの方向に行くかわからないし、進行の難しさもあるだろう。想定した学習成果が得られるかもわからない。これを許容できるかがポイントとも思う(そもそも、学校教育は学習機会は保障しているが、学習成果は保障してきたのか?という疑問も生まれるが)。
私は、対話型授業における教員の役割は、講義型以上に重要と考えている。対話までの導線,対話テーマの設定,対話から生まれた創発に対する即興的なフィードバック。極めて専門的なスキルで、良い学びにはこれが必要。だから学校・教員というものは大変重要と思っている。
『学歴』から『学習歴』へ
まず、私はこの考えに反対である。学歴重視に賛成なのではない。学習歴を重視しすぎることに反対なのだ。『学歴/学習歴』から『活動歴』、であれば賛成したい。学びとは、最もエントリーハードルの低い活動と考える。今では無料の学習用オンラインコンテンツが星の数ほどある。端末とネットワークさえあれば、学習へのアクセスは容易だ。だからこそ、学習したことを踏まえて何をしたか?何に貢献したか?の方が重要だと思う。
学校での学びにもつながる。「学んで、何をしたの?」が問われて然るべきと思うのだ。もちろん学生の立場なのだから、学ぶことに重きが置かれるべきと思う。しかし、就職までは学び、就職後にいきなり「何かせよ」はなかなかしんどい。もう少し、ソフトランディングするような形になっても良いのではないか。
『卒業後の進路』から『将来のウェルビーイング』へ
教育の目的として、児童生徒のウェルビーイングが語られることも増えてきた。また二項対立的に、卒業後の進路(いわゆる受験結果)のための学習と比較されることも多いように思う。言い換えれば、より長期的な視点で教育活動を行うことの重要性が今一度確認されているのではないか。
たしかに、小学校,中学校においては、卒業後の進路はあまり意識されていないかもしれない。進路実現の期待は、塾が担うからだ。一方、高校になると違う。多くの学校が進路実績を気にしている。高校選びの過程で、進路実績が気にされる。そして大学受験がひとしきり終わるタイミングでは、週刊誌が東大ランキングに代表される実績競争を煽っている。
学校教育は公教育だからこそ、短期的な受験競争への貢献を求められるのではなく、より長期的に”国民”に価値を提供すべきと思うので、概ね賛成である。しかし、留意すべき点もある。それは、前述したコンピテンシーを評価しづらいのと同様に、学校教育が一人ひとりのウェルビーイングに寄与したかどうかは検証しづらい。悪く言えば、「言ったもん勝ち」になってしまう。教員の立場からすれば、「受験のためになんかやってないよ」という意見もあるだろう。ウェルビーイングは重要な視点ではあるが、やっぱり大事だよね、程度の話で留めておきたい気もする。
私見的教育DX
最近の”あるあるAからB”を並べてみると今一度気づくことがある。それは「コンテンツを、講義型で教え、点数で、相対的に評価してきた」過去に対して、社会変化を踏まえ「コンピテンシーを、対話型で育み、個々の絶対的な成長を重視する」教育に舵が切られている点である。この大きな潮流を踏まえ、デジタルでどんなトランスフォーメーションを進めるべきなのか?
デバイスとネットワークにより、生徒がエンパワーメントされることは不可逆だ。税金で配備される1人1台端末の利用をコントロールしたところで、99%の高校生がスマホを持っている時代、ますます生徒は力を持つだけだ。そして時代的な要請、能動的に問題を定義し、共創を生み出し、解決に寄与できる人材はますます期待されている。
そう考えると、トランスフォーメーション後の姿は明確だ。生徒自身が学びに能動的主体性を発揮できている姿こそDX後の姿であるはず。そう考えると、学校現場でも、生徒が学習指導要領で規定された内容,評価観点から逸脱することも是とされるべきと思うのだ。教育DXとは、計画された学びを行う学校から、想定外の学びに溢れる学校に変わることではないか?そのためにも、過度に設計され課されているカリキュラム、縛り付ける評価は見直されなければいけない。このレベルであれば各校の議論で行えるのではないか?デジタル環境を整備しつつ、生徒の能動的主体性を削ぐようなカリキュラム設計,授業デザイン,評価設計はないか総点検。良い取り組みは教員間で環流させる。良い生徒の学びもどんどん生徒間の環流を促すべきだ。受験生,保護者は旧来的な学びをイメージしているかもしれない。そこに対しては堂々と、学校の議論の様子,生徒の学びの姿を体外発信すれば良い。そんな学校は、大変魅力的に映ると思われるはずだから。
最後に
だいぶ本書と関係ない記述になってしまった。まとめに変えて、本書に掲載されていたアニカ・アゲリ・ゲンロット氏の論文『Leading Digital Transformation in the School sector(学校におけるデジタルトランスフォーメーションを牽引する)』より、下記を引用したい。
📝 論文では、有用な方法とツールを提供し、それらをテストした。これをどう用いるかは、学校のリーダーと教師にかかっている。意欲,スキル,適切な判断,そして何よりも忍耐力が求められる。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
