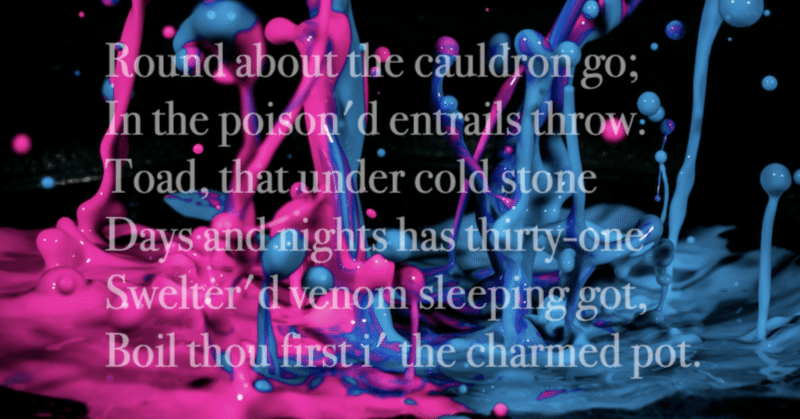
ショートショート 『狩られる』
残りの追っ手は、二人。
張は背をかがめ、朝焼けでオレンジに染まる丘の麓を南北に伸びる森林地帯に入った。
武器はサバイバルナイフだけだ。
向こうは各々自動式拳銃を持っている。圧倒的に分が悪い。おまけに張の左手のブレスレットからは、15分置きに彼の位置情報が追っ手たちに伝えられている。誤差50メートルで。
それでも最初に攻撃をしたのは、張だった。昨日のことだ………。
「帰ったら、派手にパーティをしようぜ。なにしろ見たこともないような金が入るんだ、ジオンゴにありったけのクスリを掻き集めろって言っといてくれ。そうだな、ドラゴン・アイを貸し切っても良いか?」
その若造はスマートフォンで野放図にしゃべりながら山道を歩いてきた。視界をふさぐ両側の茂みに気を配ることも、銃を手にすることもなく。
張が手製の槍で脇腹を刺したときも、彼はスマートフォンを手放さなかった。気のおけない仲間にちょっと悪さをしかけられたような顔で身をよじり、振り返った。唇には、まだ笑みが残っていた。少年と青年の間だ。
槍で人間の腹を刺すのは初めてだった。
絶叫は、自分のものか若造のものか分からなかった。張は腰を落とし闇雲に槍を押し込んだ。
若造が身体を横に折り、脇腹に刺さった槍を握った。
「畜生!」
吠え、抜こうとするが、腰に力が入らない。そのまま棘のある茂みに横倒しになる。
張は槍の根を逆手に持ち替え、跳んだ。体重を乗せる。プチっという感触。
若造は草の中で踊り狂った。腹の向こう側に赤黒く濡れた槍の先端がのぞいている。
もう一度、張は跳んだ。若造を貫いた槍が土に刺さり、昆虫採取のようにピン留めする。若造が言葉にならない悲鳴を撒き散らす。
興奮で、銃声は聞こえなかった。
熱い質量をもったものが後頭部をかすめた感覚があった。
張は若造を支点に、棒幅跳びの格好で薮のむこうに飛び込んだ。そのまま全力で走る。離れてしまえば拳銃の射撃精度などオモチャのようなものだと、トレーナーが言っていた。
確かに続けて撃ち込まれた銃弾は、あさっての方向ばかりに着弾した。樹々に邪魔をされ、張を見失ってもいる。ただ、偶然という危険はある。
張は太い杉の陰に隠れた。息が弾む。怖い。小便を漏らしそうだ。それでも抑えられない興奮がある。
張は喉の奥で、クツクツと笑った。
森に入ってきたのは、痩せた白人男だった。薄茶色の髪をポニーテイルにしている。さっきの若造よりは銃の扱いに慣れているのだろう、素早くカートリッジを入れ替えた。
「おえっ!」
地面に串刺しになった若造を見下ろし、声をあげる。若造が助けを求める。あれで即死するとは思えない。すぐに病院にかつぎ込めばどうにかなるだろう。
男はそうしなかった。
膝をつき、甲虫のようにうごめいているアジア系の若造を観察していたが、立ち上がると、こちらに向かって二発撃った。
「さっさと逃げろよ!お前も、こうしてやるからな」
と叫んだ。
張は微笑んだ。
支給される弾の数は知っている。プレッシャーをかければかけるほど、男は無駄玉を撃つ。奴に残りの弾を正確に数えるほどの知能があるとも思えなかった。
男を仕留めたのは、夕暮れ時だった。
澱んだ沼の近くまできたところで、男の弾も体力も尽きていた。
張は沼の中で待っていた。一度、やってみたかったのだ。子供の頃に観た、『地獄の黙示録』のシーンだ。張は沼からゆっくりと顔を出し、水際にへたりこんでいる男の喉笛を存分に切った。
………しかし、残りの二人は手強そうだ。
追われている感覚はある。
人里離れた山でしばらく過ごせば、人間の気配に関する感覚は研ぎ澄まされてくる。追跡者が迫っている。
距離は一キロもないだろう。張のブレスレットから発せられる信号を追い、じわりと間を詰めてくる。
張は森の中を南に向かった。樹々の葉を通して見あげる太陽は真上にあった。
罠まで3キロ弱だ。
………あれに引っかかる相手なのか?
追跡者は全部で四人。昨日、二人を迎え撃った。どちらも賞金に釣られた素人同然の男たちだった。だが残りの二人は素人レベルではなさそうだ。武器の差を過信して距離を詰めてこようとはしない。臆病なほどに慎重だ。
張は背中に手をやった。
半年前の傷だ。今でも雨が近づくと痛む。
追跡者と揉み合って滑った傾斜に突き出ていた枯れ枝が、ゴアスティックのパーカーごと張の皮膚を裂いた。待機していた医療班の陳医師が散々文句を言いながら40針縫ってくれた。あの日の教訓は、孫子の、『善く守る者は、九地の下に蔵れる』だ。あんな場所で追っ手を迎えるべきではなかった。今日はしくじらない。
陽が傾きかけた頃、罠の場所についた。
敵が近い。ガサガサと茂みを分ける音が聞こえる。暗くなる前に、カタをつけるつもりだろう。
張は苔の上を選んで歩いた。滑りやすく歩き方のスキルが必要だが、足音を吸収してくれる。
その追っ手と向き合ったのは、窪地をはさんだ高台だった。距離は100メートル。拳銃の射程距離を大きく越えている。
巨きな男だった。
窪地の上に出たところで張を発見し、戸惑った顔で動きをとめた。迷彩柄のジャケットとズボン、バケットハット。ハンターなのだろう。さすがに闇雲に撃ってこようとはしない。
………もう一人は、どこだ?
さっき杉の間を横切った影を見たと思ったが、違ったか?
巨漢の動きに、張は考えを打ち切った。
………目の前の敵からだ。
張は追われる子鹿のように藪を飛び越えた。草の露が弾ける。男の狩猟本能を刺激する。
男は直線的に追う方を選んだ。
巨体にまかせて腰まである雑草を押しのけ、窪地に降りてくる。赤鬼に見えるほど顔が充血している。
谷の中央に来たところで、男が消えた。
一瞬遅れ、絶叫が聞こえた。
罵り声。意味は分からないが、おそらくロシア語だ。
張はゆっくりと近づいていった。
男は直径2メートルの穴の底に横たわっていた。血管の浮いた猪首の横と腹、右脚を先端を斜めに削いだ竹で貫かれている。拳銃は落とし穴の中、串刺し男の手が届かない場所に落ちている。
「痛そうだな。どうだ、痛いか?」
男を見下ろし、張は聞いた。
男が血の混じったツバを飛ばして吠える。向こうの山肌から木霊が返ってくる。駄犬の無駄吠えでしかない。
………では、これまでの慎重な追跡は何だったのか?
「動かないで」
女が言った。
振り返ろうとした首を、張はかろうじてとめた。後頭部に押し付けられた銃口は無視できない。
「膝をついて、そこに座って」
張は草に膝を落とした。警戒すべきはロシア人ではなく、この女だったのだ。
「ずいぶん手こずった」
女が言った。「左手でナイフを取って、その間抜けが寝ている穴に落として」
張がサバイバルナイフを落とすと、
「後ろからが良い?それとも前から?」
女は聞いた。「言っておくけど、セックスがらみのジョークを言うと撃つからね」
「そうだな、………いきなり殺されるのは嫌だ」
「じゃあ、こっちを向いて。わたしを驚かさないようにしてね」
張は数段階に分けて膝をずらし、女のほうを向いた。
若く見える女だった。モスグリーンのジャンプスーツに、ひっつめた金髪。化粧っ気のない薄い唇。銃の構え方から、訓練を受けた者だと分かる。
穴の底でロシア人が呻いた。
「うるさい熊ね」
「仲間じゃないのか?」
「ただの囮よ。まあ、役には立った」
女は言い、弾丸の装填を確認した。
「………で、あんたの欲しかったのは、これでしょう?」
張に向かって銃口を下げる。
銃声は重なっていた。
下手な操り人形のように手足をちぐはぐに踊らせ、女が仰向けに倒れた。
張は立ちあがった。
女が投げ出した拳銃を、ロシア人の穴に蹴り入れる。
緑色の眼が、張を見あげていた。
「ルール違反でしょう?」
致命傷ではない。右の肘と膝をライフルで撃ち抜かれているだけだ。もちろん、明日には動けるという状態ではない。障害が残る可能性もある。
「申し訳ない」
張は、女に頭を下げた。「私の指示ではない。部下が勝手にやったことだ」
「ふざけないで」
「なにしろ一万人を抱える会社でね。グループ会社を入れたらその十倍になるだろう。私の不在で、彼らやその家族を路頭に迷わせるわけにはいかない。自分の趣味を優先してばかりはいられない」
張はその場に座った。女の血飛沫で汚れた葉を千切る。噛むと、鉄の味がした。
「それなら、こんな趣味はやめることね」
「分かっている」
張はうなずいた。「努力はしてきた。最初はただの狩りを楽しんでいた。鳥、鹿、象、ライオン、ヒト、合法、非合法を含め。しかし、その内に飽きが来た。あなたはどう思う?狩る側と狩られる側、どちらの快楽が大きいか?」
「マゾヒストなの?」
女は左腕を曲げ上体を起こした。
「おそらくは違う」
張は首をふった。「純粋に快楽量の問題だ。生命体の危機に際して発動する快楽だな。それで私は、狩られる側にまわってみた。間違いなかった。ベルクソンの、エラン・ヴィタールを知っているか?生の飛躍だ」
「あんたは狂ってるか、自殺志願者だわ」
「そうかもしれない」
張は立ちあがり、女を見下ろした。「今回のゲームの顛末に関しては謝罪する。あなたの治療費、もし義手や義足が必要になるようであれば、最高の技術を無償で、無期限かつ無制限に提供する」
「あんたを追うわよ。ゲーム抜きで」
「それも良い。私にとっては快楽だ」
張は微笑んだ。「では失礼する。明日の朝、シンガポールで会議なのでね」
「クソ野郎」
女に手を振り、張は南に森を抜けた。
草地の果てに、三機のヘリコプターが待っていた。
生還した主人の姿に、社員たちが忙しく出発の用意をはじめる。陳医師が渋い顔で、彼の健康状態をチェックする。
張はヘリに乗り込んだ。
ローターの騒音の向こう、森の中で銃声が2発鳴った。
頭をふり、張は薄く眼を閉じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
