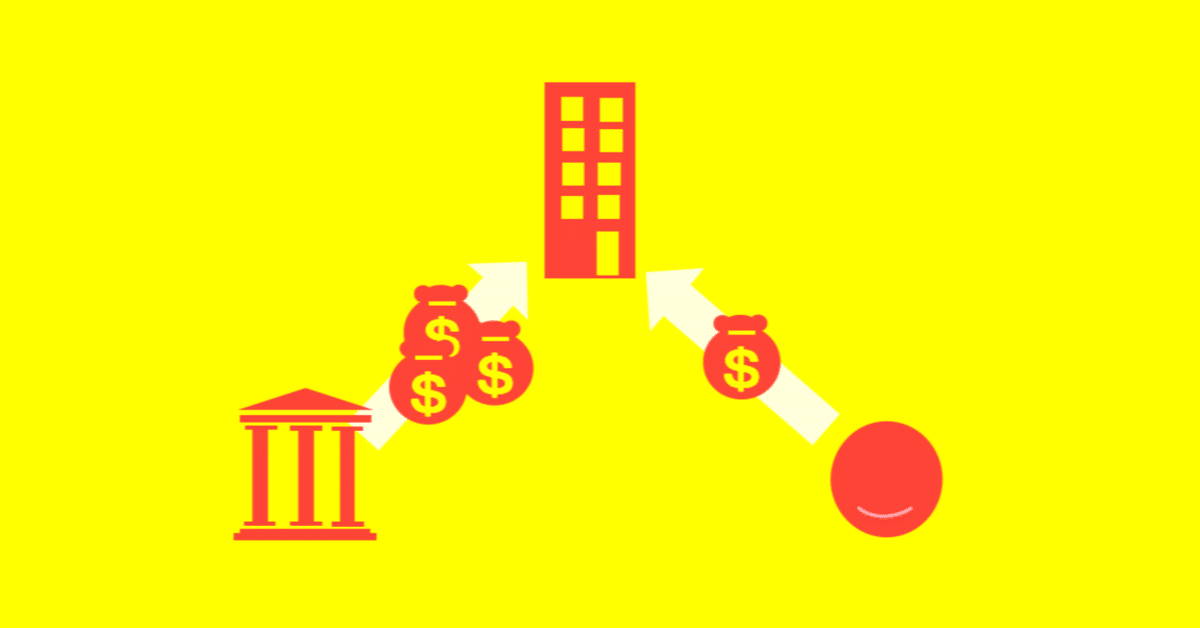
親の借金を相続したくない【相続放棄】
残された時間に大切な人を大切に。
相続アドバイザーのつむつむです。
親に借金があるのだけれど、親が亡くなった後、自分が代わりに返済しないといけないの?とても返せそうにない。
よくテレビでも、親の借金を理由にとても苦しい立場におかれる子どもが描かれることがあります。まるで親に借金は子どもが返さなければならないかのような印象を与えていて、私はとても問題だと感じています。
一方で、「相続放棄」という言葉自体はよく知られています。これは、親の借金を返さなくて済む制度です。そのため、「相続放棄」さえちゃんとわかっていれば、親の借金について悩む必要がないはずなのに、それでも多くの方が心配をされています。「相続放棄」の名前だけ知られていて、その中身がよく知られていないからなのでしょう。
この記事をきっかけに、「相続放棄」について理解して、親の借金についての不安を払拭しましょう。そして、もしもあなたの友だちが親の借金について悩んでいたら教えてあげてください。そういう意味では、みなさんが相続放棄について理解していると世の中から親の借金について悩む方が減ると思います。
「相続放棄」は、自分のために生じた相続をなかったことにできる制度です。
自分のために相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すれば、相続放棄が認められます。手続きは簡単ですね。
注意点の一つ目は、相続が発生したことを知ってから3か月以内にしなければならないこと。
同居の家族なんかは、亡くなった当日、相続が発生したことを知ると思いますので、亡くなった日から3か月以内に手続しないといけません。
注意点の二つ目は、処分行為をしないこと。処分行為とは、まるで相続人であるかのような行為、と私は説明しています。例えば、亡くなった方の預金を引き出すことは、処分行為に該当します。亡くなった方の預金は、相続人の方のものですので、あなたが相続放棄をするのであれば、手をつけるべきではないですね。たとえ、葬式代に充てるのだとしても。
他にも、亡くなった方の借金を代わりに返済することも処分行為に該当します。相続放棄をするのであれば、借金を返済する必要はありません。あなたは相続人ではなくなるのですから。この方には、父の生前お世話になったので、父の借金で迷惑をかけられないので、返済したい。なんて思って返済したら、もう相続放棄はできなくなります。相続放棄をした以上は、すべての借金について返済をしないでください。もしもあなたが連帯保証人になっていたりして、あなた自身の借金として返済をしなければならないのであれば、支払っていただいても問題ないです。けれど、自分自身には返済義務がないのに、父の借金を弁済してしまえば、処分行為に該当するので相続放棄ができなくなってしまいます。
とはいえ、この処分行為も多少は基準が緩いところがあります。たとえば、ほとんど経済的価値のない遺品を自分のものにしてしまっても問題視されることはまずありません。亡くなった方の物を何一つ残せないので悲しいですよね。
処分行為をしてしまった場合に、相続放棄を認めない趣旨は、あなたが相続放棄をしたことで、別の方があなたの分を相続することになりますが、そのときに、不利益のみを押し付けることがよくないという考え方が裏にあると思います。
裏にあると思いますというのは、もしも、「不利益を押し付けるのがよくない」というだけの考え方であれば、借金の返済をしても、相続放棄が認められなくなるというのは、おかしな話ですよね。つまり、「不利益を押し付けるのがよくない」というだけの考え方から、処分行為の考え方があるわけではないということです。
借金なんてないと思っていたら、3か月以上経過した後に多額の借金があることがわかった、なんていう場合が困りますよね。
一応、まったく財産がないと思って、相続放棄の手続きも何もしていなかった場合には、多額の借金があるとわかってからでもわかってから3か月以内であれば、相続放棄を認める、という判例があります。
但し、この判例が使えるのは、非常に限定的な場合だと思ってください。
例えば、わずかに預貯金があって、この預貯金を解約して使ってしまった後に、多額の借金があるとわかっても相続放棄はできないのです。
みたところプラスの財産もマイナスの財産つまり借金も何もないと思い込めるような状況でなければいけません。そういった場合には、将来多額の負債があることがわかった後であっても、相続放棄が可能です。
そのため、一般的には、亡くなったことを知ってから3か月以内でなければ相続放棄ができないと思っておいてください。心配なときには、とりあえず、相続放棄しておいてください。
ちなみに、他の相続人と協力できるのであれば、限定承認という方法もあります。これはまた別の記事にしたいと思います。
では、残された時間を大切な人を大切に。
