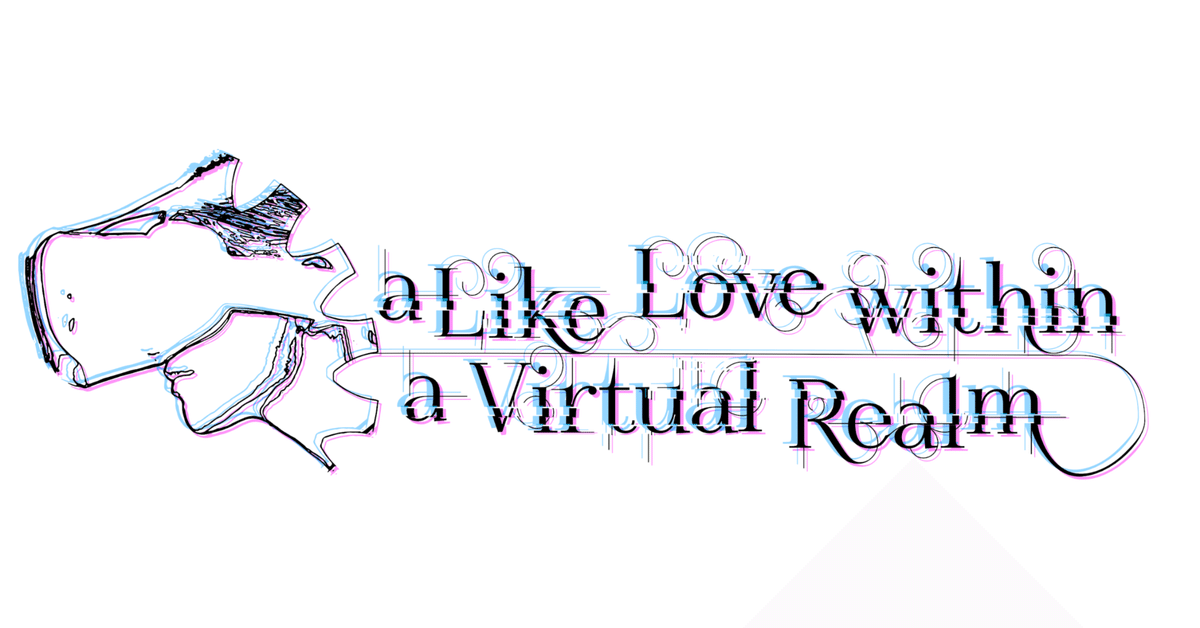
#03 #LLVR [a Like Love within a Virtual Realm]
「えーすごい! そうなんですか~」
女って大変だな、と思う。こんな男の相手なんて。
「私そういうの詳しくなくて~」
だって中身が男だとわかっていて、かわいいアバターでボイスチェンジャーで高い声にしていると知っていてこれだ。
「ふふふ。ありがとうございます~」
だから、面白いんだけど。
「いやー女の子って大変だねー」
ありがたいことに私のボイチェン技術は高いらしい。素で女の子と思われていることもあったりして、そういうのを聞くとしてやったりと思うのだ。外見はバリスではわりとよくいる感じの、銀髪を高く結ったポニーテールに瞳は赤く、そして露出度は高め服を着たアバター。胸の谷間とおへそと太ももが出ているファッションなんて、現実でやっている女子たちはすごいなぁと思う。自分がリアル女性だったらやってみたい格好だと思ってバリスではそういうふうにアバター改変をしたが、実際やるとしたら大変だろう。体型維持とか寒さ暑さ対策とか。
「カトルさんこそ、大変じゃないですか? キャバクラのイベント」
この女の子であるノルちゃんですら私を最初女だと思っていた。男だよ~とボイチェンを切ったときの反応は今年入ってからで一番良い驚きっぷりだった。
「遊びでやるからできてるんだよーこれ仕事にするとか女の子ってすごいねー」
この世界でのイベント事など所詮おままごとだ。学生たちがやる学園祭のごっこ遊び。少なくとも私はそう思っている。そう思っているから、本気で取り組めるという面もある。だって遊びなんて、本気でやらないとつまらないじゃないか。
「ノルちゃんはどうー? モテるんじゃないー?」
「いえ全然ですよ。人見知りだし」
「そーう?」
私はマイクがオンなのも気にせずついだ酒を煽った。カランカランと氷が転がる音が響いていることだろう。
「今日はアインたちは?」
「SNSで残業がーって叫んでました」
「あらら、お気の毒」
どうりでスリーの姿がないわけだ。アインがいないわけだしノルちゃんとは話したくないだろうし入る理由がないんだろう。それは見ているだけでわかる。
「この時間だと今日はインせず寝そうだなぁ」
「そうですね」
時刻は二十三時過ぎだ。二十二時から所属しているキャバクラのイベントがあって、さっき終わってノルちゃんのところへ来たばかりだ。もう少し駄弁っていたいが、ノルちゃんがいつ寝るかによる。
「――ね、ノルちゃん」
「はい?」
「ここの生活楽しい?」
「はい、楽しいです。……最近そうよく聞かれるんですけど、何かあったんですか?」
「誰に聞かれたの?」
「ディーさんとアインさん」
「ははは! 考えることは同じかー」
「?」
首を傾げるノルちゃんは確かにかわいい。リアルでもちゃんと女の子だし。おとなしめだし。声もいわゆる鈴の音のような声だし。
だからこそ警戒はすべきなのだ。女慣れしていない男が多いこの世界で変なやつに絡まれてここから去って行った女性の話なんて腐るほど聞く。そんな中ノルちゃんはラッキーだったと思う。アインに声をかけられて、変なやつと遭遇する確率の低いこのコミュニティに来れて。
「そろそろここにも慣れてきたっしょ? 変なやつも多いからさーこのゲーム」
「あー……そうですね」
ノルちゃんは苦笑いした。
「なんかあった?」
「こないだ初めて行ったイベントで、すごい質問攻めしてくる男性に遭遇しましたけど」
「あー」
よくいるタイプだ。コミュニケーションが下手で会話を繋げるためにとりあえず質問をしてくるタイプ。そしてそれをきちんとした会話のコミュニケーションとしてできていると思っているやつ。
「どうした? そいつ」
「フレンド申請が来ましたけど、スルーして落ちました」
「偉い」
よーしよーしとノルちゃんの頭を撫でる。別にこの頭は現段階ではアインだけのものではないし、ノルちゃんも嫌がってはいないので。
「でもそれくらいですね。ちょっとイベントに苦手意識ができつつありますけど……それ以外は、楽しいです」
「よかったよかった」
本当に良かったと思う。別に私が関わったことのない相手でも、変なやつに絡まれてフェードアウトしていった子達を見ると、可哀想だしもったいないなぁと思う。こんな楽しい世界を楽しめずに消えてしまうなんて。
「……これは、聞いていいのかわからないんだけど」
「はい」
「アインとは、どうなの?」
一度確認しておきたかったのだ。なにせアインは少なくともここではモテるけど長続きしないタイプで、それで傷ついた女の子がこの世界に最低一人いたことを知っている。その前の一人は、ちょっと変わったヤツだったのでよくわからないが。
「どう、ですか」
うーんとノルちゃんは上を見上げた。真似をして上を見上げる。そこにはローポリの天井が映っている。
「ありがたい、と思ってます。アインさんに会ってなかったら多分ここまで続けられてなかっただろうし。他の子から聞くような変な人に会うこともあまりないし」
「うんうん」
「――それだけ、です」
「それだけ?」
「それだけです」
「ふうん?」
ノルちゃんの顔に視線を戻して首を傾げてみたが、ノルちゃんは手を開き笑顔にして私と同じ方向に顔を傾けただけだった。その笑顔をすぐに引っ込めて、ノルちゃんは少し俯く。
「……私が、アインさんと仲良くしていると、不都合だったりするんでしょうか」
「……あー」
私はスリーのことを話すか迷った。そういえばノルちゃんの前ではスリーはほとんど喋らないから、やきもちから喋らないのではなく、普段からあまり喋らない子だと見られてもおかしくはない。ただそれを、今ノルちゃんに伝えるのは違う気がした。あいつやきもち妬いてるんだよ、じゃあ話すの控えますね、はアインの望むところじゃないだろうし、スリーの望むところに誘導するのも違う。別に私はスリー贔屓ではないし。
「いや、大丈夫だと思うよ。これまで通りで」
「そう、ですか」
よかったです。と彼女が肩の力を抜いたのがヘッドセット越しにわかった。
この子なら、アインを幸せにしてあげられるんじゃないか。なーんて思っていたが、どうだろうか。結局アイン自身が変わらないと。何も起きないだろう。
「――まあでも」
「?」
「こういうスキンシップはあまりいろんな人とはやらないようにね」
私はノルちゃんの頭を撫でる。はい、と彼女は素直に頷いた。
「ねぇフィーアちゃん、俺のこと好き?」
「やだーもうー恥ずかしいよー」
画面端に映しているフェイスミラーで確認しながら、ハンドサインで照れた顔に変化させる。このイベントの間だけ私はカトルではなくフィーアという名の女の子になる。足は内股、手は肘を閉じて胸か膝の上、首を傾げて基本目線を合わせたまま、密着した姿勢で時折相手の手や顔や太ももを触り、リアクションはオーバー気味に。露出度高めのかわいいアバターにボイチェンで高い声を出せば、あら不思議バーチャルキャバ嬢のできあがり。
「ねぇ~いいでしょ~そろそろフレンドになろうよ~」
「だぁめ。そしたらもうここに来てくれなくなっちゃうでしょー?」
「そんなことないよぉ」
しつこい客というのはいるものだ。そういうのが嫌な子はイベント用にアカウントをもうひとつ持っているが、私は面倒なので分けていない。フレンド申請はきちんと断り続けている。するとフレンドになりたがる人間は根気負けして他の嬢に行くか、このイベントに来なくなるかのどちらかだ。
「あんまりしつこいとお店にすら来れなくなっちゃうよ? 会えなくなっちゃうのやだなー」
「え~それは困るなぁ」
彼は上を向いた。リアルで飲んでいるらしい。カランと氷が転がる音がする。
「はぁーみんなガードが堅いんだからぁ」
「他の子にもそんなこと言ってるの? えーなんかショックだなー私だけだと思ってたのに」
ハンドサインを変えてしょんぼりした顔にする。
「いやいや違うよ! フィーアちゃんだから言ってるんだよ!」
嘘なのはもうわかっている。他の嬢からもしつこいという報告は上がっていて、これ以上言うようなら出禁の措置を取る、とオーナーは言っていた。
「だからさ! 特別に――」
「失礼します」
部屋の入口から低い声が響いた。紺色中心の長身体躯の姿の、最近入ったボーイの子だ。おそらくこんな客もいるから見てきて、とでも言われたのだろう。
「お酒のおかわりなど、いかがですか」
「いらないよ。邪魔しないでもらえるか」
「えぇーあたし飲みたいな。カクテルもう一杯いいでしょー?」
「んー……フィーアちゃんがそう言うなら、しょうがないな……」
「ありがとー!」
ボーイは淡々と物を出すギミックを弄りカクテルを出した。確かホストイベントでもボーイをやっているとかで、ギミックの扱いはすんなりと覚えていたし、わりとすぐにここのシステムにも慣れたようだった。こんな客も見たことがあるのか、至極冷静に対応してくれているように見える。
「こちらの今月のカクテルは梅雨をイメージしたもので、グレープフルーツリキュールにジン、レモンジュースで作られています。名前はアフター・ザ・レイン。止まない雨はない、という前向きな酒言葉がつけられています」
「へぇー素敵! ね?」
「あ? あぁ」
若干だが客のテンションは下がり不機嫌そうな声になった。二人の時間を邪魔されるのが本当に嫌らしい。新入りボーイくんはカクテルの蘊蓄で時間を稼いでくれて、去っていった。この迷惑客はフレンド申請の話題をするテンションではなくなったらしく口数少なになったので、私は適当に世間話をして時間が終わるのを待った。
「あ、そろそろ時間だ。名残惜しいけど、お別れしなくちゃ」
「えぇ~もうそんな時間かぁ……」
さすがに時間超過はペナルティになるとわかっているようで、時間になればきっちりと立ち去ってくれる。ただそれは次また来て嬢に粘着するためなので、ありがたいようでありがたくない行動だ。
「はぁー……」
相手を見送った後バックヤードへ戻る。おつかれさま、といつもより心のこもった労いの言葉がかけられた。
「ありがと」
「またしつこかったんじゃない?」
オーナーが心配そうな声色で尋ねてきた。私は手をひらひらと振る。
「いやぁめげないねぇあいつも。その根気強さ尊敬に値するわ」
「さすがに次やったら出禁ね……」
ふぅ、とオーナーは溜め息をついた。イベント運営も大変だ。私はそんなとき助けてくれたボーイくんを見つけ手を振った。
「さっきは助かったよ。リュウくんだっけ」
「はい」
「ありがとねーおかげで後半楽だったわ」
「いえ。お役に立てたなら、幸いです」
随分丁寧な子だ。このイベントはバリス内でもかなり大きなイベントなので、関わっている人も多く話したことがない人もちらほらいる。彼も前回だったか前々回だったかに入ってきたのだが、今日まで話すタイミングがなかった。
私はメニューのリストから彼を選んで、フレンド申請ボタンを押した。
「これからもよろしくね、リュウくん」
「はい」
「ああ、お店の外では源氏名呼ばないでね。カトルって呼んで。よろしく」
「リュウです」
よろしくお願いします、と彼は丁寧に頭を下げた。ここのゲームでは珍しいタイプだ。イベントだから淡々と丁寧にしているのかと思ったが、素で丁寧らしい。
「リュウくんは、普段は何してるの?」
「アバター改変ですね。仕事がそういう関係のものなので」
「CGクリエイターとかそのへん?」
「はい」
「じゃあ勉強がてら弄ってるみたいな?」
「そうです」
「へぇー」
とことん真面目な子らしい。
「ね、それどのアバターの改変? 見たことない気がする」
後ろで括った紺色の長髪に漆黒の瞳、長身体躯にスーツを着せていて、なかなか見かけないシルエットだ。
「これは、自作です」
「自作⁉」
思わず前のめりになってしまった。
「すごいじゃん! 普段は? 普段もそれ?」
「普段は――」
彼はアバターを変え、コントローラーではなくフルトラの足で綺麗にくるりと回って全身を見せてくれた。おろした紺色の髪はお尻のあたりまであり、すらりと長い手足には中華風の異国の衣服がとても似合っていた。お尻には触手のような形のふわふわした大きな尻尾がついている。黒い瞳に黒い角が、なんだか吸い込まれそうな暗闇のようだった。

「えーかっこいい! いいなぁーワンオフアバター憧れなんだよね」
「……よければ、作りましょうか」
「いやいや。そんなにお金ないよー」
「……練習がてらで、よければ、その、そんなにお金は……」
「え、まじ?」
社交辞令ではなく本気で言ってくれているらしい。私は頭の中でお金の計算をする。どれくらいの余裕が今あるだろうか。
「うん。ありがとう。ちょっと本気で考えさせて」
「はい。お待ちします」
にこ、と微笑んだ彼のアバターは、かっこいい、というよりは、美しかった。
No.03
私は嘘をつく
嘘だらけのこの世界で
私は嘘をつく
自分に対してすら嘘をつく
声を変えれば
話し方を変えれば
外見を変えれば
仕草を変えれば
現実の私とは違う私の出来上がり
私とおしゃべりしてみない?
あなたを楽しませてあげる
愉悦の門の手前まで
手を引いて案内してあげる
騙しているあなたのこと
私はとても大好きよ
嘘まみれの私を好きでいてくれる
騙されに来てくれるあなた
嘘を前提として成り立つここは
現実よりも遠くて近い
だってこんなに遠いのに
こんなに近くで囁やける
騙されてくれるあなたのこと
今だけはとても大好きよって
言ってあげるわ 嘘だけどね
挿絵:深水渉(https://x.com/wataru_fukamizu)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
