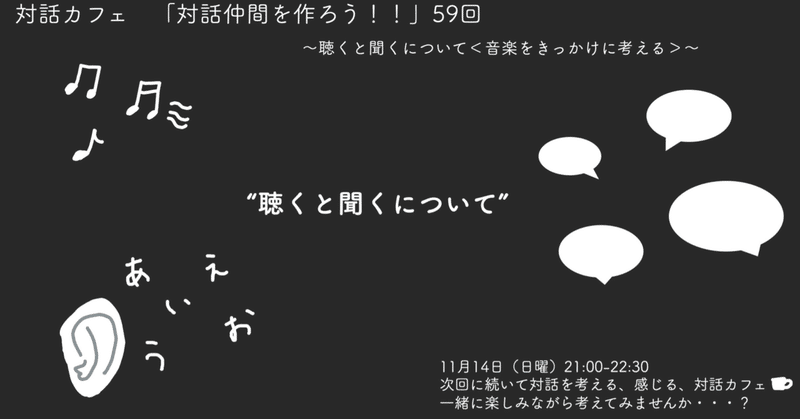
聴くと聞くについて〜対話カフェvol59〜
こんばんは。対話カフェも第59回になりました。
今回のテーマは前回対話のワークショップをやった際に好評だったことを受けて、聴くと聞くについて考えてみます。
1.初めに(好きな音楽と自己紹介)
まず最初に聞くといえば音楽🎸ということで、参加者の方の自己紹介も兼ねて好きな音楽についてききました
コブクロ「君という名の翼」
グスタフマーラー
90年代のアメリカのハードロック
小田和正やボーカロイド
沖縄音楽 独特なリズム
欅坂46 「サイレントマジョリティ」
ちなみにボーカロイドは人間に近いという意見が出ていましたが、理論的にもそうだ‼️という話も出ました。
たくさんの方とたくさんの年代の方が集まれば好きな音楽も多様で聞くだけでも楽しかったです。
2.音楽鑑賞①森洋一作曲「孤独の彼方」
荘厳な雰囲気もあり、ラジカルな雰囲気もありというこの曲の第一楽章をみなさんで聴きました。そして、この曲を作曲された森洋一さんが対話カフェに参加してくださっていたので、どんな思いを込めて作曲されたのか?について伺いました。
作曲された方に実際に生で説明していただくことはそうそう無いので嬉しかったです‼️

3.聴くと聞くの違いってなんだろう?
そこで今回のテーマであるこの問いを考えました。調べてくださった方がこんな記事を紹介してくださいました。
概ね参加者の皆さんのご意見はこんな感じでした‼️
聞く
情報が入ってくる。五感で経験する聞く
聞こえる?情報が意識せずに入ってくる?
聴く
音声より意識的に耳を傾けるもの
目的意識を持ってキク
認識を持ってキク
歴史的には後?つまり、後々入ってきた概念。
という違いがありそうだという話から、hearと listenの違いを調べてくださった班もあり、盛り上がりました。
4.音楽鑑賞②ジョン・ケージ作曲「4分33秒」
その後二曲目はこの曲を聴きました。
指揮者がタクトを降ろしても無音‼️聞こえるのは子供の声のみ。有名なこの曲ですが何も知らずに初めてきく場合は焦りそうですよね😅
この曲の感想としては
・初めに真面目に全部聞けてよかった。
・始まるまでのドキドキ感と緊張感を味わった
・途中から不安になって来る。弾いてるわけじゃないけど弾いてる。その場の足音や子供の声に耳がいった。→作品だなとわかった。鑑賞ってなんだろう?
・最初はざわざわしていたが、小さくなるものなんだなと思った。
・子供の声が気になる笑
ということが上がりました。また、学術的な解説を森さんにしていただき、
・実は三楽章ある。
・1950〜60年代は前衛的な時代。作曲家はともかくクラッシクとして前衛的なことをしていた。
・偶然、4分33秒の間で鳴った音が音楽である。
・今までの音楽を否定する意味で無音
・絶対零度で240秒+33秒
ことを教えてもらいました。みなさんはこの曲をどう聞きますか?或いは聴きましたか?

5.改めてあなたにとって「キク」とはなんですか?
というテーマで最後自由に対話しました。
・沈黙はそもそもあるのか??=雑音をいかに消すか?(音を出すことが音楽だけど、それを消すことが無音になる)音をなくすこともすごく大変なことなんだろうな
・音をない状態がないと、音がある状態がない?ってなることを示そうとしたのが音楽なのではないか?
・音がない真空の方がむしろ尊いのかなと思った(音を作ることの方が簡単・・?)
・ポリフォニーは対話っぽい?
・自分が何かをきちんと聴けているかとても不安になった。
・マインドフルネスを思い出した。外の静寂を丸ごと聞くし、風の音や何かの存在を聴く。また、己の内側の声も聞く
すごく多様なキクに溢れていて聞いていて、興味深かったです‼️必ずしも音があるようなものだけではなく、音がない状態を如何に聞くか?という点にも話が行っていて嬉しかったです。
6.アンケート
最後にアンケートです。
Q 今回考えたこと。特に聞くと聴くの違いについて
・聴く 聞く 訊く など本質的に楽しめると幸せな気がします。
・音楽を聴くとか、人の話を聞くとか様々有るんだなぁと思った。
・結局。。。。わからなかったです。違いはあるのかな?
・やはり解像度?
Q 感想やコメント
・音楽とは何だろう‥・。 音を味わうとは・。
・周波数について
・音が必ず存在する。
・ゲージはやっぱり素晴らしい
・構成の流れが簡潔でいいです。
・ありがとうございました。
Q 話したいこと
・コミュニケーションにおいて「質問」のポイントは・。
・オープンダイアログ
7.最後に
対話カフェでは結論がない世界を楽しむことも人の大切な目的ですので今回の対話を受けてさまざまな感想や気づきを持ってくだされば開催冥利に尽きるわけですが、今回このテーマを企画した理由や、私自身がどう考えているかを蛇足だとは思いますが書きます。
個人的には聞くとは単に五感的なレベルでの音や音の不在の認知であり、聴くとは聞くことを通して情報を能動的に探していくことだと思います。
聞くとは耳を使って相手の言いたいことや、周りの世界で何が起こっているかを能動的に把握しようとすることだと思っています。その点で文字通り耳から入った情報を14の心で捉えることです。
別に特にソースとかはなく勝手に考えたことで恐縮ですが、対話に必要なのはこの聴くことではないでしょうか?
人が伝えてることは何割相手に伝わるか、考えたことがあるでしょうか?そもそも、自分の言いたいことがうまく言葉にできているか?言葉に対しての認識は相手と自分で同じか?また、事前情報や背景によって言葉の意味もだいぶ変わってきますよね。そう考えると意思を相手に伝えることはとても難しいのだと思います。
ただでさえ、情報伝達は難しいものなので本当であれば細心の注意を払って聞かねばなりません。
時に浅野さんが提唱する〈対話法〉の確認型応答を使うのがいいでしょう。
聴くとは、音楽を聞いて、どういう背景で作曲したのか?どんな想いが込められているのか?言いたかったことは何か?などなどを心に留めながら聞くことだと思い、森さんの音楽を流してその想いを語っていただきました。
また、聞こえなくても聴くことはできます。無音であってもその中のメッセージ性、周りの音などを意識することが聴く。
対話においてはいろんな他者がいます。時には既に知っている話もあるでしょうし、そんな時は知っているなーと思って聞き流してしまうことたくさんあるのではないでしょうか?(私もたくさんあります)でもそんな時に、なぜ今この話をされたのか?どんな体験や思いからこの話をしているか?など言葉の裏に潜むメッセージを聴きながら対話してみてください。
もちろん自分には到底受け入れられない意見を聞くときは尚更だと思います。瞬殺的な自分のジャッジや声を一度保留をして、相手の言葉の裏まで聴いてから、自分がどう思うかを聴いても遅くはないはずです。
それでもその人の本意がわからなければ是非訊いてみるのが対話ではないでしょうか?
ご意見お待ちしてます‼️

2年前くらいに、津屋崎のLAPの合宿で感じたことでした〜
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
