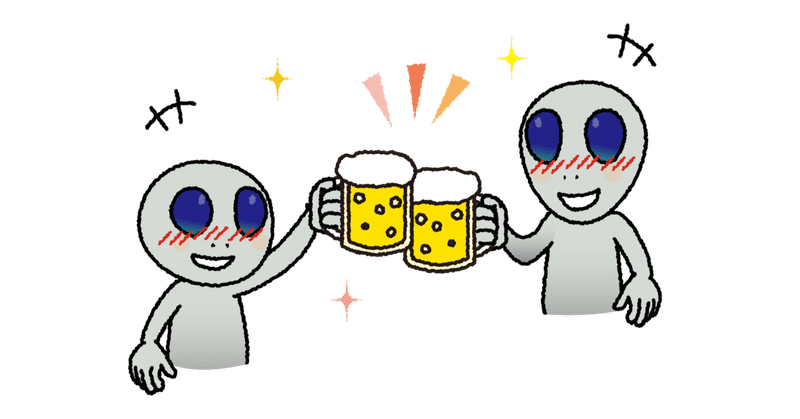
連載、ボトムアップ科学技術⑥〜ビールのイノベーションの行く末〜
さて、先週身近なものに問いを持とうという話をしましたが、1週間色んなことに気を配ってきたつもりです。皆様はどんな問いに出会えることができましたでしょうか❓
ぼくが出会った問いは
ビールの泡はどんな性質があり、なぜ人はこだわるのか?
という問いです。なんか未成年には優しくない問いが生まれてしまいましたが、どんな問いも立てること自体は自由だと思っています。もちろん問いを立てることに対してはそれなりに責任が伴うわけで、安易な答え方や結論を導くわけにはいきません。
出来る限り探求はしたいですが、あくまでその正当性を担保したり主張するものではなく、考察したものを記事にするということを断っておきます。
1.問いに出会った経緯
問いに出会ったのはとあるイベントに参加した際にこちらのビールに出会ったからです。
どうやら人気らしくて、他の参加者の方は喜んでいました。
ぼくは初めて知ったわけで、特に明け方も知らずに普通の炭酸飲料を開けるようにまずはそーっと開けました。
すると、少ない隙間に対してビールが吹き上がり🍺吹きこぼしはしなかったものの永遠に泡が出てきてしまってとても驚きました。
サイトを見たところどうやら一度に缶を開けるのが正解だったようです。
ただ、この体験からなぜ人はこうもビールの泡にこだわるのか?(この商品だけではなく、他にも様々なビールが綺麗に注げるコップなどもありますよね)
炭酸飲料の泡をこだわる人はいないのに、ビールの泡をこだわるのはどのような性質の違いがあるのか?(ビールと泡の比は7対3でしたっけ?ルールがあるのでしょうか?)
と思い、冒頭の
ビールの泡はどんな性質があり、なぜ人はこだわるのか?
という問いに行き当たりました。
(特に飲酒を勧めるわけでも販促の記事ではありません)
2.そもそもビールの泡って?
まずは自分の頭で考えて仮説を立てようと思うわけですが、ビールの泡としてやはり成分が違うのかなと思います。普通の炭酸飲料は水に炭酸ガスと砂糖が入っているわけですが、ビールは麦を発酵していると聞きます。この違いが泡の性質の違いを作っているのではないでしょうか?
また、よく洗われたグラスは泡立ちが良いということを聞いたような気がしていて、グラスの状態などによっても変化しそうです。
そんなことを思いながらちょっくら調べてみたらなんと論文を見つけました。
蛸井 潔氏のビールの泡ー基礎研究から応用開発まで―というレビュー論文ですが、これによるとビールの泡は単なる泡でもbobbleとは異なりfoarmと表現するのが適切で安定してクリーミーなものであることがわかる。
また、その原因として主に様々な蛋白質がコロイドとなることによって安定した泡を形成しているようだ。その成分は泡を形成しやすくするものもあれば、働きにくくするものもあることがわかる。
他にもこのペーパーはビールの泡の測り方や樽生ビールの測り方も解説しているため是非お読みいただきたい。
3.なんでみんなビールの泡にこだわるの?
さて、性質がわかったうえで、なぜビールの泡にこだわる(裏を返せばビールの泡が魅力の一つになっている)中考えていきましょう。
これも考察してるようなものや、アンケートは世の中にはあると思いますが、先ほど学んだ独特の泡の性質が1つビールの揺るぎない魅力なのではないか?と私は思うようになりました。
ピッチャーで注ぐようなビールはすぐに泡も消えてしまうようなbobbleの状態ですが、生ビールと称されるものはとてもクリーミーな持続的なfoarmになっており(もはや膜とも言えますよね)ビール本来の備えているポテンシャルを持っていると考えられます。
したがって人々はそれを求める結果、泡にこだわる人が多いのではないでしょうか?
正直かくいう私も普通のビールは苦くて飲めませんが生ビールは好んで飲みます。
これは必ずしも一般的で論理的に正しい答えではないと思いますが、僕の中で性質を調べることで納得した応えですのでここに記しました。皆様はどう思われますか?
ちなみにこの辺をちゃんと知るには社会調査法や、文化人類学的なエスノグラフィー。感性工学や人間工学的なアプローチから実証するんでしょうね。
3.新たらしいものって?
よくよく調べるとこの商品は一年前に既に発売されているようです。そして、その場にいた多くの方がこの商品を歓迎し、喜んでいました。
プルタブではなく、缶のように開けるビールはとても斬新ですよね。それだけでもこれには価値がありますし、これまでには無かった新しいものだと言えます。
缶なのに怪我をしない加工が施されているようで、その部分も新しいですよね。
これはいわゆるイノベーションというものです。
科学技術とイノベーションは切っても切り離せない関係にあると思います。
そこで来週はイノベーションについて記事にしようと思います‼️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
