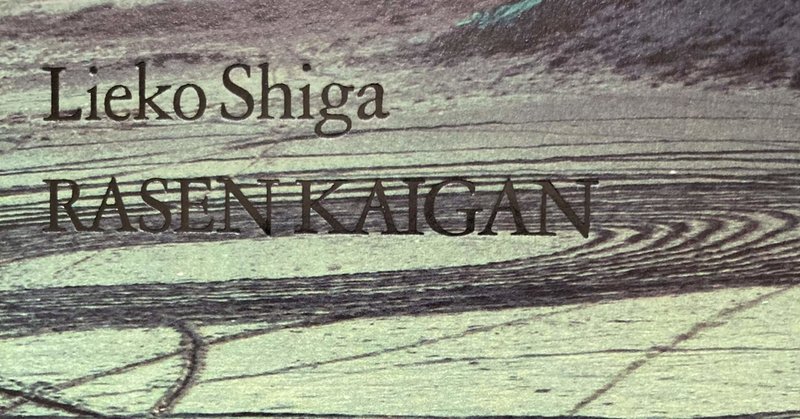
志賀理江子の芸術民俗学:岡本太郎と宮本常一を交錯させて
いま現在、最強のアーティスト、それは志賀理江子です。なんの躊躇もなく、そのように断言できるのは、せんだいメディアテークで開催中の個展「螺旋海岸」が、近年まれに見るほど衝撃的で圧倒的な展覧会だからです(現在は終了)。これほど同時代と共振し、わたしたちの心底に激しく訴えかけてくる展覧会は、少なくともここ数年見たことがありません。並みいる写真家の、いやアーティストの追随を許さないほど、今回の展覧会はずば抜けてすばらしい。
いささか大げさな言い方ではあります。けれども、そのように訝しむ人こそ、会場に一歩脚を踏み入れてみてください。そこに組み立てられた「写真の空間」を歩いてみれば、この評価があながち的外れではないことをたちまち了解するでしょう。きっと誰もが類まれな写真の強度に打ち震えるはずです。
展示されている写真は、じつに243点。それらがイーゼルのような大きな木枠に一枚ずつ貼付され、いずれも会場の中心を向きながら同心円状に設置されている。だから来場者は身の丈以上もある写真と写真のあいだを縫うように歩いて鑑賞することになります。
暗闇に浮かぶ幻想的な光景。そこには恐怖や悲哀、尊厳、反逆、そしてエロスが充溢しています。今回発表された写真のほとんどは、志賀さんがいまも暮らしている宮城県名取市の北釜で、地域の住民とともに撮影した構成写真です。構成というのは、それらがスナップ写真のように見えて、じつは入念な下準備と演出にもとづいているからです。一見すると撮影した後にデジタル技術で加工しているようですが、撮影する対象そのものに手を入れたり、その写真を再び撮影したりすることで、写真を「つくる」のが志賀さんの流儀です。
たとえば展覧会のタイトルにも用いられている《螺旋海岸》。大きな円と線が幾重にも描かれた北釜の砂浜が写されています。ランドアートのような壮大なスケール感がなんとも目覚ましい。よく見ると、砂浜を削り取った線の傍らには無数の足跡が残されていますから、このある種の「砂絵」は人力で描かれたことがわかります。
それから、ひときわ強い印象を与える《松》。暗闇の松林の中に寄り添って立つ老夫婦を写した写真ですが、なんと男性の胸の中心を木の幹が貫いている。しかも、根なのか分枝なのか、とにかく老夫婦をはるかに上回る大きさの木の塊が背中から突き出ていて、男性は胸元から飛び出た幹を両手でしっかりと支えているではありませんか。とても現実とは思えない光景ですが、赤い色調が非現実的で不穏な雰囲気を倍増させています。
志賀さんによれば、これもコンピューターで合成したわけではなく、じっさいにクレーンで木を吊り上げて撮影したそうです。たしかに木の塊の先にはロープのような直線がわずかに写り込んでいる。けれども画面全体がやや左に傾いているからでしょうか、第一印象はスナップ写真のような臨場感にあるので、これが入念にセットアップされた構成写真であることには、なかなか気づきません。
そのほかにも、会場の随所で展示されている白い岩石をクローズアップで写した写真は、石の表面に石灰を塗布したものですし、同じく頻出している穴を掘るシーンも志賀さんを含めた何人かでじっさいに穴を掘ったそうです。志賀さんの幻想的な写真は、現場を人為的に構成する並々ならぬ肉体性にもとづいているのです。
強烈なイメージがもたらすもの
志賀さんの写真の大きな特徴は、それらがつくられた構成写真であることを知ったとしても、見る者はそれでもなおそのイメージにひじょうに強いインパクトを受けることです。真紅の空に向かって何かを投擲する男や、砂浜に掘られた狭い路を自転車を押しながら歩く老婆の姿は、一度見たら決して忘れることができません。また、志賀さんの展覧会を見て以来、夜の公園で月明かりに照らされた樹木を見上げたとき、わたしはそこに志賀さんが写した白く光る樹木の写真が重なって見えることがよくあります。志賀さんがつくりだす鮮烈なイメージは、わたしたちの脳裏に深い傷跡を残すほど強烈なのです。
もうひとつの特徴は、その強力なヴィジュアル・イメージが、感情の大きな起伏を伴いながら、わたしたちに生と死の境界を垣間見せるような働きがあることです。会場を練り歩いていると、ふと死の世界に迷い込んでしまうような不安に駆られる瞬間があります。白い岩石の冷たい岩肌が「賽の河原」を連想させるからなのか、あるいは穴を掘る男たちがみずからの墓穴を準備しているように見えるからなのか、志賀さんの写真を見ていると写真の向こう側に広がる死の世界に引き込まれるような気がして、戦慄を覚えます。
見た目だけではありません。触ることのできない質感や、聴こえるはずのない声、そして感じることのない温度や湿度。それらを写真の奥に感知したような気がする。志賀さんの写真が衝撃的なのは、それらがグロテスクなイメージや心霊写真のような超自然現象をとらえているからではありません。むしろ全身の知覚がなかば暴力的に総動員されることで、わたしたちの想像力が死の世界に直面させられるからです。あの底なしの暗闇は、死の世界が開けた暗い口なのではないか。わずか一歩で踏み外してしまえば、向こう側に転落してしまうかもしれない。思わずそんな夢想をしてしまうほど、志賀さんの写真には此方と彼方の境界面が剥き出しになっているように感じられるのです。
こうした志賀さんの美しく謎めいた写真は、多くの論客によって語られ、また評価されてきました。
「志賀理江子の作品にわれわれが感じ取る危うさは、死の匂いそのものであり、同時に死を意識することによってしか存在しえない生の不確かさである」(田原寛)*1
「彼女にとって問題なのは、この死すべき肉体=現実を撃ち(shoot)、自ら撃たれ、写真という生へそれを捧げる行為、儀式そのものである」(竹内万里子)*2
「フランシス・ベーコンの油絵のような、完璧にコントロールされたダークネス」(都築響一)*3
「ブラックホールのような負の輝きを放つ」(藤原新也)*4
なかでもわたしがとくに注目したのが、写真評論家の飯沢耕太郎さんによる評論でした*5。飯沢さんは志賀さんの写真を「神話的想像力」という言葉で理解しています。
「志賀の作品世界では、生と死、エロスとタナトスがメビウスの輪のように不即不離のものとして結びつき、目も眩むような強烈な光を放ちながら、原色の、リアルな幻像として浮上してくる」
が、それは
「かけ離れたもの同士を互いに結びつけ、特殊なものに普遍性を付与し、偶然を必然化し、見えないものを感知していくような神話的な想像力」
の現われだというのです。
この見解にわたしは大いに共感しました。というのも、わたしが今回の「螺旋海岸」展を見て真っ先に思い至ったのが、志賀さんは写真と言葉によって新たな神話を物語ろうとしているのではないかということだったからです。より具体的に言い換えれば、志賀理江子の写真は岡本太郎と宮本常一の写真が交錯する地点に位置づけられるのではないでしょうか。芸術と民俗学が地重複する領域を切り開き、しかも写真の神話的想像力を岡本と宮本より一歩先に押し進めているという点が、志賀理江子を最強のアーティストであるという所以です。
「まちの写真屋さん」としての活動から
芸術家の岡本太郎と民俗学者の宮本常一には接点がありました*6。それは双方がともに日本各地の農村や漁村を渡り歩きながら写真を撮影していたことです。両者が共有していたのは、戦後の高度経済成長の陰で忘れられつつあった「裏日本」の暮らしを写真に焼きつけることで留めようとする焦燥感でした。芸術と民俗学という背景のちがいはあるにせよ、2人はともに同じ光景を見ようとしていました。
けれども、対象は同一ではあれ、その対象をいかに見るかという「まなざし」の点では、2人は明らかに異なっていました。全体的に見比べてみると、岡本の写真には動的な躍動感がみなぎっている反面、宮本のそれは深呼吸してからシャッターを押したかのような落ち着きが感じられます。大まかに言えば、岡本の写真が「表現」に重心を置いていたのにたいして、宮本のそれは「記録」に傾いていたのです。芸術写真と民俗写真の相違といってもいいでしょう。
構成と演出を信条とする志賀さんの写真を芸術写真として理解することはさほど難しいことではありません。けれども民俗写真となると、若干詳しい説明が必要となります。なぜなら記録を目的とする民俗写真にとって、構成と演出はその記録の客観的に信憑性を大きく損なってしまうからです。じっさい民俗学の創始者とされる柳田國男は、その研究方法を言葉や文字にあらかじめ限定しており、そもそも写真をさほど重視していませんでした*7。
しかし、志賀さんの写真は芸術写真でありながら、同時に民俗写真の要素をかなり色濃く含んでいると思われます。それは志賀さんが北釜の地域社会に「まちの写真屋さん」として溶け込んでいるからです。2008年、北釜の美しい松林にアトリエを建てる代わりに、志賀さんは専属カメラマンとして北釜の行事を撮影しはじめました。このあたりの経緯はとってもおもしろいのですが*8、ここで重要なのは志賀さんの記録のための写真を撮っているという事実です。しかも、その記録係をきっかけに、志賀さんは徐々に地域社会に馴染んでいき、やがてお茶飲みをしながら北釜の歴史や人びとの個人史を聞き取るようになる。これは、近年の美術史で注目を集めつつあるオーラル・ヒストリーの実践として考えられますが、むしろ民俗学に定着して久しい世間話研究のひとつというべきでしょう*9。
もちろん、こうしたことはあくまでも志賀さんの個人的な背景であって、写真作品そのものとは関係ないように見えるかもしれません。じっさい、その記録写真はとうぜん地域社会のものですから、基本的に公表されていません。しかし、お茶飲みで得られた歴史や物語をモチーフにして写真作品を制作することもあると言うように、その地域社会とのつながりがあってこそ、志賀さんの構成写真が成立していることもまた事実です。たとえば、幼少の頃、道に迷った帰り道をツツジの花を食べながら歩いたという初老の男性の記憶をもとに構成した写真があります。だから志賀さんの構成写真は、志賀さん自身が表現した写真であると同時に、北釜の人たちとの共同制作という一面もあるのです。
世間話を繰り返すことで得られた物語や歴史を写真に繰り込むこと。このような写真の撮り方は、岡本太郎ですらなしえなかったことです。一方、宮本常一はみずからの民俗学的研究を省みて、次のような暗示的な言葉を残しています。
長い調査旅行をふりかえって、私の調査なんか結結局あってもなくてもよかったようなもので、もっと創意のあるものでありたかったと、しみじみ思いまます*10。
日本全国をくまなく踏破した宮本にして言わしめた「創意のあるもの」。ここには、民俗学にたいする謙遜と自己批判が込められているのでしょう。しかし、あえて深読みすれば、宮本は従来の民俗写真に飽き足らず、創意のある写真、すなわち芸術写真に関心を向けていたと考えられなくもありません。だとすれば、志賀理江子の写真は、岡本太郎と宮本常一が実現できなかった芸術写真と民俗写真の構成──「芸術」にも「民俗」にもなりうる写真のありよう──を果たしているといえるのではないでしょうか。
新たな神話の再編成
ご存知のように、東日本大震災は太平洋沿岸に位置する北釜に壊滅的な被害をもたらしました。今回の展覧会で発表された写真には、震災後の北釜で撮影された写真も数多く含まれています。神話が現実の根拠や真実を物語る口頭伝承だとすれば、現実を根底から覆したこの震災は神話の再編成を余儀なくしました。そのとき、志賀理江子の写真は大きな力を発揮するはずです。なぜなら、その芸術にも民俗にもなりうる両棲類的な写真は、神にも庶民にも届く、ある種の強欲なイメージにほかならないからです。
志賀さんはとても興味深いエピソードを紹介しています。ある人は捨てるはずだった写真を風呂敷に包んで自宅の石藏に保管していたのですが、津波がすべてを流してしまった。ところが瓦礫の中からその写真を見つけると、みんな親切心から避難所にいる持ち主に届けてくる。もともと捨てるはずのものだったから改めてどこかに投棄しても、また誰かが発見して手元に帰ってくる。そんなやりとりが何度も続き、ついに持ち主は写真をビニール袋に入れて「これはゴミです」と書いて捨ててしまったという。新たな神話の萌芽はこうしたころにあるのではないでしょうか。
*1──田原寛「志賀理江子 死に向かう時間を止める祈り」『週刊ダイヤモンド』2008年5月17日号
*2──竹内万里子「写真という生に向かって」『美術手帖』2008年7月号
*3──「心の闇とらえた木村伊兵衛賞」『朝日新聞』2008年3月18日
*4──同前
*5──飯沢耕太郎『写真的思考』河出書房新社、2009年
*6──岡本太郎・深沢一郎・宮本常一「残酷ということ─『日本残酷物語』を中心に─」『民話』第18号、1960年
*7──菊池暁「柳田國男と民俗写真」『日本民俗学』224号、2000年11月
*8──12月に発行される展覧会カタログに掲載される予定。
*9──世間話研究会による論文誌『世間話研究』が1989年より発行されている。
*10──宮本常一「岩波写真文庫」『民間伝承』1954年4月号
初出:「美術手帖」2013年1月号
志賀理江子 螺旋海岸
会期:2012年11月7日〜2013年1月14日
会場:せんだいメディアテーク


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
