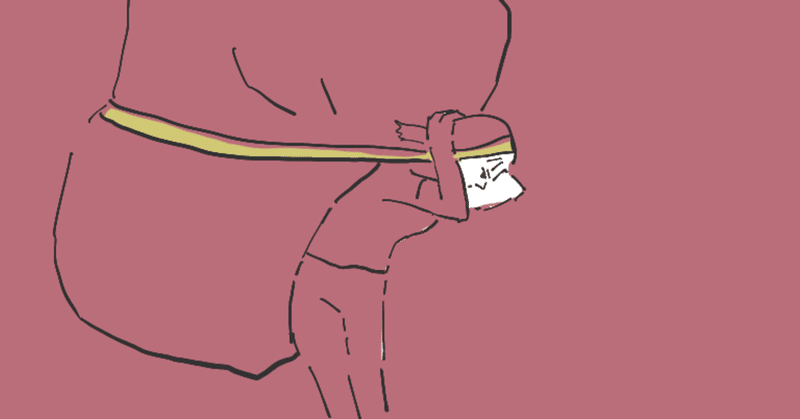
長い道のりは、小分けしたゴールを目指してすすむ。
「何もできてないんですよね」
「もっと頑張らなくちゃと思うんですけど…」
とても熱心にコトに向き合っている人からそんな言葉を聞くと、いやいや、ストイックすぎない?疲れちゃうよ?と思うことがあります。
「何もできてない」のはきっと、自分の目指している状態と現状を比べてギャップに感じるから。それが自分を奮い立たせるエネルギーになるのなら決して悪いことではない。ただ、あまりにそのギャップに打ちのめされ続けていると、自分自身が疲れてしまい、長い休息が必要になってしまうことも。
「自分は何もできていない」「得意も強みもない…」と不安や無力さを感じている人に人に対して「気楽にいこうよ〜〜」なんて気休めにしかならない。うーーーん、どうしたものかなあと思っていたところ、「小分けしたゴールを目指す」という考えに出会いました。なので今日は、長い道のりに息切れするくらいなら、小分けしたゴールで補給しながら進もうよ!という話を書いてみます。
あの電柱まで、歩こう。
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」というビジョンを掲げるマザーハウス代表の山口さん。
起業して間もなくの頃は、昼夜問わずどれだけがんばっても、「とてつもなく大きくて抽象的なビジョン」に対して、自分たちは「何もできていない。何も成長していない」と感じる時期があったそう。ただ、著書「Third Way 第3の道のつくり方」の中にこんな一節がありました。
私には大きなゴールしか見えていなかったのだが、そこにつながる道にはたくさんの交差点もあり、歩道橋もあり、右折左折もある。「小分けしたゴール」たちを道にきちんと散らばせよう。最初の交差点にはもしかしたらもう立っているかもしれないな。そう思えると、自分でもエネルギーが湧いてきた。つまり、経験から得た学びだ。小分けしたゴールは自分次第でいくつでも配置できる。最終ゴールまでの道のりが長すぎて息切れしそうなときには、まずは小分けしたゴールの一つ目に向かおう。
山口絵理子. Third Way 第3の道のつくり方 ※太字は著者注
(この本、ビジネスと社会性、経営と現場、個人と組織のような一見相反する者同士の"ジレンマ“に悩んでいる方、とってもおすすめです。揺さぶられる言葉がたくさんありました)
本を読みながら、小学校の頃を思い出しました。
山口さんのビジョン(ゴール)に対して「小学校時代の思い出」を事例に引っ張り出すのは気がひけるのだけど。小学校時代の僕にとって「学校に行く」ことが果てしなく遠く感じる時期があった。
「いってきま〜〜す」とだるい声で家を出たあと、下校時間の14時まで駐車場の影に隠れていたことも。空腹と暇な時間を耐えに耐え、「お腹もこれだけ空いたし、そろそろ昼過ぎだろう」と、あたかも小学校から帰ってきたかのように「ただいま〜!」と元気に玄関を開けたら11時。
それくらい、小学校までの1.5キロの道のりは遠かったのだけど、そんなとき学校へ向かう手助けになったのが、等間隔にある電柱でした。
「学校」はあまりに遠くて歩きだす気力がわいてこない。ただ、「あの電柱まで」だったら、なんとか頑張れる気がする。
30m先の電柱にたどり着いたらまた、次の電柱を目指す。...なんてことを繰り返して、気づくと学校の入り口にたっていました。
学校へ行くことは遠いゴールだったけど、あの電柱という小分けしたゴールがあったからこそ、心が折れずに学校に行くことができたんですね。(電柱が地中にある新興住宅地に住んでいたら、学校にいけてなかったかもしれない...)
小分けしたゴールが、前へ進むエネルギーに
「自分が目指すゴール」というと、どんなことが思い浮かぶでしょうか。
例えば、就職。
しばらく働いていない期間があれば、「就職」というゴールはとても感じるかもしれません。だったら小分けにしてみて、まずは「家から毎日出る」とか「求人を1日1つ見る」とか「1週間の短期バイトをしてみる」とか。
就職がゴールだと、「就職して働いていない自分」に目が向いてしまうけど、ゴールを小分けにすることで、「今日はここまでできた」「今月は◯日働くことができた」と、日々、何かしら前に進む実感を感じることができるんじゃないかと思うんです。
ゴールが遠すぎて、何をしても、進んでも進んでも近づかない。長い道のりに息切れをして、進むことを辞めてしまうと、再び動き始めるまでに止まるとき以上のエネルギーが必要です。(ダイエットや毎日の早起きも、中断したあとの再開って大変じゃないですか?)
だったら自分がご機嫌に進み続けられるように、小分けしたゴールを道のりに散りばめさせてみてはどうでしょうか。
自分に合った、前に進むための負荷
甘いかな?「人が前に進むには、ある程度の負荷が必要だ」という考えもあるかもしれません。
僕も負荷が嫌いなわけじゃない。だらしなく面倒くさがりな自分だから、負荷をかけてあげないと「とことんさぼってダメになるんじゃないか」という怖さがあります。
ただ、自分が耐えれる負荷を超えてしまうと、回復するまでに長い時間が必要なんじゃないか...という怖さもあります。
筋肉も、適切な負荷をかけることでよく育つように(過度な負荷は怪我の元。体の回復に時間がかかっちゃうんですね)、人が前に進むためにはその人にあった適切な負荷があると思うんです。
けれど難しいのは、自分で自分にあった負荷を判断すること。
猛烈元気に仕事をしていたある日突然、布団から出れなくなってしまう。
「この世でいちばん遠い場所は、自分の心」とは言ったもので、自分が耐えれるキャパの判断って難しい。
だから、よりよい体づくりにパーソナルトレーナーがいるように、「働くこと」においても自分を活かしながら前へ進むための伴走者とも言えるトレーナーがいてくれると安心だなと思う。
身近に信頼できる話せる人がいれば、定期的に話をしてみる。
ただ、もし身近にいなければ、何より身近な自分自身が、自分の声を聞く時間をつくること。僕は就寝前の2−3分、ストレッチをしながらちょっと静かな時間を取るようにしています。
なんやかんや就活も転職も事業もプライベートなあれこれも、長い道のりになることが多いもので。小分けしたゴールで補給をしながら、気楽にいきましょ!
(頼りない締め方になりましたけど、「働く人の心を整える技術(仮)」と題して仕事の不安やストレスとの付き合い方を考える機会をつくりたいな、と考えています。関心のある方いらしたらぜひご連絡ください!Twitter、Facebook)
いただいたサポートは書籍の購入代に充てさせていただきます!
