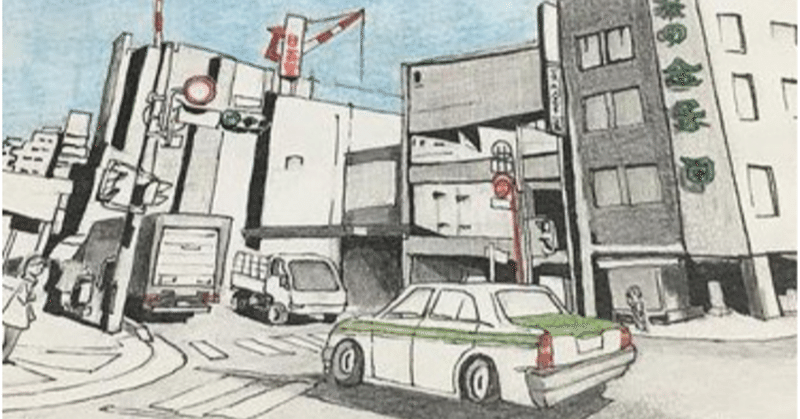
人口減少の今後を考える
12月14日の日経新聞で、「米中のGDP逆転せず ゼロコロナ余波、日経センター予測」というタイトルの記事が掲載されました。日経センターは毎年12月を目途に、直近の政策や経済情勢を織り込んだ最新の推計値を公表しているようですが、昨年までの予測から変わっているという内容です。
同記事の一部を抜粋してみます。
日本経済研究センターは14日、中国の名目国内総生産(GDP)が米国を逆転しないとの試算を発表した。昨年は2033年に逆転すると予測していた。新型コロナウイルスの封じ込めを狙うゼロコロナ政策の余波や、米国の対中輸出規制強化で中国の成長率が下振れするとした。長期的には人口減少による労働力不足も足かせとなる。
新型コロナの流行が始まった20年の予測では、中国が感染の早期封じ込めでいち早く経済の正常化に着手した結果、28年にも米中逆転が起こると推計した。21年の予測では中国政府によるIT(情報技術)規制の強化が技術革新を阻むと想定、逆転時期は33年にずれ込んだ。
22年の最新予測は、中国経済の成長率がさらに下振れする内容となった。30年代の実質成長率は3%を割り込み、35年は2.2%まで鈍る。米国(1.8%)とほぼ並び、21年に予測した値より0.8ポイント低い。名目GDPでみた経済規模は米国に少しずつ近づくが、35年時点でも米国の87%にとどまる。
中国経済が下振れする要因は主に2つある。1つは厳格な移動制限などを敷いたゼロコロナ政策だ。政府は7日に緩和策を発表したが、北京市などでは感染が広がっている。日経センターは海外との往来を含めて規制が事実上なくなるのは、25年に入ってからと想定した。
ゼロコロナ政策の後遺症もある。中国国家統計局が発表する消費者マインドを示す指数は、上海市のロックダウン(都市封鎖)で景気が悪化した4月に過去最低を記録。直近10月もほぼ同水準にとどまる。家計の節約志向は常態化しつつあり、先行き不安を拭うのは簡単ではない。
もう1つの要因は、米国の対中輸出規制の強化だ。日経センターは、この2つの要因が中国の生産性向上のペースを鈍らせると分析する。台湾有事の懸念が強まるリスクシナリオでは海外企業の「中国離れ」が加速し、対中投資の減少がさらに成長を下押しするという。
長期的には、人口減少が中国経済の足かせになる。国連の最新推計では、中国の総人口は22年7月1日時点で減少に転じた。生産性上昇の勢いが弱まることに労働力不足も加わり「36年以降も米中逆転は起きない」とした。
今後の経済成長に対して長期的に影響が大きい要素は、人口動態です。
先日の投稿「社員構成の未来を想定する」では、出生率の低下が短期的には経済成長を加速させることを取り上げました。子どもという、1から人材育成する投資が必要な対象者数が減ることで、子ども1人に対する集中的な投資がエリア全体で可能になります。そして、20代以上の実質的な労働力人口が全人口に占める比率が高くなることで、エリア全体の生産性が高まるためです。
しかし、やがて人口動態の年代別グラフがスライドしていき、少ない母数の子どもが20代以上を形成していって人口減少が加速するようになると、全体の成長が止まるというわけです。日本の80年代までの経済成長とその後の経済停滞の一因を、このことに求めることができると思います。
そして、中国でも今後同様のことが起こり得るのを、上記記事は示唆しているのだと言えます。加えて、同じことはほとんどのアジア諸国で当てはまります。
日本以上に少子化が進んでいる韓国や台湾をはじめ、ベトナム・タイなども少子化が進んでいます。「世界経済のネタ帳」によると、1980年代には3を超えていた合計特殊出生率も、2020年でベトナムは2.05、タイは1.50です。既に長期スパンで総人口維持に必要な値を下回っています。
これと同じことは、基本的にすべての国に当てはまることです。そのうえで、米国や欧州の場合、移民の受け入れが挙げられます。以前からその国に住んでいる人の間で少子化というアジアと同じ現象が起こっても、それを上回る労働力人口とその子どもが流入し、トータルで人口が緩やかに増え続けています。しかも、そうした人たちは貪欲で労働意欲も旺盛です。このことが、米国や欧州で経済成長を続けることができている大きな要因のひとつのはずです。
アジア諸国の場合、欧米ほどの移民受け入れのマインドやインフラが整っていません。これからどれだけそうした受け入れができていくのか、あるいは韓国や台湾のような、国家戦略として特定産業・分野を育てていくような取り組みを成功させることができるのかが、今後の持続的な発展の有無を分けるひとつの要因になると考えます。
いずれにしても、今後中長期的に、日本経済と同様の構造的な低迷がアジア諸国でも起こっていく可能性は、想定しておく必要があると思います。
<まとめ>
人口動態に根差した日本経済の発展→低迷の現象が、アジア諸国でも起こっていく可能性がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
