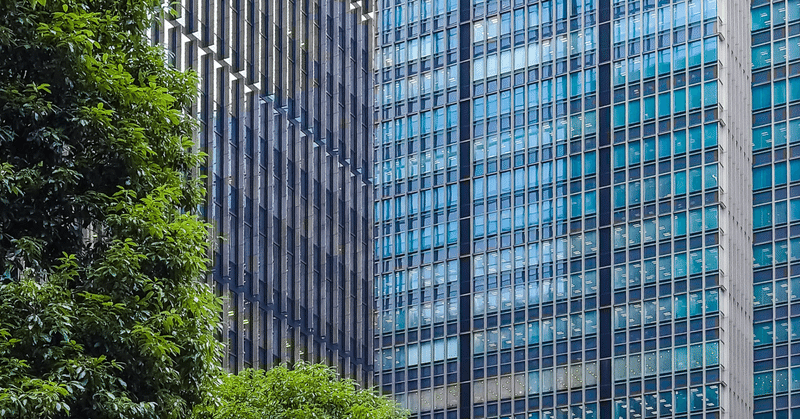
大幅賃上げの企業事例を考える
1月11日の日経新聞で、「ファストリ、国内人件費15%増へ 年収最大4割上げ」というタイトルの記事が掲載されました。同ニュースは各所で取り上げられ、インパクトも大きかったようで、周囲の経営者や人事部門役員の間でも話題になっています。
同記事の一部を抜粋してみます。
「ユニクロ」を運営するファーストリテイリングは3月から国内従業員の年収を最大4割引き上げる。パートやアルバイトの時給の引き上げも既に実施しており、国内の人件費は約15%増える見込み。
ファストリ本社やユニクロなどで働く国内約8400人を対象に、年収を数%から約40%引き上げる。新入社員の初任給は月25万5千円から30万円に、入社1~2年目で就任することが多い新人店長は29万円から39万円になる。
同社は2022年9月に国内でパートやアルバイトの時給を平均2割引き上げた。従業員では20年に一部の職種の初任給を引き上げていたが、2000年前後に現在の制度を導入して以降では全面的な賃金の引き上げは初めてとなる。
ファストリは能力や実績、成長意欲などに応じて約20段階のグレード(等級)に分けて基本給を決めている。3月に国内外でグレードごとの基本給と賞与に報酬を一本化する。従来、国内従業員については基本給とは別に、部長などの役職や勤務地に応じて手当を支給していたが、廃止する。
世界3位のアパレル企業であるファストリはグローバル企業として本社のある日本での人材育成を重視している。従業員の賃金制度を国内外でそろえることで、日本で採用し育てた人材を海外へ異動しやすくする狙いがある。海外採用の従業員も日本に赴任しやすくなる可能性もある。
東京商工リサーチによると、上場企業3213社の21年度の平均年間給与は605万円で、そのうち900万円以上は110社にとどまる。ファストリの国内で働く従業員平均給与は959万円と国内小売業でも最高水準にある。ただ、国内の総合商社や外資系企業などに比べ見劣りは否めない。海外企業の賃金と比較しても低水準にある。
日本企業の賃金は国際的に低い。人材コンサルティングの米マーサーによると、マネジャー級の年収は22年7~9月期の平均レートの1ドル=135円で算出した場合、日本は22年12月時点で9万6374ドルで前年比10%減った。米国(21万9976ドル)に比べ約半分の水準で、中国に比べても低い。
ファストリは22年8月期の連結売上高の半分を海外ユニクロ事業が占め、連結営業利益では国内ユニクロ事業を上回る。年収でも欧米などの海外従業員は既に国内を上回っているという。今回の国内従業員の年収の引き上げで世界の水準に近づける狙いもあるという。
「新入社員の初任給が月30万円、入社2年目で新人店長に就任すれば39万円」といった数値は、20代の新入社員の賃金イメージをガラッと変える内容と言えます。仕事・会社選びをする若手人材にとって、かなり魅力的に映る数字だと思います。
日本の賃金水準が国外の賃金水準に見劣りしているという状況は、以前から指摘されています。欧米圏に対しては、すべての層で日本の賃金水準が下回っています。東南アジア諸国に対しても、非管理職層の賃金であれば依然として日本がまだ上回っていますが、管理職層の賃金であれば国によっては既に現地企業の水準を下回っているような状況です。
このような状況では、国外の人材を日本に呼ぶことは難しさがあります。日本の人材を国外拠点に赴任させるにあたっては、現地水準に合わせて賃金上乗せするのはよいですが、日本に帰った時に日本の水準に合わせてまた下げるのかなどの問題が発生します。垣根をなくすことで、上記記事に見られるような人材戦略は進めやすくなります。
同記事から2つのことを感じました。ひとつは、今後企業の優勝劣敗が進むだろうということです。
同社は「情報製造小売業」を標榜し、仕入れ・製造から最終の店頭小売まですべて自社でコントロールできる強みがあります。よって、商品・サービスの価格や事業プロセスの経費など、上げた賃金をカバーできる様々な取り組みが自社内で可能です。例えば、小売は小売でも、自社で製造していないビジネスモデルの企業であれば、人件費増の対応でできることが限られてきます。
今後、同社のような動きをとっていく企業も増えてくることが予想されます。
賃金相場が上がっていく中で、自社のビジネスモデルでできることは何か。それを定義して取り組まないと、労働市場の変化に対応できなくなっていきそうです。
2つ目は、従業員により多くのことが求められるだろうということです。
賃金が上がる分、当然ながら、一人あたりの生産性向上が求められます。ユニクロ店舗での自動レジ化などもすでに進んでいます。シンプルに、今までと同じ規模の業務を今までより少ない人で行い、人材はその業務の統括や企画など、求められる機能の種類が変わっていくことになります。
国内外の区分がなくなるということは、その発揮度合いを国外の人材とも本格的に競うということになります。
賃上げが社会的な課題テーマになっています。そして、実際に賃上げが実現していくなら、それと同時に各人材が自身の付加価値を高めていくことも課題テーマになる。そして、その動きが加速していきそう。同ニュースからは、そのように感じた次第です。
<まとめ>
賃上げと同時に、各人材の付加価値向上も一層課題テーマになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
