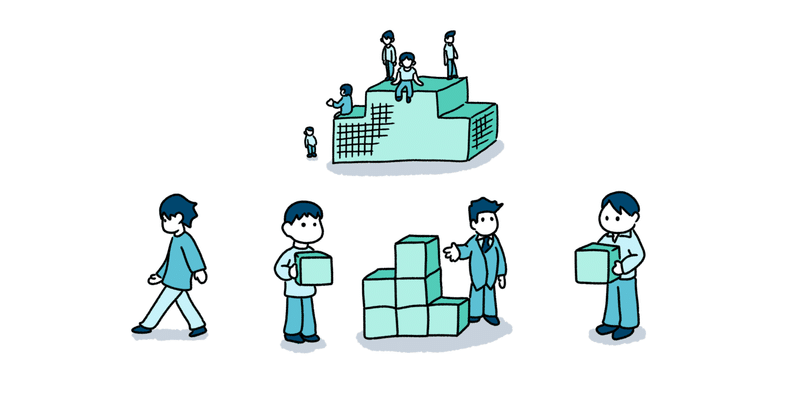
賃金上昇と生産性向上
2月17日の日経新聞で、「イノベーション 起こすには(中) 賃金上昇・安価な新技術カギ」という記事が掲載されました。日本の生産性が諸外国より低いこと、それに関連して賃金上昇幅が抑えられてきたことが各所で言われていますが、そのことについて示唆的な考察を加えている内容です。
同記事の一部を抜粋してみます。
2017年の労働1時間当たり付加価値を日米間で比較した滝澤美帆・学習院大教授の推計によると、日本の産業の生産性が全般的に米国より低いわけではなく、化学工業では日本の生産性が米国の1.28倍となっている。
一方、卸売り・小売り(0.32倍)、不動産(0.27倍)など、サービス産業に相対的な生産性が著しく低い産業が多く、しかもそれら産業の付加価値ウエートが大きいため、日本全体の米国に対する相対的な生産性を押し下げている。
さらにこうした産業には中小企業のシェアが高いという特徴がある。16年の「経済センサス」によると、従業員30人未満の事業所の従業員数シェアは全産業48.8%、製造業30.3%に対し、卸売・小売業では61.9%、不動産業では60.3%だ。生産性引き上げには、それを構成する中小企業の生産性が上昇する、あるいはそこから資源が生産性の高い産業・企業に移動することが必要とされる。
例えば米国と比較した場合、産業全体として日本の生産性のほうが低いとしても、個別に見ていくと化学工業など日本のほうが生産性が高い業種も一部あるというわけです。
私たちは、「日本の生産性が低い」と聞くと、そのことをすべての環境や現場に適用させてモノを見ようとしますが、個別に是々非々でとらえるべきだということを改めて感じさせます。課題の本丸は、生産性向上の余地が大きい規模の事業所・業種にあるというわけです。
手がかりは経済史の中に見いだせる。多数の中小規模生産者に技術革新が普及して生産性が上昇した事例として20世紀初めの日本の織物業がある。当時、織物業は日本の主要産業の一つだったが、紡績会社が兼営する織物工場を別にすれば、多数の小規模工場と、問屋により組織された零細な家内工業で構成されていた。そうした状況下で20世紀初めに小規模工場に動力で駆動する織機(力織機)が急速に普及した。力織機は単純な製品を生産する工場で特に急速に普及し、その典型は福井県の羽二重工場だった。
1905年には力織機を使用する羽二重工場は福井県に存在しなかったが、1914年にはほぼ全工場が使用するまでになった。力織機の生産性効果は大きかった。1905~14年の工場別データを用いた筆者の推定では、力織機工場の労働者1人当たり生産量は、労働時間の差をコントロールしたうえで、非力織機工場の約2.6倍に達した。
この技術革新の急速な普及はいくつかの要因で生じた。第1は新技術の採用が容易になったことだ。国産の力織機の開発で価格が低下し、また電力ネットワークの拡大により動力へのアクセスが可能になった。
第2は賃金の上昇だ。実際、福井県では賃金が上昇しており、その中で採用が容易になった労働節約技術への切り替えが進展したとみられる。加えて強調したい点は、技術変化が一層の賃金上昇を引き起こすという因果関係の方向もあったことだ。
力織機の導入が与えたインパクトを統計的に分析すると、導入の年から賃金が有意に上昇したことがわかる。力織機の導入による労働の限界生産性上昇を反映した動きと解釈できる。賃金上昇と新技術へのアクセス改善が新技術の普及をもたらし、それがさらに賃金の上昇を引き起こすという循環だ。
1968年版「中小企業白書」は、中小企業の設備投資が66年以降活発化したことを指摘したうえで、その動機の一つとして「労働力不足などの環境変化に対処するため、合理化、近代化への投資意欲が根強いこと」を挙げている。
これらの歴史的経験から日本経済が直面する問題に重要な示唆を引き出せる。事例には、多数の小規模生産者の生産性上昇を引き起こす2つのドライバー(動因)が共通している。
第1に賃金上昇、第2に低価格での新技術へのアクセスだ。日本経済の現状をみると、前者については労働力の減少がその条件を与える。人口減少と高齢化による労働力不足は賃金上昇を通じて、逆に日本経済復活のテコとなり得る。
後者についても人工知能(AI)やロボットなどの汎用技術の発達により、潜在的に条件が準備されつつある。新しい汎用技術を応用して低価格で使いやすい労働節約的技術が開発されれば、第1の条件と相まって小規模事業者に普及して生産性を引き上げ、さらにそれが20世紀初めの力織機の事例にあったように一層の賃金上昇をもたらして、日本経済は長年の低賃金と低生産性の罠(わな)から脱却できる可能性がある。
上記からは、かつて工業を営む中小企業で生産性が低いという問題テーマが存在したこと。賃金上昇=コスト増の動きが加速する中で生産性向上を迫られ、必要投資を行うことで生産性を改善し飛躍していったことがうかがえます。そして、そのことが現在同様の問題を抱える、サービス産業を営む中小企業でも当てはまることを説明しています。
上記はサービス産業に限らないと考えます。私も普段さまざまな企業の現場に行ったり話を聞いたりする機会がありますが、工業系の現場においてもまだまだ生産性向上の余地はあると感じます。
人手不足の採用難の折に賃上げの社会的要請も高まり、どの企業も難しいかじ取りを迫られていることと思います。そのうえで、今は生産性向上に特に向き合うべき時期=発明に必要な母だと捉えようというわけです。アクセスしやすくなった新技術への必要投資を行って今の局面を乗り越えることができれば、生産性にあふれた職場環境が見えてくるのではないかと、同記事は示唆しているように感じます。突破口を見出して取り組めば光が差してくる。そう思えば、力も出てくる気がします。
同時に、投資を必要としないレベルでの効率化も一層必要です。お客様に提供しているサービスの中で付加価値を伴わない過剰なもの(お客さまがそこまで求めていなかったり、価格に反映されなかったりする)、お客さまへの提供とは直接関係ない内部活動で時間をかけているものなどについては、圧縮するかやめることができないか取り組んでみることも大切です。
<まとめ>
賃金上昇、低価格で新技術へのアクセスが可能になる今の環境は、生産性向上の絶好の機会である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
