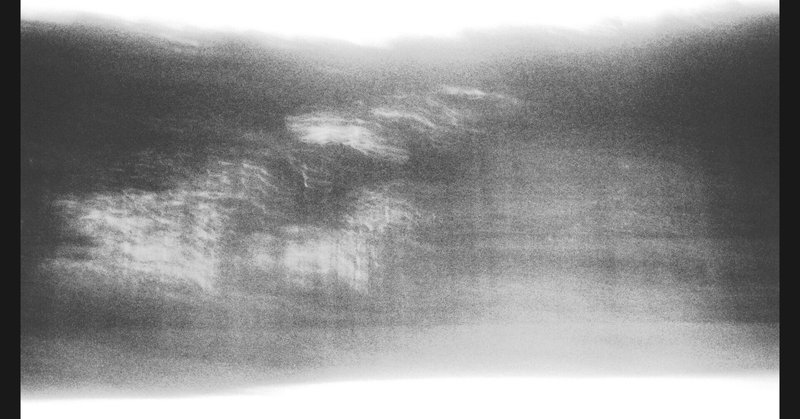
【小説】ドーナツ・ショップ
うまく説明はできないのだけれど、耳に入るだけでそれはクリスマスソングだとわかった。
英語も、楽器も、音楽のことも私はよく知らない。それでも。
おそらくは、12月の街で聞こえた音楽の記憶で判断しているだけなのだろうと思う。
私はコートのポケットに手を入れたまま、連絡通路の壁にもたれかかった。
それはあの日と同じコートだった。
クリスマスソングは今でもまだ好きになれずにいる。
ガラスの向こうでは、雪が降り始めていた。
それはあの日と同じような雪だった。
何年か前のある朝、私は学校を休んだ。
なにか理由があったわけではない。
学校に向かっている途中で気が変わっただけだ。
誰かを困らせたかったわけでもないし、反抗したかったわけでもない。
ただなんとなく、学校よりもまともな場所に居たくなっただけだ。
制服のままであることがすこし気になったけれど、丈の長いウールのコートは制服をうまく隠してくれた。
ドーナツショップの窓は白く曇っていた。
私はそこになにかを描くわけでもなく、つまらない窓を眺めていた。
華やかに浮かれた店内から目をそらすためにはそうするしかなかった。
「ヘイ彼女」と彼女は言った。
ヘイ彼女なんて言葉を現実で耳にすると思っていなかった私は、すぐに反応することができなかった。
一拍ののちに振り向くと、背の高い女性が椅子に座ったまま私を見ていた。
「ごめんね、こわくないよ」と彼女は言った。
私はなにも答えなかった。
もしも補導されるのだとしたら、なんと答えるのが正しいのだろう。
「ずっと窓見てるから、ヒマなのかなと思って」
「あ、大丈夫です」と私は答えた。
なにが大丈夫なのだろう。
「コート、暑くない?」と彼女は言った。
制服を隠すために、私はコートを着続けていた。
もちろん店内は十分に暖房が効いていた。
「大丈夫です」と私は言った。
私は汗をかいていた。大丈夫ではなかった。
「補導されると思ったんだ」と彼女は笑った。
「なんとなく」
「警察に見える?」
「ぜんぜん」と言ったあとで、私はそれが失礼な返事である可能性についてすこし考えた。
たぶん大丈夫だろう、と私は思った。
金髪の警官なんていないような気がしたからだ。
「あたしといれば、制服でも怪しまれないんじゃない?」
私は曖昧に頷いた。しかし、コートを脱ぎたいのは確かだった。
「あの、私はなにかを買わされたりするんでしょうか」と、私はコートを椅子の背にかけたあとで聞いてみた。
「どゆこと?」
「幸運のなにか的な」
「幸運になりたいの?」
「いえ、間に合ってると思います」
「それはなにより」と彼女は言った。
彼女は仕事を辞めたばかりだった。
なにか理由があったわけではない、と彼女はタバコを指に挟んだまま私に話した。
禁煙席なので火は点いていなかった。癖なのだろうな、と私は思った。
「ただなんとなく仕事を辞めて、ただなんとなくコーヒーを飲みに来て、ただなんとなく話しかけちゃった」
「すごいですね」と私は言った。
自分も似たようなことをしていることはすっかり忘れていた。
「すごいはちょっと意味わかんないけど、なにやってんだろとは思う」
「そんな大人もいるんだなって」
「大人なんかじゃないよ」と彼女は笑ったけれど、すこし悲しそうにも見えた。
私はそれについてなにも言わなかった。
店内には例に漏れずクリスマスソングが流れていた。
彼女はそのワンフレーズを鼻歌で歌った。
「ちゃんと聴いたことなんてないのに歌えちゃうよね」と彼女が言った。
「いっぱい流れてますもんね」と私は答えた。
「好き?」
「苦手なんです」
「この曲が?」
「というか、クリスマスソングが」
「そうなんだ」
「だから、それが聞こえる季節のことも、街のことも、連鎖するみたいに好きになれなくて」
「いや、でも、ちょっとわかるよ」
「よかった」
「というか、考えたことがなかっただけで、あたしもほんとは好きじゃないのかもしれない」
「そっか」
「どうして嫌いになったのかは、聞いてもいい?」
「家庭の事情です」と私は言った。
家庭の事情でしかなかった。
それ以上でもそれ以下でもない。
「わかった」と彼女は言った。
私は彼女としばらく話した。
彼女は重要そうな話はなにもしなかった。
ありがたい言葉も、格言も、説教もない。
学校を休んだ理由も、手首の傷のことも聞いてこなかった。
私はそんな大人に会うのははじめてだった。
「もしさ」と彼女が言った。
「もしこの先あたしのことを思い出すことがあったら、今この店内にイヤというほど流れてるクリスマスソングとセットで思い出しちゃうのかな」
「もしかしたら」
「苦手なクリスマスソングと一緒に」
私はすこし考え込んだ。
なぜだかそれは違う気がした。
「それはたぶん大丈夫です」と私は言ってみた。
声に出してみると、それは本当のように思えた。
「クリスマスソングは好きになれないかもしれないけど、たぶん大丈夫です」
私は今でもときどきあの日のドーナツショップを思い出す。
曇った窓とコーヒーの匂いを思い出す。
すこしだけ世界を好きになれそうな気がしたことを思い出す。
連絡通路の向こうから彼女が来るのが見えた。
私はまだ見つけていないふりをするために、ちいさな音で口笛を吹いた。
こともあろうに、それはクリスマスソングだった。
私は俯いてちいさく笑った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
