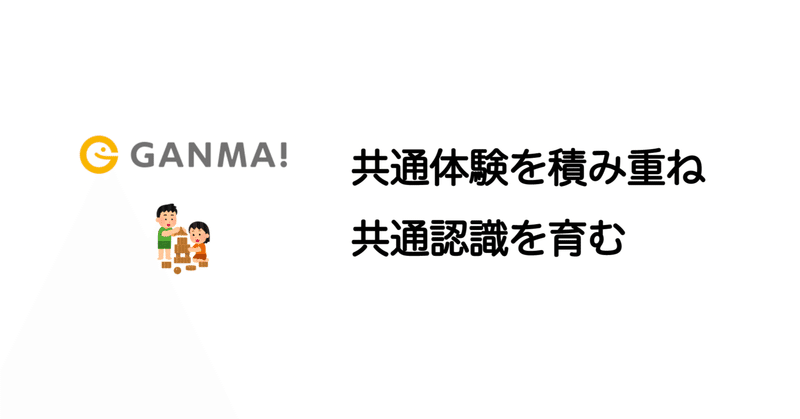
一人のユーザー行動を観察することで得られる発見と共通認識(体験)の偉大さ
GANMA!(ガンマ)というマンガアプリを運営しています、コミックスマート株式会社の福西(ふくにし)です。昨年に続き今年もお声がけいただき「モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2021」の9日目を書かせていただきます。貴重な機会をありがとうございますmm
今回は「やっぱりいいなユーザー行動観察」と「それがもたらす共通認識」について、詳しく紹介させていただきます。
最初に、ここで言う共通認識について少々…
「共通認識とは何か?」といったすごい定義をしたいわけでなく、例え話を少々。
Gさん「辛いラーメン食べにいこうよ!」
Rさん「いいね。どれくらい辛いの?」
Gさん「そんなに辛くないよ、中辛だね。」
Rさん「中辛ってどれくらいよ?」
Gさん「うーん…3辛」
不安の残る会話ですね。Gさんが辛いもの好きで、Rさんがそうでもなかった場合、悲劇が起こりそうです。

Gさんがこう答えていたらどうでしょう。
Rさん「いいね。どれくらい辛いの?」
Gさん「この前一緒に食べた麻婆豆腐と同じくらいだよ」
前者の会話になくて、後者の会話にあるものはなんでしょう。
それは、「共通体験(たいけん)」です。
共通認識があることによってコミュニケーションが円滑になる。認識の相違によって痛い目をみる(などなど)。ここに疑う余地はありませんので説明を省きます。
共通認識は、「知識」や「情報」だけではなく「共通体験(たいけん)」があることによって、ものすごく作りやすくなります。
やっぱりいいな、ユーザー行動観察
N1ユーザーの行動を一緒に観察しよう
前回のアドベントカレンダーでも少し触れていた「ユーザー行動観察」を、改めて強くおすすめします。
GANMA!チームがユーザー行動観察を習慣化しはじめたきっかけは、こちらの本でした。
「一人の分析」をユーザーインタビューから始めたわけですが、うまく本音を聞き出せない…、インタビュー相手を確保できなくなっていく…、といったよくある課題にぶつかっていきました。
それでも、定量的な集計結果では見えにくくなっていた「一人」を認識できるようになり、そこにある行動という事実から得られる気づきがとてつもなく大きなものであることを身に沁みて感じることができました。
うーんうーんうーん…と四苦八苦しているとき。
データアナリスト「Googleアナリティクスのユーザーエクスプローラで、擬似的なN1分析できそうですよね」
できました(拍手)!
掻い摘んでになりますが、GANMA!の実データを交えながら「一人のユーザー行動を観察することで得られる発見」の一例を紹介します。
ケース:ある日の新規ユーザーの行動を観察してみる
Googleアナリティクスで「新規ユーザー(デフォルト)」セグメントを選び、「ユーザーエクスプローラ」でIDをクリックして行動をみていくだけです。
Googleのデータポリシーに則っていますので、性別や年齢などのパーソナルな情報は取得できません。あくまでユーザーの行動になります。
どこからGANMA!アプリに来てくれたのか

このケースでは、GANMA!のブラウザ版からアプリストア(AppStore)に遷移しインストールしています。GANMA!ではAdjustのキャンペーン情報と紐付けています。(メディアやキャンペーンを計測できないメディアも多々あります)
インストール後にマンガを手に取り、読み始めるまでの行動は

アプリインストールし初回起動した後、Adjustの「ディファードディープリンク」が機能し、『七瀬さんの恋が異常』というマンガの作品トップへ自動遷移していることがわかります。その後、第1話へ遷移していますがすぐに作品トップへ戻り、第2話へ入り直しています。これが観察から得られる行動の事実です。
仮説としては、ブラウザ版で第1話を読んでから、ブラウザ版より読みやすい環境を求めてアプリをインストールしているため、第1話は閲覧済みだったのでは?となります。
どのようにマンガを読み進めているか

第2話から第3話へ遷移するときには、もっと短い遷移で簡単に移動できるのですが、このユーザーは一度作品トップに戻り、次の話を選択しています。直進すればたどり着けるのに迂回している状態です。
集計されたデータではこのケースは見過ごされがちです。検知できたとしても、集計されたデータでは事実の解像度がなかなか上がりません。イメージが弱いと、発見や気付きも限られ、改善に向けた行動が誘発されにくくなります。
「困っている人がいるようだ」を知ることと、「困っている姿を自分で目にする」ということには、得られる発見に大きな違いがあるのです。

一人の行動をスマホ片手に真似してみると「なるほど、この画面のこの表現がわかりにくいのか」と現場検証も可能です。刑事ドラマなどを思い出してください。ほぼ必ず現場検証から犯人特定に至りますよね(笑)。
マンガの閲覧に繋がっていない行動を考察する

このユーザー行動は、すでに最新話まで読んでいるマンガをランキングで目にし、タップして遷移しているのですがマンガ閲覧には繋がっていませんでした。なぜなら最新話はまだ配信されていないからです。「次の更新いつだっけ?(チェック)」「最新話配信されているかな?(期待)」があったのではないかと推測できます。
こういった行動が存在することを認識することで、更新通知を受け取ってもらう、配信中のものを読み返してもらう、他のマンガをレコメンドする、などの施策を考えるきっかけに繋がっています。
いろんなユーザーを、たくさん観察する
Googleアナリティクスの「ユーザーエクスプローラ」の良いところは、いろんなシチュエーションのユーザーを簡単に観察できることです。その利点を活かしてとにかくいろんなユーザーを観察し続けています。
インストールしたけどマンガを読まずに離脱したユーザー
初日にプレミアムプランを購入しているユーザー
プレミアムプランを解約したユーザー
平日ユーザーと休日ユーザーの違い
セッション回数が少ないユーザー・多いユーザー様々なので、一人のデータを観察する時間はそれなりに掛かります。地味で、手間です。(でも発見の宝庫なので絶対にやるべきで、続けるべきです。)
一方、「ユーザーエクスプローラ」の課題はというと、インタビューではないので「why(なぜ)?」を深ぼってヒアリングすることができません。だからこそ、類似シチュエーションのユーザーをたくさん観察しています。行動パターンの統計をしたいわけではなく、回数を重ねることで人の行動とプロダクトの課題が立体的に見えてくるようになります。
サービスのグロース・改善に取り組む上で、データ集計して全体を俯瞰し、課題発見をすることは皆さん必ずやっているかと。しかし、一人の行動を追いかけて観察し、その行動を真似してみながら現場検証するということは、割と後回しにされてしまいます。どちらもやることで、集計されたデータの見え方も大きく変わっていきます。
みんなで一緒に観察しよう = 共通体験をしよう
上記のユーザー行動観察を、GANMA!では毎週チームで取り組んでいます。
「今週はあなたとあなたね」というように毎週担当を決め、定例ミーティングまでに観察結果の行動サマリーをまとめ発表してもらいます。その上でみんなで「ここはGOODだね」「ここはMOTTO(もっとよくできる)だね」「こんな機能や施策があるとよさそうだね」「こんなユーザーもいるんだね」とディスカッションします。

「一人の行動」をみんなで観察・現場検証し、ディスカッションすることの良いところは、
伝言ゲームをしないので事実が間違って伝わらない
お互いが同じシーンをイメージするまでの時間が圧倒的に早い
行動を想像で語ることがなくなる
の大きく3点あると考えており、「行動を想像で語ることがなくなる」がとても重要だと感じています。
行動に含まれる事実
・When(いつ) : ◯月◯日(土) AM 00時25分 に
・Where(どこで) : 作品トップページ で
・Who(だれが) : △△経由でアプリインストールした人が
・What(何を) : 第2話を
・How(どのように): 最短距離ではなく迂回して
『新機能をリリースしたが期待した利用率に達していない』といった漠然とした課題に対して、これらの行動に含まれる事実を想像で語ってしまうケースはないでしょうか?「ワタシ ハ コウオモウ」「ボク ハ コウオモウ」と…。
本来であればWhy(なぜ)を追求しなければいけないのですが、ついつい目の前にある統計データそのものを「こんな人だろう」という大きな括りにした議論をしてしまいがちです。あくまでも一人一人の集合体であって、集合体という人ではありません。
15歳のAさん
16歳のBさん
34歳のCさん
35歳のDさん
平均年齢 → 25歳
極端な例ですが、25歳という誰かを想像してしまいませんか?
ここを出発点にした議論がたどり着くのは、ユーザーとサービスにとって悲しい結果になりそうですよね(涙)
「大学院生かもしれない」「もしくは新社会人が多そうだ」「じゃあこんなデザインにしよう」などなど…
『新機能をリリースしたが期待した利用率に達していない』という話題に戻して考えるのであれば、利用したユーザーと利用していないユーザーを2人ずつ抽出し、みんなで一緒に行動を観察することで「行動を想像で語る」ということが減っていきます。そして、お互いの中に同じ事実がインプットされるので、共通認識が育まれていきます。

共通認識は、覚えるものではなく育むものなのだと最近感じています。そのためには共通体験(一緒にユーザー行動を観察する)を積み重ねることはとてもよい方法であったと、結果的にではありますが行き着くことができました。
サービスのグロースやマネタイズを担当する基本メンバーに加え、プロモーション担当・エンジニアなども一緒に観察する機会を設けたりしています。
Googleアナリティクスの「ユーザーエクスプローラ」はあくまでもテキストデータになるのでユーザー行動のイメージを一致させるために、各々が事前観察してくるだけでなく、その場でzoomの画面共有をしながらユーザー観察を行うことも定期的に取り入れています。まずはこちらをおすすめします。(開発チームが行っているペアプロ・モブプロを真似しました)
おわりに

ご一読いただきありがとうございます!ここまで書き終えると、冒頭の辛いラーメンの下りは必要だったのだろうかと、自分でも首をかしげるわけですがかわいい「いらすとや」に免じて残させてくださいませ。
「モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2021」に参加のみなさまが、それぞれ示唆に富んだ事例を紹介されています。併せて読んでいただくことで、各社の事業・サービスにとってより良い発見があること間違いなしです。社内メンバーや関係者にシェアしていただき、取り入れられる試みがあればぜひトライしてみてくださいませ。私自身もたくさん参考にさせていただきますmm
