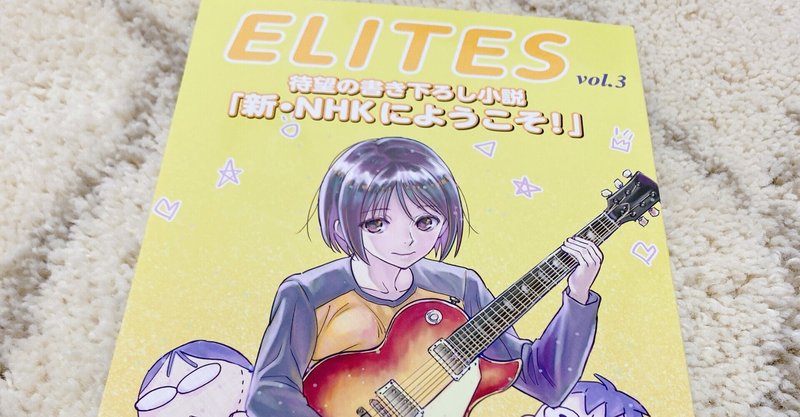
【文フリ感想①】『ELITES vol.3』『奇書が読みたいアライさんのソローキン全作紹介SP』『二人の獣 ~美しい口許~』
第三十二回文学フリマ東京で購入した本の感想を書いていきます。
まずは新刊の三冊。
・『ELITES vol.3』(エリーツ)
・『奇書が読みたいアライさんのソローキン全作紹介SP』
・『二人の獣 ~美しい口許~』(妄人社 乃木口正さん)
■『ELITES vol.3』(エリーツ)

小説家・文筆家の方々により結成されたバンド・エリーツの雑誌。
著名人の先生方のサークルだけあって、今回の文フリ東京で最も賑わっていた(お客さんが並んでいた)ブースだったと思います。
さて中身ですが、一番の売りは書き下ろし小説『新・NHKにようこそ!』。
『NHKにようこそ!』作者、滝本竜彦先生の完全新作です。
あとはエリーツの初ライブルポ、メンバーの方々のエッセイ等が収録されています。
・まず『新・NHKにようこそ!』ですが、一言で言うと「とても秀逸な作品」でした。
原作時から二十年が経っており、否が応でも「その時間的なズレをどうするか」「今書く意味とは?」という点が問われる訳ですが、
そこについて、言い訳でもファンタジーでもなく、奇妙な不安感を読者に持たせつつ、「ちょっとした行動で世界を選択できる(のか?)」という『NHK』らしいテーマを掲げることで返答している点が素晴らしく感じました。
また物語論的に言えば、最後は佐藤が〇〇〇〇〇に〇〇ことで「何か」が変わるべきなんでしょうが、敢えてそれをしないのは、流石佐藤、流石『NHK』だと思います。
そして、「〇〇なくても小説を終えられる、いやむしろ〇〇ないからこそ終えられる」という滝本先生の決断は、『NHK』の世界を信じているからこそ出来ることだと思うのです。
それほどまでに『NHK』の世界は強固であり、だからこそ佐藤達はいつまでもそこに居るのでしょう。
とっくに成人した僕にとって、『NHK』を読んでいた怠惰な学生時代は「大昔に消え去った世界」だったのですが、こうした小説や、楽しそうにバンドをしているエリーツのメンバーを見ると、「もしかしたら、まだ何処かにあるのかも」と夢見ていいような気持ちになります。
勿論それは(僕にとっては)夢で、月曜からまた辛く苦しい労働が待っている訳ですが、それでも佐藤達が今もどこかで「青春」をしているという事実は、ほんの慰めにはなるかと思うのです。
・作品外のことですが、学生時代から傾倒している佐藤友哉先生にお会いできて感激しました。ですが緊張しすぎて、声をかけるどころか目も合わせられずじまいでした。
・同じく憧れのPhaさんにもお会いできて嬉しかったです。Phaさんの日記(曖昧日記)をいつも拝見しているのですが、本当に僕の一番理想の生活だと感じています。
※ただ、僕には会社を辞める度胸はなく、普通に暮らしています……。
『曖昧日記』(紙)も購入しましたので、拝見いたします。
■『奇書が読みたいアライさんのソローキン全作紹介SP』(奇書が読みたいアライさん)

Twitterで大人気、「奇書が読みたいアライさん」の本。
勿論フォローさせて頂いていて、お会いできて大変光栄でした。夫婦揃ってアライさんのファンです。
今回買った本はnoteでも公開しているようです↓
内容ですが、何よりもまずソローキンのあらすじがぶっ飛んでいて、吹き出してしまいます(詳細は読んでみて下さい)。
とはいえ、時空や思想や倫理観がぶっ飛んだプロットの中にも、ロシア文学らしい母国愛(大地に対する愛)が色濃く反映されているように感じます。最果てにはいるものの、ソローキンも古典ロシア文学を軸に歩き始めた文学者の一人なのだと感じました。ソローキン一冊も読んでませんが。
この『ソローキン全作紹介SP』のポイントは、こうした奇書を「頭おかしい」などと茶化して笑いものにするのではなく、愛をもって真摯に薦めているアライさんの態度にあります。
「〇〇な人には、この作品から入るのがおすすめ!」等とも書いてあり、「少しでも一人の読者がソローキンを手に取りますように」という祈りが込められた、優しい紹介本です。
(Twitter読んでてもそこが心地いいです)
僕は最初から『青い脂』から行ってみようかな……と思っています。読んだらまたご報告します。
■『二人の獣 ~美しい口許~』(妄人社 乃木口正さん)
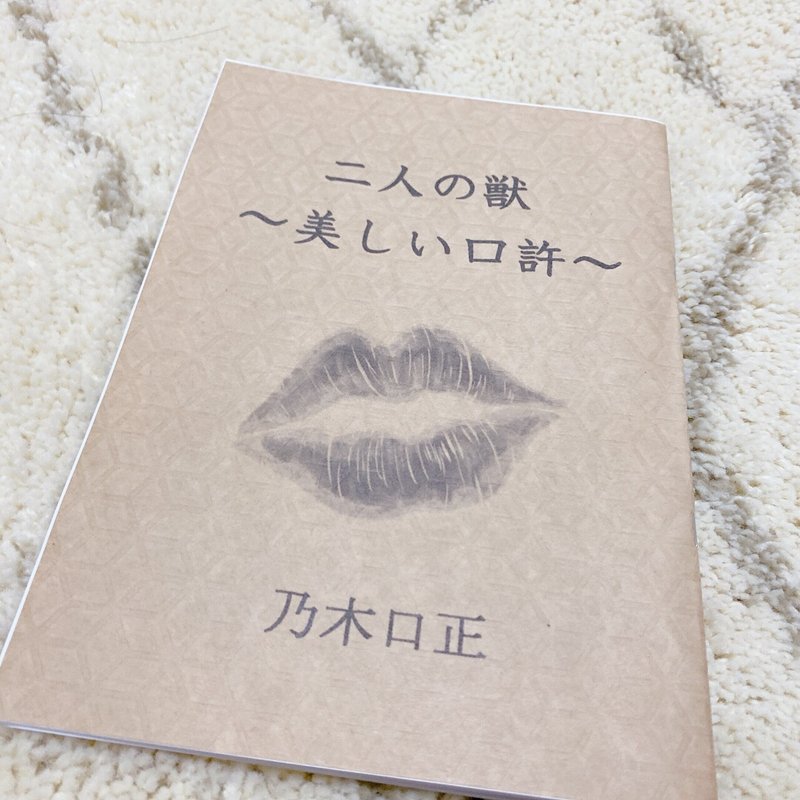
文フリ ミステリの常連、乃木口正さんの新刊です。
今回もドキっとするような表紙ですね。この口許、イラストですよね……?
内容は、血で塗れたナイフを持つ女性が、誘われるように不思議なバーに辿り着くところから始まる短篇ミステリ。
まず、しっかりと謎解き(かなり変則的なフーダニット)になっている点は流石。嬉しいです。
話の始まり方も、「何故だがナイフを持っている、誰を殺したのか覚えていない」という珍しい+キャッチーな展開で、これぞ、という感じがしました。
(以下、ネタバレにならないと思いますが、まっさらな状態で読みたい人は飛ばしてください)
謎解きの1つは、この時代ならではの答えとなっており、素直に「なるほど!」と思いました。
作者はおそらく普段の生活の中で気付かれたのだと思いますが、そういう気付きをきちんと覚えていて作品に反映させられるのは素敵なことだと思います。
近年、某ミステリ新人賞受賞作も「youtuberをトリックに用いる新しさ」を褒められていましたし、言われてみれば、時代性をまとったミステリって意外と無いのかもしれません。
(単に今のミステリシーンが懐古趣味的すぎるきらいがあるのかもしれませんが)
ミステリ部分以外だと、主人公がやや自分勝手な(悲劇のヒロイン体質の)性格なのも、終盤の展開の伏線だったのかなあ……と後から考えてしまいました。だとしたら、恐ろしく丁寧な構成だと思います。
舞台設定(不思議なバー)については、前作に引き続き登場とのことですが、今後も広がりのありそうな舞台装置だと思います。
(↑ここまで)
---
今回は以上です。
買った本のうち「新刊」と銘打っていたものについてご紹介しました。
それ以外の本についても、順次ご紹介していく予定です。
お読みいただきありがとうございました。
※上記の紹介文のうち、「作者としては、この部分は消してほしい」といった要望がございましたら、ご連絡ください。対応させて頂きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
