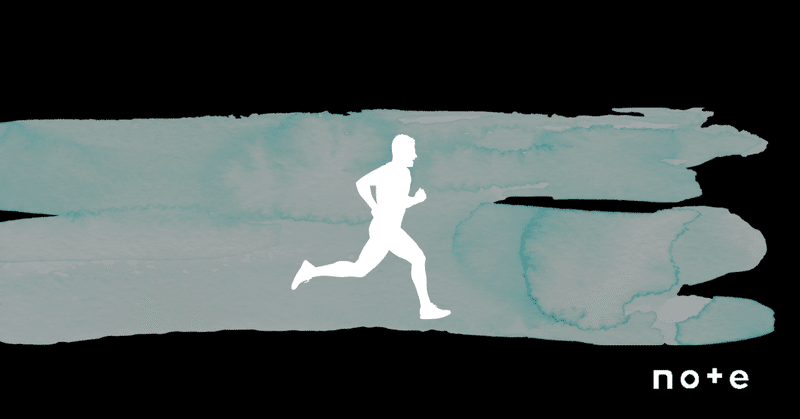
自己はVR空間において「デザイン」可能か?(後編)
※この記事は後編です。まだ前編をお読みでない方は、先にそちらを閲覧してから本文を読むとさらに理解度が深まるかと思います。後編単体で読むつもりで閲覧している方はこのままお進み下さい。
第三章.揺れ動く自分、そしてアバター
1.概要
私は第二章一節において、アイデンティティは他者によって、もしくは他者を経由して形作られると述べました。また、その上で自分がアバターを通してVRChatという空間においてアイデンティティを得て(つまり、空間内において有意味な存在として)存在できるのは、コミュニケーションの中で絶えず存在する他者との共同空間に限られると説明しましたが、言うは易く行うは難しとはまさにこのことで、有意味な存在として存在するのは中々難しいものです(現実でもそのような悩みはありふれていますし、noteでもアイデンティティを巡る戦いで疲弊したVRChatterの独白が散見されます…….)
本章においては、VRSNSにおいてそのような運動がどのようにして生じているのかをお砂糖関係を通して考察していきます。考察と言うよりは事例紹介に近しい内容にはなってしまいますが、お付き合いください。
2.その事例-お砂糖
お砂糖という言葉はVRCをプレイしていればよく耳にしますし、実際に自分のフレンド同士がお砂糖関係な人もいるかもしれません。仮にいなかったとしても、X(旧Twitter)を開けば今日もどこかでお砂糖報告やお塩報告がツイートされているかもしれません。

「ソーシャルVR国勢調査2021」でもお砂糖に関する項目が設けられ、その結果が「メタバース進化論」において紹介されています。このグラフの通り、プレイ時間とお砂糖経験の有無は有意な相関関係があります。その位、この文化はVRCにおいて大きな地位を占めています。では、その中でアバターはどのような立ち位置にあるのでしょうか。
導入でも触れましたが、VRCにおけるアバターの種族分布は人間・亜人間(「動物の耳や尻尾や羽が生えているなどファンタジー要素のある人間型」と本文中では定義されています)が全体の約89%を占めている点で非常に偏っています。なので、多くのお砂糖関係では互いにこのどちらかの種族のアバターを使用している可能性が高いのは言うまでもないでしょう。そして、お砂糖の語源が一般的に「美少女アバター同士が仲良く撫で合ったりイチャイチャしている姿がお砂糖のように甘く見えること」から来ていると言われている通り、「お砂糖」と「かわいい」は不可分とまではいかなくとも結びつきやすいのが現状です。
これは完全に私の想像でしかありませんが、このような状況において、その89%ではない人々はお砂糖をする際にもしかしたら、「今の自分のアバターをそのまま使用し続けたい」と「お砂糖関係を結びたい」という二つの願望が同時に両立しないかもしれません。例えば、周囲から何気なく「もっと可愛らしいアバターにすればいいんじゃない?」と老婆心ながら助言されたり、「まぁ、そのアバターが好きな人もいると思うよ」とあっさり流されたりしてしまうことも考えられます。その際、その人は現実的な解としてその願望のどちらかを選択することを迫られるでしょう。この例を参照すれば分かる通り、「なりたい自分」がデザイン可能であっても、そのまま有意味に存在するのは難しいのです。
3.処方箋としての分人主義
現実でこのような状態が生じてしまった場合、どちらか片方を抑圧する選択肢を選んでしまうことは多いです。しかし、VRSNSではアカウントを分けるなどすることで、自分のより見せたい部分を強調した形で分割して見せることが出来ます。つまり、現実よりも自分を分散させ、よりその場に適した形で存在できるのです。このような状態はVRSNSに限らず通常のSNSでも多く見受けられますが、一方でその明確に複数存在するアカウントという名の自分の中で「どれが本当の自分なのか」と葛藤してしまう人もいるかもしれません。そのような負い目を却って積極的に肯定する思想として、「メタバース進化論」内で紹介されているのが「分人主義」です。ねむ氏は以下のように分人主義を紹介しています。
たった一つの「本当の自分」を追いかけるのを止めて、対人関係ごとに見せるこれら複数の顔全てを「本当の自分」として認めよう、ひとりの人間の多様な側面を認めよう、という考え方です。
また、その数文後にこのように続けています。
初めの頃は新しい自分に戸惑いもありましたが、いまではフォーマルとカジュアルで衣装を変えると気分が変わるような気軽さで、分人を「着替えて」色んな自分を楽しんでいます。
ここ注意ですが、ねむ氏は分人を「着替えて」という能動性を感じる表現をしていますが、これは恐らく比喩で、アイデンティティ同様に「分人」というのは自分によってコントロール可能な物ではありません。分人主義を提唱した張本人である平野啓一郎氏の著作『私とは何か 「個人」から「分人」へ』内では以下のように明確な断り書きがされています。
分人は、こちらが一方的に、こうだと決めて演じるものではなく、あくまでも相手との相互作用の中で生じる。
話を戻しまして、仮に分人主義の立場を取った場合、単一で静的な自己(個人)というのはあくまでも想像上のものであり、私達が現実的に存在しているのは「分人」として、すなわち相手との相互作用の中で映し出されるいくつもの自己の集合ということになります。このように考えることで、事例であったようなアイデンティティ・クライシスを和らげられるor置き換え可能なものに出来るのです。無論、その先でもアイデンティティを巡る競争は絶えることがありませんが、それはずっとマシなものであるはずです。
また、分人主義の立場を堅持することは現実空間とVRSNSの対立を乗り越える一つの手段でもあります。何故なら、分人主義においては「どちらの空間にいる自分が本物なのか?」という問いは「どちらの空間にいる自分が自分にとって価値が高いのか?」という問いに置き換え可能であり、仮に片方を選択したとしてもその両方の空間の存在自体は肯定することが出来るからです。仮にどちらかの価値が低かったとしても、それ自体の価値がなくなったわけではないのですから。
ここまでの主張を総括すると、三つのプロセスが見えてきます。
①私達はVRSNSに飛び込む前に(もしくは、操作に慣れながら)アバターを選択し、その過程で私たちの何らかの概念がアバターに一方向的に投射された形で現れる。
②そのアバターが周囲(自分以外の他者全般)と接触し、その空間の中で自分が有意義に存在できるかの競争が生じる。
③その競争の中で自分へとフィードバックされながらVRSNSにおけるアイデンティティが形成されたり、その影響でアバターに投射される概念が変化したり、時には周囲に受け入れられず頓挫したりする。
以上のような流れの元で、私達のアバターは実在するのです。
ここまでの主張の具体例を挙げるとするならば、このような例は皆さんも経験があるのではないでしょうか。参考になれば幸いです。
①女性である私は周囲には隠しているが、自室の中でこっそりと男装をするのが趣味であった。ある日VRCに出会い、そこでなら自分らしく生きられると考えてVRHDMとゲーミングPCを購入した後、boothから自分好みなアバターを持ってきて使用する事にした。
②最初に入ったコミュニティでは可愛いアバターに比べてあまり受けが良くなく、当初の夢を諦めてしまいそうになった。しかし、次に私が入ったコミュニティはそんな私を暖かく向かい入れてくれて、私の趣向やこだわりを十分に認めてくれた。
③そんな中で過ごしている内に私の趣向であったそれが自分にそのまま憑依しているような気分になる事が増えたり、時折ボイチェンを使用するようになったりと少しずつ周囲への関わり方が変化しながらも、自分はこのアバターを使い続けている。
第四章.アバターの身体性は何を語るのか
1.概要
私は序章から第三章に渡ってアバターを『何かの概念を体現する存在』と定義し、主に「なりたい自分」という概念がアイデンティティという別の概念に昇華されていく過程から考察を進めてきました。ここでは少しその定義から逸れて、アバター自体について、つまりはアバターの身体性について考察を進めていこうと思います。具体的には、アバターの表情と非言語的コミュニケーションについてです。
従来のテキストチャットや通話などのオンラインコミュニケーションと比べて、メタバースにおけるコミュニケーションが極めて優れているのは、この情報量の多くを占める非言語コミュニケーションを行うことができるからなのです。
VRSNSでのコミュニケーションにおいて、非言語的コミュニケーションは非常に重要で欠かすことのできないものです。皆さんもVRChatにログインしている際は誰かに向かって手を振ったり、写真を取るときにピース等のポーズを取ったり、人によっては誰かの頭を撫でたりするでしょう。
2.VR空間における潜在的不安
その中でも、まずは表情に注目していこうと思います。boothなどで販売されている人型アバターならほとんど、VRoidStudioなどで自作する場合でも大体の場合は手のジャスチャーに対応した表情をアバターに対して設定しているかと思います(ピースに対して「笑顔」を割り当てたり等々)。その上で私たちは写真を取るとき以外でも、たった今ちゃんと自分が出したい表情が出ているのかを常に把握するために(もしくは自分の背後を確認するために)カメラを内向きにして設置したりパーソナルミラーを使ったりしますし、直接向かい合って話すのではなくワールドのミラーに向かって話し合ったりもします。
よくよく考えてみると、このような様子は傍から見ると何も見えない所に向かって皆で話しているようで中々奇妙です。殆どの人にとって現実空間で鏡などを通して自分を見る機会は精々洗面台の前に立っている時など物理的にそれが設置してある場合に限られますし、化粧直しなどを目的に手鏡を持ち歩いている方であっても人の会話中にそれを開いたりすることはないでしょう。では、この現実空間とVRSNSの間にある”差”はどのような理由から生じているのでしょうか。
私はこのようなVRSNSの現状を、近年の自意識の変化に結び付けて説明をしたいと思います。第二章においても引用した鷲田清一氏は著書『じぶん・この不思議な存在』において、自己意識が過剰になった現代社会を表現する言葉として「サランラップ・シティ」という言葉を引用しています。少し長くなりますが、引用します。
わたしたちはじぶんの表面、じぶんがじぶんでなくなるその場所に意識過剰になっている。相手の眼、相手の表情ばかり気にする。身体の接点、そこをとおしてじぶんと他人の意識が行ったり来たりするような場所が乏しすぎる。みんな画像のなかの存在、ショーウィンドウ越しの存在、透明ラップに包まれた存在になっている。あるいはまるで、全身、コンドームにくるまれている。そうした感受性が浸透している都市を、以前にある建築家は「サランラップ・シティ」と呼んだことがある。
私は鷲田清一氏が『画像のなかの存在、ショーウィンドウ越しの存在、透明ラップに包まれた存在』と呼んでいるそれは、まさにアバターそのものなのではないかと思わずにはいられません。私たちは綺麗に整えられた肌のテクスチャや特定のジェスチャーを出せば必然的に生じる表情などを内在させたアバターを使用しており、前述した通りそれらはデザイン可能な物として現れています。このことによって「魂と魂による本質的なコミュニケーション」(同書(p.281). 株式会社技術評論社. Kindle 版. )が可能になるとねむ氏は述べていますが、そのような美化されたコミュニケーションの裏で捨象されたものの一つが、生々しいコミュニケーションであり、表情であるように私は思います。
これは私見ですが、現実空間における表情というのは完全に手中に収まったコントロール出来るものではありません。自分では心から笑っているつもりでも周囲から「笑顔が怖い」と言われたり、逆に自分は普通の顔をしているつもりなのに周囲から「いい表情してるね」と言われたりするのが残念ながら普通です。一方VRSNSでは表情は即ち特定のジェスチャー(撫でられた時などに自動的に特定の表情を出すアバターもあるようですが)を出すことですからコントロール可能ですし、万が一何か表情がその場において変だとしたら、それは「本心」ではなく設定ミスか操作ミスにすぎないのです。
その際に現れているのは、自分に対して現れてくる周囲の非言語コミュニケーションへの潜在的不安です。仮に私に対して相手が「笑顔」を向けていたとしても、その相手は本当は単に空気を読んで笑っているだけで本心は笑っていないかもしれない。身振り手振りは嬉しそうでも、形式的にそうしているだけかもしれない。相手は今こっちを向いているけど、実は自分を見ていないのかもしれない……。しかも、相手の非言語コミュニケーションというのは相手がコントロール可能なので声調位にしかイレギュラーが生じず、自分が相手の機微に気付ける可能性は現実空間よりも低くなっている。このような状況で、私たちはVRSNSにおいて非言語コミュニケーションを行わざるを得ないのです。勿論、このような状況自体は現実空間でも同じですが、その先がより不明確であるという点で潜在的に狂乱状態に陥るリスクを抱えているのを私たちは直視していないのではないでしょうか。
3.「曖昧さ」がもたらす心地よさ
無論、このような曖昧さは技術の発展によって現実と大差ないレベルまで広がる可能性は十分にあります。今はまだ発展途上ですが、「アイトラッキング」「フェイストラッキング」のような技術が普及すればこのような現状が覆るかもしれません。しかしながら、周囲の反応とインタビューから察するに、そのような曖昧さを積極的に除去しようとするようなムーブメントはあまり感じられません。
ここに私は現在のVRSNSの特異性を見出せると思います。VRSNSでのコミュニケーションに特異なのは、自身をその場に存在させながらも自身の外見的な情報量(アバターや名前など)を恣意的にデザインできる点です。そして、それがVR空間全体で行われていて、それぞれの情報量が規制されていながらも、各ユーザーが相手に対して互いの曖昧さを取り払うように(つまり、安定的で永続的な関係を望むように)アプローチしたり、却ってその曖昧さの中に留まることに心地よさを感じている点です。
このような捉え方をした時、アバターはその特異な身体性を持ちながら前述したアイデンティティと同時に他者とのコミュニケーションに起き入れられます。この二面性はアバターを考察する上で非常に有益に働くでしょう。
終章.VR空間はそれでも可能性で満ち溢れている
以上四章に渡って私個人の考察を展開してきましたが、いかがだったでしょうか。私自身ここまで長い文章を書くこと自体久々で、同じような言い回しが多くなってしまったのは自覚しています。また、内容がどれも批判ばかりで、VRSNSが思っていたよりもリアルで期待はずれに思えた人もいるかもしれません。ただ、私はそれでもVRSNSは可能性に満ち溢れている空間だということを確信しています。何故なら、VRSNSがそれらしさを保っているのはすなわち、現実空間とは違った条件の元で各々が行動しているからに他ならないからです。それが外部から見て歪であったり、異様に見えたとしてもユーザーにとってはそれが「現れ」なのは言うまでもないでしょう。
私はまだVRChatを初めて1年程度で、プレイ時間も150時間程度しかない未熟者ですが、この短い時間の中でも私は様々な人と出会い、本文も私自身の持つ興味関心を広げ、伸ばし、高めてくれるフレンドや自分の雑多な思想を批評して頂ける哲学カフェの皆様のご協力あっての賜物に他なりません。
最後に、ここまで閲覧して頂きありがとうございました。
補遺 声について
普段何気なく使っている「イケボ」「カワボ」に代表されるような声に関する言葉は、紛れもないインターネット文化の一つです。近年ではASMR音声に代表されるバイノーラル音声も流行しており、声に重きをおくそのムーブメントはさらに高まっているように思えます。
VRSNSにおいても、声をその人の実在性に結び付けて語る方は比較的多いように感じます。実際問題として、フレンドがアバターをいつもコロコロ変えていて外見では判別出来なかったり、ネームプレートをオフにしたりしている場合に声というのはユーザーを区別する上で非常に重要です。また、インタビューでも『現実空間でエンカウントした際にも、見た目がどうであれ聞き馴染みのある声が聞こえることで「あぁ、やっぱりこの人は○○さんなんだ」と思えた』と仰っていた方が何人かいらっしゃったのを踏まえると、声は現実空間とVR空間の架け橋的存在でもあります。
私がここで本文の補遺として言及しようと思ったのは(ここではイケボのみの言及に留めます)、イケボには単に「私が好きな声」という意味以上に「聞くだけでその人の容姿がカッコいいに違いないと想像してしまう声のこと」という定義がされている場合があるからです。音声作品の場合には大体の場合、想像力を働かせる触媒としてカッコいい人のイラストが添付されていますが、VRSNSではアバターをそのような人に設定した上で実際に立ち振る舞うことが出来るのですから、相性は言うまでもなくバッチリです。すなわち、その人にとっての声という存在がアイデンティティそのものになる可能性が高いということです。
また、イケボとは直接関係ありませんが「ボイチェン」「読み上げツール」などの観点からVRSNS上での「声」に対してアプローチすることも出来ます。
「声」は、自己のアイデンティティを完全に自由にデザインして「なりたい自分」になれる世界を完成させるための「最後の鍵」であると言えるでしょう。
ねむ氏も私と同様にVR空間上での「声」の重要性を認識しており、現在ではは技術的な使用難易度の高さや欠点によって未だ普及してはいないものの、いずれはメタバースにおいて加工音声で喋るのが当たり前になるとさえ述べています。
本文では触れませんでしたが、以上のような状況を察するに、「声」というのはVRSNSにおいて非常に重要な役割を果たしており、考察の余地は十分にあるように思えます。補遺は以上です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
