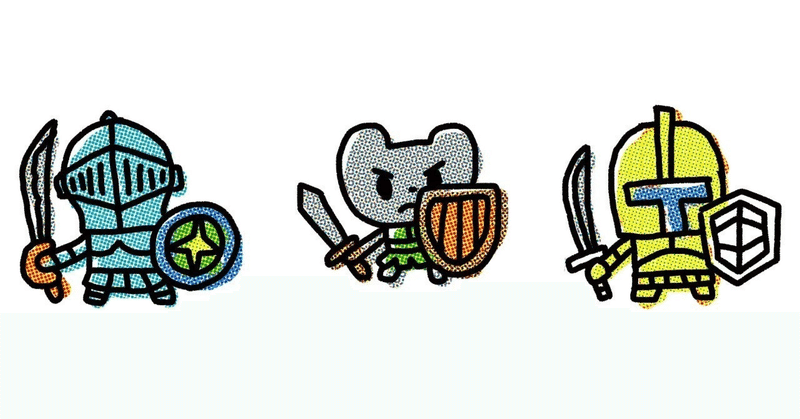
逃げることと立ち向かうこと
こんばんは、飛び亀です。
突然ですが、あなたは「困難からすぐ逃げてしまうタイプ」ですか。それとも「困難に立ち向かうタイプ」ですか。僕は逃げるタイプです。
いわゆる「昔ながらの教育」といえば、「逃げるな、立ち向かえ」ですよね。しかし近年では、特に心理学にかかわる人たちから「つぶれる前に逃げましょう」というアナウンスが出て、その声が大きく広まっていると思います。
そして、この2つの考え方がぶつかり合っている。いろいろな場面で、そんな様子を目にすることが増えた気がします。
そういうわけで今回は「逃げましょう」と「立ち向かいましょう」、正反対のように見える2つの精神論について考えたいと思います。
人はなぜ「逃げる」のか
もともと生き物は、自分より強い生き物に出くわしたり、火災など手に負えない自然現象を前にしたりして、自分の生命の危機を感じたときに「逃げる」ことを選択してきました。
現代の人間にも、それは当てはまります。
生命の危機に瀕した場面で「逃げるな」と言われることは、そうそうないと思います。戦争でもない限り。
しかし本当は生命の危機なんてなくても、生き物は「逃げる」ようにできています。何から逃げるかと言えば、「ストレス」からです。
この「ストレス」という言葉はとっても意味合いが広いのですが、実は本当の意味は「神経の緊張」です。簡単に言うと「神経つかってる」ときのことです。
人間に限らず、生き物は「神経つかってる」ときに逃げたくなります。
怖い・不安・緊張・つらい・苦しい・悲しい……マイナス感情が出ているときには、だいたい神経をつかってます。
そういうネガティブな場面で逃げたくなるのは、本能なのです。
現代の人間は特に「神経つかう」マイナス要素が身の回りにたくさんあるので、逃げたくなるのです。
人はなぜ「立ち向かう」のか
生き物が「逃げずに立ち向かう」のは、どんなときだと思いますか。
子や家族を守るとき、ナワバリを守るとき、自分の命を守るとき……
現代の人間にもまた、これは当てはまります。
何かを守るためには、立ち向かうしかないこともあります。
加えて、現代の人間は「自らの成長のため」立ち向かうこともあるでしょう。困難を乗り越えることで、経験を積んで、人は成長する。そう信じて立ち向かうのです。ゲームのレベル上げの感覚です。
しかし実は、生き物が「立ち向かう」ことを選択する理由は、そこに「ストレス」があるからなのです。つまり生き物は「神経つかってる」ときに戦いたくなるのです。
もっと噛み砕いて言うと、怖い・不安・緊張・つらい・苦しい・悲しい……こういったマイナス感情(神経つかう)を打ち消すために、立ち向かうのです。
ネガティブな場面(問題)に対して、立ち向かいたくなるのも本能なのです。
根っこは同じ
そう、「逃げる」も「立ち向かう」も根っこは同じなのです。
「闘争・逃走反応」というオシャレな言葉遊び……じゃなくて、専門用語があります。
英語では "fight-or-flight response" って言うんですって!
めっちゃ言葉遊び!
ともかく逃げることも立ち向かうことも、「神経つかう状況」(ストレス)に対する本能行動なんです。
だから当たり前ですけど、どっちが良いとかどっちが悪いとかじゃない。
逃げることも立ち向かうことも、古今東西の生き物がずーっとやってきたことなんです。
「逃げちゃダメだ!」なんてこともないし、「逃げなきゃダメだ!」なんてこともない。本能のままに、あなたがどちらを選ぶかなのです……
いやいや、そんなのって無責任ですよね。
もう少し掘り下げましょう。
第3の選択肢「立ちすくむ」
出典はWikipediaで申し訳ないのですが、先の記事を読んでみると「逃げる」「立ち向かう」の2つに加えて、第3の本能があるようです。
それが「すくんで動けない」です。
ストレスのかかる怖い・不安・緊張・つらい・苦しい・悲しい……状況を前にして、逃げることもできず、戦うこともできず、ただただその場に固まってしまう。
これ、実体験ある人けっこういるんじゃないですかね。
理屈で考えたら、これはストレスに直面し続けることになってしまうので、一番よろしくない選択ですよね。しかし、神経系のつくりのせいで、これもまた生き物の本能なのです。
固まっちゃうのも仕方ないんです。
古今東西の生き物がそうだったのです。
淘汰されていないんだから、この本能も悪いことばかりじゃないのかもしれませんし。死んだふりとか。
逃げるが勝ち
まあしかし理屈で考えたら、嫌な状況でわざわざ固まっているよりは「逃げる」ほうが役に立ちそうですよね。
「逃げる」ことには、どんなお得があるでしょうか。
何より、ストレスから離れることができます。
嫌なこと言うやつ、いじめてくるやつ、怖い夜の教室、苦手な勉強、仕事、自分の嫌いなところ、相手の嫌いなところ……
立ち向かった場合、もしも勝てなかったら(直せなかったら)余計にストレスにぶつかり続けることになります。もしかしたら、もっとストレスが強まるかもしれません。
そんな賭けに出るよりは、さっさと状況を切り替える。そうした「逃げ」のほうが安全なことはたくさんあるでしょう。
では、「立ち向かう」ことに意味はないのでしょうか。
立ち向かって得られるもの
先に書いたとおり、立ち向かうことは「賭け」とも言えます。
ストレスに負けて何も得られない可能性や、もっとストレスが強まる可能性があるということです。
しかし、それでも生き物は「立ち向かう」ことを本能に残し続けました。昔ながらの先人たちも「逃げるな戦え」という言葉を残しています。いったい何が得られるというのでしょうか。
……小一時間考えてみました。
まず「ストレスそのものをぶっ倒す」可能性です。
逃げた場合はそこに残ってしまうストレスを、立ち向かうことでぶっ倒せる可能性があります。物理的に(精神的にも)敵が1体減るのです。
そして「ストレス攻略法を得る」可能性です。
同じ敵にまた出会ったときに、もっと簡単にぶっ倒す能力を身につけられる可能性があります。巷の大人たちが「困難にぶち当たって成長しろ」というのはこれです。
もちろん逃げ続けることでも「よりスムーズな逃げ方」を学習していけるものです。ただ、実は逃げても逃げても追い詰められる可能性というのがあります。「逃げる」ことには、袋小路に追い込まれるリスクがあるのです。
特に人間は「記憶力」という能力がそこそこ高いです。こいつが厄介で、ホンモノのストレスから逃げても「記憶」の中から幻影が襲ってくる、なんてことがあります。
ストレスに立ち向かってぶっ倒すことさえできれば、そいつから逃げる必要もなく、袋小路に追い込まれる心配もなくなります。
軽々しく「立ち向かえよ」なんて言ってくるのは、そういう成功体験(ストレス勝利経験)を積んできた人間なのです。しかし、彼らの言うことは間違ってはいません。ストレスに勝つことができれば、間違いなくそこに平穏があります。そして、次の戦いが起きても勝てる可能性が高まります。
冷静に選ぶことが大事
逃げることの良さとリスク、立ち向かうことの良さとリスク。
当たり前のことばかりですが、とりあえず書き連ねてみました。
1つ書き忘れていたのは、使うエネルギーの違いです。
例外はあると思いますが、基本的には「逃げる」ほうが省エネです。「立ち向かう」ことには割と多大なエネルギーが必要です。ただ、逃げても逃げてもストレスが追ってきた場合(つまり何度も逃げなきゃいけない場合)、結果的に逃げるほうが疲れちゃうこともあるでしょう。
とにかく「逃げる」ことにも「立ち向かう」ことにも、もしかしたら「立ちすくむ」ことにも、それぞれ良い点悪い点があります。
いざという時こそ意固地にならず、冷静に考えることをオススメします。
今の自分にとってお得なのは、果たして「逃げる」ことか、「立ち向かう」ことか。
選ぶヒントになるのは、敵がどんなストレスなのか知ること。つまり「何に神経つかっちゃってんのか」知ることです。
そしてもう1つ、「自分を知ること」です。
ちなみに、知るべきは自分の能力だけじゃありません。ストレスと戦うための武器や味方を持っているのかどうか。それもよーく見渡してみることが大事だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
