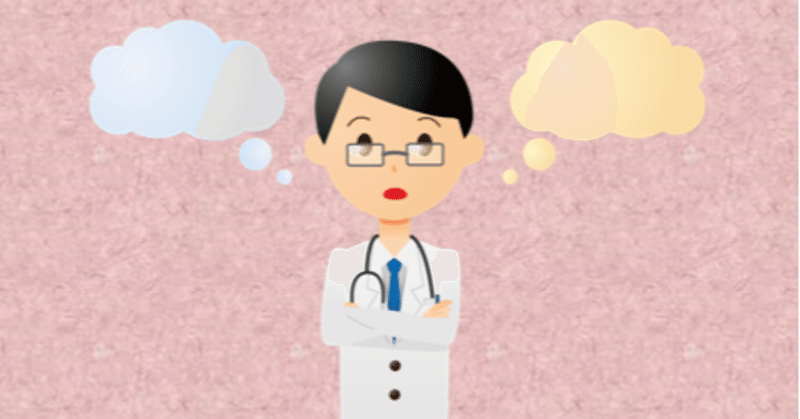
「日本昔話再生機構」ものがたり 第3話 産業医の闘い 3. ギムレット
『エル・スリナリ産業医の闘い/2.機構設立の経緯』からつづく。
「日本昔話再生支援機構」のエル・スリナリ産業医は、小さなバーのカウンターで地球から伝わったカクテル、ギムレットを飲んでいた。客はカウンターにスリナリ医師が一人。テーブル席に怪しげな中年男女のカップル、それだけ。カウンターの中では、初老の店主兼バーテンダーがイスにかけ、クロスワードパズルを解いている。
スリナリ医師が行きつけのこのバーは、「支援機構」本部のあるソーダシティからリニアモーターカーで2駅離れた郊外の町にある。そもそもが人口の少ないさびれた町で、しかも、このバーは駅から徒歩15分。店主は根は親切な好人物だが、愛想や商売っ気は、まるでなし。客が少ないのは当然だろう。もっとも、それが、スリナリ医師にとっては好都合だった。
「機構」で苦い思いをし、その感情を自宅まで持ち帰りたくないとき、スリナリ医師は、このバーで心をとろかすことにしている。ここなら、「機構」の幹部職員に出食わす危険がない。連中は、ソーダシティの一流の店で飲み食いする。「機構」幹部は高給取りで、社会的地位も高いのだ。
リニアモーターカーの終電まで、まだ二時間ある。もっとも、そこまで居座らなくても、あと一時間も酔いに身をゆだねていれば、今日の部長定例会で味わった苦痛を消してくれるだろう。
ギムレットはカクテルとはいっても、地球基準でアルコール度数25パーセント。地球人よりアルコールに弱いラムネ星人の感情を洗い流すには十分すぎるほどだ。

しかし、感情は流しても問題意識を流してはならないと、スリナリ医師は思っている。「機構」は、クローン・キャストを単なる道具としか見ていない。それは違うだろうと、彼は思う。
クローン・キャストには、天然のラムネ星人と同じく、心がある。魂を持っている。それは、一度でもキャストたちと胸を開いて語り合えば、わかることだ。魂を持った存在を道具扱いしてはならない。
もっとも、スリナリ医師のような天然のラムネ星人がクローン・キャストに心を開いてもらうのは、容易なことではない。
クローン・キャストたちは、自分たちがラムネ星人から道具としか見られていないことを知り尽くしている。キャストたちは折り目正しく冷静にラムネ星人と接するが、それは、キャストたちが心の底ではラムネ星人に何も期待していないからだ。キャストたちは、ミッションで出会う「むかし、むかし、あるところの日本人」たちの方に、はるかに親しみを感じている。
そんなキャストたちでも、持病や昔話再生中に受けたトラウマのケアで定期的にスリナリ医師の診察を受ける者たちは、少しずつガードを下ろしてくれるようになる。今では、胸を割って話し合えている――と、少なくともスリナリ医師が思っている――キャストが数人いる。
キャストたちの労働環境は元々決して良くなかったが、「ラムネ星統合政府」が推し進めている《働き方改革》が「機構」のクローン・キャストにも適用されるようになって、さらに悪化した。
休日の昔話再生を禁じて見かけ上の残業時間を減らしたが、年間の昔話再生回数とクローン・キャスト数は変えていないのだ。平日が過密スケジュールになり過重労働になるのは、誰が見たってすぐ分かることだ。
だが、「機構」も、その上にある「ラムネ星統合政府」も残業時間の帳尻合わせをしただけで、労働環境を改善したことにしている。改善どころか、現実は、改悪だ。
休日の昔話再生を禁止してからの1年間で、クローン・キャストの休職者が20パーセントも増加した。メンタルの不調を訴えるキャストは40パーセント増加し、全キャストの6割が不眠、抑うつ傾向、処方薬への過度の依存などを抱えている。
スリナリ医師は、その実態を資料にまとめ「機構」の部長たちに送り付け、月例部長会の席で労働環境の改善を求めた。
しかし、「機構」の利益を体現したようなプロジェクト管理部長と技術部長から攻撃され、頼みの綱のはずのクローン・キャスト育成部長には、のらりくらりとかわされてしまい、結局、何も前に進まなかった。
「ギムレット、もう一杯」
スリナリ医師は、店主に声をかける。これで五杯目だ。思考と感情を切り離すなんて離れ業を、アルコールの力を借りたくらいで出来るはずがない。そんなことは、医師である自分が、一番よく知っているはずなのに。
自己嫌悪がきざしてくる。それをアルコールで流し去ろうと、ギムレットのグラスを口に運ぶ。
「先生、ピッチが速すぎるぜ」
めったに世話をやかない店主が心配そうな顔でこちらを見る。
「余計なお世話だ」と言いかけて、止めた。店主は、自分のことを心配してくれている。そして、彼の心配がもっともだということを、医師である自分はよく理解している。
「そうでしたね。でも、この一杯までは」
と言って、スリナリ医師は手元のグラスを空にする。
「何か、温かいものをもらえますか?」
店主に尋ねる。
「珍しく地球産のコーヒーが手に入ったんけど、飲む?」
「いいですね。お願いします」
際どいところだった。店主の声かけと自分の医師としての矜持がなかったら、とめどなく酒に溺れていただろう。今夜のところは、何とか持ちこたえた。だが、こんなことを、いつまで続けていられるだろうか?
店主がコーヒー豆を挽き始め、香ばしい香りが漂い始める。スリナリ医師は、明日を思い煩うことを止め、コーヒーの香りに身をゆだねることにした。
画像出典:
〈『ギムレット奉行』につづく〉
