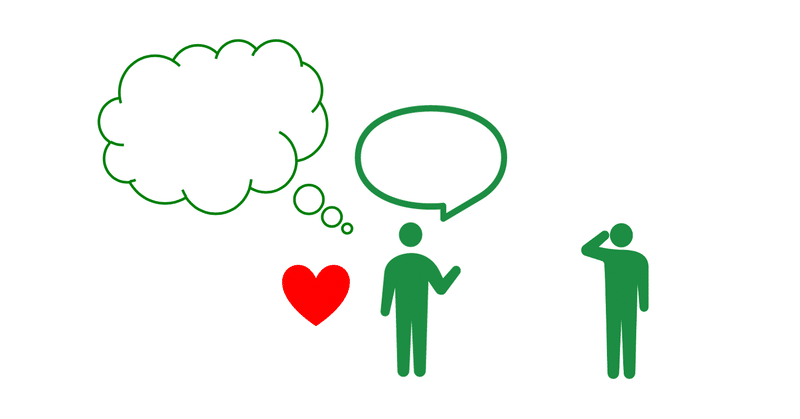
管理職・リーダーのためのコミュニケーション能力(その6)
今回は、「褒める・叱る」ということについて書いてみます。
このテーマは、管理職研修などでも必ず取り上げられますし、管理職やリーダー向けの本などにもよく書かれています。
一般的には、
*褒めると叱るの比率は9:1くらいが望ましい
*褒めるのは人前で、叱るのは二人きりの場で
*結果ではなく過程を褒める
*相手を責めるのではなく事実を叱る
*叱るのは一度に一つのことに限定する
*褒める基準、叱る基準をブラさない
などといったことが言われています。
どれも大切なことで、一つひとつのことの意味をよく考えて理解しておくことが管理職・リーダーには求められます。
ここでは、ちょっと足を止めて、褒めることや叱ることの意味について考えてみたいと思います。
そもそも、何のために褒めるのか?
そもそも、何のために叱るのか?
この二つは、対極に位置するように見えて、実は微妙に違う性質のものであると弊社では考えています。
まず、「褒める」から考えてみます。
褒めるのは何のためか?
それは、よくできた業務遂行のポジティブなフィードバックであると考えます。相手の行動や姿勢のよい点を客観的な評価として本人に伝え、その後の継続やさらなる改善に向けての本人の動機を高めるために行うものです。その意味では、褒めることは「本人の内発的な動機を高めるための外発的動機づけ」と言えます。
だとすると、ちょっと注意が必要です。
「褒められるとやる気が出る」という人は、「褒められ続けないとやる気を出さない」という人になってしまう怖れがあるということです。
心理学者のアドラーはこの点を指摘しており、「褒める」ということを否定しています。
ではどうすればよいのか?
「褒める」のではなく「感謝を伝える」ということでフィードバックを行うのです。「○○がよくできたね」ではなく「○○してくれてありがとう」とか「○○してくれて私は嬉しい」というように、こちらの気持ちを伝えるようにするといいでしょう。
次に、「叱る」について考えてみます。
叱るのは何のためか?
これもフィードバックであることには変わりはないのですが、二つのケースに分けて考えたほうがよいと思います。
一つは、相手が絶対にやってはいけないことをしてしまったときのフィードバックです。たとえば、規則に反することをしたとか、手順を逸脱したなどです。この場合は、二度と同じことをすべきではないので、理由を含めてしっかり説明し、きつく是正すべきです。
もう一つは、相手の取り組み姿勢や態度が不十分なときのフィードバックです。たとえば、仕事に本気で取り組んでいないとか、周りに対して協力的でないなどです。この場合は、「感謝を伝える」の反対で、「残念さを伝える」と効果的です。
「褒める」についても「叱る」についても、相手との信頼関係が構築されていることが前提となります。
メンバーが管理職・リーダーのことを信頼していないと、どんな言葉も響きません。
相手との信頼関係を前提に、気持ちを伝えることが相手の行動を変えることにつながります。
管理職・リーダーのためのコミュニケーション能力、
その6は「褒める=感謝を伝える、叱る=残念さを伝える」です。
いかがでしたでしょうか。
次回は「効果的な教え方」ということについて書いてみたいと思います。
株式会社F&Lアソシエイツ
代表取締役 大竹哲郎
https://www.fl-a.co.jp/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
