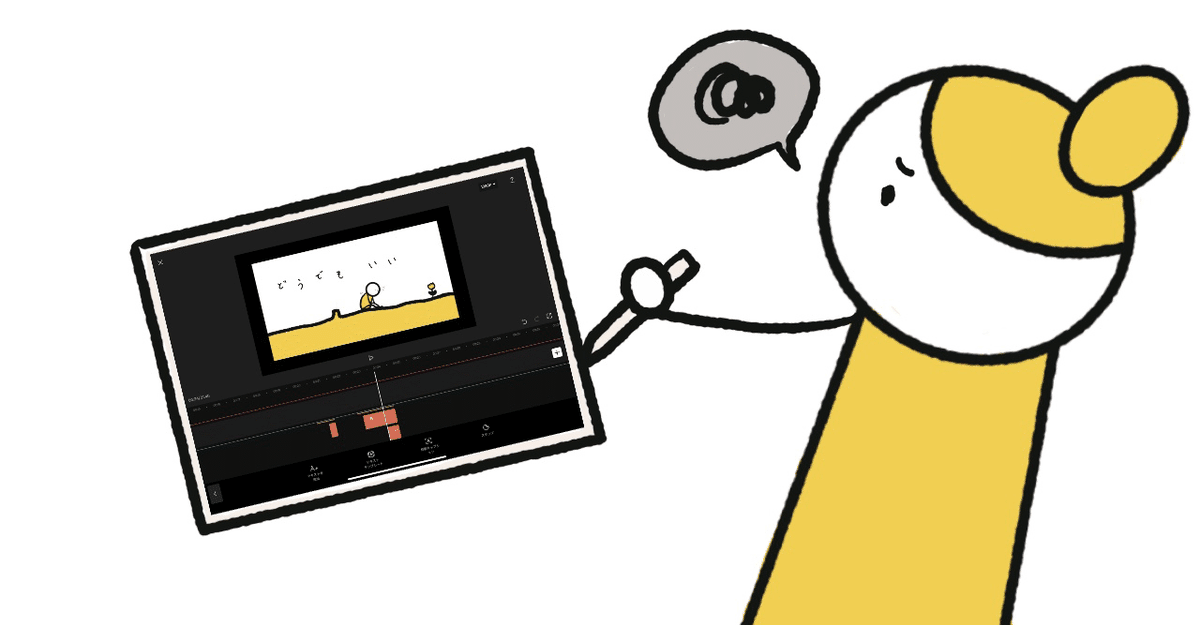
2月28日(月):コンセプト+α
昨日は日経MJの「SCの針路」という記事を引き合いに脱画一化で地域ごとの特色あるモール作りが進みつつある旨を記しました。
ただ一口に特色あるモールといっても、それを様々な地域で具現化していくのは容易なことではありません。
そのためにはコンセプト、大きな絵を描くことが必須ですね。
かつて飲食業界では居酒屋がチェーン展開を進めるなか、それとは逆行するようにダイヤモンドダイニングは100店舗100業態を掲げていました。
コロナ禍で多くの画一的なチェーンが店舗網の縮小を余儀なくされた状況を踏まえると、やはり特徴的なお店であることの強さは光ります。
そうやって常に新しいもの、オリジナリティあるコンセプトを描き続けられれば良いですが、それが一飲食店の規模ではなく、SC全体ともなると難しさは増しますね。
またコンセプトについていえば最初はマーケットのニーズから発想していても、いつしか今までにないもの、新しいことをやるのが目的になり、マーケットとの間にギャップが生まれてしまう、というのは商品開発でもよくあるケースでしょう。
そして地域の生活と密着したSCの場合、ある程度は盛り込んでいかなければならない要素、機能の面で重なりは出てきます。
そうなると結局のところ、SCや大型モールにしても国内には相応の数があるから、いずれ似たような幾つかのコンセプトに収斂をしていくステージが来ますね。
だから特徴あるSC作りに向けてコンセプトを明確にするのは重要ですが、コンセプト頼みだけでは長続きしないのも事実でしょう。
コンセプトによって一時的な新規性は創ることができても、地域の方が繰り返し足を運ぶうちに、それがユーザーにとっての既視感になるのは避けられません。
だからモールにしてもハコモノを作って終わりという発想ではなく、大事になってくるのはその後の運営力に他ならないはずです。
企画力や実行力はもちろんのこと、自分たちが地域やユーザーとの距離をどう縮めていくか、ですね。
最終的にはそういった部分が地域にとって必要な「場」になっていくための要件だと思っています。
宜しければサポートお願い致します!
