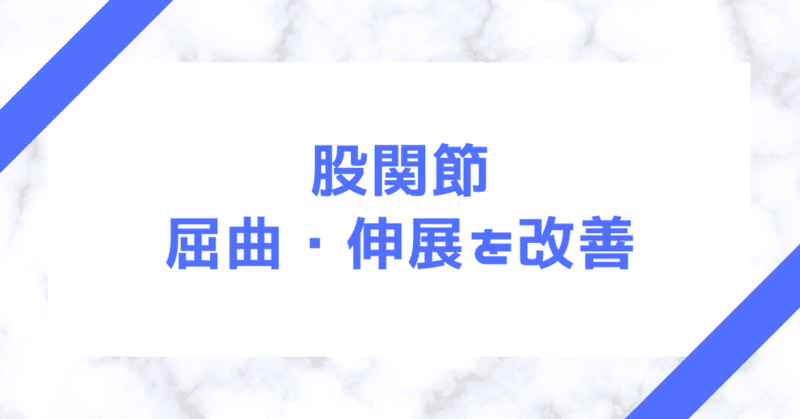
股関節屈曲・伸展可動域を変える
※この記事は、すべて無料で読めます。次の記事も読みたいと思ったら、こちらの記事をご購入ください。そちらのお金をエネルギーとして新しい記事を書かせていただきます。
今回は、股関節の屈曲と伸展を可動域を改善するためにアプローチするポイントについてまとめていきたいと思います。
股関節が動くには、骨盤・脊柱の動きが必要
股関節の正常可動域は、屈曲125°、伸展15°とされています。
ただ、これは股関節だけの可動域ではなく、骨盤・腰椎が複合的に動いたときの可動域なんです。
股関節と骨盤が複合的に動く代表例として、大腿骨盤リズムというものがあります。
『 大腿骨盤リズム 』
股関節を屈曲した際、屈曲10°までは、骨盤は前傾方向に動く。
10~90°屈曲した際は、骨盤後傾1°に対して股関節屈曲6°の割合で変化する。
このように股関節屈曲の際は、骨盤後傾運動が必要なんです。
実際に、股関節だけの屈曲角度は約90°しかないともいわれています。
つまり、屈曲可動域125°は、股関節屈曲90°と残り35°は骨盤後傾・腰椎後弯で補っている感じです。
股関節の屈曲・伸展の動きをまとめると
●股関節屈曲+骨盤後傾+腰椎後弯
●股関節伸展+骨盤前傾+腰椎前弯
股関節の可動域を改善する際は、骨盤・脊柱の動きも合わせて改善する必要があることを知っておきましょう。
股関節屈曲制限を改善
股関節屈曲に必要な動きをまとめてみましょう。
●股関節屈曲
●骨盤後傾
●腰椎後弯
●仙骨のニューテーション
上記のどの部分の動きが制限されているのか、評価する必要があります。
※股関節最大屈曲時に仙骨が腸骨に対して、前屈位となる報告があります。つまり、股関節屈曲時に仙骨がニューテーション方向に動くことが必要ということです。
次に股関節屈曲を制限する軟部組織の制限因子をまとめてみましょう。
『 制限因子 』
●外旋筋群
●腸腰筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋、縫工筋
●殿筋群(大殿筋、中殿筋)
●ハムストリングス
上記の太字となっている筋は、臨床を行っていると特に制限になりやすいポイントだと感じています。
●外旋筋群
股関節が屈曲する際は、副運動として大腿骨が後方滑りする必要があります。大腿骨頭の真後ろを通る外旋筋群が硬くなると、この大腿骨の後方滑りが阻害され、屈曲制限につながります。
さらに、外旋筋群が硬くなることで大腿骨が前方に押し出され、大腿骨頭の前方シフトが生じます。大腿骨頭が前方シフトすると運動軸が変化するため、正常な股関節の動きが困難になります。
また、大腿骨頭の前方シフトが生じることで大腿前面筋(腸腰筋、大腿直筋)に過剰なストレスが加わります。
まとめると
●屈曲時の大腿骨の後方滑りが阻害
●大腿骨頭の前方シフトによる運動軸の変化
●大腿骨頭の前方シフトにより股関節前面筋に過剰なストレスが加わる
上記のような現象が起こり、股関節屈曲制限につながります。
なので、外旋筋の柔軟性を獲得することはかなり重要です。
●腸腰筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋、縫工筋
股関節前面筋が硬いと股関節屈曲時に前方でインピンジメントが起こり、痛みが生じたり、つまり感が生じます。それによって、屈曲が制限されます。
なので、股関節前面筋、特に腸腰筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋は、硬くなりやすく制限因子になることが多いので、柔軟性を確保しましょう。
股関節伸展制限を改善
股関節伸展に必要な動きをまとめてみましょう。
●股関節伸展
●骨盤前傾
●腰椎前弯
●胸椎伸展
股関節伸展には、骨盤前傾と腰椎前弯が必要になります。
骨盤を前傾方向に動かすためには、胸椎の伸展が必要になります。
胸椎の伸展が制限されている人は多いので合わせてみておきましょう。
次に股関節伸展を制限する軟部組織の制限因子をまとめてみましょう。
『 制限因子 』
●腸腰筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋、縫工筋
●外旋筋群
●恥骨筋、短内転筋、長内転筋
上記の太字となっている筋は、臨床を行っていると特に制限になりやすいポイントだと感じています。
●腸腰筋、大腿直筋、大腿筋膜張筋、縫工筋
股関節前面筋は、股関節伸展で最も伸張される筋なので、必ず柔軟性を確保しておきたいです。
●外旋筋群
外旋筋群は、屈曲制限で説明したように柔軟性が低下すると大腿骨頭の前方シフトが生じ、運動軸の変化し、股関節前面筋への過剰ストレスが加わることになります。
なので、運動軸が変化した状態では正しい股関節伸展の動きができません。
また、股関節前面筋へ過剰ストレスが加わることで、過緊張となり股関節前面筋の柔軟性が低下し、股関節伸展が制限されます。
このように、外旋筋群の硬さも伸展可動域を拡大するために重要なんです。
●恥骨筋、短内転筋、長内転筋
内転筋群も柔軟性が低下していることが多いです。
内転筋でも特に近位部の柔軟性が低下していることが多いです。
なので、股関節伸展可動域を拡大するためには、内転筋群、特に恥骨筋の柔軟性を確保することが大切です。
今回はここまで。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
何か意見やアドバイスがあれば、コメントよろしくお願いします。
ここから先は
¥ 150
最後まで読んできただきありがとうございます。(^^♪ 理学療法士・ピラティスインストラクターの身体の専門家が有効な記事を皆様に届けます!!
